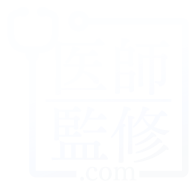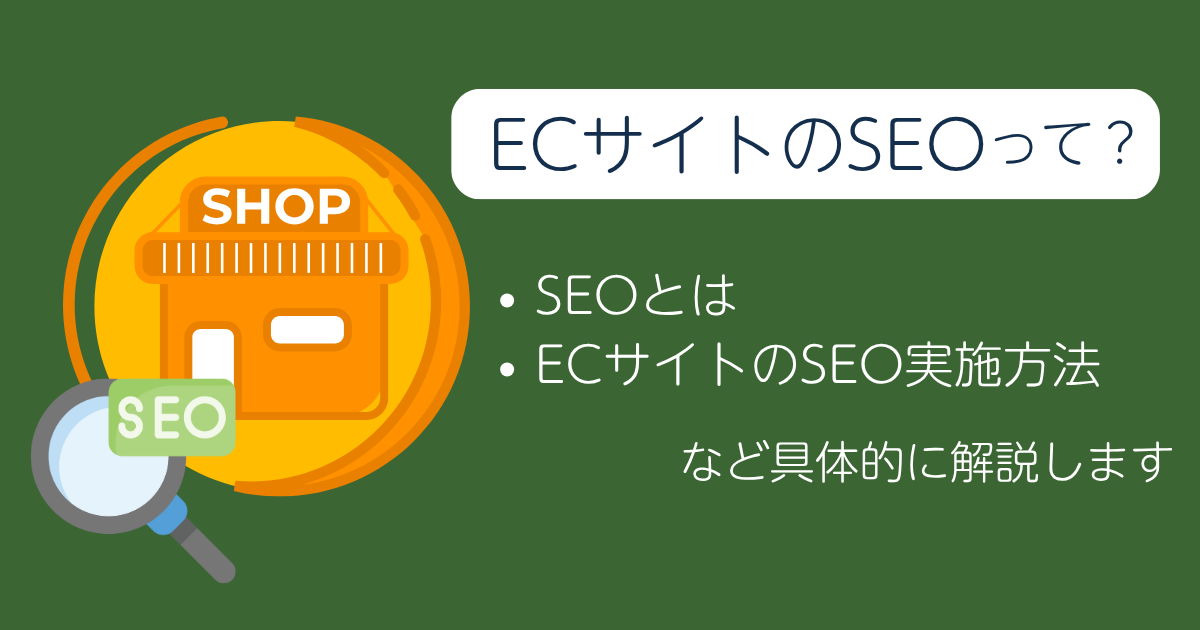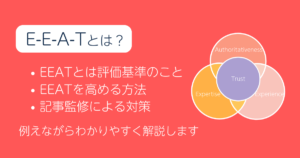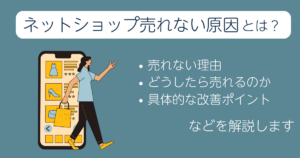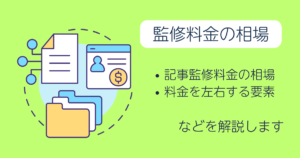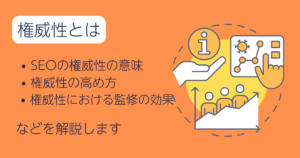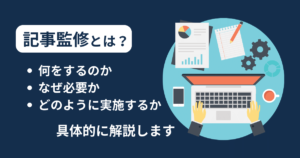ECサイトで売り上げを伸ばすためには、ECサイトへの流入を増やさなければなりません。流入数を増やす手段の一つとして、検索エンジンからの流入を増やすための最適化であるSEOに力を入れる企業も増えてきています。今回は、ECサイトのSEO対策に関する方法とポイント、注意点について詳しくご紹介します。検索結果の上位表示を目指す担当者などは、参考にしてみてください。
医師監修.com
記事監修をはじめとした
コンテンツマーケティング支援サービス

SEOについておさらい
SEO(Search Engine Optimization)は、日本語で検索エンジン最適化とも呼ばれ、検索エンジンに上位表示されるための対策のことです。
自社のECサイトが上位表示されれば、能動的な「買いたい人」にリーチできるため売上の向上につながります。SEOの効果を高めるには、検索エンジンに評価されるサイト作りを継続することが大切です。
現状大手検索エンジンであるGoogleでは、ユーザーファースト=ユーザーにとって役立つ・有益なサイトやコンテンツが重視されています。このため、ユーザーを最優先に考えたサイト設計が大切になります。
SEOの内部と外部
SEOは大きく内部対策と外部対策に分けられます。
内部対策では、商品ページのコンテンツ作りを強化したり、構造化データの実装したりして、サイトの「内側」で対策します。多くの人が想像するSEOは、内部対策にあたることが多いでしょう。
外部対策はサイトの「外側」で実施する対策のことで、他社サイトや外部ユーザーから被リンクを獲得するなどして、「サイトの信用」を底上げし、検索エンジンに評価されやすい下地をつくるなどします。
SEOに強いECサイトを作る理由
ユーザーは「検索」によって商品にたどり着くことが多いです。比較検討段階にあるユーザーや、ニーズはあるけど商品を認識していないユーザーが「商品」の購買にたどり着くまでには、広告だけでなく検索エンジン、YoutubeなどのSNS、口コミなど実にさまざまな媒体で調べたり、情報に触れたりしています。
こうしたユーザーとの接触面積を増やすのが、検索結果上位に表示させるSEOの役目なのです。
また、有料広告では継続的に費用をかけなければ集客できませんが、SEOによって一定の流入が確保できれば、広告にかける費用を減らすこともできます。検索結果画面への表示には、費用が掛からないため、上位になればなるほど流入が見込め、お得に集客できることになります。
実際、ECサイトへの流入において自然検索(SEO)が占める割合は非常に高く、明確に「購買意図」を持ってアクセスするユーザーを集められるため、コンバージョン率も良い傾向にあります。
ECサイトにおける内部SEO
内部SEOは多岐にわたるため、施策とその目的をしっかりと理解して、優先順位をつけながら実施する必要があります。ここからはECサイトが実施している内部SEOについて紹介します。
商品ページを強化
ECサイトの要となる商品ページは、どのサイトでも力を入れて取り組んでいる部分でしょう。商品ページの強化は、SEOにおいても重要です。
Googleのような検索エンジンでは、ECサイトの商品ページから情報を抽出して検索結果に表示させます。ときには商品ページそのものが検索結果の上位に入ることもあるため、手を抜けません。
SEOの基本的な方針は「ユーザーファースト」です。商品ページも例外ではなく、ユーザーにとってわかりやすく有益な情報を掲載することが評価されます。
商品ページ内に記載する情報を定型化し、可能な限り詳細を記載しながら「オリジナリティのある情報」を入れることが重要です。
たとえばユーザーファーストな商品情報とは:
- 基本情報:商品番号、商品名、商品画像、価格
- 詳細情報:スペック、特徴、利用シーンのイメージ
- 購入支援情報:送料、お届け予定日、在庫状況、再入荷予定
- 信頼性向上要素:ユーザーのレビュー、関連商品、保証
上記のような情報は漏れのないようなるべく記載し、オリジナリティのある商品説明欄を作ってください。
自社商品ではなく、他社商品を仕入れて販売しているECサイトでは、メーカーが用意している商品説明をそのまま転用している場合も多いでしょう。しかし、検索エンジンは「他のサイトにない情報」をオリジナリティがあり、ユーザーにもより有益なものとして評価します。
このため、そのまま転用するのではなく、自分たちで新たに説明文を作成するとより効果的です。
コンテンツマーケティングで強化する
コンテンツマーケティングは、ユーザーに価値のある情報を届け、サービスの利用や商品の購入へつなげる取り組みのことです。コラム記事の作成が代表的で、ECサイトにおいては、「お悩み解決情報を届けて解決策として商品を提案する」といった形で活用されることもあります。
ECサイトのメインはあくまで商品のため、コラム記事などには取り組んでいないところも多いでしょう。しかし、商品ページのみで検索結果画面の上位を獲得できる検索クエリ(※)は限定的です。購買意志がある程度固まっているようなユーザーは獲得しやすいですが、このようなニーズが「顕在化」しているユーザーは多くありません。
より売上を増やすためには、ゆくゆくは、ニーズが「潜在」的な母数の多いユーザーにもアプローチできるようにしなければなりません。CVは作れてきたけれど、売り上げが伸びないといったタイミングで、導入していくとよいでしょう。
重要なのは「商品ページ」にコンテンツを追加して作りこむのではなく、「集客用のSEOコンテンツ」と「商品ページ」は分けて作成することです。
商品ページは購入に直結するため、過不足なくわかりやすいページが求められます。商品を求めている人の悩みやニーズは多岐にわたるため、こうしたニーズを喚起させる情報をすべて入れるのは現実的ではありません。別ページでターゲットを絞ってコンテンツを作成する方が、よりユーザーに刺さる内容にすることができます。
ECサイトのSEOにおいては、購入用ページと集客用ページは分けるようにしておきましょう。以下では、コンテンツマーケティングとして記事コンテンツの作り方を簡単に紹介します。
※ユーザーが検索するキーワードのこと「PC 通販」など検索窓に入れる文字
①キーワード選定
SEOではキーワードベースで対策します。ユーザーの検索クエリ、すなわち検索窓に入れるキーワードは、そのままユーザーのニーズにつながるものです。集客したいターゲット像に合わせて、対策するキーワードを選定することになります。ユーザーが検索するとき、ニーズは大きく次の4つにわかれるとされています。
※ユーザーが検索窓に入れたキーワードのことを「検索クエリ」、サイト運営者が管理上扱う検索キーワードのことを「キーワード」と呼びますが、ここではわかりやすいよう以降キーワードに統一して解説します。
| キーワード(クエリ) | 概要 |
|---|---|
| Know(知りたい) | 「○○対策」「○○ △△ 違い」「~とは」など、なんらかの疑問や悩みなどを解決するために検索されるキーワード。アピールしたい商材を解決策の一つとして据えることが多い |
| Go(行きたい) | 「地域 レストランの名前 店舗」など店舗名、サービス名、目的地など、「目的地」や「アクセスしたい先」がすでに決まっており、そこにアクセスするための手段として検索されるキーワード。一見ECサイトは関係ないように見えるが、「楽天市場 商品名」「Amazon 商品名」などサイト名での指名検索もここに含まれる。サイト名を認知させる必要があり、優先順位としてはサイトが育ってからのことが多い |
| Do(やりたい) | 「ストレッチ やり方」「カレー 作り方」など、やりたいことがすでに決まっている人が、どうやるかを調べるキーワード。アピールしたい商材を解決策の購入に関するクエリ。行動購入につながるキーワードを探すとよい |
| Buy(買いたい) | 「○○ 比較」「○○ 最安値」など。4種類の中でコンバージョンにつなげやすいが、アクセスする母数は少ない |
KWの傾向と、自分たちが集めたいターゲットを考慮して選定してみてください。
Google広告に出稿しているなら、キーワードプランナーから検索キーワードのボリュームを確認できます。月間の検索ボリューム10未満といった、極端に見る人が少ないキーワードは、大幅なアクセスアップを見込めません。狙いたいキーワードに、検索需要があるかどうかを確認してから対策しましょう。
最初はボリュームが1,000程度までのロングテールキーワードから対策することが多いです。
ロングテールキーワードとは、3語以上で構成されたキーワードのことです。月間の検索数が比較的小さく、1語で成り立っている「ビッグキーワード」よりも難易度が低いキーワードです。キーワードがいくつも並んでいるため、検索意図を読みやすく、ニーズに答えられるコンテンツを作りやすいでしょう。
たとえば、「おしゃれ マグカップ プレゼント」は、プレゼントに適したおしゃれなマグカップを求めている状態で、「マグカップ」という単一のキーワードより明確な意図を持っています。
キーワードを選定したら、ユーザーのニーズに合わせたコンテンツを作成します。
②タイトル・ディスクリプション作成
タイトル
タイトルはユーザーが検索結果画面で目にする最初の情報です。同じキーワードで出てくる競合のページと比較され、クリックするかどうかの判断基準となる重要な要素となります。
ユーザーの知りたいことがあるかどうか、他サイトとどう違うのか、より有益な情報があるかどうかなどをアピールして、クリックしたくなるようなタイトルを付けてください。キーワードはなるべく先頭に配置し、全体で30~35文字程度に収めましょう。
例:
キーワード「おしゃれ マグカップ プレゼント」
タイトル「プレゼントに喜ばれるおしゃれなマグカップ厳選5つ!」など
ディスクリプション
検索結果においてタイトルの下に表示される文章です。最近ではあえて設定しなくても検索エンジンがコンテンツからテキストを抜き出して掲載してくれますが、こちらもタイトル同様、クリックするための重要な情報です。
検索結果画面に表示される120文字以内におさめ、コンテンツの内容を説明して、読みたくなる・クリックしたくなるような導入文を作成してください。
③本文と画像の作成
とくに記事コンテンツでは、ユーザーの検索ニーズを満たす本文が重要です。ユーザーの疑問や知りたいことに答え、ECサイトで売りたいものにつなげられるようなコンテンツを作成しましょう。
商品ページも同様ですが、ECサイト用のSEOコンテンツでは画像を多用することも多いでしょう。しかし、画像によって表示速度が遅くなると、掲載順位に影響を及ぼしたり、せっかく来てくれたユーザーが離脱したりします。
可能な限りファイルサイズを小さく抑え、表示速度を落とさないようにしてください。画像の表示を遅らせて、テキストだけ先に表示させる(読み込みの優先順位を変える)こともできるため、サイトの状況に合わせて調節しましょう。
構造化データにする
構造化データは、サイトのページ構造を検索エンジンへわかりやすく伝えるためのコードをのことで、<head></head>内などでマークアップします。こうすることで検索エンジンなどが情報を認識しやすくなり、検索結果画面での強調表示(リッチリザルトなど)に反映されやすくなるといわれています。
Googleの支援ツールもあるので、最初はこうしたツールを活用しましょう。対策したいページの、構造化したい部分を選択して自動生成されたHTMLを<head>内に設置するだけで完了します。
- 商品情報(Product):商品名、価格、在庫状況、レビューなど
- パンくずリスト(BreadcrumbList):サイトの階層構造を示す
- レビュー(Review):商品やサービスの評価と口コミ
- 組織情報(Organization):企業情報と連絡先
構造化データを実装しても必ずリッチリザルトが表示されるわけではありませんが、実装しなければ表示される可能性はゼロです。ECサイト運営では必須の施策といえるでしょう。
重複ページを消す
同じようなページがたくさん存在していると、検索エンジンから「検索順位対策で低品質なコンテンツをわざと量産している」とみなされることがあります。
商品ページはとくに類似ページが多くなりやすいジャンルです。canonicalタグを活用するして、類似ページを整理しましょう。canonicalタグとは、Aのページに似たBやCページのURLを、AページのURLに統一するようなものです。検索エンジンへ、類似ページのうちどのページが優先されるべきか、などを示すことができます。
販売終了ページの対策を行う
商品ページの中で既に販売終了済みの商品が掲載されている場合は、早めにページを削除したり、類似商品を案内したりするようにしてください。
再販の予定がある場合は、欠品中の情報や再販予定日などをページ内に掲載するなどして、ページ内の情報を「最新版」にするよう意識しましょう。
品切れ・販売終了済みの商品ページが放置されていると、ユーザーの離脱率を高めてしまいます。ユーザーがすぐに離脱するページは「ユーザーに有益なページ」とは言い難く、検索エンジンからの評価にもつながります。
販売終了・在庫切れの対処例:
- 完全販売終了の場合:404エラーまたは301リダイレクトで類似商品ページへ誘導
- 一時的な品切れの場合:再入荷予定日を明記し、メール通知機能を提供
- 代替商品の提案:類似商品やおすすめ商品を同ページ内で紹介
サイト構造の最適化
5回・6回とクリックしなければ商品ページにたどり着かない構造は、購買につながりにくいです。ユーザーは購買ページまでにステップを挟めば挟むほど離脱します。
また検索エンジンのクローラー(Webページの情報収集を行うプログラム)にとっても複雑な構造は、情報収集しにくいです。
ディレクトリ構造を意識した設計にし、パンくずリストも設置しましょう。
ディレクトリ構造は、上位表示させたいビッグキーワードの記事からカテゴリ、個別ページといった、ツリー上に内部リンクをつなげる階層構造のことです。たとえば、トップページからカテゴリページへ遷移し、カテゴリページから商品ページへアクセスできるようなイメージです。
パンくずリストは、現在表示しているページがサイト内のどの階層にあるのか示したもので、一般的にサイト内の上部に記載されるよう設計されます。一見地味なポイントですが、パンくずリストがあることで、ユーザーも「サイト内のどこにいるのか」がわかりやすくなり、商品カテゴリや、記事ページに戻りたくなった場合もすぐに遷移できるため、サイト内の回遊率もよくなるでしょう。
ユーザビリティを高める
ユーザビリティは、ユーザーの使いやすさを示す単語です。これまでに説明してきたポイントに比べると非常に大枠な概念ですが、商品を探したり、比較したりして滞在時間が長いECサイトではとくに重視すべきでしょう。
使い勝手の悪いサイトは、商品ページにたどり着く前に離脱される可能性があるばかりか、買いたい商品があっても煩雑さに諦めて決済まで完了してもらえない可能性もあります。
ユーザビリティを高める施策 代表例:
- ページの表示速度を向上させて見やすくする
- ボタン配置に気を付ける
- ユーザーの操作や入力を可能な限り減らす
- モバイルフレンドリーに対応する
- 常時SSL化で安全性を高める
- 直感的なナビゲーションを設置する
モバイルフレンドリー対応とは、PCだけでなくスマートフォンなどの画面の小さい端末から見ても問題なく閲覧できるように配慮した対応のことです。文字色やサイズを調整して見やすくしたりスクロールしやすいデザインに調整したりします。
サイトのインデックス登録を行う
ECサイトやオウンドメディアを運営する際は、サイトマップの送信などでインデックス登録を促すのも大切です。
検索結果にWebサイトを表示してもらうには、サイトやページを検索エンジンが認識し、データベースへ登録(これをインデックスと言います)する必要があります。
検索エンジンのクローラーは自動で巡回しているため、何もしなくても登録されることも多いです。しかし、早めに検索エンジンに認識されるためにも、サイトやページを作成した段階でこちらから登録しておくことが推奨されます。
たとえばGoogleに対して手動でインデックスの申請やサイトマップの送信をするときは、Google Search Consoleを使用します。
Google Search Consoleを活用することで:
- サイトマップの送信
- 個別URLのインデックス登録リクエスト
- クロール状況の確認
- 検索パフォーマンスの分析
URLは英語で短くまとめる
各ページのURLを設定する際は、英語で短くまとめるようにしましょう。これはSEOの評価に直結する対策ではありません。一般的にURLの文字列や文字数は、検索エンジンの評価に影響しないといわれています。
しかし短いURLなら手軽にコピー・ペーストでき、SNSでの文字数制限にも引っかかりにくいため、ユーザーに拡散してもらいやすくなります。SNSでの拡散が大きくなれば、ユーザーの流入が増えるだけでなく、のちに説明するように検索エンジンからも評価されやすくなります。
日本語のURLは、SNSなどへ貼り付けると英数字の長い文字列で変換されてしまうため、英語が推奨されます。
良いURL例:
- /products/smartphone-case/
- /category/electronics/
- /blog/seo-tips/
避けるべきURL例:
- /products/商品ページ/スマートフォンケース/
- /category/電子機器商品一覧表示ページ/
ECサイトにおける外部SEO
共感される・信頼のある情報の発信とシェアボタンの設置は、外部SEOにおいて重要な被リンク獲得につながります。
同じようなジャンルで検索エンジンから高評価を受けているサイトや、権威あるサイトからのリンクはある種の「推奨投票」のようなものであるといわれています。第三者からリンクされれば、ECサイトの認知向上のみならず検索エンジンからの評価も見込めます。
思わずシェアしたくなるような情報、共感を呼ぶようなコンテンツ作成などに力を入れ、簡単にシェアできる仕掛けづくりを忘れないようにしましょう。
効果的な外部SEO施策:
- 高品質なコンテンツの作成:業界のトレンドや使い方ガイドなど
- プレスリリースの配信:新商品や企業ニュースの発表
- インフルエンサーとの協業:商品レビューや紹介記事の依頼
- 業界メディアへの寄稿:専門知識をもとにした記事提供
- SNSマーケティング:商品の魅力を伝える投稿とユーザーとの交流
ECサイトのSEOではE-E-A-Tを高めることも大切
続いては、E-E-A-Tの種類とECサイトにおいて重視すべき理由を解説します。
E-E-A-Tは4つの領域に関する評価
E-E-A-Tは、経験(Experience)・専門性(Expertise)・権威性(Authoritativeness)・信頼性(Trust)の頭文字を合わせた用語で、サイトの品質を評価するための指標の一つでもあります。
こうした指標をクリアすれば検索順位が上がると保証されているわけではありませんが、Googleが示す「ユーザーファーストなサイト」の条件のようなものであるため、重視されています。
つまり、コンテンツや商品ページにおいては
- 実体験に根差した情報がある
- 専門性が高いサイトで言及されているため信頼できる
- 有資格者などによって言及されているため信頼できる
- 公的機関による情報発信であるため信頼できる
- 情報の発信元や参照元が明示されているため信頼できる
こうした要素が、ユーザーにとって「より信頼でき有益である」と評価されるのです。
たとえば、医師の監修している記事と素人の医療記事では、前者の方が信頼でき、安心して情報を活用できるでしょう。このようにE-E-A-Tは、ユーザーの情報の取捨選択の判断基準となるような指標なのです。
ECサイトにおいてもこうした「信頼できるかどうか」は無関係ではありません。買ってもらうためには「このサイトなら買っても問題なさそう」だと信用してもらう必要があるためです。
ECサイトにおけるE-E-A-Tの例:
Experience(経験):
- 商品やサービスを実際に使用した体験談
- 業界での実務経験や実績
- ユーザーからのレビューや口コミ
Expertise(専門性):
- 取り扱う分野における深い知識
- 関連資格や認定の保有
- 継続的な情報発信と更新
Authoritativeness(権威性):
- 業界内での認知度と信頼
- 他の専門サイトからの被リンク
- メディアでの言及や紹介
Trust(信頼性):
- 運営者情報の明確な記載
- SSL化やセキュリティ対策
- 透明性のある企業活動
YMYL領域のECサイトはとくに信頼性が大切
ECサイトで取り扱う商材の多くはYMYLに含まれます。ジャンルでもあります。
YMYL(Your Money or Your Life)とは、人々の生活や生命に大きな影響がある領域のことで、ECサイトにおいては健康食品などがとりわけ当てはまるジャンルです。こうした領域においては、ユーザーの安全を考慮し、検索エンジンはコンテンツの質だけでなくE-E-A-Tをとくに重視します。
YMYLに該当するECサイトの例:
- 健康食品・サプリメントの販売
- 医療機器・健康器具の販売
- 金融商品・投資関連商品の販売
- 高額商品(車、不動産、宝石など)の販売
- 子供向け商品の販売
金銭がかかわるため、ECサイトはもともとE-E-A-Tが強く重視される領域ではありますが、上記ジャンルの商材はさらに厳格に評価される傾向にあります。競合も力を入れていることが多いため、置いていかれないように対策しなければなりません。
SEOの一環としてECサイトのE-E-A-Tを高めるには監修がおすすめ
E-E-A-Tはコンテンツやサイトの信頼を問う指標です。サイトそのものの専門性を高めたり、公的機関ではない企業などが「権威」あるサイトとして育ったりするにはかなりの時間を要します。
こうした場合は、資格を持つ専門家の力を使い、「監修」という形でコンテンツや商品ページにかかわってもらうことで「信頼性」「権威性」を強化すれば、早く・手軽にユーザーが安心できるコンテンツづくりが可能となるのです。
たとえばECサイトでは次のように活用することでE-E-A-Tの強化にもつながります
- 自社商品の監修
- 専門家コメントの掲載
- オウンドメディアの記事監修
「監修」は監修した専門家の情報を掲載できるため、資格情報としてもユーザーからの信頼を集めやすいです。商品ページすべてに監修を入れるのは現実的ではないため、実際には主力の自社商品や、集客用のページで活用する傾向にあります。
弊社サービス「医師監修.com」では上記のような形での専門家の起用をお手伝いしています。ECサイトでの活用も可能なため、ぜひ下記ページより詳細をご確認ください。
監修を活用したE-E-A-T対策の例:
商品監修:
- 専門家による商品の成分・安全性の解説
- 使用方法や注意点のアドバイス
コンテンツ監修:
- 業界の専門家による記事の監修
- 商品説明文の専門的な観点からのチェック
- FAQ(よくある質問)の監修
監修者プロフィールの充実:
- 専門資格や経歴の詳細な記載
- 顔写真付きのプロフィール
- 過去の実績や著書の紹介
SEOに強いECサイト作りで集客力をアップさせよう!
流入強化のためにはSEOに強いECサイトづくりが欠かせません。とくにECサイトはYMYL領域と深くかかわるため、通常のSEOのみならずE-E-A-T対策も重要です。
ECサイトや販売ページのSEOにお悩みの方は、今回の記事を参考にしながら「医師監修.com」の監修サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
SEOは長期的な取り組みが必要ですが、適切な施策を継続することで確実に成果につながります。ユーザーファーストの姿勢を忘れずに、質の高いECサイト運営を心がけましょう。