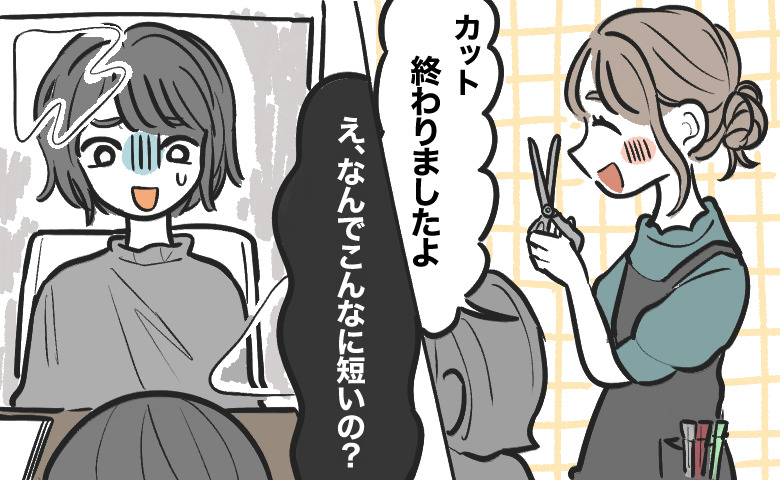前回は相続の基本となる「人が亡くなった際に誰に財産を引き渡すか」「どのような基準で相続税がかかるか」をご説明しました。応用編として今回は、子育て世代に関わるおじいちゃん・おばあちゃんからお孫さんへの教育資金の贈与と住宅資金の生前贈与についてご説明いたします。
贈与は相続を生前中に済ませる意味にも
贈与とは、「お互い同意のうえで、自分以外の人に財産を与えること」ですが、人が亡くなったときに財産を受け継ぐ(=相続)を生前のうちに済ませる意味合いもあります。税金を考えた場合に、亡くなった際に財産を引き継ぐと相続税がかかるから、生前に財産を贈与してしまえば相続税をなくすことができると考える人もいるので、相続税を補う意味で贈与にも税金がかかる仕組みとなっています(=贈与税)。
ちなみに、同じ金額を相続された場合と贈与された場合では、一般的に贈与された場合の税率が高いです。また、通常の場合では、贈与された金額が1年間で110万円を超えると贈与税がかかりますが、一定の用途や条件に当てはまると贈与税がかからなくすることができますので、一例をご紹介します。
ケース1
◼︎祖父母などから1500万円以内の教育資金の一括贈与を受けた場合、贈与税を非課税にできます。
3年前から始まった制度ですので、覚えている人もいると思いますが、平成31年3月31日までの間に、30歳未満の人が、教育資金の目的で信託銀行などの金融機関の手続きを経て、祖父母(曽祖父母でも可)から贈与を受けた場合、1500万円までの金額に対しての贈与税がかかりません(=非課税)。
贈与を受けた人が30歳になった際の残額や教育以外の用途で資金を使った場合は、贈与税がかかりますのでご注意ください。単純におじいちゃん・おばあちゃんからお孫さんの預金口座に振り込むだけではこの制度は使えず、信託銀行等でこの制度の対象の“教育資金口座の開設”が必要となります。
この制度を検討する際は、最寄りの税務署や金融機関にしっかりと確認したうえで進めるようにしましょう。
ケース2
◼︎両親や祖父母などから住宅資金の贈与を受けた場合、一定の金額の贈与税を非課税にできます。
平成31年6月30日までに、両親や祖父母(曽祖父母でも可)から、住宅の新築・購入、増改築などの目的で贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税がかかりません(=非課税)。
住宅購入などの契約日と住宅が、一般的な住宅か省エネなどの住宅かで贈与税がかからない金額の上限は異なり、平成28年1月1日から平成29年9月30日までに契約した一般的な住宅の場合は700万円までの贈与については、贈与税がかかりません。
この制度も手続きが必要で、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署で手続きする必要があります。制度の詳細は、最寄りの税務署または国税庁のホームページをご確認ください。
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。