
親が育児で困ることの1つに、子どもの癇癪があります。何でもイヤイヤと拒否をして、スーパーに行けば「これほしい!」と寝転がって泣き叫び、家でもちょっとしたことでキーッっとなり、一日中泣いたり叫んだりで親もヘトヘト。そんなこどもの癇癪と対策についてお話します。
癇癪は「健やかに成長している証」
親が何を言っても何をしても「イヤイヤ」と聞かない、そんな子どもの癇癪は実は「健やかな成長の証」なんです。2歳半から3歳の子どもは自我の発達が著しく、自分が「こうしたい」という意識が芽生えます。でも意思表現がうまくできなかったり危険を察知したりできません。
親が危険を感じて制止し、正しいやり方を教えようとすると、子どもながらに自尊感情を傷つけられ、その結果、激しく泣き叫んだりひっくり返って怒り出すという行動を示します。
「育てにくい子」の癇癪の場合は専門家へ
生まれてから2歳、3歳を過ぎ、6歳になっても「長期間一貫して」癇癪がひどく、育てにくい状況が続く場合は、地域にある育児の相談窓口で相談してみましょう。
発達の状態に凸凹があり、子ども本人が困っているケースがあるからです。その場合は、小児発達の専門医や心理士に子どもに合った関わり方を教えてもらいましょう。また、自治体によって個人または集団での療育をしてくれるところもあります。
親は自分の感情と向き合おう
成長の証でも、本人が困っているサインでも、癇癪の激しい泣き叫びを目の当りにすると「どうして言うことを聞いてくれないの?」と指示に従わない子どもへ怒りが沸き、あせることもあります。
でも、まだ子どもは自我が芽生えたばかり。「自分をコントロールする術がないのね・・・」と見守っていきましょう。そして、おいしいお茶を飲んだりパパと育児を交代してひと時の休息を持ったりして自分の気持ちのケアも大切にしてください。
子どもの成長が著しい乳幼児期に激しい癇癪が続き、この時期を乗り越えるにはママ1人ではなかなか難しいもの。親子で心落ち着く生活を過ごすために、家族や専門家の力も借りて、自分の休息も大事にしてくださいね。
(TEXT:もも助もも太郎)









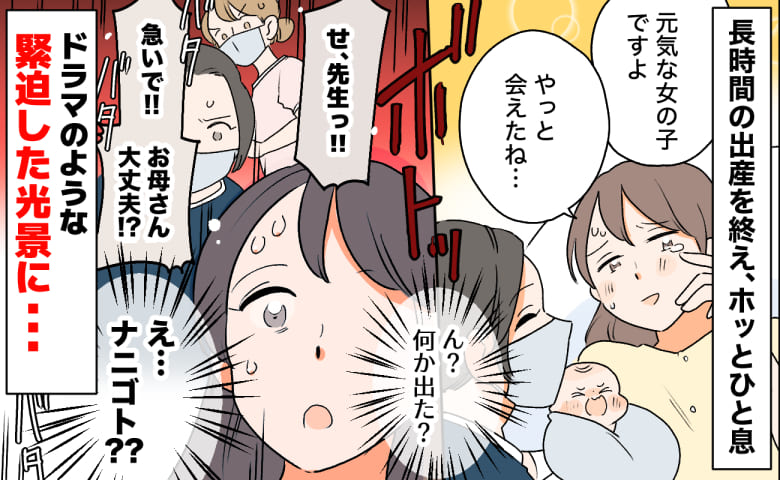
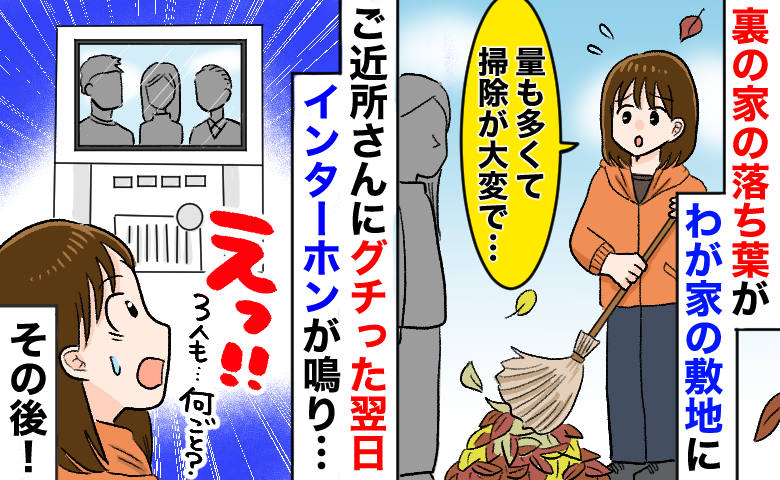
.png)