.jpg)
待ち望んでいた妊娠がわかったとき、やったー!とよろこばれる方が大半だと思います。しかし、その次に赤ちゃんに異常はないかという不安も襲ってくるのではないでしょうか。
私が妊娠中のときに、少し先に妊娠した友人が、妊婦健診時に「ダウン症の疑いが少しあります」と言われたと聞き、私の子どもは大丈夫だろうか?出生前診断を受けるべきだろうか?と悩んだことを覚えています。
新出生前診断とは?
新出生前診断(正式名称:無侵襲的出生前遺伝学的検査)とは、母体から採取した血液で、胎児の染色体異常を調べる検査のことで、NIPTともいわれます。
以前から、羊水検査や絨毛検査など、胎児の健康状態を診察する医学的手法が確立されていましたが、これらの診断方法には、穿刺針で母体を傷付け、流産のリスクを高めてしまうという問題点がありました。
一方、NIPTは、20ccほどの採血だけで済むため、母体への負担を大幅に軽減することができる診断方法なのです。診断精度も高く、80~90%前後の確率で胎児の先天異常を予見することができるとのことです。
増え続ける受診者とその背景
NIPTが実施され始めてから4年が経ちました。そして、この4年間に「検査を受けた人数は計4万4,645人だった」とする集計結果を、各地の病院でつくる研究チームが16日、発表しました。
検査を受けた人の数のうち、4年目は約1万4,000人で前年より約12,00人増加。高齢出産の増加などの背景もあり、受診者は年々増加傾向にあるとのことです。
デメリットが浮き彫りに
くわえて、検査の結果、染色体異常の疑いがある「陽性」と判定され、さらに別の検査に進んで異常が確定した妊婦の94%が人工妊娠中絶を選んでいるという結果も発表されました。
現在、NIPTは、日本医学会が認定した施設で臨床研究として実施されているものです。この施設には、夫婦らの意思決定を支える遺伝カウンセリング体制の整備が施設の要件とされています。なぜなら、安易にこの検査が広がると、「命の選別」につながる恐れがあると考えられているからです。
わが子が健康に、五体満足に生まれてきてほしいと願うのは親としては当然のことかもしれません。事前にわかるのであれば、知りたいと思うのもまた自然なことかもしれません。出生前診断を受けることで、事前に準備を整えられるというのもまた事実だと思います。検査の結果をどう受け止めるのか?しっかり考えたうえで、受診するかしないかの選択をしなければならないと思います。(TEXT:東 裕子)








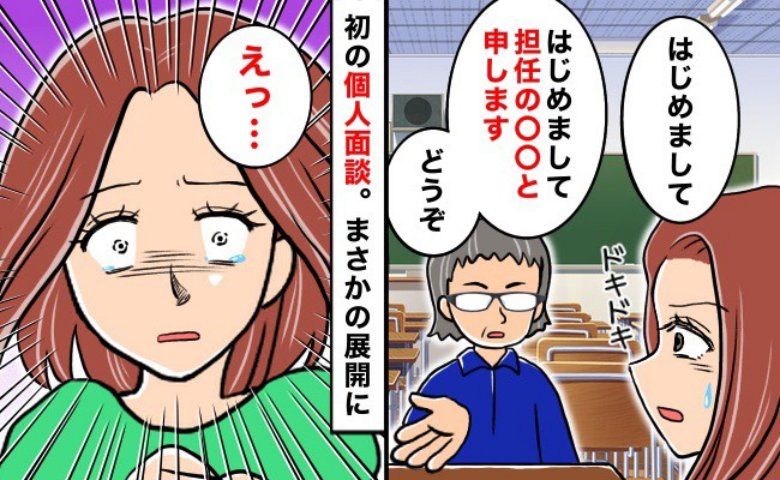
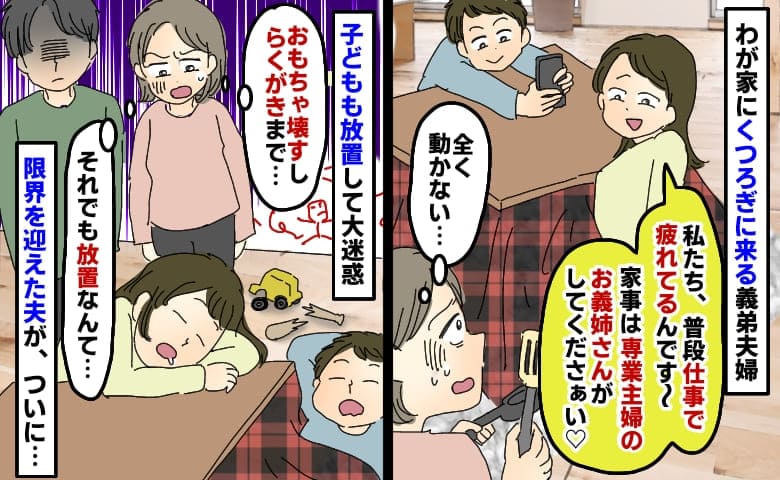

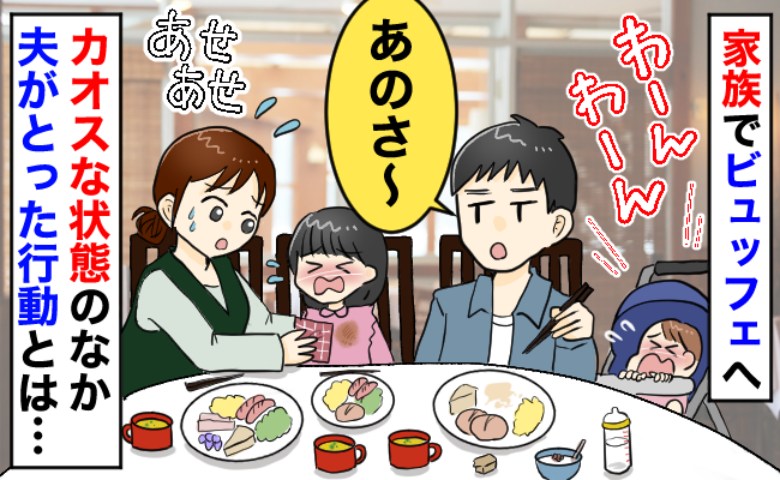
また、NIPTでわかるのは障害のうちのごく一部で、たとえ結果が陰性でも、健常の子が生まれるとは限りません。生まれてからしかわからない障害もたくさんあります。ですので、決して「安心するための検査」でないことがおわかり頂けるかと思います。ご夫婦だけでなく、できれば双方のご両親も含めてよく話し合ってから、検査を受けるかどうか決めることをお勧めします。