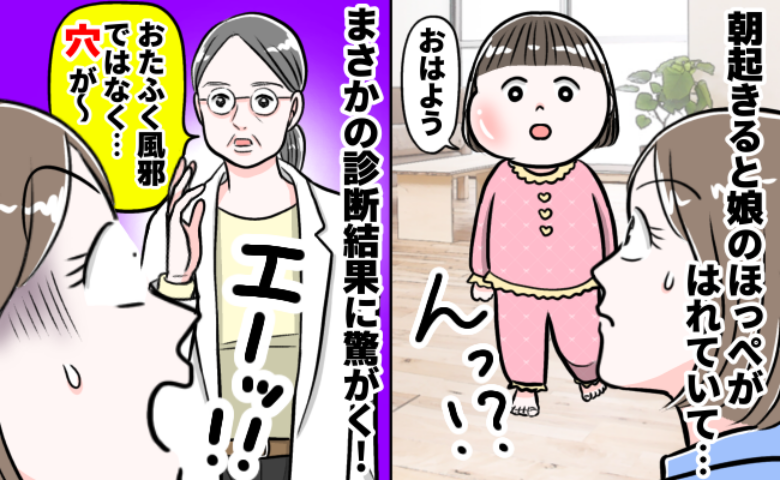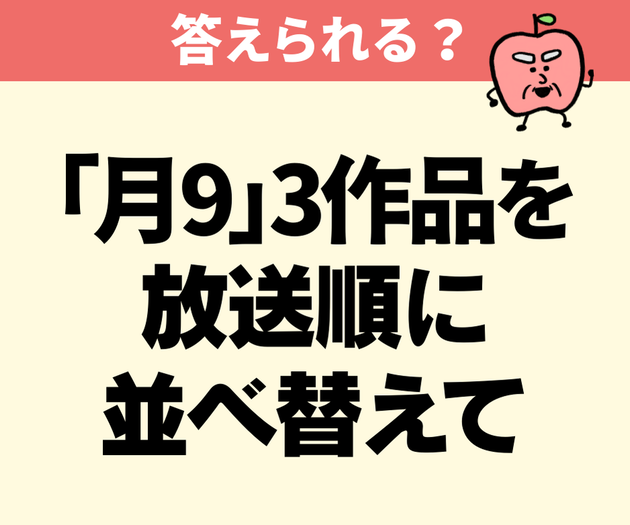政府の発表により、8月15日17時をもって「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」による特別な注意の呼びかけが終了しました。しかし、大規模地震の発生の可能性がなくなったわけではありません。気象庁は引き続き、「日頃からの地震への備え」を実施するよう呼びかけています。
地震発生時、大切なわが子を守るため、慌てず適切な対応をとれるように知っておきたいことをまとめました。
今回は、災害時に気をつけたい脱水症状についてご紹介します。
被災した場合、脱水症に注意が必要
災害時は、さまざまなストレスやトイレが整備されていないことが原因で、水分をとる量が減りがちになります。さらに、断水等によって水の供給が断たれると、飲料水や生活水が十分に確保できない状況も考えられます。
赤ちゃんは新陳代謝が活発なため、大人よりも多くの水分を必要としています。特に乳幼児は、必要な水分量や水分不足を感じにくく、発汗機能や腎機能が未発達なため、注意が必要です。
脱水症になると、おしっこの回数や量が減る・おしっこの色が濃くなる、舌・唇・口の中や皮膚が乾燥する、呼吸が速くなるなどの症状が出るほか、重症になると意識障害が起きてウトウトとしたり、けいれんを起こしたりする、唇や爪が青みがかるなど、赤ちゃんの命を脅かすような症状に発展する場合があります。
脱水は、水や電解質(体内の塩分やカリウムなどのミネラル)が汗で失われている状態でにあるため、水分だけでなくミネラルの補給も大切です。
赤ちゃんはどうしたらいいの? 基本の水分補給
■欲しがったときに母乳や育児用ミルクを
生後0〜5カ月くらいまでの水分補給は、母乳や育児用ミルクが基本です。生後6カ月以降は麦茶や湯冷ましをプラスしてもOK。母乳や育児用ミルクを欲しがったときに、与えましょう。
■暑い日はいつもより2〜3回授乳をプラス
いつもより暑い日や赤ちゃんが汗をたくさんかいているときは、2〜3回授乳を増やすと良いでしょう。タイミングは、遊んだあと、お昼寝のあと、おむつ替えのあとなどお世話の節目に与えるとスムーズに増やせます。
■回数よりも総量でチェック!
1日何回水分補給したかよりも、1日合計でどのくらい飲んでいるかが重要です。まずは、1日どのくらい飲めたかチェックしてみましょう。
■1歳を過ぎたら麦茶などを取り入れて
1歳を過ぎたら、日中は母乳や育児用ミルクより、麦茶やおやつの牛乳など他の飲み物で水分補給をします。
大人はどうしたらいいの? 脱水予防に「経口補水液」を
水分補給の際、水やお茶ばかり飲んでいると、血液が薄まり、体内の電解質の濃度が下がってしまうため、脱水症状が改善しません。水分補給の際には電解質と糖分の補給が重要です。経口補水液は、ナトリウムなどの電解質や糖分がバランスよく含まれているため、脱水状態に必要な水分と電解質を速やかに補給することができます。
災害時は感染症のリスクが高く、食事や水分摂取不足から脱水状態に陥りやすいと言われています。いざというときのために、経口補水液の作り方を覚えておきましょう。
【材料】
・水 1L
・砂糖 約40g(大さじ4 or ペットボトルのキャップ8杯)
・塩 約4g(小さじ0.5 or ペットボトルのキャップ1/3杯)
【作り方】
水に砂糖と塩を加え、よく混ぜます。
経口補水液は母乳や育児用ミルクが飲めていれば、飲用できると思われますが、赤ちゃんに飲ませる場合は医師に相談することをおすすめします。
脱水は、水分補給がうまくできないときだけでなく、過度な発汗、下痢などでも起こり得ます。赤ちゃんの衣類や掛け物を調節したり、赤ちゃんの口に入れる物を扱うときは十分に手指を消毒することが大切です。不安な症状があるときは、早めに医師や保健師などに相談しましょう。