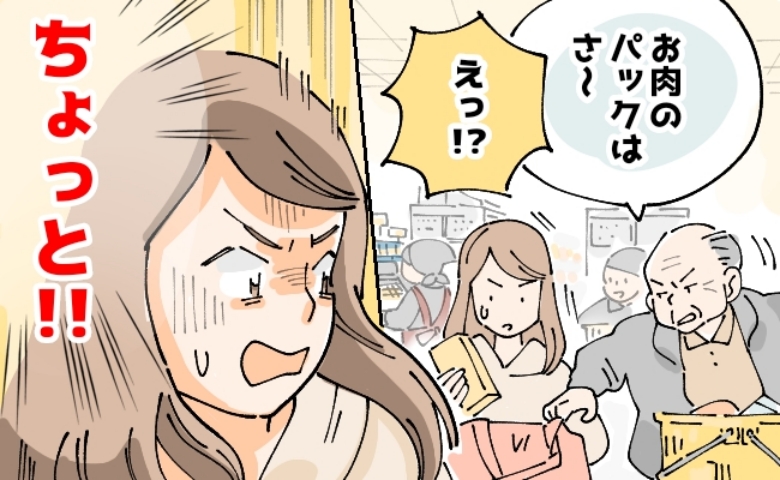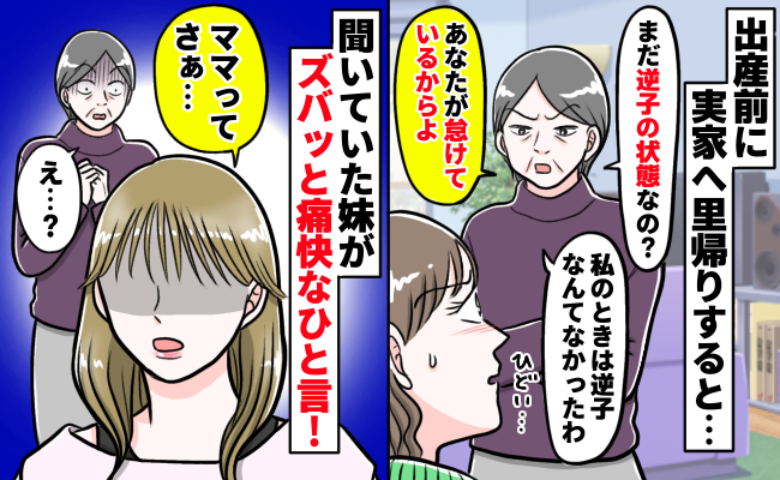こんにちは。保育士の中田馨です。子どもはいろんなものに興味を示します。誤飲や誤嚥しやすい食べ物や、何気なく口に入れてしまうものも数多くあります。
そこで今回は普段から注意しておきたい誤飲(誤嚥)しやすい「食べ物」や「身の回りにある注意しておきたいもの」についてお話しします。
普段から気をつけたい食べ物
普段から誤飲や誤嚥に気をつけたい食材はいくつかあります。
具体的には下記の食べ物に注意しておきましょう。
噛み切りにくい食べ物
肉類やれんこん、りんごなど大人でもよく噛まなければ小さくなりにくい食材は、子どもにとっては更に噛み切りにくいものです。このような食材の場合、他の食材よりも小さく刻むのはもちろん、子どもが離乳食期であれば時期に合った形状で食べさせるようにしましょう。
丸い食材
プチトマト、ぶどう、ウズラの卵、丸いチーズ、白玉団子、カップゼリー、飴などの食材は丸いので、ツルンとのどに入ってしまう恐れがあります。食べるさせる際には、1/4程度に小さくカットして食べさせるようにしましょう。
また、白玉団子などのおもちや飴を食べさせるのは幼児期後半(3歳児以降)になってからでも遅くはありません。
口の水分をとる食べ物
パン、ご飯、いも、スポンジケーキ、せんべいなどを与える場合には、1回に入れる量を小さくして与えましょう。また、水分をそばに置いて、口を潤しながら食べるのも大切ですね。
食環境にも気をつけて!
誤嚥するときの食環境についても考えましょう。例えば、寝転んだり歩いたり走ったりして食べていないか?口いっぱいに食べ物をほおばっていないか?泣いているときに口に入れていないか?なども、誤嚥しないためには大切な要素になります。
また、子どもの噛む力や飲み込む力には、その月齢や年齢、個人個人に違いがあります。お子さんの発達に合わせて食材を選んでいきたいですね。
身の回りにある誤飲に注意したいもの
その他にも、口に物を入れる時には、普段の生活の中で誤飲や誤嚥に気をつけたいものがあります。
例えば、絵本もしゃぶっているうちに紙が取れてしまうことがあります。家の中の物を仮止めしているようなテープ類も上手に剥がして口に入れることもあります。また、外では、どんぐりや小石を口にすることも。
子どもの口の大きさは直径約39mmです。これはトイレットペーパーの芯とほぼ同じ大きさと言われています。直径約39mm以下のものは、子どもの手に届く場所に置かないように大人が環境を整えることはとても重要です。
誤飲(誤嚥)してしまった時の対処法は?
子どもが物をのどに詰まらせたときの対処法には、背中をたたく(背部叩打法)や腹部突き上げ法(ハイムリッヒ法)などがあります。
具体的には、1歳未満の場合は背部を叩き、1歳以上の場合は腹部を突き上げるハイムリッヒ法で喉に詰まった異物を取り除きます。ただし、スパンコールのように薄いものが喉に貼りついてしまうと、これらの方法では取れない可能性もあります。口の中に異物が見えており取れそうな場合は手を入れて掻き出しますが、異物が見えない状態で手を入れて掻き出そうとすると、口内を傷つけたり、嘔吐を誘発したりするほか、異物を奥に押し込んでしまう可能性もあるので危険です。
もしもの時のために対処方法も一度確認しておくとよいでしょう。
※直径39mm以下(トイレットペーパーの芯を通るもの)は誤飲するおそれがあります。赤ちゃんに渡さないでください。
※赤ちゃんが遊んでいるときはママは赤ちゃんから目を離さないようにしてください。
安全に生活するには、大人のちょっとした環境づくりや配慮が欠かせません。この機会に今一度、お家の中の様子を子ども目線で確かめてみてくださいね!
参考資料:Vol.569 パン等による子どもの窒息や誤嚥(ごえん)に気を付けましょう!|消費者庁
参考資料:赤ちゃんの「誤嚥」、特に気をつけるべき食べ物とは?覚えておきたい救命救急法【3児ママ小児科医が解説】|ベビーカレンダー