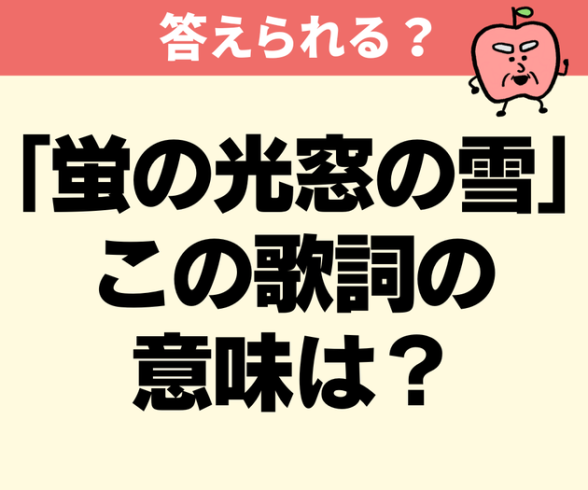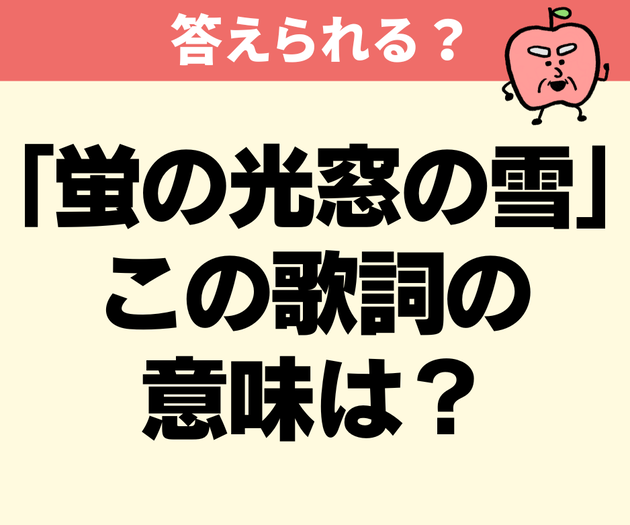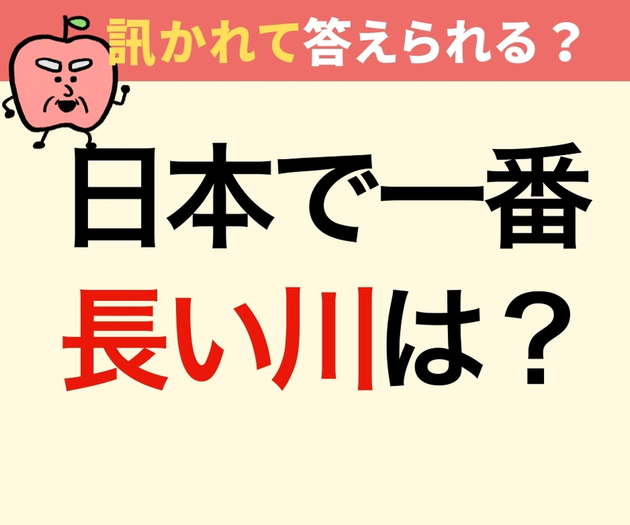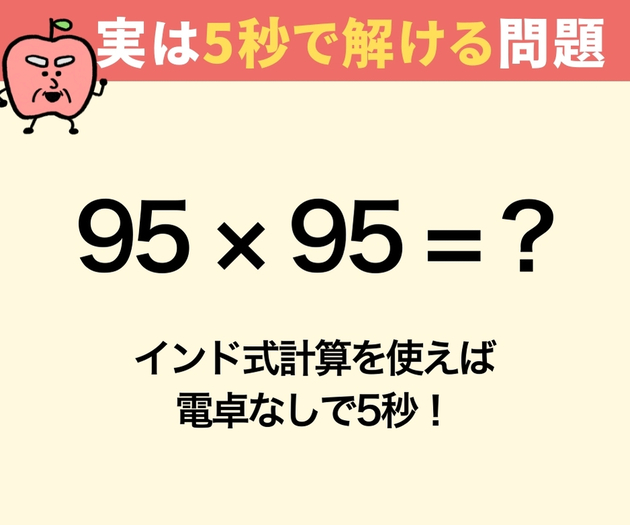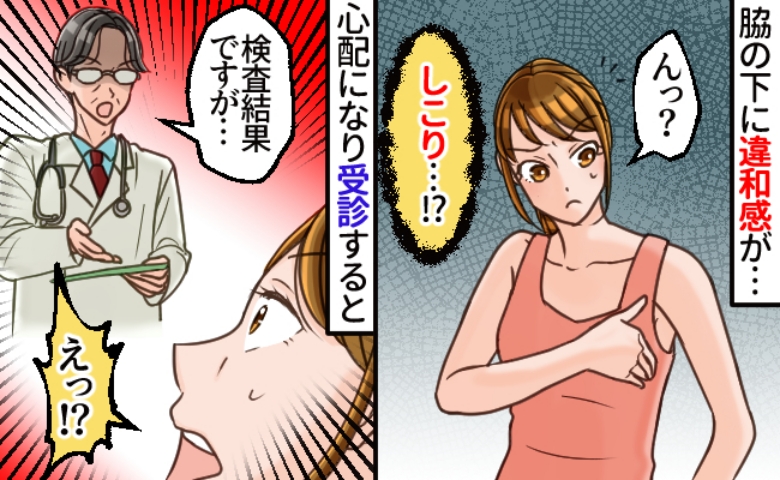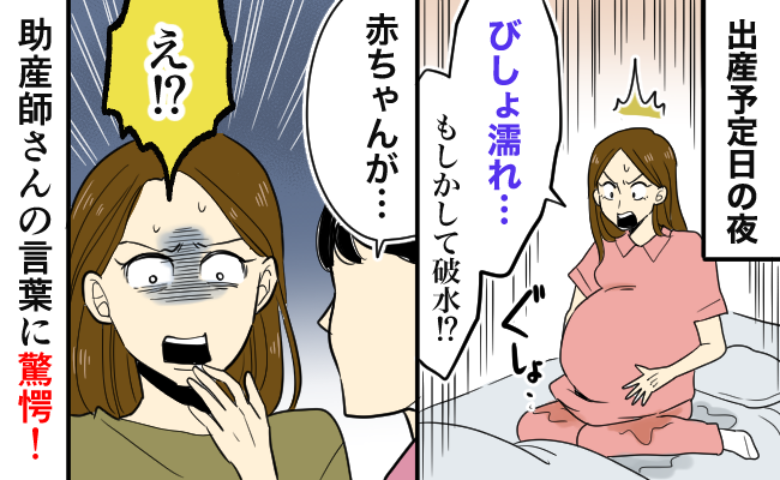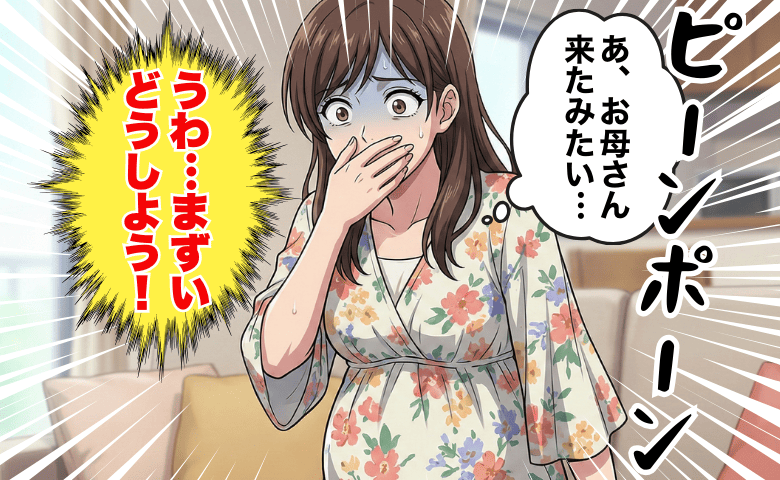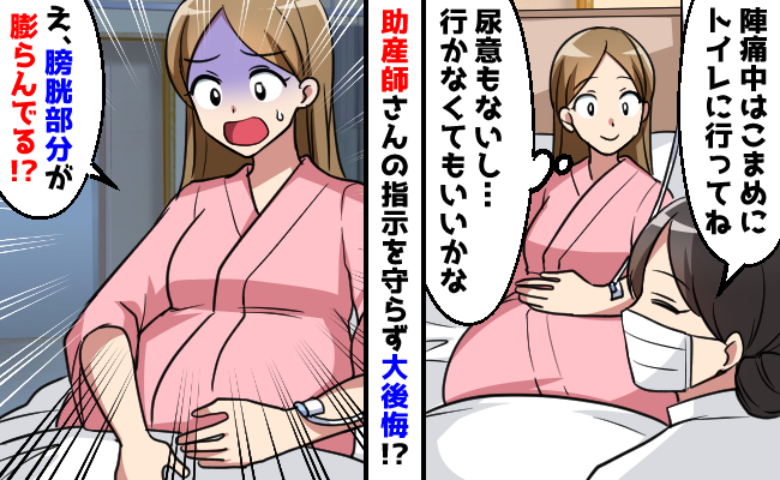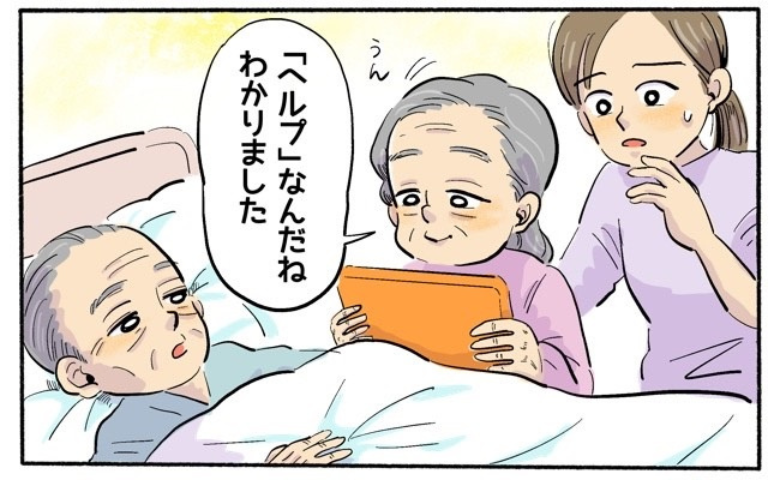そもそも「鼠径ヘルニア」ってどんな病気?

鼠径ヘルニアは、脚の付け根である鼠径部で、腸管や内臓脂肪の一部が筋膜を越えてポコッと飛び出す病気です。一般的に大きさはピンポン玉程度からソフトボール大まで、人によってさまざま。医学的病名は「鼠径ヘルニア」ですが、広く「脱腸」と呼ばれることもあります。
【鼠径ヘルニアの特徴的な症状】
- 鼠径部(脚の付け根)に膨らみができる
- 立ち上がったりおなかに力を入れたりすると膨らみが目立つ
- 横たわったり手で押さえたりすると消えることがある
- 鼠径部に突っ張るような違和感や不快感、痛みを感じる
特に、肥満の方は皮下脂肪で膨らみが目立たないことがあるため、違和感がある部分を触ってみないと気づかないことも。鼠径部に違和感があるけれど膨らみがない場合も注意が必要です。
鼠径ヘルニアの種類と原因
ここからは、鼠径ヘルニアの仕組みや種類、原因について解説します。
鼠径ヘルニアのしくみ

おなかの形は筋肉が内臓を支えることで保たれています。しかしながら、鼠径部は筋肉がないため代わりに筋膜が手助けしています。そのため、腹圧がかかって筋膜に負荷がかかり緩んでしまうと、筋肉と筋肉の間から内臓が飛び出てしまい、鼠径ヘルニアになってしまうのです。これが、筋トレでは鼠径ヘルニアを予防できない理由でもあります。
主なヘルニアの種類
- 外鼠径ヘルニア(がいそけいヘルニア):典型的なタイプ。小児・成人がなりやすい。
- 内鼠径ヘルニア(ないそけいヘルニア):特に中高年の男性は加齢や前立腺肥大などに伴う腹圧上昇の機会が多く、この部位の支持組織が弱りやすいため女性よりも発症しやすい。加齢などにより筋膜が緩み、内臓を支えきれずに飛び出してしまう。
- 大腿ヘルニア(だいたいヘルニア):骨盤の構造的特性や大腿管周囲の組織の弱さなどが原因で、中高年の女性が発症しやすい。嵌頓*を起こしやすいため、早期治療が推奨される。
*嵌頓(かんとん)……腸が詰まって血流不全を起こすこと。重症化すると患部が壊死してしまうため、緊急手術が必要となることも。
鼠径ヘルニアの原因
鼠径ヘルニアは、先天性と後天性の2つに分けられます。
先天性の鼠径ヘルニアは子どもに多く見られ、胎児のときに自然と閉じるはずだった腹膜の穴が開いたまま残ってしまうことで発症。後天性は、加齢や生活習慣、健康状態、妊娠などが原因です。
こんな方は要注意! 鼠径ヘルニアになりやすいのは?
50歳以上から多く見られやすく、男性の3人に1人が経験するといわれる鼠径ヘルニア。シニア世代が注目すべき病気の1つですが、普段の生活サイクルが発症の原因となってしまうケースもいくつかあります。以下のケースに当てはまる人は注意しましょう。
| 具体例 | リスク要因 | |
| ケース1 |
長年、仕事で重い資材を持ち上げる機会が多い(現場作業、肉体労働を伴う職業の方) |
合計で1日4トン以上の重さを上げ下げすること |
| ケース2 |
立ち仕事に従事している(理美容師、飲食関係の職業の方) |
1日6時間以上の立ち仕事 |
| ケース3 | 便秘がち・排便時に力むことが多い | 慢性的に腹圧をかけるタイミングがある |
よくある質問と誤解Q&A~基本編~
Q1.脱腸は、女性はあまり発症しないですか?
A.鼠径ヘルニアの罹患割合は女性:男性=1:8程度ですが、女性でも出産を経験した方や立ち仕事が多い方は注意が必要です。
Q2.脱腸はただ膨らむだけだから放っておいても大丈夫ですか?
A.鼠径ヘルニアを放置していると膨らみが大きくなり、嵌頓のリスクが高まります。嵌頓になると激しい痛みや吐き気、嘔吐などの症状があらわれるほか、腸が戻らなくなって8時間が経過すると壊死し始めます。気づいた段階で早めに治療してしまうのがおすすめです。
Q3.脱腸を自分で治すことはできますか?
A.鼠径ヘルニアは一度発症してしまうと、一時的に進行速度を緩めることはできても自然に治ることはなく、手術するしかありません。鼠径ヘルニアの手術は外科手術ですが、入院なしで日帰り手術をおこなうクリニックもあります。ライフスタイルに合った方法を医師と相談してみましょう。
Q4.脱腸のような膨らみはないのですが、脚の付け根に痛みや違和感があります。
A.膨らみに気づきにくい場合もあるほか、別の病気であるケースもあります。CT検査や腹部超音波検査などで診断できるので、一度医療機関に相談しましょう。
Q5.筋トレすれば脱腸が起こるリスクを抑えられますか?
A.鼠径ヘルニアは筋トレや体操で予防することはできません。筋膜は鍛えることができず、筋トレで過度な腹圧をかけると逆に鼠径ヘルニア発症のリスクが高まることもあります。
Q6.脱腸の原因にストレスは関係ありますか?
A.鼠径ヘルニアの原因に精神的ストレスが関係しているというエビデンスは今のところありません。
鼠径ヘルニアの予防法と受診のタイミング

鼠径ヘルニアはいつ発症するか予測ができず、予防することも困難です。しかし、生活習慣を改めることで筋膜が伸びたり緩んだりしにくくすることはできます。ここからは、普段の生活の中で意識できる予防方法と、軽度の段階で気づくためのポイントをご紹介します。
生活習慣で予防するポイント
- 過度な力を入れないように腹圧管理をする
- 適正体重(BMI20前後)を保つ
- 一度に食べ過ぎない、食物繊維を含む食品を意識して摂取するなどで便秘を予防する
- 体重管理のために適度な運動をする
- たばこを吸わない
腹圧をかけ過ぎない生活を意識することで、筋膜への過度な負担を予防できます。まずは身近なところから取り組んでみましょう。
鼠径ヘルニアに軽度で気づくための3つのポイント
- 脚の付け根(鼠径部)に膨らみができていないか定期的に確認
お風呂場の鏡などを利用し、定期的に確認する習慣をつけましょう。特に、40代以上の男性は、鼠径部の状態をこまめにチェックし、普段から異変に気づきやすい状態にしておくのがおすすめです。
- 姿勢を変えたときの変化を観察
立ち上がる、重たいものを持ち上げる、横になるなどの動作で、膨らみが出たり消えたりするか観察してみましょう。
- 違和感を見逃さない
痛みがない場合も、鼠径部に違和感や突っ張るような感覚がある場合は医療機関を受診しましょう。鼠径ヘルニアではない可能性もあります。
まとめ
鼠径ヘルニアは、予防は難しいものの、腹圧をかけ過ぎない生活習慣を意識し、日常的なチェックで早期発見を心がけることが重要です。鼠径部に違和感があれば放置せず、医療機関で診察を受けましょう。適切な治療を受けることで、日常生活への影響を最小限に抑えることが可能です。健康的な生活を維持するためにも、正しい知識を持って備えましょう。
※記事の内容は公開当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。
取材・文:原のどか/お父さんラブな甘えん坊男児を育てる転勤族ライター。趣味の「神社仏閣でおみくじを引く」を楽しみに、行く先々で家族を連れまわして開拓中。「育児も人生もなんとかなる!」をモットーに、困ったことも楽しみながら情報を発信していきます!
シニアカレンダー編集部では、自宅介護や老々介護、みとりなど介護に関わる人やシニア世代のお悩みを解決する記事を配信中。介護者やシニア世代の毎日がハッピーになりますように!
シニアカレンダー編集部
「人生100年時代」を、自分らしく元気に過ごしたいと願うシニア世代に有益な情報を提供していきます!