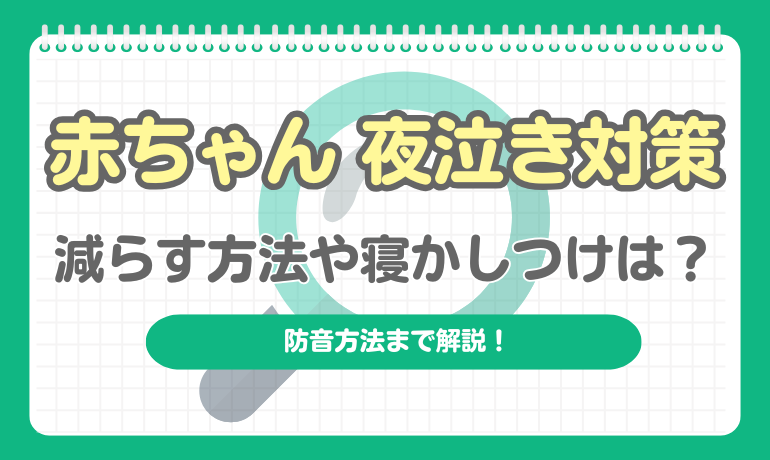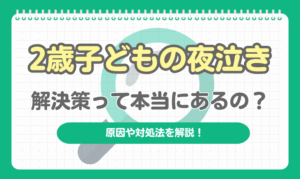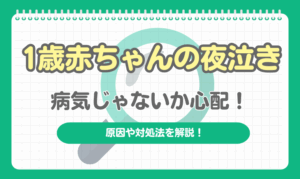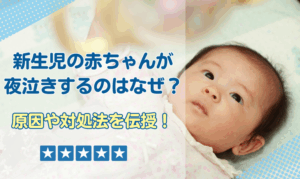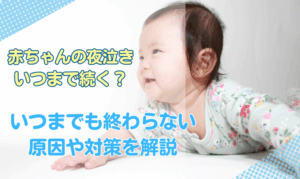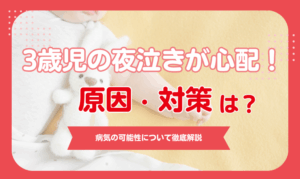「またこの時間…」「どうして泣き止んでくれないの…」
赤ちゃんの夜泣きが続くと、ママもパパも心身ともに疲れ果ててしまいますよね。睡眠不足で日中の家事や仕事に集中できず、精神的にも追い詰められてしまうこともあるでしょう。
しかし、安心してください。夜泣きは多くの赤ちゃんが経験する成長過程の一つであり、決してママやパパの育て方が悪いわけではありません。そして、適切な対策をとることで、夜泣きを減らしたり、上手に対応したりすることは可能です。
この記事では、夜泣きに悩むママ・パパのために、以下の内容を詳しく解説します。
- 夜泣きを未然に防ぐための基本的な対策
- 夜泣きで起きてしまったときの上手な寝かしつけ方法
- ついやってしまいがちだけど、避けるべきNG対応
- 【新生児・6カ月・1歳・2歳など】月齢別の原因と対策
- ご近所への影響が気になるときの防音対策
この記事を読めば、赤ちゃんの夜泣きに対する不安が和らぎ、今日から実践できる具体的なヒントが見つかるはずです。辛い夜を乗り越え、親子で穏やかな夜を取り戻すために、ぜひ最後までご覧ください。
赤ちゃんの夜泣きを減らそう!基本の対策6つ
まずは、夜泣きそのものを減らすための「予防策」から見ていきましょう。日中の過ごし方や寝る前の環境を少し見直すだけで、赤ちゃんの眠りの質は大きく変わります。
生活リズムを整える
赤ちゃんが夜にぐっすり眠るためには、毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるという生活リズムを整えることが最も重要です。
生まれたばかりの赤ちゃんは昼夜の区別がついていませんが、生後3〜4カ月頃から徐々に体内時計が整い始めます。この時期に意識して生活リズムを作ってあげることで、「夜は眠る時間」ということを赤ちゃんが体で覚えていきます。
【具体的な方法】
- 起床時間: 毎朝7時までにはカーテンを開けて部屋を明るくし、赤ちゃんを起こしましょう。
- 昼寝の時間: 昼寝が長すぎると夜の睡眠に影響します。月齢に合わせた適切な昼寝時間を意識し、夕方以降は寝かせすぎないように注意しましょう。
- 就寝時間: 夜は19時〜20時頃には寝室へ行き、眠る準備を始めるのが理想です。
毎日きっちり同じ時間でなくても構いません。「朝は明るくなったら起き、夜は暗くなったら眠る」という基本的なサイクルを意識することが、赤ちゃんの体内時計を整える第一歩です。
日の光を浴びる
生活リズムを整える上で欠かせないのが「朝日を浴びること」です。
人間の体は、朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が調整されるようにできています。朝、光を浴びてから約14〜16時間後にメラトニンの分泌が活発になり、自然な眠気が訪れます。
つまり、朝にしっかりと太陽の光を浴びさせてあげることが、夜の快眠に直接繋がるのです。
【具体的な方法】
- 天気の良い日は、午前中に5〜15分程度、お散歩やベランダでの外気浴を取り入れましょう。
- 雨の日や外出が難しい日でも、窓際で外の光を浴びるだけでも効果があります。
日中の適度な疲れも、夜の深い眠りを誘います。お散歩は赤ちゃんにとって良い刺激になり、気分転換にもなるのでおすすめです。
入眠前のルーティンを決める
「これをしたら、おやすみの時間」という入眠儀式(スリープトラッド)を作ることで、赤ちゃんは心の準備ができ、スムーズに眠りに入りやすくなります。
毎日寝る前に同じ行動を繰り返すことで、赤ちゃんの中に「これが終わったら眠るんだ」という条件付けができあがります。興奮した気持ちを落ち着かせ、リラックスさせる効果も期待できます。
【おすすめの入眠ルーティン】
- お風呂に入る
- パジャマに着替える
- 寝室の照明を暗くする
- 絵本を1冊読む
- 子守唄を歌う
- 背中を優しくマッサージする
- 「おやすみ」のキスをする
ポイントは、静かで落ち着いた内容であること。テレビやスマートフォンなどの強い光や音は脳を興奮させてしまうため、寝る1〜2時間前には消すようにしましょう。時間は5分〜15分程度で構いませんので、毎日続けられる簡単なものがおすすめです。
抱っこではなく布団の上で寝かしつける
「抱っこじゃないと寝てくれない」「布団に置いた瞬間に泣き出す(背中スイッチ)」という悩みは非常に多いですが、できるだけ「眠りにつく瞬間は布団の上」という習慣をつけることを目指してみましょう。
抱っこで寝かしつけるのが癖になると、夜中に目が覚めたときにも「抱っこされていないと眠れない」と泣いてしまう原因になります。赤ちゃんが自力で眠りに入る力を育てるためには、眠くてうとうとしてきたタイミングで布団に寝かせ、トントンなどで寝かしつけてあげるのが理想です。
もちろん、月齢が低い時期や、どうしても寝てくれないときは抱っこで安心させてあげることも大切です。しかし、「寝かしつけ=布団の上」を基本のスタイルとして意識しておくと、後々の夜泣き対策が楽になります。
睡眠環境を整える
大人でも、寝室が暑かったり明るかったりすると寝苦しいですよね。赤ちゃんは大人以上に敏感なので、快適な睡眠環境を整えてあげることが非常に重要です。
【チェックしたいポイント】
- 明るさ: 豆電球も消し、できるだけ真っ暗にするのが理想です。光はメラトニンの分泌を妨げ、眠りを浅くしてしまいます。遮光カーテンなどを活用しましょう。
- 温度・湿度: 赤ちゃんが快適に感じる室温は、夏場は25〜27℃、冬場は20〜22℃が目安です。湿度は年間を通して50〜60%を保つように、エアコンや加湿器・除湿機で調整しましょう。汗をかいていないか、手足が冷たすぎないか、赤ちゃんの様子をこまめにチェックしてください。
- 音: 生活音が気になる場合は、換気扇の音やホワイトノイズマシンなど、単調な音を流すと赤ちゃんが安心して眠れることがあります。これは、ママのお腹の中にいたときの音(胎内音)に似ているためと言われています。
- 服装・寝具: 汗を吸いやすく、肌触りの良い素材のパジャマを選びましょう。寝冷えが心配な場合は、スリーパーを着せるのがおすすめです。窒息の危険があるため、顔の周りにはぬいぐるみやタオルなどを置かないようにしてください。
離乳食の内容を見直す
離乳食が始まると、その内容が夜泣きの原因になることもあります。
特に、夕食の時間が遅かったり、消化に悪いものを食べたりすると、寝ている間も胃腸が働き続けることになり、眠りが浅くなる可能性があります。
【見直したいポイント】
- 夕食の時間: 就寝の2〜3時間前までには済ませるようにしましょう。
- メニュー: 脂っこいものや繊維質の多いもの、初めて食べる食材などは避け、おかゆやうどん、豆腐、白身魚など、消化の良いものを中心にしましょう。
- 鉄分不足: 生後6カ月を過ぎると、ママからもらった鉄分が不足しがちになります。鉄分が不足すると、睡眠が不安定になることがあると言われています。レバーや赤身の魚、ほうれん草など、鉄分が豊富な食材を意識的に取り入れてみましょう。
もし、特定の食材を食べさせた日に夜泣きがひどくなるようであれば、アレルギーの可能性も考えられます。気になる場合はかかりつけの小児科医に相談してください。
上手に寝かしつけよう!夜泣きで目が覚めたときの対策8つ
どんなに予防策を徹底しても、赤ちゃんが夜中に泣いて起きてしまうことはあります。そんなとき、どう対応すればスムーズに寝かしつけられるのでしょうか。慌てず冷静に対処するための8つのステップをご紹介します。
おむつや体温などを確かめる
赤ちゃんが泣いているのには、必ず理由があります。まずは、身体的な不快感がないかを確認しましょう。
- おむつは濡れていないか?
- 汗をかきすぎていないか?(暑すぎないか?)
- 手足が冷たくなっていないか?(寒すぎないか?)
- 鼻が詰まっていないか?
- 服のタグや縫い目がチクチクしていないか?
- 熱はないか?(体調は悪くないか?)
これらの不快感を取り除いてあげるだけで、すんなり泣き止んでくれることも少なくありません。夜中に対応しやすいように、おむつや着替えは枕元に準備しておくとスムーズです。
すぐに抱き上げずに様子を見る
ふえ〜んと泣き声が聞こえると、すぐに抱き上げてあげたくなりますが、まずは2〜3分ほど、慌てずに様子を見てみましょう。
赤ちゃんは眠りが浅いときに、寝ぼけて泣く「寝言泣き」をしている場合があります。このとき、すぐに抱き上げたり声をかけたりすると、かえって完全に覚醒させてしまうことがあります。少し様子を見ていると、自分でまた眠りに入っていくことも多いのです。
もちろん、火がついたように激しく泣いている場合は、すぐに次のステップに進んでください。
背中をさすったり優しく声をかけるスキンシップ
すぐに抱き上げるのではなく、まずは布団に寝かせたままスキンシップを試してみましょう。
- 背中やおしりを優しくトントンする
- 胸にそっと手を置く
- 眉間や頭を優しくなでる
- 「大丈夫だよ」「ママ(パパ)はここにいるよ」と静かな声で話しかける
ママやパパの温もりや優しい声は、赤ちゃんにとって何よりの安心材料です。この段階で落ち着きを取り戻し、再び眠ってくれることもよくあります。
赤ちゃんが落ち着く音を流す
スキンシップでも泣き止まないときは、赤ちゃんが安心する音を聞かせてあげるのも効果的です。
前述したホワイトノイズ(テレビの砂嵐のような「ザー」という音、換気扇や空気清浄機の音など)や、ビニール袋をカシャカシャとこする音は、ママの胎内で聞いていた音に似ているため、赤ちゃんをリラックスさせる効果があると言われています。
スマートフォンのアプリなどでも手軽に流せるので、試してみる価値はあります。
それでもだめなら抱っこする
何をしても泣き止まない場合は、我慢せずに抱っこしてあげましょう。赤ちゃんはただただ、ママやパパに抱きしめてほしくて泣いているのかもしれません。
【抱っこのポイント】
- 密着感を大切に: 赤ちゃんのお腹とママ・パパのお腹をぴったりとくっつけるように抱っこすると、安心感が増します。
- 優しく揺れる: その場でゆっくりとスクワットをしたり、バランスボールに座って軽く弾んだり、単調なリズムで揺れると落ち着きやすいです。
- 体勢を変えてみる: 横抱きでダメなら縦抱きに、それでもダメならゲップをさせるときの体勢にしてみるなど、赤ちゃんが心地よいと感じるポジションを探してみましょう。
抱っこで落ち着いたら、完全に寝入る前に布団に戻すのが理想ですが、まずは赤ちゃんを安心させてあげることを最優先に考えましょう。
一度完全に起こしてしまう
色々な方法を試しても30分以上激しく泣き続ける場合は、一度部屋を明るくして、完全に起こしてしまうというのも一つの手です。
リビングに移動して水分補給をさせたり、おもちゃで少しだけ遊ばせたりして、気分転換を図ります。赤ちゃんも泣き疲れて興奮状態になっていることがあるため、一度リセットしてあげるのです。
ただし、これはあくまで最終手段です。「夜中に起きても良い」という習慣がついてしまう可能性があるため、頻繁に行うのは避けましょう。5〜10分程度で切り上げ、再び寝室に戻って寝かしつけを再チャレンジしてみてください。
夜泣き対策グッズを使う
世の中には、夜泣きに悩む親子のための便利なグッズがたくさんあります。上手に活用することで、寝かしつけがぐっと楽になるかもしれません。
- おくるみ・スワドル: 赤ちゃんの体を優しく包み込むことで、ママのお腹の中にいたときのような安心感を与えます。手足が動いて起きてしまう「モロー反射」を防ぐ効果も期待できます。
- スリーパー: 寝ている間に布団を蹴飛ばしてしまう赤ちゃんの寝冷えを防ぎます。
- 寝かしつけ用プロジェクター: 天井に優しい光と映像を映し出し、リラックス効果のあるメロディーを流して、赤ちゃんの眠りを誘います。
- ホワイトノイズマシン: 赤ちゃんが安心する様々な音を流せる専用の機械です。
色々なグッズがあるので、ご自身の赤ちゃんに合いそうなものを試してみてはいかがでしょうか。
ママだけでなくパパも協力して乗り切る
夜泣き対応で最も大切なことの一つが、「ママ一人で抱え込まない」ということです。
夜泣きが続くと、対応するママは深刻な睡眠不足に陥り、心身ともに疲弊してしまいます。産後うつや育児ノイローゼの原因になることもあり、決して一人で頑張りすぎてはいけません。
【パパができること】
- 夜泣き対応を交代する: 「月・水・金はパパ、火・木・土はママ」のように曜日で分担したり、「夜中の2時まではママ、それ以降はパパ」と時間で区切ったりするなど、ルールを決めましょう。
- 授乳以外のすべてを担当する: ミルクであればパパも授乳できますし、母乳の場合でも、おむつ替え、抱っこ、寝かしつけなど、パパができることはたくさんあります。
- ママを休ませる: 週末の昼間などにパパが赤ちゃんの面倒を見て、ママが一人で外出したり、数時間でもまとまって眠ったりする時間を作りましょう。
夫婦で夜泣きの辛さを共有し、チームとして乗り越える体制を築くことが、この困難な時期を乗り切るための鍵となります。
辛くてもやってはいけない夜泣き対策4つ
夜泣きが続くと、精神的に追い詰められて「もうどうしていいか分からない!」と感じることもあるでしょう。しかし、そんなときでも絶対にやってはいけないNG対応があります。
泣き止まないのにずっと放置する
「泣き癖がつくから放置した方がいい」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは誤解です。赤ちゃんが助けを求めて泣いているのに長時間放置すると、赤ちゃんは「泣いても誰も助けてくれない」という無力感や不安感を抱き、心身の発達に悪影響を及ぼす可能性があります。
前述した「寝言泣きか見極めるために2〜3分様子を見る」ことと、「助けを求めているのに無視し続ける」ことは全く違います。赤ちゃんのサインに応え、安心感を与えてあげることが、親子の信頼関係を築く上で非常に重要です。
泣き止むからと授乳する
赤ちゃんが泣くと、ついおっぱいやミルクをあげてしまうというママは多いかもしれません。確かに授乳には赤ちゃんを落ち着かせる効果がありますが、空腹以外の理由で泣いているときに毎回授乳で対応するのは避けましょう。
これを繰り返すと、「夜中に目が覚めたらおっぱい(ミルク)をもらう」という癖がついてしまい、かえって夜中に何度も起きる原因になってしまいます。まずは授乳以外の方法(おむつチェック、抱っこなど)を試し、それでも泣き止まず、前回の授乳から時間が空いている場合にのみ、授乳を検討しましょう。
揺さぶったり口をふさぐ
これは言うまでもありませんが、絶対にやってはいけません。
イライラして赤ちゃんを激しく揺さぶると、「揺さぶられっ子症候群(SBS)」を引き起こし、脳に深刻なダメージを与え、重い障害が残ったり、最悪の場合死に至ることもあります。また、泣き声を聞きたくないからと口をふさぐ行為は窒息の危険があり、虐待です。
もし、カッとなって手を出しそうになったら、すぐに赤ちゃんを安全な場所(ベビーベッドなど)に寝かせ、一旦その場を離れて深呼吸をしてください。パートナーや家族に助けを求めたり、公的な相談窓口に電話したりすることもためらわないでください。
寝かしつけ方法をコロコロ変える
「今日はこの方法、明日はあの方法」というように、寝かしつけの方法を一貫性なく変えてしまうと、赤ちゃんは何をすれば眠れるのか分からず、混乱してしまいます。
効果が出るまでには少し時間がかかることもあります。入眠前のルーティンや寝かしつけ方法は、少なくとも1〜2週間は同じ方法を続けてみることが大切です。赤ちゃんが安心して眠りの習慣を身につけられるよう、一貫した対応を心がけましょう。
月齢別:夜泣きの原因と対策
赤ちゃんの夜泣きは、その成長段階と深く関係しています。ここでは、月齢ごとの主な原因と効果的な対策を見ていきましょう。
新生児(生後0カ月〜1カ月)の夜泣き
- 原因: この時期の夜泣きは、まだ昼夜の区別がついていないことが最大の原因です。お腹が空いた、おむつが気持ち悪い、暑い・寒いといった生理的な欲求を泣いて知らせています。
- 対策: 赤ちゃんが泣いたら、まずはお腹が空いていないか、おむつは汚れていないかを確認しましょう。授乳やミルク、おむつ替えといった基本的なお世話で対応するのが中心になります。部屋の温度や服装も快適かチェックしてあげてください。
6カ月・7カ月の夜泣き
- 原因: 生後半年頃になると、寝返り、おすわり、ずりばいなど、運動機能が急激に発達します。日中にできることが増え、脳が興奮して夜中に目が覚めやすくなります。また、夜間の授乳が癖になっていることも原因の一つです。
- 対策: 日中にたくさん体を動かして遊ばせ、適度に疲れさせてあげましょう。寝る前はテレビなどを消し、絵本を読むなど静かな遊びに切り替えて、脳の興奮を鎮めることが大切です。夜間の授乳回数を少しずつ減らしていく「卒乳・断乳」を考え始めるのもこの時期です。
1歳の夜泣き
- 原因: つかまり立ちや伝い歩き、あんよが始まり、さらに活動的になります。自我が芽生え始め、ママやパパに甘えたい、構ってほしいという気持ちから夜泣きをすることもあります。また、保育園に入園するなど、生活環境の変化が影響することもあります。
- 対策: 日中は赤ちゃんの好奇心を満たすような遊びをたくさん取り入れましょう。夜は寝る前に抱きしめるなど、たっぷりとスキンシップをとって安心させてあげることが効果的です。環境の変化があった場合は、赤ちゃんが新しい生活に慣れるまで、焦らずに見守ってあげてください。
1歳半の夜泣き
- 原因: 記憶力が発達し、日中に経験した怖いことや嫌だったことを夢に見る「悪夢」が原因で泣き出すことがあります。また、ママの姿が見えないと不安になる「分離不安」が強まる時期でもあります。
- 対策: 泣いて起きたら、「大丈夫だよ」「怖い夢見たの?」などと優しく声をかけ、抱きしめて安心させてあげましょう。日中、ママと離れることに不安を感じているようなら、「必ず帰ってくるよ」と伝え、戻ってきたときにはたくさん褒めてあげるなど、安心感を育む関わりが大切です。
2歳の夜泣き
- 原因: いわゆる「イヤイヤ期」に突入し、自分の思い通りにならない感情をうまく言葉で表現できず、かんしゃくを起こして夜泣きに繋がることがあります。昼間の興奮や疲れ、怖い夢なども引き続き原因となります。
- 対策: なぜ泣いているのか、理由を優しく聞いてあげましょう。うまく答えられなくても、「これが嫌だったんだね」と気持ちを代弁し、共感してあげることが大切です。日中の生活リズムを見直し、昼寝をしすぎていないか、夕食後に興奮するような遊びをしていないかなどをチェックしてみましょう。
夜泣きの声が気になるときの防音対策
マンションやアパートなどの集合住宅では、赤ちゃんの夜泣きの声がご近所の迷惑になっていないか、気になってしまいますよね。そのストレスが、さらなる寝かしつけのプレッシャーになることも。ここでは、夜泣きの声が気になるときの防音対策をご紹介します。
1. 家具の配置を工夫する
最も手軽にできる対策は、家具の配置を変えることです。
- 窓際に背の高い家具を置く: 窓は音が漏れやすい場所です。本棚やタンスなど、背の高い家具を窓際に置くことで、音を遮る壁の役割を果たしてくれます。
- 隣の家との壁際に家具を置く: 隣接する部屋の壁側に家具を置くことでも、音が伝わるのを軽減できます。
- ベビーベッドを壁から離す: 赤ちゃんが寝る場所は、できるだけ部屋の中央や、隣の家と接していない壁際に移動させましょう。
2. 防音グッズを活用する
市販の防音グッズを取り入れるのも効果的です。
- 防音カーテン: 通常のカーテンよりも厚手で、音を吸収・遮断する効果が高いです。外からの音を防ぐ効果もあるため、赤ちゃんがより静かな環境で眠れるというメリットもあります。
- 防音・吸音シート/パネル: 壁に貼り付けるタイプのものです。赤ちゃんの泣き声が響きやすい壁に設置すると効果的です。デザイン性の高いものも販売されています。
- 窓用の隙間テープ: 窓のサッシに貼ることで気密性を高め、隙間からの音漏れを防ぎます。
3. 近隣住民への声かけとコミュニケーション
物理的な対策と同じくらい、あるいはそれ以上に大切なのが、ご近所とのコミュニケーションです。
赤ちゃんが生まれる前や、引っ越しの挨拶の際に、「赤ちゃんがいるので、泣き声でご迷惑をおかけするかもしれませんが、申し訳ありません」と一言伝えておくだけで、相手の心象は大きく変わります。
また、日頃からエレベーターや廊下で会ったときに「いつもお騒がせしてすみません」「こんにちは」と挨拶を交わすなど、良好な関係を築いておくことも重要です。多くの人は、事情が分かっていれば「お互い様」と理解を示してくれるものです。
夜泣きでパニックになっているときに、ご近所への迷惑まで考えてしまうと、ママやパパの精神的な負担は計り知れません。事前にできる対策をしておくことで、少しでも心に余裕を持つことができます。
まとめ:夜泣きは必ず終わります。一人で抱え込まず、頼ることを忘れないで
今回は、赤ちゃんの夜泣きを減らすための基本的な対策から、実際に起きてしまったときの上手な寝かしつけ方法、月齢別の原因と対策、そして防音対策まで、幅広く解説しました。
【夜泣き対策の重要ポイント】
- 予防: 生活リズムを整え、快適な睡眠環境を作ることが基本。
- 対処: まずは不快感を取り除き、スキンシップで安心させる。
- 協力: ママ一人で頑張らず、パパとチームで乗り越える。
- 知識: 月齢ごとの原因を知り、成長に合わせた対応を心がける。
夜泣きの真っ只中にいると、この辛い夜が永遠に続くように感じてしまうかもしれません。しかし、赤ちゃんの夜泣きには必ず終わりが来ます。成長とともに、朝までぐっすり眠ってくれる日は必ずやってきます。
今、あなたがすべきことは、完璧な対策をすることではありません。色々な方法を試しながら、ご自身の赤ちゃんとご家庭に合ったやり方を見つけていくことです。そして何より、ママ・パパ自身が休息をとり、心と体の健康を保つことです。
辛いとき、しんどいときは、パートナーや家族、友人、そして地域の相談窓口など、周りの人を頼ってください。一人で抱え込まず、上手に周りのサポートを活用しながら、この時期を乗り越えていきましょう。