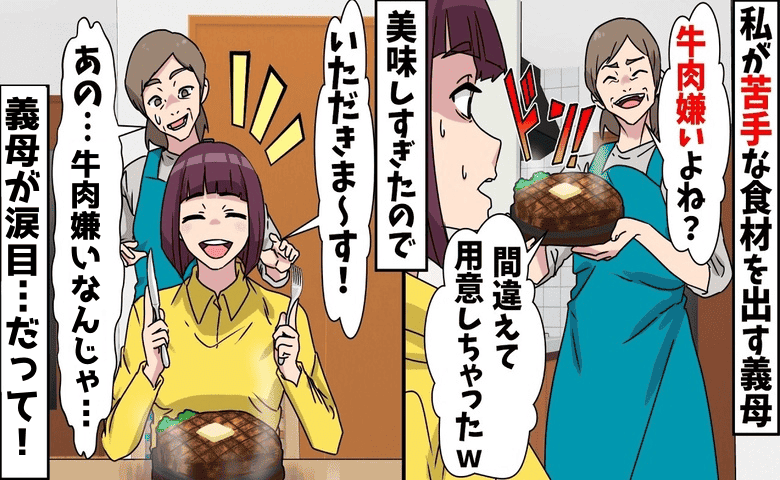過酷だった伯母夫婦との生活
私と妹は、私が中学3年生のときにシングルマザーだった母を病気で亡くしています。その後、母の姉にあたる伯母夫婦に引き取られたのですが、そこでの生活は過酷なものでした。
私たちが引き取られた背景には、母が残したお金を“管理する立場”を得たいという伯母夫婦の思惑もあったように思います。必要以上に厳しい生活を強いられ、私たちのためのお金がどのように使われていたのかはわかりません。
私たち兄妹に最低限の衣食住を与えてくれたことには感謝していますが、親のような愛情を注いでくれることはありませんでした。
「お兄ちゃん、早くここから出たいね」
そう泣いていた妹は、高校を卒業するとすぐに「同級生の彼と結婚したい」と言い出しました。しかし、伯母たちは「世間体が悪い」「まだ早い」と猛反対。結局、妹は駆け落ち同然で家を飛び出し、結婚したのです。
その後、妹夫婦には娘(私にとっての姪)が生まれました。私は伯母夫婦には内緒で、妹一家と時折会い、ささやかな交流を続けていました。
しかし、突然の訃報がすべてを打ち砕きました。地獄のような家で支え合った戦友であり、唯一の家族だった妹と、妹を大切にしてくれた義弟。深い絶望に襲われましたが、遺された姪のためにも、私はなんとか自分を奮い立たせて葬儀の日を迎えました。
妹夫婦の葬儀で始まった「姪の押し付け合い」
妹夫婦の葬儀の日、遺された姪はまだ7歳でした。両親を一度に失い、小さな体で震えている姪。しかし、親族たちの関心は「誰がこの子を引き取るか」という厄介ごとの押し付け合いに向けられていました。
「うちは無理よ、受験生がいるし」
「男の子ならまだしも、女の子はねぇ」
「そもそも、勝手に家を出て行った子の娘じゃない。迷惑よ!」
「施設に入れるしかないんじゃない?」
親族たちは姪の目の前で、平然とそんな言葉を吐き捨てます。姪は俯き、必死に涙をこらえていました。その姿が、かつて両親を亡くして絶望していた幼いころの自分と重なり、胸が張り裂けそうになりました。
気がつくと、私は姪の前にしゃがみ込み、目線を合わせて声をかけていました。
「……うちの子になるか?」
その瞬間、親族たちは一斉に私を見ました。
「はあ? あんた正気? 独身男に子育てなんてできるわけないでしょう」
伯母は鼻で笑いながらそう言いました。他の親族たちも「まあ、好きにさせればいい」「これで一安心だ」と、厄介払いができたことに安堵した表情を浮かべていました。
「この子は俺が守る」手探りの子育てと、救いの手
私はその日のうちに姪を連れて帰りました。勢いで言ってしまったものの、独り身の男に7歳の女の子が育てられるのか、不安がなかったわけではありません。しかし、震える姪の手を握ったとき、「この子は俺が絶対に守る」と男としての覚悟を決めたのです。
とはいえ、現実は甘くありません。いざ姪との生活が始まると、朝の髪の結び方もわからず、お弁当作りにも悪戦苦闘。「やっぱりママがいい」と涙する姪を前に、私は途方に暮れていました。
そんなとき、救いの手を差し伸べてくれたのが、私と妹の共通の幼なじみでした。
彼女は妹の葬儀にも参列しており、親族に責められる私と姪の姿をずっと心配して見てくれていたのです。
「もう、ひとりじゃないよ。私も手伝うから」
彼女は手際よく姪の髪を結い、おいしい食事を作ってくれました。彼女のやさしさに触れ、強張っていた姪の表情も次第に和らぎ、家の中が温かい空気へと変わっていったのです。
その後、私は正式に姪と普通養子縁組の手続きを進めました。無事に家庭裁判所に認められ、姪との養子縁組が成立。職場にも事情を説明し、幼なじみのサポートも受けながら、私たちは少しずつ「家族」としてのかたちを作っていきました。
身勝手な親族たちとの絶縁
私たちがそうして、だんだんと家族としての絆を深めていく一方で、親族たちの間では醜い争いが勃発していました。
きっかけは、高齢になった伯父の母の介護問題でした。私が家を出てからは、伯母夫婦が自宅に呼び寄せて同居していたようですが、いざ本格的な介護が必要になると、他の親族と責任のなすりつけ合いを始めたのです。
そして、自分たちで解決できなくなると、その身勝手な矛先を私に向けてきました。
「親戚なんだから助けるのが当たり前だろ」
「介護費用として、少し金を貸してくれないか」
あんなに姪を邪魔者扱いして切り捨てておきながら、自分たちが困った時だけ都合よく頼ってくる神経が信じられません。
私は彼らの厚顔無恥さにあきれ果て、即座に弁護士を介入させました。二度と私たちに関わらないよう法的に手続きをおこない、きっぱりと絶縁しました。今では彼らがどこで何をしているのか、知る由もありません。
あれから数年が経ちました。中学生になった娘は、私の背に追いつきそうなほど大きく成長しました。そして私の隣には、これまで支えて続けてくれた幼なじみが、妻として今も寄り添ってくれています。
「お父さん、お母さん、いつもありがとう」
そう言って笑う娘の顔を見るたび、あのとき、勇気を出して引き取って本当によかったと心から思います。大変なこともありましたが、今のこの温かい毎日が、あの日、私が選んだ道は間違いではなかったと教えてくれている気がします。
※本記事は、実際の体験談をもとに作成しています。取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。