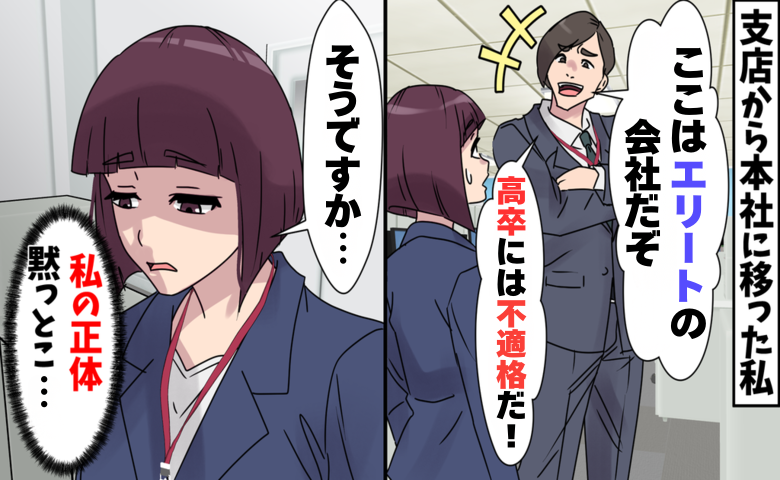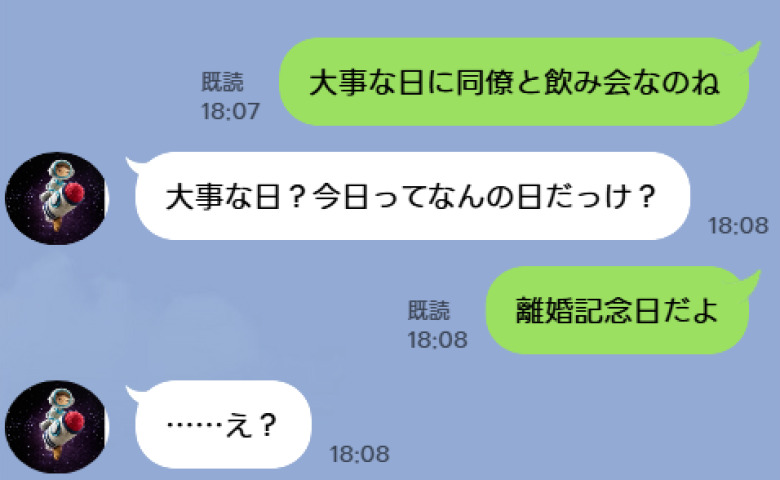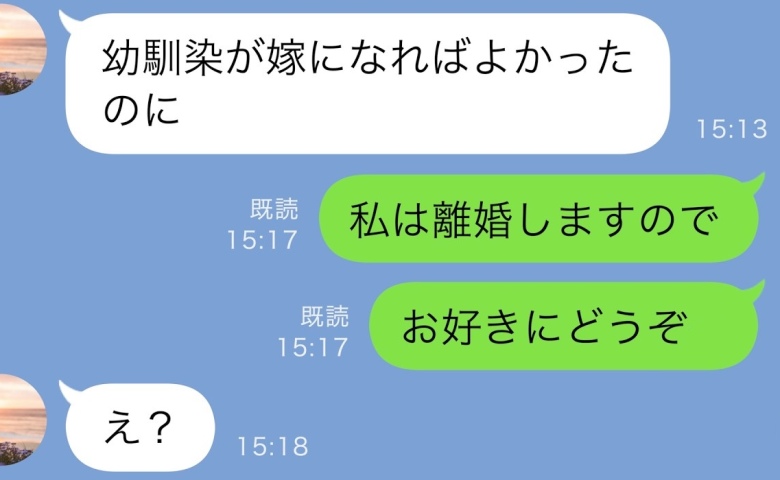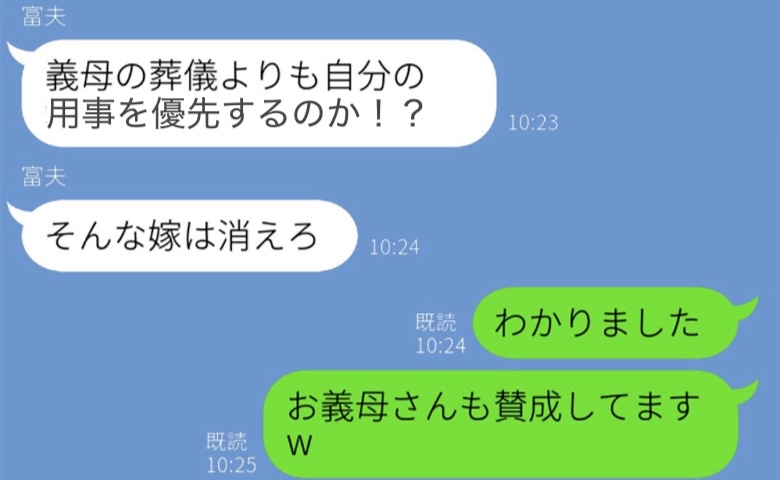「どうしたの?」思わず声をかけると、彼はうつむいたままつぶやきました。
「うっせぇな……母ちゃんが死んだんだ。だから金が全然ねぇんだよ」
父親は早くに家を出て、頼れる人もいないと言います。その言葉に、母は「じゃあ、うち、定食屋だからご飯食べていきなさい。おなか空いてるでしょ?」と言いました。
彼は少し迷ったあと、小さくうなずき、私たちはそのまま店へ向かいました。
一杯の味噌汁から始まった縁
店に着くと、母は慣れた手つきで味噌汁をよそい、ご飯を盛りました。
「遠慮しないで、たくさん食べなさい」
彼は黙って箸を取り、ひと口、またひと口と食べていきました。そのうち涙がぽつぽつとこぼれ落ちます。
「……うめぇ」
その声が、かすかに震えていました。
母はそっと言いました。
「お金がないって言ってたね。うちで働く? 放課後だけでもいいから」
「え……いいんですか」
彼は照れたように笑いながら、「やってみます」と答えました。
変わっていく少年の背中
彼は放課後になると定食屋に顔を出し、皿洗いや片付けを手伝うようになりました。最初のうちは不器用で、皿を落としたり、オーダーを間違えたりとミスを連発していましたが、失敗するたびに「次はちゃんとやれます」と素直に頭を下げる姿が印象的でした。
働き始めて少し経つと、金髪だった髪は黒く染められ、ミスも次第になくなりました。
お客さんの中には「最近よく働く子がいるね」と声をかけてくれる人も増え、彼はいつの間にか店の一員になっていました。
彼の夢は
それから数年、彼は高校を卒業し、料理の専門学校を経て再び定食屋に戻ってきました。今では厨房を任されるほどの腕前です。味の感覚も鋭く、常連さんの中には「この子の唐揚げが食べたい」と言う人まで出てくるようになりました。
「俺、自分の店を出すのが夢なんです。お母さんの味を、もっと広めたくて」
そう話す彼の目は、かつて公園で見た寂しげな少年とはまるで違っていました。
店を支える日々の中で、私と彼は少しずつ距離を縮めていきました。同じ厨房で汗を流し、忙しい時間を共に過ごすうちに、互いに支え合う存在になっていったのです。
母が体調を崩して店を休むことが増えたころ、彼は「自分が守ります」と言って厨房に立ち続けました。その責任感の強さに、家族の誰もが彼を頼もしく感じるようになっていきました。
そんな日々の積み重ねの中で、自然と「この先も一緒にやっていこう」という話が出るようになりました。
家族の一員に
そして、彼の夢が叶うころ──私たちは結婚。数カ月後に妊娠がわかり、無事に男の子を出産しました。
あの日、公園で出会った金髪の少年は、今では定食屋の大切な一員です。母の味を受け継ぎながら、今日も私たちは変わらない日々を積み重ねています。
※本記事は、実際の体験談をもとに作成しています。取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。


.jpg)