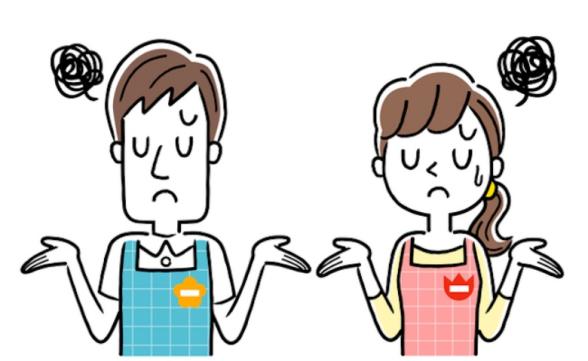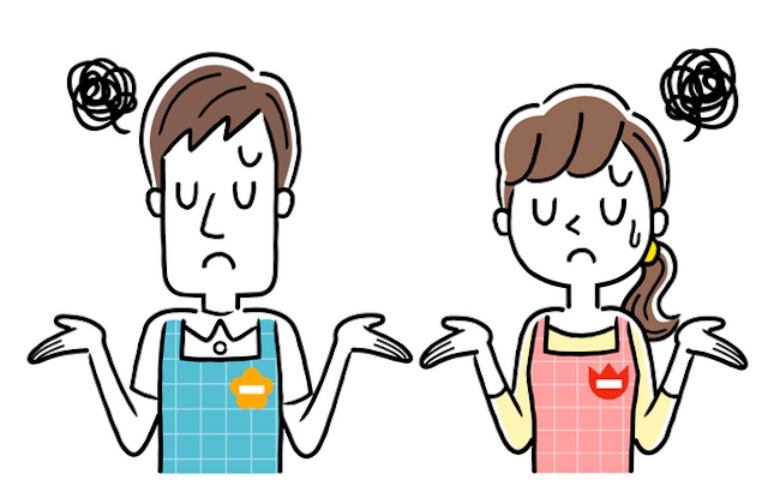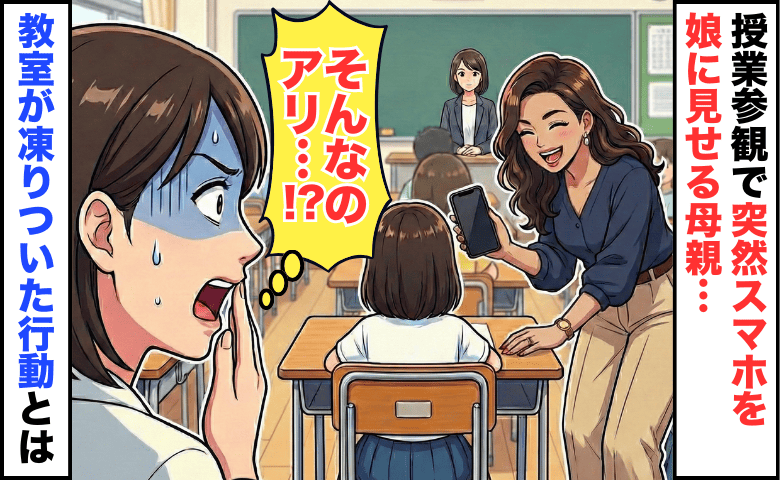「いい保育園」を見抜く十か条
いったい、「いい保育園」とはどんな保育園なのでしょうか。長年保育の現場に携わってきた、大阪教育大学教育学部教授、小崎恭弘先生は、保育園を選ぶ目安として厚生労働省が公表している『よい保育施設の選び方 十か条』を勧めています。
厚生労働省の「よい保育施設の選び方 十か条」
一 まずは情報収集を
二 事前に見学を
三 見た目だけで決めないで
四 部屋の中まで入って見て
五 子どもたちの様子を見て
六 保育する人の様子を見て
七 施設の様子を見て
八 保育の方針を聞いて
九 預けはじめてからもチェックを
十 不満や疑問は率直に
「厚労省が提示するこの十か条は、専門家から見ても過不足なくチェックポイントがまとまっていると思います」
乳児ではなく、ある程度子どもの好みや性格が分かるような年齢になっている場合は、子どものタイプにも配慮したほうがよさそうです。
「大事なのは、園の方針と保護者の思い、そして子ども自身の性格や特徴が一致しているかです。子どもの性格を考えて選ぶことです。『園の方針』はホームページで公開されているところも多いですから、いろいろ比べて検討してください」と小崎先生は話します。
たとえば保護者が「自然の中でのびのびと育てたい」と考え、外遊び中心の園を選んでも、子どもの性格がその方針に合っていないと、入園後にあまり馴染めないかもしれません。
もちろん、遠いといった物理的な問題や、地域によっては待機児童問題でなかなか希望通りの園に通えないこともあります。自治体によってはたくさんの希望を書くこともできますから、この十か条を参考に検討してみてはいかがでしょうか。
専門家おすすめ! 第三者評価が見られるサイト
園選びで小崎先生がおすすめするのは、社会福祉施設情報が集約されているWAM NET(ワム ネット)。独立行政法人「福祉医療機構」が運営しているサイトです。ここに第三者評価の結果を公表している保育所もあります。」
〈第三者評価の検索方法〉
「子ども・家庭」→「福祉サービス評価情報」→「福祉サービス第三者評価・地域密着型サービス外部評価・運営推進会議等による評価情報」→「施設名で検索」
適切な運営管理ができているかどうかの見極めのひとつが「評価」です。保育所は第三者評価の公表を義務付けられていませんが、「意識の高いところは、サービスや質の向上を意識するために第三者評価を公表している」と小崎先生は言います。
「ここにはすごくていねいに保育の取り組みや内容が書かれています。いいことばかり公表されているわけではありませんから、参考になります。ここまで調べる保護者の方は少ないかもしれませんが、気になる園があるなら、公表しているかどうか調べてみてください。公表されている中身も参考になると思います」
こんな保育園には気をつけて!
専門家の視点から「これだけはNG」と感じるチェックポイントも教えてもらいました。
これはNG1! 保育士が条件付きで叱っている
小崎先生が絶対にNGとするのは「保育士が威圧的であるところ」「暴力的なところ」「条件を出して叱るところ」です。威圧的や暴力的な態度は言語道断ですが、「条件を出して叱る」は意外な落とし穴のようです。
「早くお着替えが終わらないとおやつなしですよ」
「ごはん食べないならお昼寝しませんよ」
こうしたやりとりは、ともすればご家庭のやりとりでもやりがちですが、こうした声がけはNG。保育現場でこうした場面を見たら、要注意だそうです。
「叱ることは止むを得ない場合もありますが、条件を出して叱る保育士は専門家として不適切です。これは子どもにとって、言葉の暴力なんです。見学者がいるとなかなか普段の状況は見られないかもしれないですが、逆に見学者がいるのにそういう一面が見えてしまった場合は注意が必要だと思います」
これはNG2! 「なんとなく嫌かも」という直感があった
見学したときに感じた「なんとなく嫌」という感覚。言葉で表現しにくい直感も、大事にしたほうがいいと小崎先生は言います。
「においが気になる、雰囲気が嫌、なんとなく暗いといった第一印象の直感ってありますよね。そういう感覚も実は大事なんです」
その直感が「ダメな園」の見極めポイントと繋がっていることも。
たとえば……
・庭の手入れが不行き届き
・あいさつがぞんざいになっている
・トイレがにおう
・殺伐としている
・古いプリントがいつまでも貼られている
・掲示や壁面の装飾が古くなってボロボロになっている
などです。
これはNG3! 大人の目線の高さに物が置いてある
環境へ配慮することは保育の基本です。万が一に備えて、安全な環境を作っているかという視点でも要チェックです。
たとえば……
・高いところにカセットデッキがある
・消火器を子どもの頭上のあたりでぶら下げている
などです。
「大人の目線の高さに重い物を置いていないか、という点も見ておいたほうがいいです。地震で万が一落下したとき、下に子どもがいたら大けがにつながります。『神は細部に宿る』という言葉がありますが、一時が万事。そういうこまかいところの配慮に子どもへの配慮が表れていることがあるんです」と数多くの保育現場を知る小崎先生は指摘します。
休みやサービス、料金の条件もチェック

ママパパが必要としているサービスの有無や休み、料金などの条件面も事前確認が必要です。自治体によっても差があるため、将来の校区も含め、長期的な視点で住む場所を決める段階から下調べするのがベストです。
「自治体によって保育料もサービスも違います。千葉県流山市では駅から保育所を送迎バスでつなぐサービスがあります。こういうサービスも調べておいたほうがよいでしょう」
保育所によって休みも違います。お盆や年末年始の休みも確認しておきたいところ。園のサービス内容によっては持ち物にも大きな違いがあるようです。
「最近では紙おむつのサブスク『手ぶら登園』を導入している園や、ベッドのようなものを貸し出している園もあります。反対に布おむつを使っている園もあります。行事への取り組み方も園の特徴が出ると思います。和太鼓や金管楽器をやっているところもあり、全くやっていないところもあります。どれもどちらがいいというのではなく、親がどう子どもを育てたいかという方針になります。もし可能なら保護者会などの取り組みも調べておいたほうがよいですね。保育所より比較的保護者会の活動がさかんなのが幼稚園型認定子ども園といわれています。なかには『働いている人にはしんどい』と言われるところもあるみたいです。『お父さんの会』がある園もあります。これらが有意義で楽しいと思う人もいるだろうし、苦痛だと思う人もいると思います。その辺はよく検討してもらいたいです」と小崎先生は言います。
保育園選びはパパも積極的に!“子育て観”をたしかめる機会に
保育園選びは、さまざまなチェックポイントに加え、親自身の子育て観が大きく関わってきます。とはいえ、多様化する保育施設。置かれた環境も規模もサービスもさまざまです。都市部の保育施設では園庭のない施設もあります。こういう複雑化した保育園選びには「パパも積極的に参加を」と小崎先生は呼びかけます。
「この問題を全部ママにまかせるというのは無理がありますね。やはり一緒に考えて、複数の視点で見て相談するというのが大事なんです。1人ではチェックしきれなかったり、感じ方が違ったりしますから」
こうした会話の積み重ねが、夫婦2人の子育て観をたしかめ合う機会にもなりそうです。
「常識的なことを除くと、保育には絶対的な正解/不正解はないと思っています。それぞれの園なりの方針や想いがあるので、最終的には親の思いを話し合って考えて欲しいなと思います。2人でどういう子どもに育てたいか。話し合ういい機会と捉えるといいでしょう」
取材・文:大楽眞衣子/社会派子育てライター。全国紙記者を経てフリーランスに。専業主婦歴7年、PTA経験豊富。子育てや食育、女性の生き方に関する記事を雑誌やWEBで執筆中。大学で児童学を学ぶ。静岡県在住、昆虫好き、3兄弟の母。