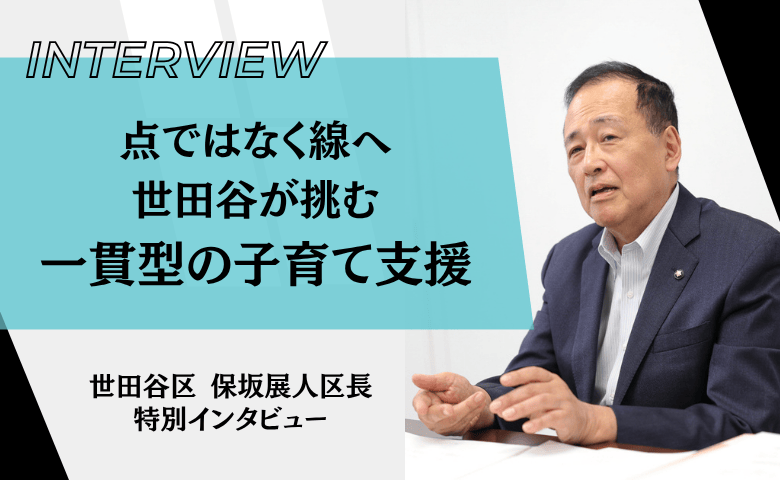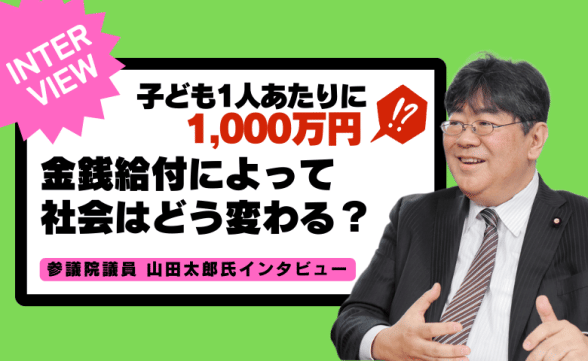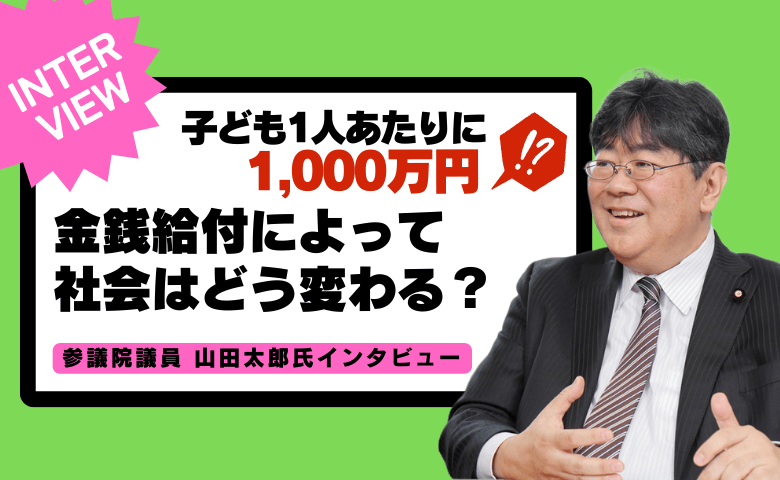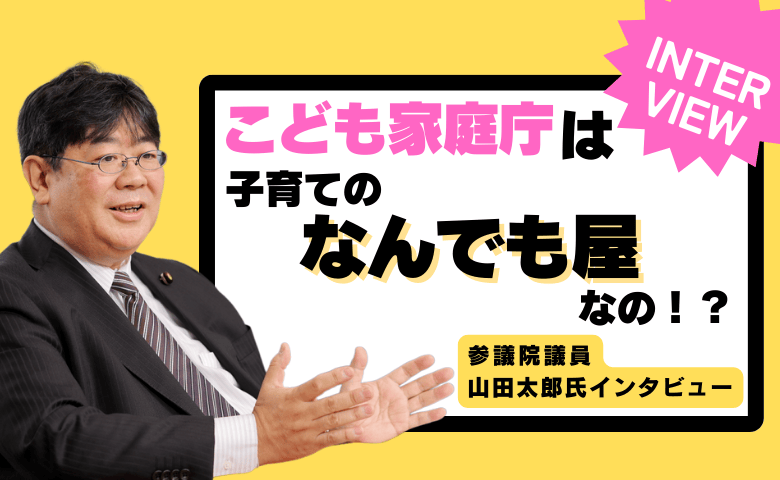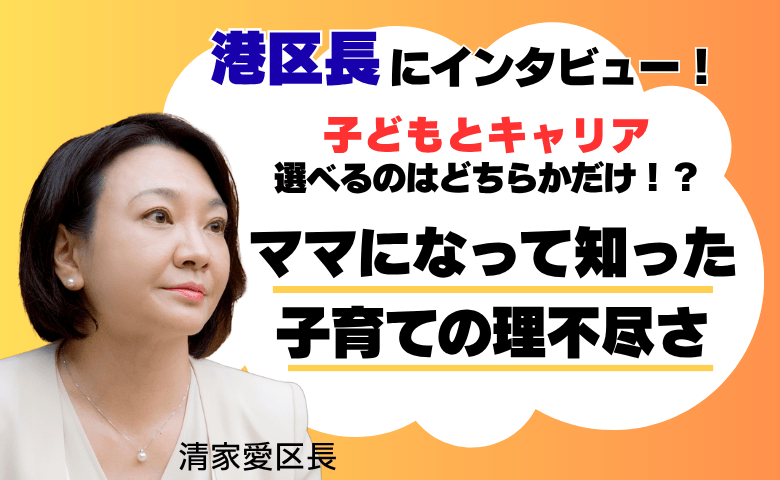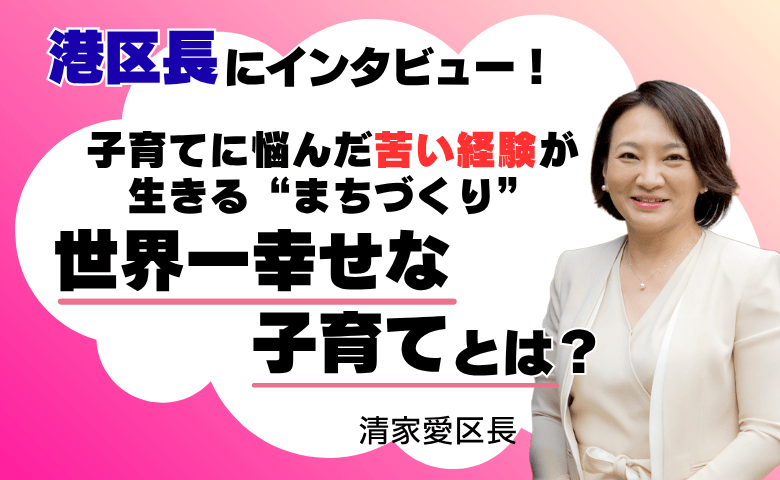「子育て支援は一貫していなければならない」
──世田谷区の子育て支援は手厚く、現場の声を起点にした独自性のある施策が多い印象です。これらの施策が生まれた理由を教えていただけますか?
保坂展人区長(以下、保坂さん):以前は、子育て支援が各部署ごとに「縦割り」になっており、全体像を把握している職員が少ない状況でした。職員自身にも他部署が担当する支援の内容がわからず、適切な案内ができないため、支援を受けられない住民が出てしまっていたのです。
しかし子育て支援は継続的で切れ目のないものでなければなりません。そこで、まず体制の見直しから着手しました。
──どのような体制に変わったのでしょうか?
保坂さん:保健師・助産師・保育士がチームを組み、連携して対応する体制に変更しました。参考にしたのは、フィンランドの「ネウボラ」という子育て支援の仕組みです。ネウボラでは保育士がひとりで継続的に支援していますが、世田谷区では支援を必要とする家庭が多いため、複数名の専門家が連携して対応しています。
妊娠届の提出時には「ネウボラ面接」という面談を実施し、妊娠の経緯や背景を伺いながら、子育てに関する基本情報や区内の支援制度をまとめた「せたがや子育て応援ブック」で提供サービスを案内したり、「妊婦支援給付金」の申請方法や「せたがや子育て利用券」の活用法をお伝えしたりしています。
10代での妊娠や未婚で出産を迎える方もいます。そうした背景にも丁寧に耳を傾け、必要な支援へつなげていくことが、面談の重要な目的です。
──経済的な支援についてはいかがでしょうか?
保坂さん:面談時には「子育て応援ブック」とあわせて、産後ケアセンターなどで使える1万円分のクーポン券をお渡ししています。「妊婦支援給付金」も2回に分けて支給され、妊婦さんの不安を少しでも軽減できるよう努めています。
給付金の1回目は妊娠中、2回目は出産後に申請が可能です。マタニティ用品やベビーグッズ、健診費用など、出費がかさむ時期に現金で支給することで、ご家庭の状況に応じた活用ができるようにしています。
「孤育て」から「共育て」へ。徒歩15分圏内に必ずある親子の居場所
──メンタル面でのサポートについて教えてください。
保坂さん:長年、教育ジャーナリストとして子育てや教育の課題を見てきましたが、なかでも大きな問題が「孤育て」です。誰にも頼れず、家庭内だけで子育てを担う状況は、精神的に大きな負担になります。
子育て支援策を考えるにあたってお願いした妊婦さんへの事前アンケートでも、「夫と子どもと自分だけで妊娠・出産・子育てを乗り越えなければならない」と感じている方が多くいました。実家が遠い、友人が少ないなど、孤立しやすい環境が背景にあります。
そこで世田谷区では、区内のどこに住んでいても徒歩15分圏内に親子で立ち寄れる「おでかけひろば」があるように、整備をしています。気軽に立ち寄れる場所で、他の親とつながり、話すことで心が軽くなる。そんな居場所づくりを進めています。
──徒歩15分という距離に込めた思いとは?
保坂さん:雨の日でもベビーカーでも無理なく行ける距離を意識しました。2025年6月時点で、おでかけひろばは区内に(児童館のおでかけひろばを含め)70カ所以上あり、今後は80カ所程度まで増やす予定です。
特徴的なのは、実際に子育て中のママたちがNPO法人などを立ち上げ、一軒家を借りて改装し、地域の親子を受け入れる場所を自ら作っていることです。そこに区が助成金を出し、専任のスタッフを配置することで、地域と行政が連携した支援が実現しています。
──「おでかけひろば」にはどんな機能があるのですか?
保坂さん:すべてではありませんが、「らっこルーム」や「らっこスペース」といった、ママ・パパが少しでも休める空間を設けた施設もあります。部屋の一角にカーテンで仕切った簡易ベッドスペースをつくり、スタッフが子どもを見守る中で、安心して休息をとってもらえるよう配慮しています。

ママ・パパの“ひと言”が支援を動かす 声から生まれた新しい選択肢
──子育て中のママ・パパが、日中に安心して休める時間があるというのは心強いですね。
保坂さん:そうなんです。「昨日あまり眠れなかった」なんていうことは、子育てをしている方なら誰もが経験されていると思います。そうした“リアルな声”に耳を傾け、それをどう支援に結びつけていくか、それこそが私たち自治体の大切な役割だと感じています。
──ママ・パパたちの声は、どのように集めているのですか?
保坂さん:SNSを通じて呼びかけ、「カフェトーク」という、区民のみなさんと直接お話ができる場を設けています。そこでは実際に子育てをしているママさんたちから、さまざまなご意見を伺っています。
たとえば、「フルタイムの保育園ではなく、週に1〜2回、2〜3時間だけでも仕事に集中できるような環境が欲しい」といった声がありました。その声をもとに、おでかけひろばと同じ建物の別部屋にコワーキングスペースをつくったんです。開設に向けて厚生労働省とも半年ほどやり取りを重ねて、ようやく実現できました。
このように世田谷区の子育て支援は、子育てをするママ・パパたちの「生の声」から生まれているのです。
◇◇◇◇◇◇◇◇
子育て支援は、行政の制度だけで完結するものではありません。今回の取材で印象的だったのは、ママ・パパの「ちょっと困る」「こうだったらいいのに」という小さな声が、現場の専門職や地域の力を借りて少しずつ“かたち”になっていくプロセスでした。
世田谷区の取り組みも、そのひとつのケースにすぎません。正解が決まっているわけではなく、試行錯誤を共有しながら「孤育て」を減らしていく歩みこそが、これからの子育て支援のカギだと感じます。
ベビーカレンダーは今後も、各地で生まれている実践やアイデアを取材し、読者のみなさんに「これならできるかも」と思えるヒントを届けていきます。子育ての悩みや工夫を共有し合うことで、誰もが「ひとりじゃない」と思える社会へ——。現場の声を起点にした取り組みの広がりを、私たちも追い続けていきます。