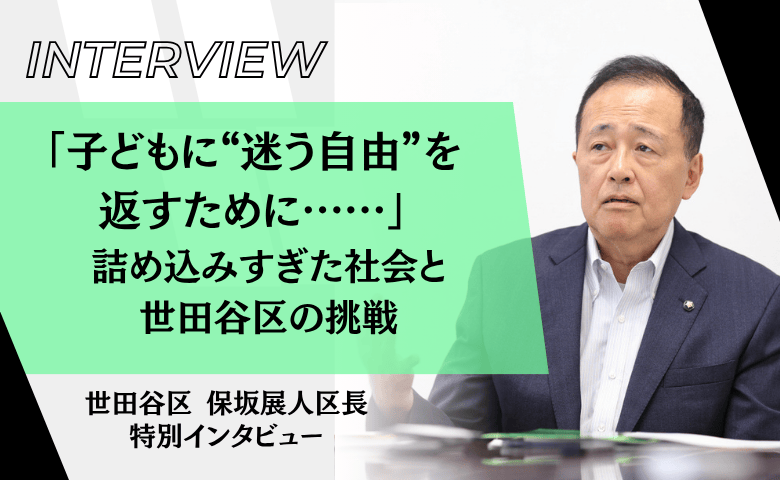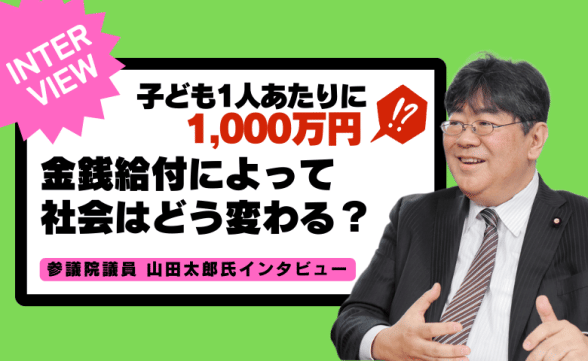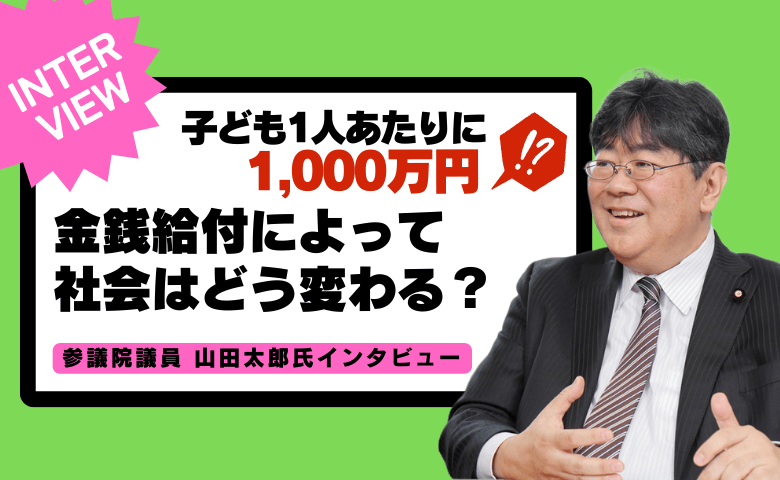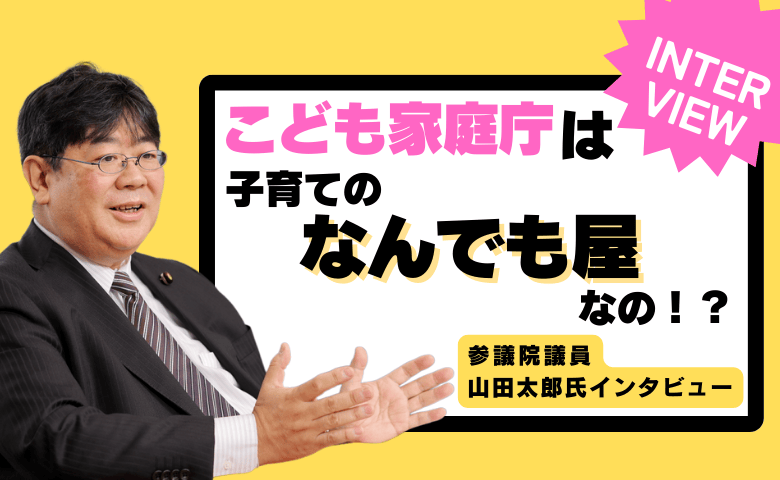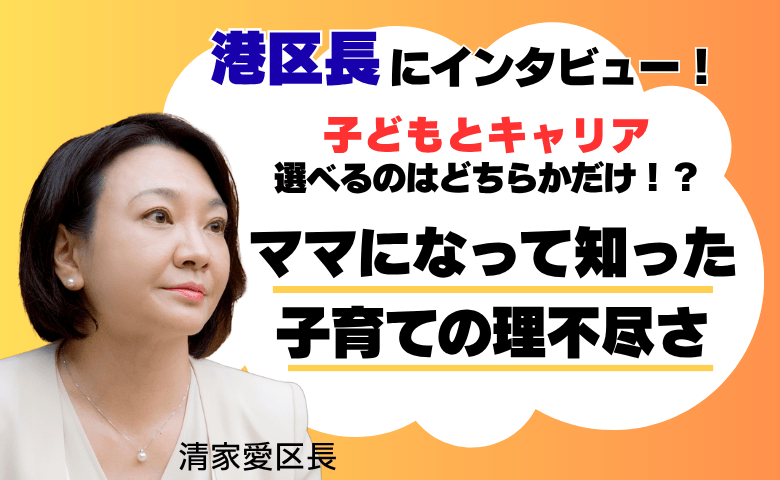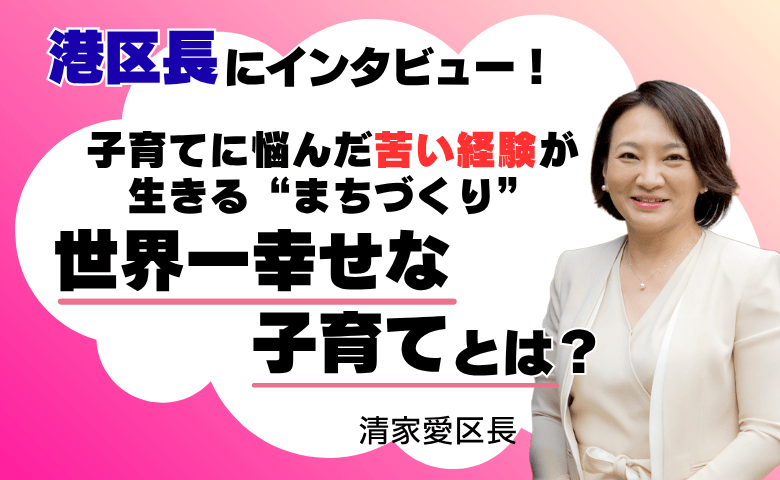子どもに必要なのは「迷走する時間」世田谷区長が語る、これからの子育て
──区長ご自身が大切にしている「子育ての考え方」について教えてください
保坂さん:最近、子どもたちが自由に遊べる時間や場所がどんどん減っていると感じています。「就学前に漢字を書けるようにしなきゃ」「赤ちゃんから英会話を」といったような、極端な早期教育の広告も目にしますよね。親の不安をあおるようなメッセージがあふれています。
でも私は、子どもには“何も予定がない時間”がとても大切だと思っています。何もせず、ただぼーっとする時間。その中で、ふと「じゃあ、次は何をしようかな」と自分で考える時間。そうやって、子どもは自分で人生の時間を使う感覚を覚えていくものなんです。
今の子どもたちは、朝から夜までスケジュールがぎっしり。起きている時間のほとんどを、大人に決められた予定で過ごしています。自分で「やってみようかな」と考えて行動する経験が、一度もないまま大人になってしまうかもしれない。これはとても危ういことです。
さらにスマートフォンの普及で、学校が終わってもSNSでずっと“誰かとつながっている”。人間関係から離れてひとりになる時間が持てない。これは“自由”とはほど遠い状態です。自由な発想や、本当に興味があることを見つけるには、「寄り道」や「迷走」する時間が必要です。いろんなことに手を出して、失敗したり戻ったりすること。そうした心と時間の余白が、子どもたちにはもっと必要なんだと思います。

──時間の余白を作ること以外に、必要だと感じることはありますか?
保坂さん:「将来子どもに不自由させたくない」と願う親心は、よくわかります。でも何気ない遊びの中でこそ学べることもたくさんあるんです。
たとえば友だちと喧嘩して、翌日にはまた仲直りして一緒に遊ぶ、そんな経験。今の若者のニュースやトラブルを見ていると、こうした経験を十分にしてこなかったのかなと感じることがあります。遊びの中では、感情をぶつけ合う場面も出てきます。「ごめんね」「いいよ」というやり取りを何度も繰り返す中で、人と関わる力が育っていく。人間関係の原点となるような“感情の土台”は、こうした体験を通してしか身につかないんです。
そうした原体験があれば、大人になって他者からの干渉やプレッシャーに出会っても、自分を保ちながら乗り越える力になります。
──では、子どもたちにそういった経験をしてもらうために、世田谷区ではどのような取り組みをされていますか?
保坂さん:そのひとつが「プレーパーク」です。2025年3月には区内5カ所目となる「砧あそびの杜プレーパーク」も開園し、体験の場が広がってきました。

プレーパークには、遊びを見守る「プレーワーカー」や地域のボランティアの方が常駐し、子どもたちが自由に、そして安全に遊べる環境を整えています。大人の目の届く範囲で、火を使った遊びなどもできるんですよ。
また外遊びの価値を広めるために「外遊び推進員」も配置しています。子どもたちの外遊びに関心を持ってくれる大人を増やすこと。さらには、地域の人材や団体とつながって、遊びを支えるネットワークも構築しています。
遊びの質を豊かにするのは、施設だけではありません。地域にいる“ちょっと気にかけてくれる大人”の存在が、何より大切なんです。
誰ともつながらず、何も決まっていない時間。そこから“退屈”を感じて、自分で考え、何かを始める。そういう時間が、今の子どもたちからどんどん奪われています。
もしかしたらママも「やらせすぎかもしれない」と感じているかもしれません。しかし将来が不安で、やめる勇気が持てない。社会も学校も「先取りしないと遅れる」と言ってくるプレッシャーの中で、親も子も疲れているのが現実ではないでしょうか。
そんな背景から世田谷区では、ただ遊ばせる場所を増やすのではなく、“子どもが子どもらしくいられる時間”を取り戻す取り組みに力を入れています。
◇◇◇◇◇◇◇◇
詰め込むよりも、こぼせる余白を。教えるよりも、感じられる余裕を。
保坂区長が語る「子育て」は、親の不安を責めるものではありません。不安を抱えながら、それでも「今」を大切にしようとする人たちの背中を、静かに支える言葉です。
社会がつながりすぎている今だからこそ、“あえてつながらない自由”を、子どもに返していく。
それは甘やかしではなく、大人たちの覚悟なのかもしれません。
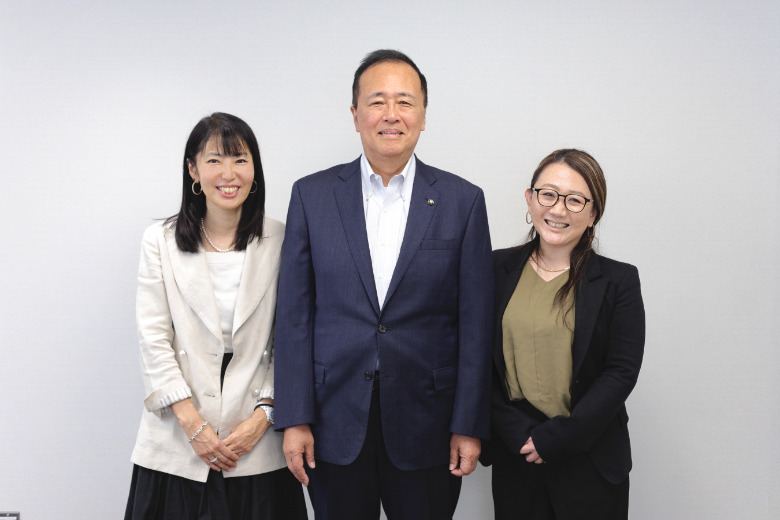
保坂区長とベビーカレンダー編集長・担当編集
子どもにとっても、親にとっても、“空白”や“迷い”の時間は本来あっていいもの。けれど今は、それすら「もったいない」とされがちです。保坂区長の言葉は、そんな窮屈さのなかに小さな風穴を開け、「それも必要」と教えてくれるものでした。
また、世田谷区の取材を通じ、市民の力が地域を変えられることを再確認できたように思います。簡単ではないけれど、そこから子育ての風向きが変わっていくのかもしれません。ベビーカレンダーでは、これからもママや子どもたちの幸せに寄り添いながら、歩みを進めていきます。