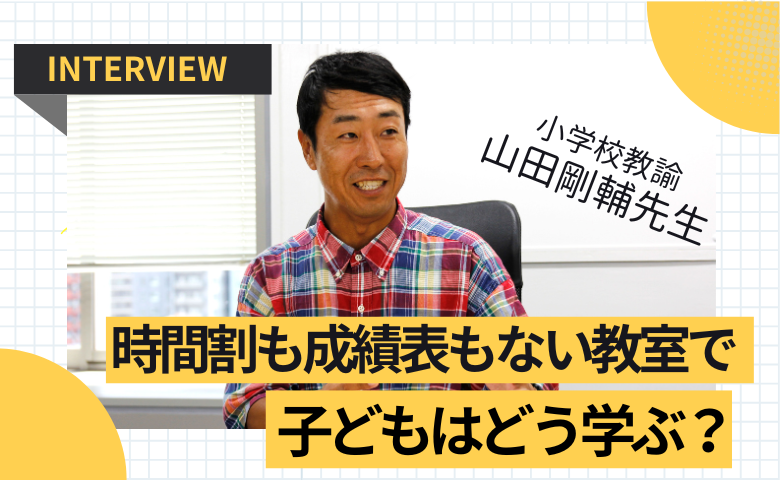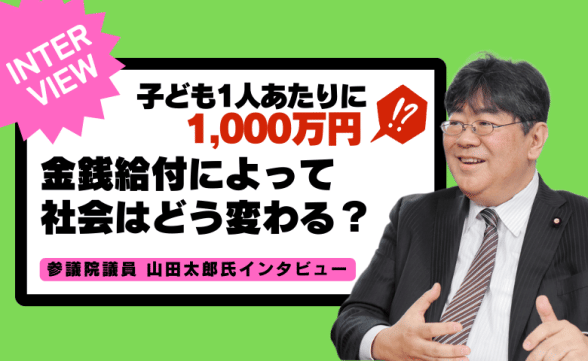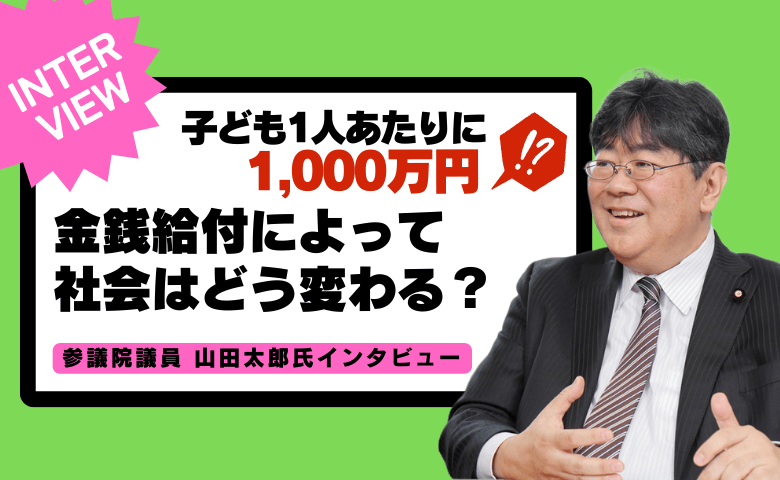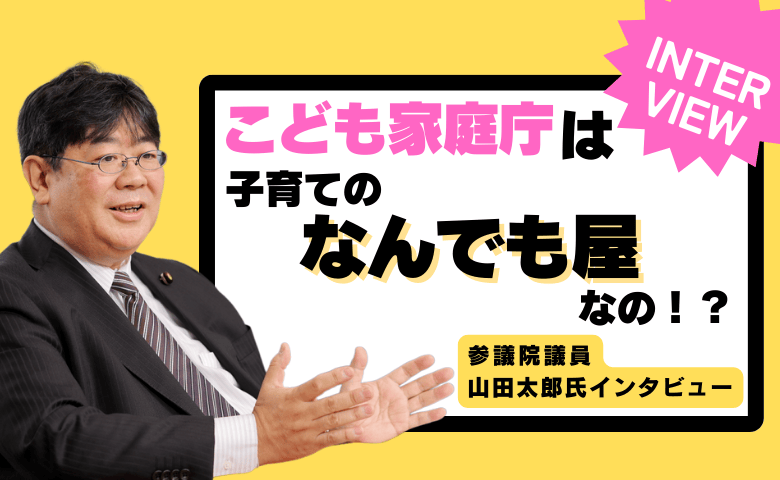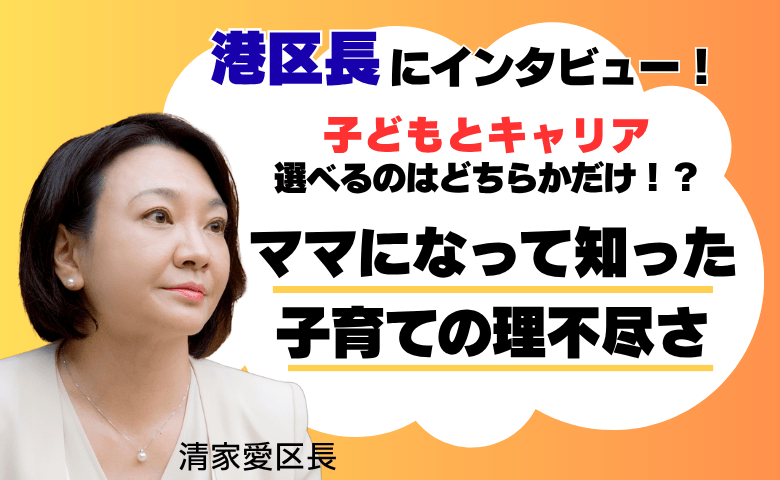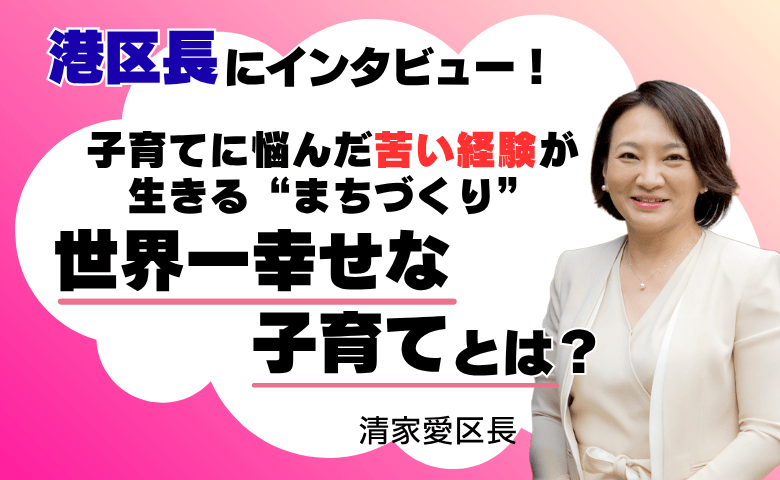従来の枠組みにとらわれない学級で、どのように学習指導要領に沿った学びがおこなわれているのか、また子どもたちの成長や取り組みをどのように評価しているのか。山田先生にお話をうかがいました。
授業はひとつのプロジェクト!? 時間割がないクラスで勉強に不足は出ないの?
――一般的な時間割は設けず、複数の教科を組み込んだひとつの「プロジェクト」を作り上げ、さまざまな視点から学んでいく「プロジェクトベース」の授業を展開されているとうかがいました。学びにおける子どもたちの興味・関心を取り入れることと、学習指導要領を満たすことは、どのように両立されているのでしょうか。
山田剛輔先生(以下、山田):「時間割がない」と聞くと、まるで好き勝手に学んでいるような印象を受けるかもしれません。けれど実際には、授業の土台になっているのはあくまで教科書や学習指導要領の内容です。「プロジェクトベース」とは、教科を活動に組み合わせ、その枠組みの中で学びが進む仕組みが特徴です。つまり、その学年で学ぶべき内容を、従来とは異なる方法で学んでいるだけなのです。
子どもたちにとって「どのような状況で学ぶことに意味があるのか」を先生が工夫しながら授業を組み立てており、学習指導要領とはまったく別のことをしているわけではありません。
――授業の基礎はあくまで学習指導要領にある、ということですね。
山田:その通りです。学習指導要領に沿って授業を進めつつ、子どもたちの興味を引き出しながら、より理解が深まるような学びの場をつくることを大事にしています。
単に教科書を読んで、黒板の板書をノートに写し、先生の解説を聞くだけの授業では子どもたちは退屈してしまいます。知識理解や点数獲得だけを目的とした授業では、子どもたちのモチベーションは高まりません。
一方、プロジェクトベースで授業をおこなうと、「なぜ学ぶのか」という目的が自然に生まれるんです。
プロジェクトは「種まき」から始まる
――「学習指導要領を過不足なく網羅できる授業が設計できるものなのか?」と疑問に思う保護者もいると思います。具体的には、どのようにプロジェクトの中に必要な教科の勉強を組み込んでいるのでしょうか?
山田:最初に「種まき」をします。資料を提示したり、動画を見せたりして、子どもたちの中に問いや関心の芽を生み出すんです。
たとえば環境問題を扱うときは、プラスチックごみに関する動画を見せます。そこには「1年間に海に流れ出すプラスチックごみは〇〇トン」という数字が出てきます。子どもたちにとっては途方もなく大きな数値です。
ここで算数の学びにつなげられます。4年生のはじめには「大きな数」の学習があるので、動画で出てきたデータをもとに大きな数字を学ぶことができるのです。
さらに、プラスチックごみは社会科や総合的な学習のテーマにもなります。「ごみを減らすために自分たちにできることは何か」を探究するのは総合学習にあたりますし、「ごみ問題に向き合ってどう感じるか」を考えることは道徳にもつながります。
このように、ひとつのプロジェクトの中に、算数・社会・総合・道徳など、複数の教科の要素を含んでいるのです。
――プロジェクトベースの授業を作り上げるのは、決して簡単ではないように思います。どのように教科書や既存の学習教材と結びつけていらっしゃいますか?
山田:教員歴が長くなると、学年ごとにどのような学習内容があるのかが大体頭に入っています。ですから「この内容をプロジェクトベースでどう出会わせようか」と考えるのは、楽しい作業ですね。逆に、1時間ごとに細かい計画を立てて進めるほうが私には大変に感じます。
授業をデザインするうえで大切なのは、授業に「目的」があることです。たとえば、プロジェクトで“大きな数字”を見せてから「どう書くんだろう?」と子どもに問いかけると、自然に教科書に戻っていくことができます。
資料や動画を動機にして教科書へ立ち返り、「こういう書き方なんだ」「こう読むんだ」と確認する――これは“振り返り学習”に近い感覚です。つまり、教科書ありきで進めるのではなく、あくまで子どもたちの探究の途中で「教科書に戻る」。教科書を、学びを補完する「参考資料」として位置づける、そんな逆転の発想で授業を組み立てています。
――各教科を網羅するプロジェクトを毎回考えておられるのでしょうか?
山田:もちろん、プロジェクトベースの授業のみで各教科を完全に網羅するのは難しいです。だからこそ、最初から綿密に計画を立てすぎないようにしています。
授業を進める中で「このプロジェクトはあの教科につなげられるのでは?」と探しながら増やしていき、最終的にひとつにまとまっていくイメージですね。最初から全部を構想してしまうと、授業構想が間に合わなかったり、かえってアイデアが出にくくなったりするんです。
もちろん、プロジェクトベースでは扱いにくい単元もあるので、そうした場合は通常の授業として、できるだけわかりやすく・楽しく学べる工夫をしています。
子どもたちはどう変わった? 「カレーライスの例え話」
ーー従来の授業からプロジェクトベースに変えたことで、子どもたちの学力にはどのような変化がありましたか?
山田:学力について語るときには、まず「学力とは何か」という定義を考えなければなりません。私が小学生だったころは「どれだけ多くの情報を覚えて、テストで正しくアウトプットできるか」が学力の基準でした。その定義でいえば、今の授業は反復練習の時間が少ないぶん、必ずしも学力が高まっているとは言えないかもしれません。
私は学力についての説明をするとき、よく「カレーライス」の例えを使います。カレーを食べたことがない人に「辛い」「でもおいしい」という知識を言葉だけで伝えても、その感覚は本当にはわかりませんよね。実際に食べることで「辛い」とはどういうことか、「おいしい」とはどういうことかが経験として残ります。学び(学力)も同じで、体験を通してこそ知識は本当の意味で自分のものになるのです。
だからこそ、ただ知識を暗記するだけでは不十分です。文部科学省も現在は「コンピテンシー(資質・能力)」を重んじており、覚えた量だけでなく、それがどれだけ子どもの中に蓄積され、実際の行動や新しい挑戦につながっていくかが重要視されています。
これを体現しているのがプロジェクトベースの授業です。知識を体験として取り込むことで、子どもたちは「学んだことが役に立った」という実感を持ち、学びが自分ごとになります。その経験は自信となり、次の挑戦へ自然につながっていくのです。
ーープロジェクトベースの授業で、子どもたちに「変化があった」と感じられた経験はありますか?
子どもたちの学習に向かう姿勢やアウトプットの仕方には、たしかな変化を感じます。たとえば「自分たちの活動をもっと多くの人に知ってもらおう」となったとき、子どもたちはこれまでのプロジェクトでの経験を生かして動き出します。
「チラシを作って配ろう」「校内放送で呼びかけよう」といった具合に、自分たちで方法を考え、実行に移していくんです。ひとつのプロジェクトで得た学びや体験が、次の行動や新しい学びへと確実に積み重なっていくのを感じています。
「この授業で大丈夫?」保護者の反応は……?
ーープロジェクトベースの授業や従来の◎◯△などで評価する成績表を廃止したことで、保護者の方からさまざまな意見があったのではないでしょうか?
山田:当初は「授業の進度が遅いのではないか」「進学に必要な学力はつくのか」といったご意見をいただきました。ただし、プロジェクトベースの授業そのものに対して大きな批判はありませんでした。
また、成績表の廃止には経緯があります。廃止の狙いは、数字や記号で子どもを一律に並べるのではなく、学びのプロセスや表現を重視した評価へと移行することでした。そして、子どもが自らの学びを振り返って次につなげていく「メタ認知」をすることを大切にしていたのです。
それに、成績表がなくても必要に応じてペーパーテストはおこない、学習指導要領に示されている三観点のうち「知識・技能」を測る場面ではしっかり確認していました。
そのうえで、プロジェクト学習では子どもたちがアウトプットしたもの。たとえば「大きい数」の学習では、自分で調べた億や兆のスケールをもとにクイズを作る、といったパフォーマンスを評価の中心に据えていたのです。
しかし一方で、成績表がないことへの不安の声も根強くありました。そこで保護者の要望を受け、2024年度に成績表を再開しました。現在の成績表は「学びの過程」と「学力の成果」の両面をバランスよく伝える形に着地しています。そして、子ども、保護者、先生の三者で面談をして、これまでの学びとこれからの学びについて対話しながら共通認識をもって歩みを進める評価を実現しています。
プロジェクトベースの授業においても、学力を軽視することなく、むしろ多様な活動を通して得られた成果を本物の学力として評価しています。その点は丁寧に説明し、すべての保護者に理解していただけるよう努めています。
◇◇◇◇◇◇◇◇
子どもたちが自ら問いを立て、学びを広げていく「探究学習」のひとつのかたちとして注目されるプロジェクトベースの授業。テーマから出発し、教科書へと立ち返る逆転の発想は、従来の授業観を大きく揺さぶります。
テストの点数では測りきれない子どもたちの成長を、どう評価し、どう見守っていくのか――。それは学校や教師だけでなく、保護者や社会全体に投げかけられた問いかもしれません。