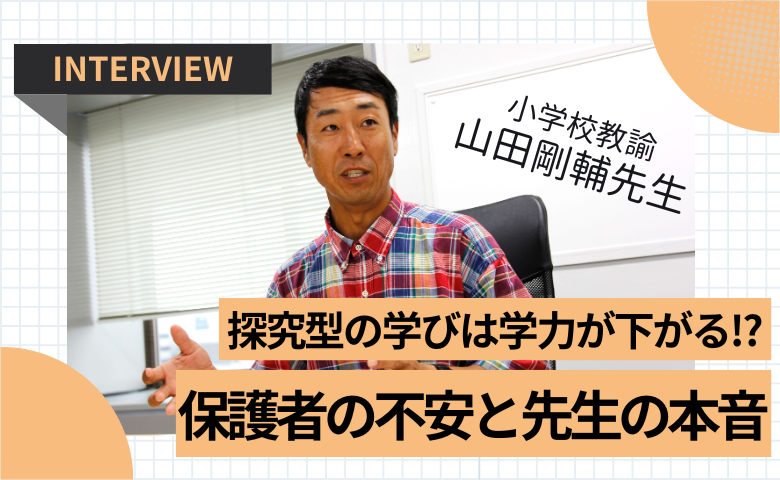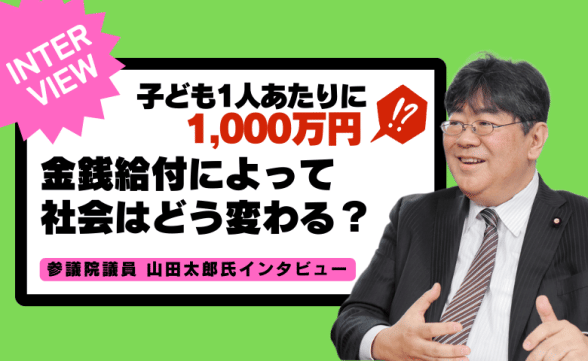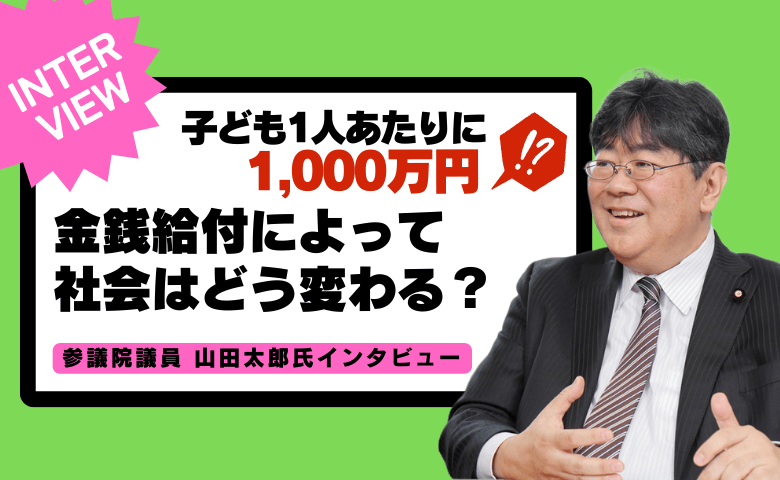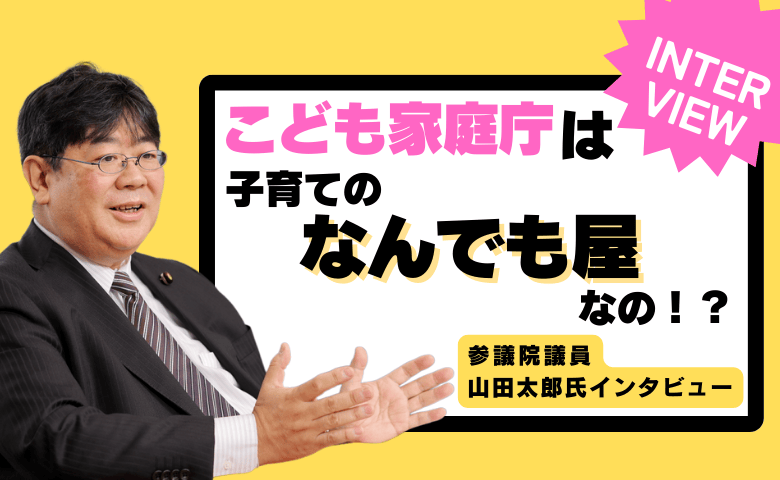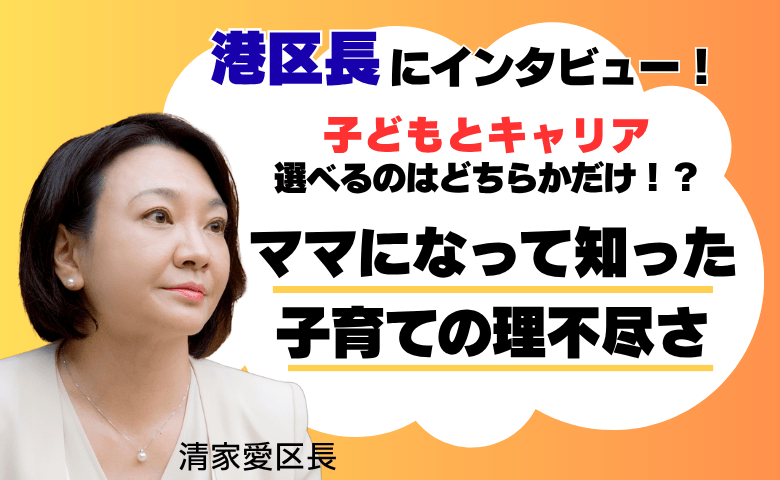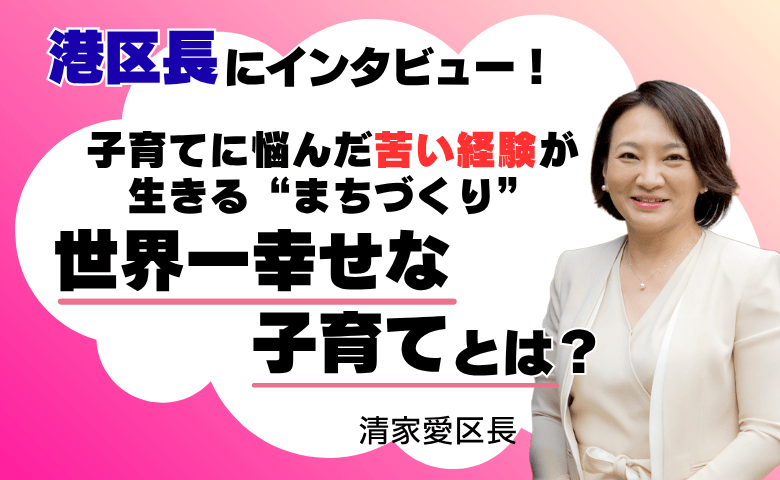今回は、時間割や成績表に縛られず、複数の教科を組み合わせてひとつの「プロジェクト」を作り上げ、さまざまな視点から学びを深める「プロジェクトベース」の授業を実践している、茅ヶ崎市立の小学校教諭・山田剛輔先生にお話をうかがいました。
新たな学びへの期待と学力低下への不安に揺れる保護者に求められることとは
――山田先生のクラスでは、複数の教科を組み込んだひとつの「プロジェクト」を作り上げ、教科書や時間割にとらわれず、さまざまな視点から学んでいく「プロジェクトベース」の授業をしていると聞いています。これまでになかった学びのかたちに戸惑う保護者も多かったのではないでしょうか。学力低下への不安を感じる保護者には、どのように対応していますか?
山田剛輔先生(以下、山田):「中学・高校入試だけをゴールにせず、もっと先を見てみてください」とお伝えします。大学入試も今は約半分が総合型選抜入試や学校推薦型選抜です。もちろん従来のペーパーテストを受ける一般選抜の道も残っています。社会に出ても採用の方法は多様化していて、大学名を見ない企業や、プロジェクトへの関わり方を評価する企業もあります。
だからこそ、保護者には「成績」だけに縛られず、子どもが内側から湧き上がる意欲で取り組めることを大切にしてほしいと思います。点数以上に大事なのは、子どもが自分の考えを持ち、仲間と協力し、人と関わりながら物事を成し遂げられる力。そうした力を伸ばすことこそ、小中学生の時期に育むべき「学び」ではないでしょうか。
しかし、入試制度がある以上、成績に不安を抱かない保護者はいないと思います。私たち教員が入試制度そのものを変えることはできません。それをわかっているからこそ、不安になるのもわかります。
「学力への不安」には、まず「『何ができたか』ではなく『夢中になれるものがあるか』を一緒に見ていきましょう」とお伝えします。子どもに目標や「やりたい!」という気持ちがあれば、自ら学んでいくからです。だからこそ信じて待つことをお願いしています。
それでも不安にとらわれてしまうときは「裏を返せばお子さんを信じ切れていないサインかもしれません」と率直にお伝えし、信じて見守っていただくようにとお伝えしています。
――山田先生自身もお子さんがいらっしゃいますが、勉強についてどのように伝えてこられましたか?
山田:長女は中学で勉強に苦労しました。短期記憶が得意ではなかったんです。でも声楽の道を志し「高校は音楽科に進みたい」と決めてからは、勉強もレッスンも一気に主体性を持って取り組むようになりました。
普通科よりも道は限られるし、成績も専門的な勉強も必要で負荷は大きい。でも本人がやりたいからこそ、夢中になって取り組んでいます。そんな姿を見ていると、親として「大丈夫だ」と思えたのです。
習い事を続ける? 辞める? 子どもの「辞めたい」に対して保護者ができること
――子どもの「やりたい」を見つけ、応援することが大切ということですね。しかし、子どもの「好き」から始まったことなのに、「辞めたい」と言うこともあるでしょう。そのとき、保護者はどのように対応すべきでしょうか?
山田:子どもが「辞めたい」といった理由を聞いて決めることが大事だと思います。
子どもが何か壁にぶつかっていて、それがクリアできる、乗り越えていける理由だったら、保護者から「〇〇ができるようになったら楽しくなるよね」という働きかけができるでしょう。
壁にぶつかったからすぐ次、もしくは、一度始めたのだから簡単に辞めさせない、ではないと考えます。壁にぶつかったときこそ「乗り越える」経験を積むことが大事なのです。だから何に困っていてやりたくないのか、何をどうしたらもっと楽しくなっていくのかを、子どもから詳しく聞いてみてください。
乗り越えるトライをしてみても「乗り越えるのは難しいね」「それはたしかにしんどいね」という結果が親子共通のものになったら、辞めてもいいと思います。これは子どもが生きていく中で、壁にぶち当たったとき、「もうやりたくない」と感じたときに、どう乗り越えるかの練習でもあると考えています。
続けるか続けないかだけの問題ではなく、困難なことがあったときにどう乗り越えていくのかを親子で一緒に 相談しながら考えていく場だと思います。結果が辞める辞めないのどちらになってもいいんです。「辞めたい」という声が上がったときに、立ち止まって親子で一緒に考えることが大切です。
「うちの子、このままで大丈夫かな…」そんなとき保護者は?
――一方で「好きなことも見つからないし、勉強もあまり得意ではない…」と悩む声もよく聞かれます。そんなとき、保護者はどうすればいいのでしょうか?
山田:学びのかたちは今、大きく変わっています。その中で保護者に求められるのは、「信じて待つこと」のほかに、「環境を整えること」です。幼児期には、文字や計算の練習よりも、主体的に対象と関わって考えながら工夫できる遊びを大切にしてください。やりたいことに没頭できる力があれば「勉強が遅れている?」という不安を抱く必要はなく「わが子は大丈夫!」と信じて、学校などで学ぶ機会を待ってもいいのではないかと思います。
さらに、学校の雰囲気や保護者同士のつながり、先生とのコミュニケーションといった要素が、子どもを包む「あたたかな環境」を形づくります。そんな環境に身を置くことで、子どもの学びはさらに広がります。
この2つを意識するだけで、子どもの未来はぐっと豊かに育っていくはずです。
◇◇◇◇◇◇◇◇
山田先生の話を聞くと「すぐに結果が出なくても焦る必要はない」と思えるのではないでしょうか。子どもと一緒に色々な体験をして、子ども自身が夢中になれるものを見つける瞬間を信じて待つことの大切さを再確認できます。
成績や結果に一喜一憂するのではなく、挑戦を見守り、共に楽しみながら歩む姿勢が、子どもの未来を大きく支えるのかもしれませんね。