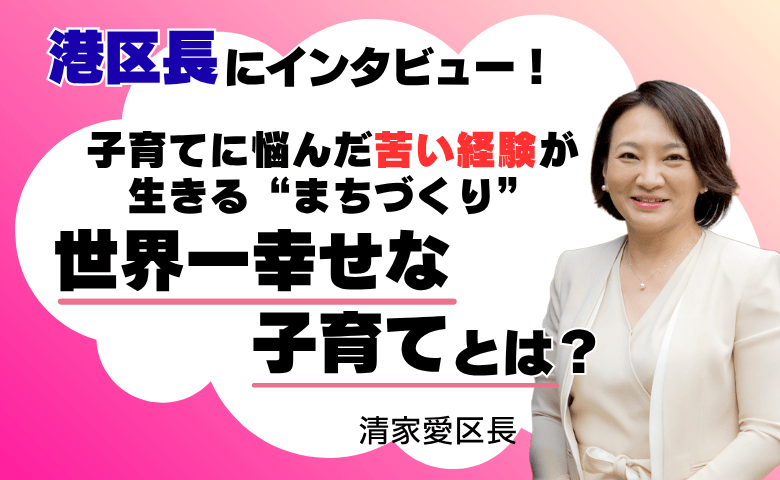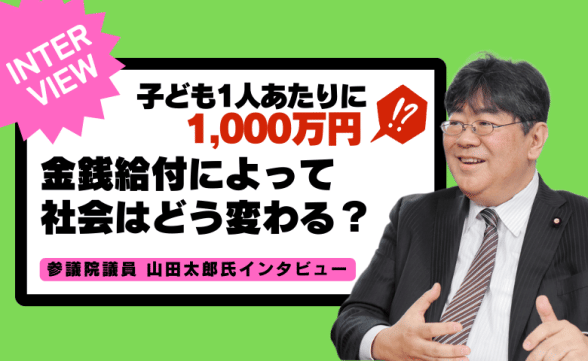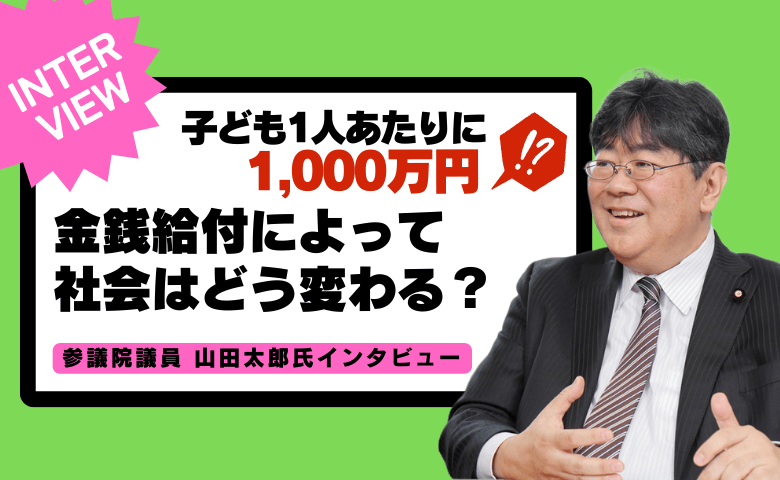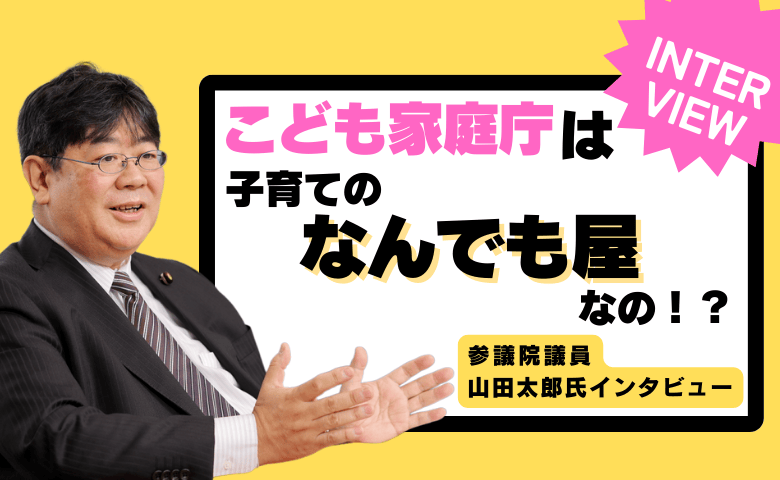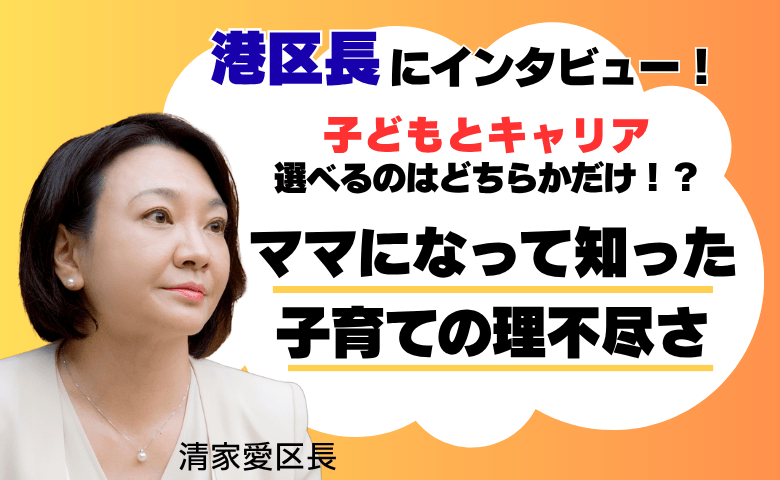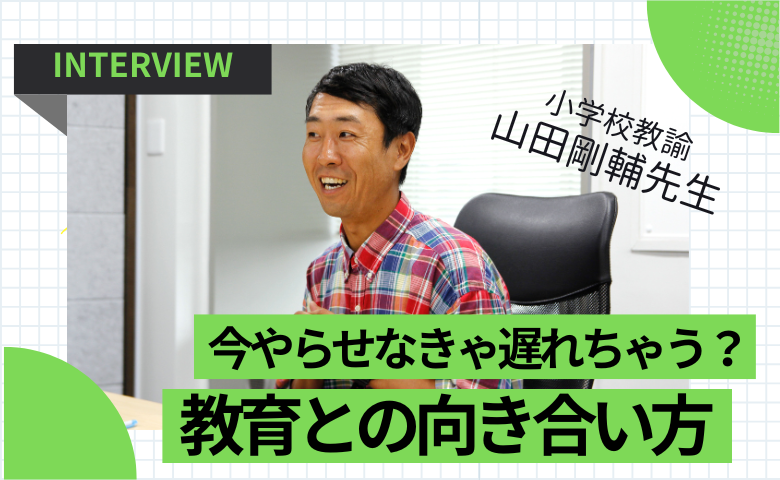そんな港区で、2025年9月ベビーカレンダーが産後ケア事業をスタート。ビジョンの一端を担うべく、「世界一幸せな子育て」とは何か、どうすれば実現できるのか、そして、ベビーカレンダーに期待することは何かを探ってきました。
「港区ママの会」から始まった改革。区長自身の子育て経験が政策の原点に
――清家区長が掲げる「世界一幸せな子育て・教育都市」とは? また、それはどのようにして生まれたのでしょうか。
清家愛港区長(以下、清家):このビジョンの原点は、私自身の子育て経験です。18年前の娘の出産がすべての出発点でした。大学卒業後、新聞社で記者として働いていたのですが、新聞記者という仕事は当時男性中心の、いわば「男社会」で、女性が子育てと仕事を両立できる環境が整っていませんでした。
長時間仕事をすることが多かったですし、休暇を取りづらい風土がありました。当時の仕事環境はとてもファミリーフレンドリーとは言い難かったですし、「結婚や出産をしたら仕事は無理だ」といった発言も日常的に耳に入る環境でした。
それでも新聞記者の仕事は好きでした。ですが、父親の体調悪化やその父に孫の顔を見せたいという思いもあり、悩んだ末に会社を辞めて、フリーランスになることにしたんです。
ところが、出産したあとに、当時の港区は待機児童の数が23区ワーストレベルであることを知りました。そして「フリーランスでは点数がたりないので、保育園には入れません」と言われたのです。
途方に暮れていたところ、児童館などで、私と同じように仕事と子育ての両立で悩みながら保活に苦しむママさんたちと出会い、子育てや仕事にまつわるさまざまな悩みを聞いていくなかで「子どもが幸せだと感じるには、まずはママが幸せでなければならない」と強く感じるようになりました。これが「世界一幸せな子育て」というビジョンの始まりです。

――保活に追われていた当時、ブログを書いていたそうですね。今読み返すと、どんな気持ちになりますか?
清家:当時の必死さと同時に、このブログのおかげで今があると感じます。働きたいのに働けない、外との関わりがなく“孤(こ)育て”をしていた私にとって、一歩を踏み出せた記録であり、同じ境遇のママたちとつながるきっかけにもなりました。メールで「私も同じです」と届いた言葉に、どれだけ救われたかわかりません。
そうした声が積み重なり、『港区ママの会』という場が生まれました。『港区ママの会』は、保育園や学童クラブに入れない不安、仕事と子育ての両立の難しさを共有しながら、行政に声を届けていく場です。この場においてママたちがお互いの思いを語り合い、やがて政治に反映できる流れを作れたことは、私にとって大きな転機でした。
――当時、『港区ママの会』にはどのような声が寄せられたのでしょうか?
清家:「歯医者に行く時間もない」「美容院にさえ行けない」「自分が寝込んでも子どもを見てくれる人がいない」――そんな切実な声が相次ぎました。これは単なる一家庭の悩みではなく、社会全体で共有すべき課題だと強く感じたのです。
それが区長になってから立ち上げた事業「赤ちゃん応援定期便(ファミリー・アテンダント事業)」につながっています。これは1歳未満の赤ちゃんがいるご家庭が対象で、見守り支援員が各家庭を訪問して親御さんたちの悩みや不安をお聞きする支援です。
利用者から「悩みを聞いてもらえたことで孤独感が薄まり、ようやく救われた気持ちになった」という声をいただくたびに、この事業が単なる支援にとどまらず、社会の仕組みを変える第一歩になっていることを実感します。ママが安心できれば子どもも笑顔になる。そんな循環をつくることが行政の責務だと改めて思いました。
「世界一幸せな子育て・教育都市」をめざして
――「世界一幸せな子育て・教育都市」というビジョンにおける“子育ての幸福度”。もしこれを測るとしたら、どんな指標を重視しますか?
清家:まず大切なことは、子ども自身が「今、幸せだ」と感じられること。そのためには、子育てにかかわる保護者との愛着形成が欠かせません。
港区は実家が遠い核家族が多く、初産年齢も高めという傾向があります。産後は睡眠不足やホルモンのせいで気持ちも不安定になりやすい時期です。自身の経験からも、子育てにかかわるママが追い込まれてしまうと、子どもにしわ寄せが来てしまうということを実感しています。
そのため、まずは子育てにより深くかかわるママたちを支えることが、子どもの心と発達を守る近道だと位置づけています。
また、多様な子どもたちが安心して過ごせる居場所を整えたいと考えており、その取り組みのひとつが公教育の充実です。
港区は私立に進学する子が多いのも事実ですが、公立でも質が高く、経済的な負担が少ない選択肢を用意することをめざしています。区立の中高一貫校構想もその一環です。こうした基盤づくりが、子どもたち一人ひとりの安心につながり、やがて社会の幸福度を高めると信じています。

――では、その「今、幸せ」と子どもたちが感じられるのは、どのような場面だと思いますか?
清家:子どもたち一人ひとりが自分の「好き」を持っているときではないでしょうか。自身の「好き」や「能力」が評価されたり「ここに居場所がある」と思えたりした瞬間に、子どもは幸せと感じ、安心して未来に向かえるのだと思います。
そして夢は子どもによってさまざまで、「世界で活躍したい」という子もいれば、「地域で自分らしく暮らしたい」という子もいる。そのような多様な夢を受け止められる教育環境を整えていくことが行政の役割だと考えています。
行政・助産師会・メディアの「三位一体モデル」で新たな挑戦
――ベビーカレンダーが芝浦港南地区に新たに開設した産後ケア施設で導入されている、行政・助産師会・メディアがタッグを組んだ「三位一体モデル」にはどのようなことを期待されますか?
清家:行政サービスには「対象者に情報が適切に届きづらい」という課題があります。出産を機にさまざまな行政サービスがあることに気がつき、活用したいとは思っているものの、制度が複雑で理解しづらいと感じている方も少なくありません。
そこで重要になるのが、広報やメディアの情報発信力です。行政としても制度を整え、「伝わる広報」に取り組んでいるところではありますが、メディアにご協力いただくことで、発信力を強化できます。対象者に情報がきちんと届くことで、初めてサービスが生きたものになります。
また、産後ケア施設は産後の特定の時期のみに利用する施設ですが、行政サービスの案内がそのサービスを利用して終わってしまうのではなく、保育園探しなどその後の子育てサービスにも自然につながっていくような“循環する情報の仕組み”を、メディアと一緒に作り上げたいと考えています。
――新たにオープンした産後ケア施設は区にとってどのような存在になると考えていますか?
清家:2025年8月1日現在、区の0歳児は2,268人で、そのうち芝浦港南地区は623人(27.5%)と最も多い地域です。地域の皆さんが待ち望んだ施設であり、地域に根ざし愛される場所になることを期待しています。
この施設では休養の機会や母体ケア、育児相談を通じて、親子の愛着形成を支えるとともに、地域のママ同士が出会い、つながるきっかけをつくることもできます。ニーズは高く、「こうした場所がもっと身近にほしい」という声も多く届いています。だからこそ、既存施設の受け入れ拡充や新設を進め、区内のどこに住んでいても安心して利用できる“子育ての拠点”を増やしていきたいです。

◇◇◇◇◇◇
ママが安心して子どもを育てられること。それは子どもの笑顔を生み、やがて地域や日本の未来を明るくします。けれども、その環境をつくるためには制度や施策だけでは不十分で、私たち一人ひとりの理解と行動が欠かせません。
ママを支え、子どもが安心できる居場所を整える取り組みは、確実に動き出しています。ママも子どもも、そして社会全体が笑顔でいられる日常へ……。ベビーカレンダーもそんな社会をつくるための挑戦をこれからも続けていきます。
芝浦産後ケアサロン「ベビーカレンダーひより」with品川港助産師会
▶︎詳しくはこちら!