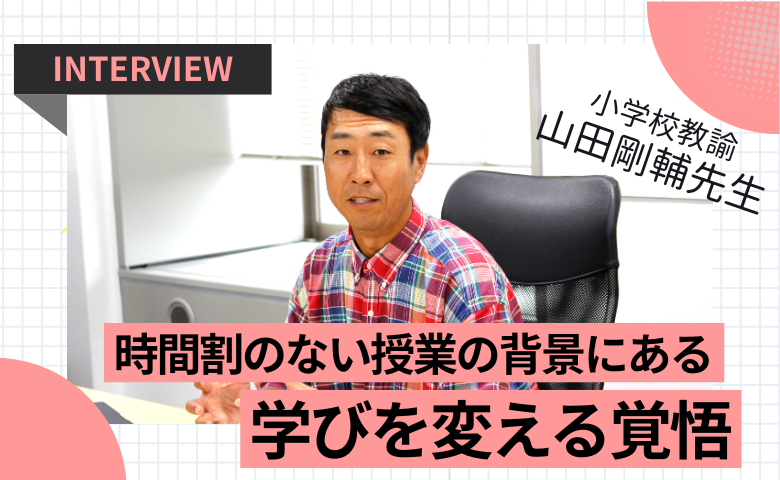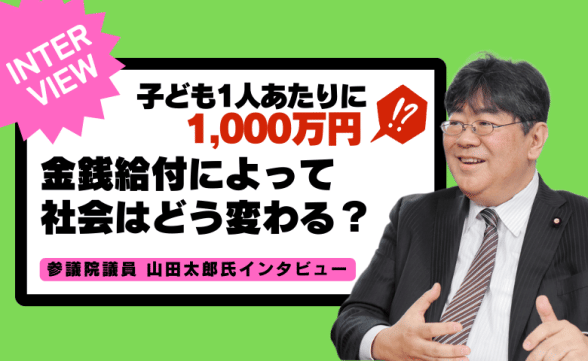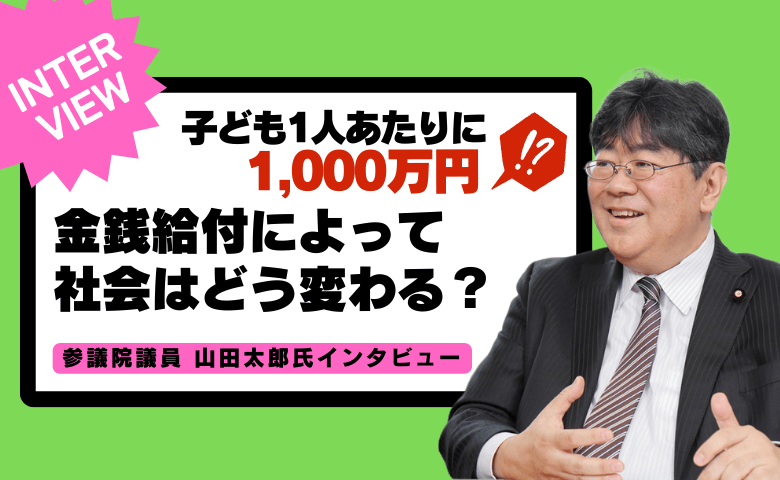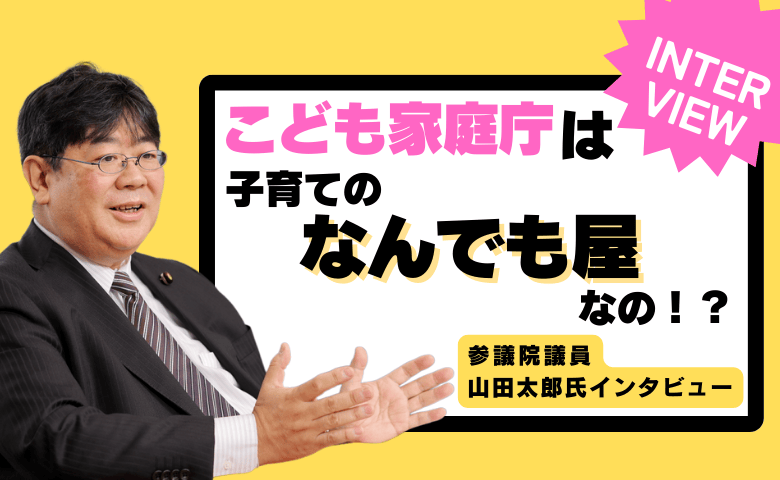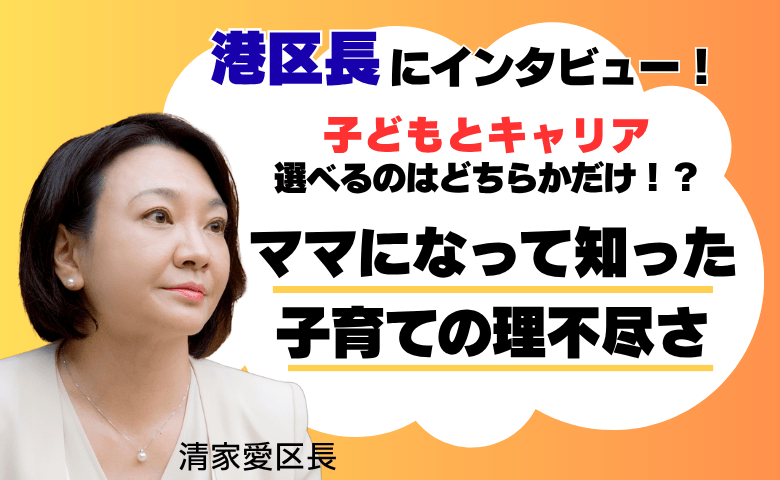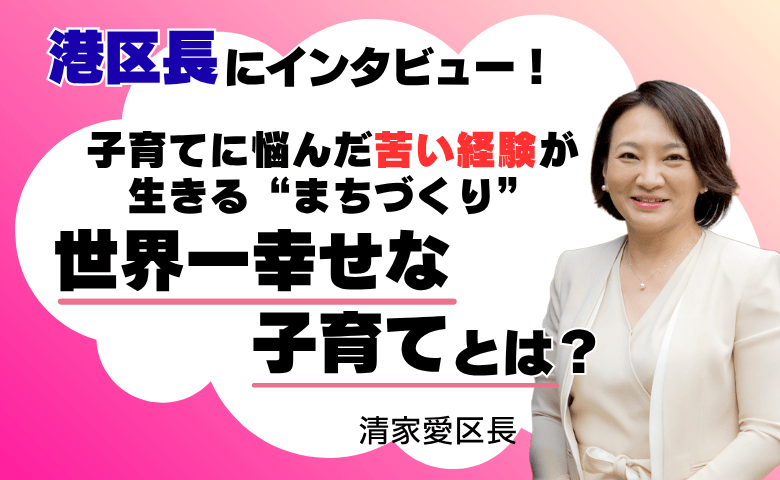ほかにはない授業をおこなうことで、保護者や同じ学校の先生からはどのような反応があったのでしょうか。山田剛輔先生にうかがいました。
学校と家庭は車の両輪ー 先生の個性あふれる授業で目指す共通のゴール
――山田先生のクラスで学びたい、という児童は少なくないのではないでしょうか?
山田剛輔先生(以下、山田):「私のクラスで学びたい」と言ってくれる児童が多いのは、本当にありがたいことです。しかし同じ学校内で、私とまったく同じやり方で授業をしている先生はいません。
――要望があるにもかかわらず、なぜ広がらないのでしょうか?
山田:やはり学校というのは「全員が同じことをやるのが良い」という空気が強くあります。児童だけでなく先生も「周りと同じようにしなければ」と考えてしまうのです。その背景には常に保護者の“目”があります。
先生たちも「自分だけ違うことをしたらどう思われるか」「保護者の反応はどうか」と常に意識せざるを得ません。保護者からの評価は先生にとって大きなプレッシャーで、「この先生はやってくれる/やってくれない」といった目線が、“横並びで同じようにやること”を優先させてしまうのです。結果として革新的な実践が広まりにくい現状があります。
どの先生が教えても同じ授業、という「安心感」を優先した結果、学校が塾のようにただ教科書を淡々と進める場所になってしまう危うさがあります。私はそこに「つまらなさ」を感じるし、だからこそ挑戦を続けたいと思っています。
「出過ぎた杭は打たれない」学びを変える覚悟
――挑戦する中で、他の先生方から指摘を受けたり意見を言われたりすることはありますか?
山田:この挑戦をはじめた当初は、同僚から「ひとり違うことをするのはやめてほしい」と言われたこともあります。しかし、今は違います。「出る杭は打たれる」ということわざがありますが、私は「出過ぎた杭は打たれない」と考えています。私の取り組みは、まさにその状況です。
通常、新しい授業を始める際には校長や同僚に相談する人がほとんどです。しかし授業の進め方を何から何まで校長先生や同僚に相談していては、自分のやりたいことができなくなってしまいます。だから私は相談はせず、思い切って実践することにしました。ただし情報共有は欠かしません。「こういう授業をやろうと思います」と伝える程度にとどめています。
そうすると不思議なもので、他の先生方もそれぞれ自由に、自分のやりたい実践を進めてくれるようになりました。たしかに「どのクラスでも同じ学びをすべき」という考えも理解できます。でも、せっかく先生が違うのですから、授業の個性もあっていいと思います。
先生にはそれぞれ個性や考えがあり、それぞれのクラスに在籍している子どもたちも一人ひとりが違う存在です。その状況で「みんな同じように学ぶ」というほうが、むしろ不自然で難しいのではないでしょうか。
保護者の意識が変わった! クラスに生まれた良い循環とは?
ーー先生方への理解は、出すぎる杭になることで防げたかと思いますが、保護者からの理解を得るのは難しい気がしますが、いかがでしょうか?
山田:たしかに、保護者の考えを変えていくのは簡単ではありません。それでも諦めるのではなく、それぞれの先生が自分の影響の及ぶ範囲で少しずつ変えていくことが大切です。まずは先生自身が変わり、その変化が子どもたちの学びに表れ、楽しそうに学ぶ姿が保護者に伝われば「この学び方はいいな」と感じてもらえるはずです。
実際、私がプロジェクトベースの授業を実践していた茅ヶ崎市の香川小学校では、そんな良い循環が生まれていました。授業に参加した保護者からは、「探究学習で学力が維持できるのか不安だったけれど、授業を見て安心した」「発達特性のある子も、プロジェクト型学習の中では、その子の持ち味が生きている」といった声がありました。
探究学習は、必ずしもテストが得意な子だけが活躍するわけではありません。むしろ従来の“学力”で測れるものは、子どもの力のほんの一部にすぎないと実感するのです。
さらに良かったことは、保護者自身が授業に参加し、子どものころには経験できなかった学びを楽しんでくれたことです。学校が保護者をも巻き込み、共に学ぶ場になる――その可能性を強く感じました。
実際に私の授業に参加していただいた保護者の方々からは「もう一度青春している気分」といった非常に前向きな意見がありました。子どもたちと同じように課題に取り組み、仲間と協力して発表する、そうした経験は大人にとっても新鮮で、かつての学校生活を思い出させるものだったのでしょう。つまり“改めて学びに接すること”そのものが、青春を追体験するような楽しさにつながったのだと思います。
学校は子どもに教えるだけ、保護者は見守るだけ、という一方通行である必要はありません。子どもと保護者が一緒に学び、楽しみ、充実した時間を過ごす。そんな未来を、プロジェクトベースの学びは切り拓けると思っています。
そのためにも、保護者の方には「先生ごとに異なる学びのかたち」を認めていただきたいと思っています。先生も保護者も目指すところは同じ――「子どもたちに質の高い教育を」「子どもたちの幸せを」なのですから。
プロジェクト型授業は全国に広がる? これからの学びの方向性
ーー学びの形を変えることや、先生ごとの個性ある授業の実践は、全国の小中学校でも実践できると思いますか?
山田:学びのあり方は、今まさに大きく変わってきています。例えば東京都渋谷区では『探究「シブヤ未来科」』という独自の探究プログラムが始まっています。文部科学省の「授業時数特例校制度」を活用し、総合的な学習の時間を拡張しているんです。
渋谷区の教育委員会は、人材バンクのような仕組みをつくり、登録企業と連携しながら小中学校の探究学習をサポートしています。教科の枠を超えた学びを通じて、子どもたちが「社会とつながりながら生きる力」を育むカリキュラムになっているのです。
こうした事例に見られるように、これからの教育の方向性は「子どもの発想や学びをどう社会に生かすか」「社会とどうつながるか」という点に向かうと思います。実際に小学校でも動きが出ていますし、大学でも同じ潮流があります。
探究学習を進める方向性は正しいと私は考えています。ただ一方で、社会全体として「これまで学力として測られてきたものをどう扱うか」という課題は残ります。だからこそ、私自身が実践しているように、教科学習の要素を探究学習の中に埋め込み、融合させていくことが大切だと思っています。
私が考えているのは、学校だけでなく保護者や地域も含めて「子どもたちの学びの場」を一緒に支え、共通の目標を持つことです。「学校は座って授業を受けるだけの場所じゃない」「〇〇を目指したいよね」といったビジョンを共有し、その実現に向けて先生はそれぞれの個性や持ち味を生かす。そうした多様性を認め合える仕組みが必要だと思っています。だからこそ、私は日々、個人としても実践を重ねているのです。
◇◇◇◇◇◇◇◇
いま社会全体の学びは探究型へとシフトしています。その変化のなかで、保護者もまた「学び」や「学力」に対する考え方を少しずつ柔らかくアップデートしていくときかもしれません。きっとそれが、子どもたちにとってより豊かな学びにつながっていくのではないでしょうか。