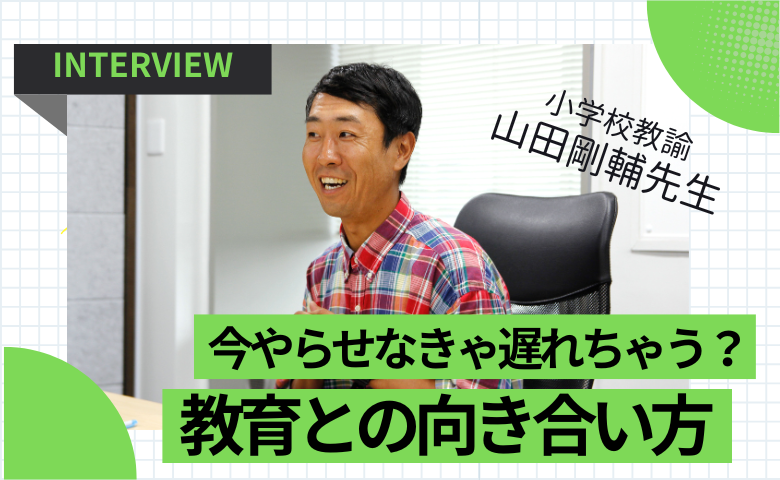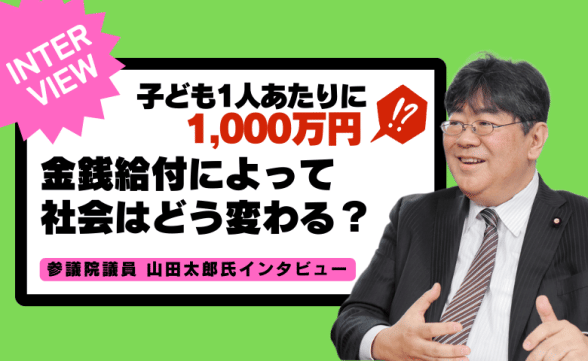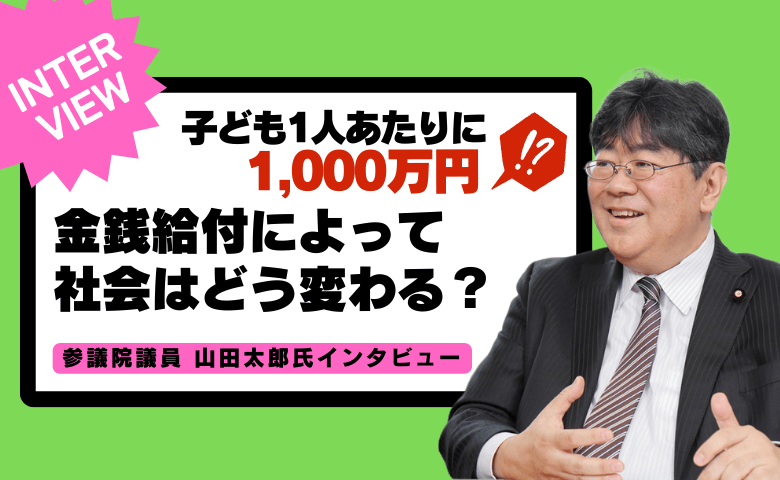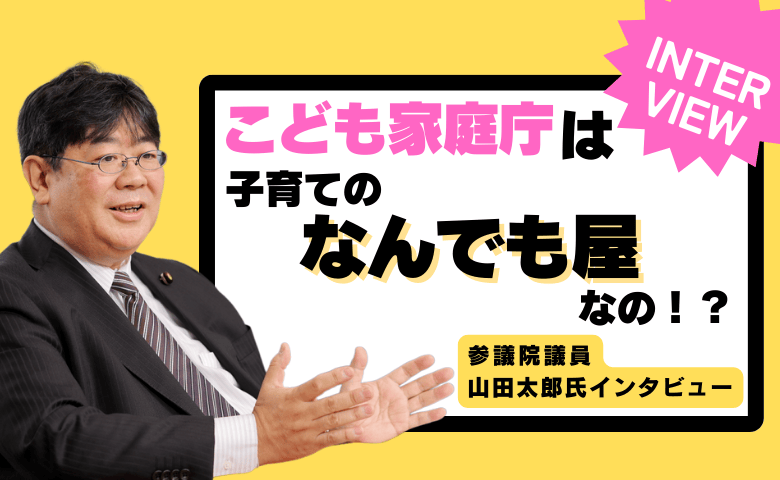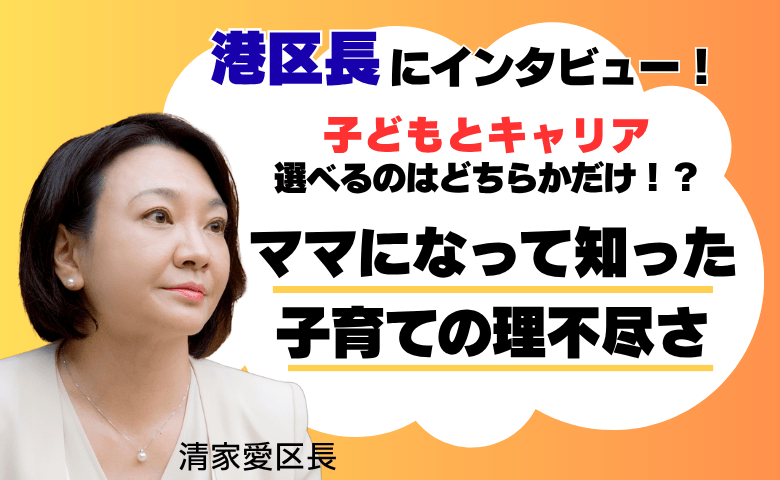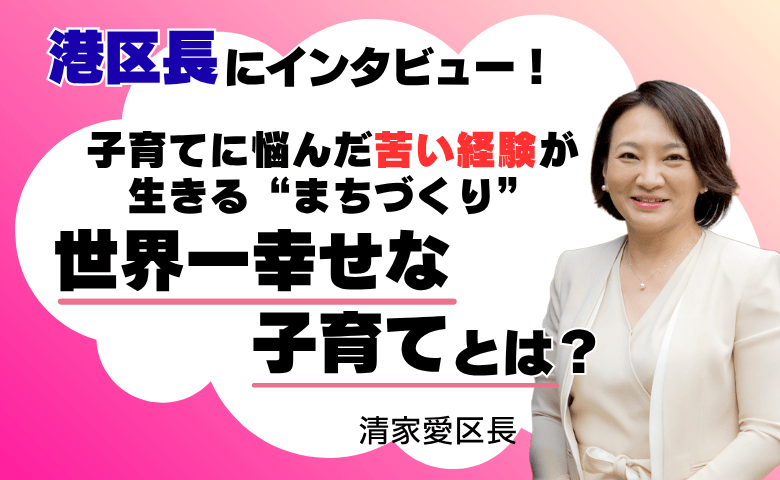時間割を設けず、子どもたちと一緒に問いを立てて学ぶ“プロジェクト形式”の授業を実践する山田剛輔先生に、未就学児の勉強の是非や習い事との向き合い方についてお話をうかがいました。
幼少期の子どもに勉強は必要?
――近年、未就学児から読み書きや計算を始めたほうがいい、という考えもあります。英語や塾などに早くから通い始める家庭もありますが、先生ご自身は子どもの学びについてどうお考えですか?
山田剛輔先生(以下、山田):子ども自身が「やりたい」「楽しい」と思えることなら、どんどんやらせていいと思います。体調や睡眠を整えるのは保護者の役割ですが、心身を害さない限り、子どもの意志を尊重してほしいですね。
一方で、たとえ将来に役立つことであっても、子どもが「今はやりたくない」と感じているなら、無理にやらせる必要はありません。モチベーションが下がり「学ぶこと=嫌なもの」と結びついてしまう危険があるからです。
大人だって同じですよね。仕事で疲れて帰ったあとに、自分にとって必要性を感じられない資格の勉強をしなさいと言われたら苦痛です。子どもはなおさら将来を見通せないので、「今やりたくないこと」に向き合うのは難しいのです。
もちろん、「食わず嫌い」をしないために、まずは経験してみることは大切です。ただし無理は禁物。やってみて楽しいと思えたら続ける、そうでなければ今はやめる。そのくらいのゆとりを大人が持つことが、子どもの健やかな学びにつながるのだと思います。
小学校入学前に大切なのは「愛情」と「想像力を育む遊び」
――そうは言っても、子どもに何かしらを学ばせようとしたり辞めさせないようにしたりすることも大切なのでは……と思ってしまいます。親が子どもにしてあげられることはあるでしょうか?
山田:まずは、乳幼児期にたっぷりの愛情を注いであげてください。小学生を見ていると「親の期待に応えよう」と頑張る子が多いですが、その前提には「無条件に愛されている」と安心できる環境が必要です。
「できたから愛される」のではなく、「自分の存在そのものが大切にされている」と伝わること。これが子どもに自信を与え、挑戦する力につながります。逆にその安心感がなければ、子どもは自分からチャレンジすることなく、親の言う通りにする、もしくは、親に反発することにもつながってしまうかもしれません。
そして幼児期に欠かせないのが「遊び」です。ここでいう「遊び」は、主体的に自分で興味を持ったものを自分でやりたい方法でおこなうこと(探索や探究)で、それこそが「学び」です。これは、教えられる「勉強」とはまったく異なります。
特に自然に触れる体験――たとえば、虫や草花との出会いは知的好奇心や学ぶ意欲を大きく育ててくれます。そのとき「おもしろいね」と共感してくれる大人がそばにいると、子どもの主体性はさらに伸びていくでしょう。
そばで見守る大人に求められるのは「遊び」に没頭する子どもたちに共感して一緒に楽しむことです。誰しも自分の経験したことに「共感」してくれないと、つまらなくなってやめてしまうでしょう。それは子どもも同じです。共感して一緒になっておもしろがってくれる人がいないと、せっかくの好奇心や意欲をなくしてしまいます。
「ママパパ、見て!」という子どもたちの声を、ひとつずつていねいに拾って、子どもの感性と感覚を味わいながら楽しんでいただきたいですね。そして大人の決めた“正しい遊び方”にこだわらず、安心して自由に遊べる環境を保証してあげること。それこそが親の大切な役割だと思います。
ーー自然が身近にない場合、日常的にできることはありますか?
山田:主体性が育つ「遊び」がいいと思います。幼児期におすすめしたいのは、積み木のように可変性がある材を用いた「工夫の余地」のある遊びです。積み上げて形を変えたり、ドミノのように並べたり、同じ色を集めてみたり、自分なりの遊び方を広げられるものが理想的です。
大人がアイデアを添えることは大切ですが、最終的にどう遊ぶかは子どもが決める――その自由さが想像力を育てていきます。
ある事例から考える、早期教育の落とし穴と自主性の大切さ
ーー早期教育について「本当に子どものためになっているのか」と悩む保護者は多いと思います。先生が印象的だったケースはありますか?
山田:実例として印象に残っている親子の話があります。高校3年生の女の子が、お母さんと一緒に私の講演会に来てくれました。その子は努力を重ね、どこの大学にも合格できる学力を身につけていました。
早期教育は、やっているときはたしかに学力がついたように感じます。でもその一方で、「親に言われたことをやれば大丈夫」という考え方も身についてしまう。つまり、自分で考える力を奪ってしまっているのです。
その女の子も「自分が何をしたいのか」「自分の得意なことや好きなことは何か」がわからず、進学先を決められずに浪人することになりました。誰かに教えられてきたことの成果は出せたけれど、自分の夢や気持ちは置き去りになってしまっていた。――これは、親主導の早期教育や詰め込み教育の弊害といえるでしょう。
だからこそ、幼児期には自由な発想を広げるための「遊び」の時間が必要なのです。
子どもの人生は子どものもの 「やりたくない」をどう受けとめるか
――子どもが「やりたい」と言って始めたことなのに、「やりたくない・やめたい」ということも少なくありません。これは保護者にとって対応に迷う事態です。山田先生の授業でも、子どもがモチベーションを高く持って取り組めないこともあると思います。そういった子どもにはどのように関わっていますか?
山田:私はまず「子どもの声を聞く」ことを大切にしています。たとえば過去に「マット運動をやりたくない」と言った1年生がいました。その子はみんなと一緒にはやらないけれど、体育館の隅でこっそり同じ動きをしていたんです。つまり「やりたくない」と言っても、本当はやりたい気持ちや興味が隠れている場合があるんですよね。
子どもの「やりたくない」には、実はさまざまな理由があります。「失敗したくない」「友だちに見られるのが恥ずかしい」「実はやりたいけれど気分が乗らない」など、その背景を理解しないまま大人が「やりなさい」と押しつけてしまうと、子ども自身の意思を奪ってしまいます。
だから私は「やらないならそれでもいい」と選択肢を残しながら、まずじっくりと話を聞いて、なぜやりたくないのかを探ります。その上で「どうすればできそうかな」「どんな工夫をすれば気持ちが前向きになるかな」と一緒に考えます。小さなハードルを下げたり、遊びの要素を取り入れたりすることで、子どもは自然とチャレンジできるようになるのです。
目標に届かない瞬間があっても、その子なりのペースで進んでいけばいい。学校のカリキュラムも本来は「授業の1時間でできるか」ではなく、学期や年度といった大きなスパンで成長を見守るべきなんです。
子どもが自分の選択に責任を持ち、自分の人生を生きていると感じられるようにすること。それが「やりたくない」を受け止める大人の姿勢だと思います。
わが子の力を引き出す学びの環境に出会うには?
ーーわが子にとって「安心して学べる場所」や「好奇心を伸ばせる出会い」を用意したい、と考える保護者は多いと思います。そうした環境に出会うためにできることはありますか?
山田:公立の学校は住む地域で決まり、先生も異動があるため、「学校そのもの」を選ぶのは難しいのが現実です。ただし、学校の雰囲気は保護者や子どもたちの関わり方で大きく変わります。そのため、先生との関係づくりが欠かせません。距離を取りすぎず、ざっくばらんに話せる関係でいると、保護者からの提案も受け入れられやすくなります。
また、保護者同士のコミュニティもとても大切です。価値観が似ていて気が許せる仲間とつながり日々の悩みや情報を共有し合うことで不安が減り、親が前向きに過ごせると、子どもにとってよい環境を作ることができます。つまり学びの環境との出会いを待つのではなく、「作る」という考えです。
学校を作るのは先生だけではありません。保護者も一緒に関わることで、子どもにとってより良い学びの場になるのです。小学校の6年間は本当にあっという間ですから、先生や保護者仲間と一緒に支え合える環境を作って、今しかない児童期の子育てを子どもと共に楽しんでいただきたいと思います。
「自分の人生の主人公は自分」これから大人になる子どもたちへ
ーーでは最後に、これから大人になっていく子どもたちに、先生からメッセージをお願いします
山田:子どもたちには「自分の人生の主人公は自分なんだ」という意識を持って生きてほしいと思っています。誰かに任せるのではなく、自分の手で未来を切り開いていく存在だということを理解してほしいのです。
ゲームの主人公のように、自分の行動次第で物語が変わっていく。その感覚を大切にしてほしいと思います。私自身にも言い聞かせていることですが、やりたいことを楽しみ、目的を見つけて学ぶことが、人生を前に進める力になります。
小さいうちは目的がなくても構いません。欲求のままに遊ぶことが学びになります。学年が上がれば「なぜこれをやるのか」という目的を意識できるようになり、学びがより深まります。たとえば「ひらがなの勉強」を「次の1年生のために教室の表示を作る」と結びつけると、学びが他者や社会とつながり、主体的に取り組めるようになります。
私は「アンパンマンの歌」が好きなのですが、「何のために生まれて、何をして生きるのか」という歌詞は、まさに人生のテーマそのもの。そこから逆算して「今、自分はどうありたいか」を考えていくことができます。子どもたちにも、成長の過程でそうした目的意識を持ってほしいと願っています。他でもない「自分の人生の主人公は自分」なのですから。
ーー保護者の方へ、伝えたいことはありますか?
山田:お伝えしたいのは「子どもの人生は親の人生とは違う」ということです。子どもは子どもの人生を生きる存在です。だからといって突き放すのではなく、一緒に伴走する存在でいてほしいと思います。その過程で、親自身も新しい学びや気づきを得られるはずです。
子育ては大変なことも多いですが、その大変さも含めてかけがえのない経験です。子どもがいるからこそ味わえる喜びや悩みがあり、それ自体が人生の豊かさにつながります。
このような話をしていると「もう間に合わない、取り返しがつかない」と思う人もいるかもしれません。たしかに過去を取り戻すことはできませんが、「今」から関わり方を変えることはできる。どの瞬間からでも遅すぎることはありません。教育も同じで、自分にとっての当たり前が社会にとっての当たり前とは限りません。だからこそ常に子どもと一緒にアップデートし続けることが必要です。
大切なのは、教育を「与えられるもの」と捉えるのではなく、大人も子どもも地域も一緒に関わり合って育んでいく姿勢です。それぞれの立場にしかできない役割があります。保護者、学校、地域がチームとなり、子育てを楽しみながら支えていける社会になればと思います。
◇◇◇◇◇◇◇◇
子育てには「こうすればいい」と頭では理解していても、思うようにできないことがたくさんあります。日々の生活のなかでは「このままで大丈夫だろうか」と不安になり、つい先回りしたくなるものです。親心として心配が尽きないのは当然であり、誰もが迷いながら歩んでいるのだと思います。
だからこそ、山田先生のお話は、時々思い出して軌道修正できる道標になるのではないでしょうか。
親もまた子どもと同じように成長の途中にあります。もし、接し方を間違えてしまったと思うことがあっても、それはこれから先の糧。「子どものためにこうすべき」という重い肩の荷が、少しでも和らぐきっかけとなれば幸いです。
ベビーカレンダーはこれからも、保護者や先生はもちろん、地域で子どもを育てる社会を目指して情報発信を続けてまいります。