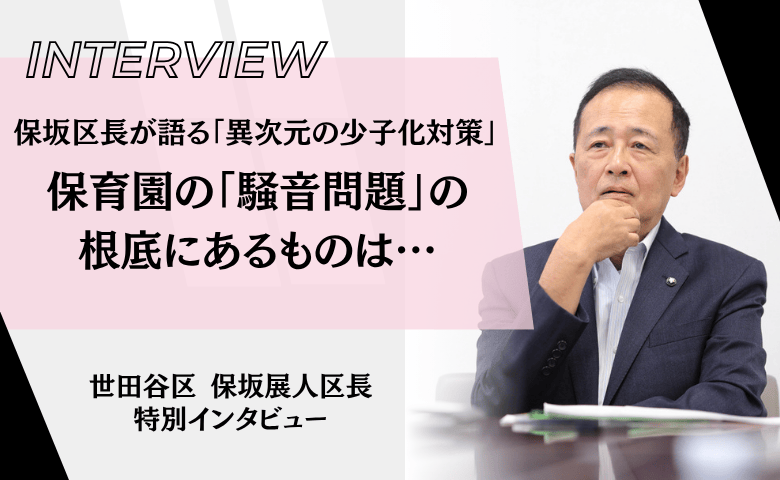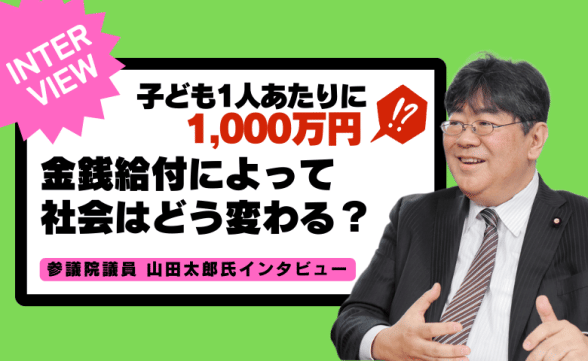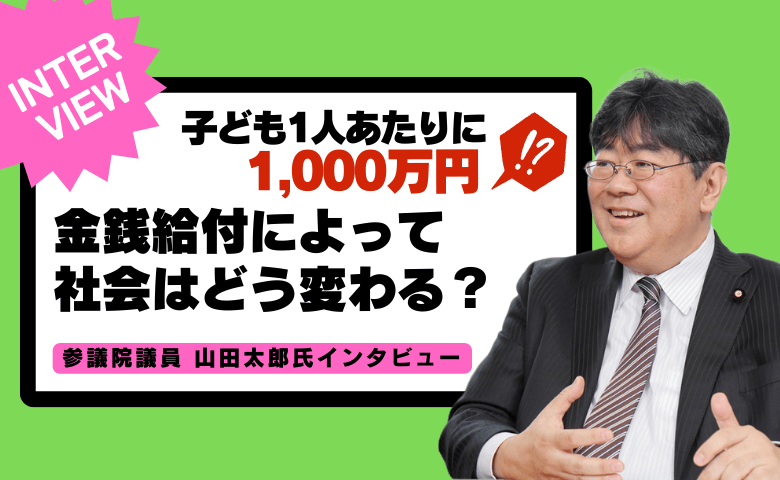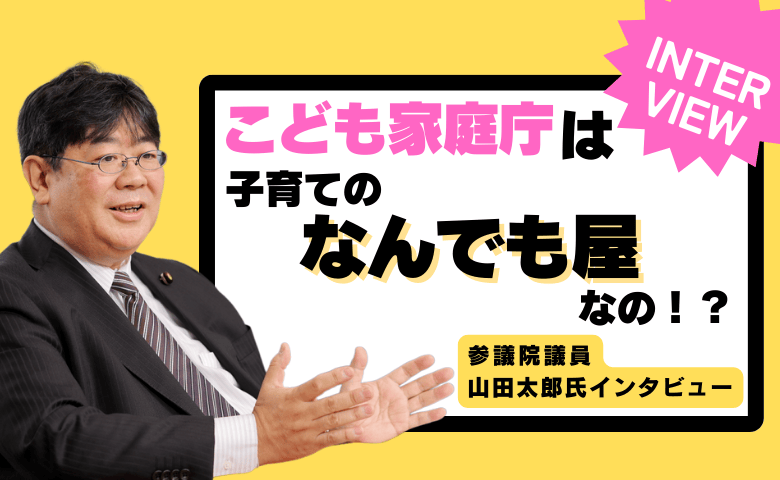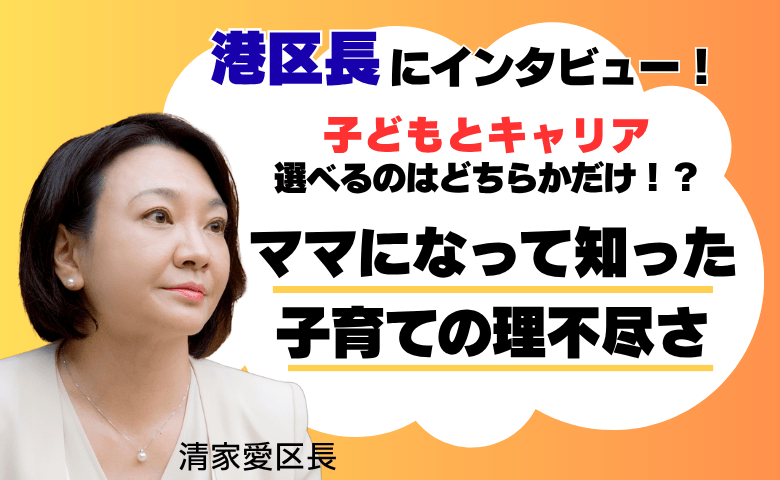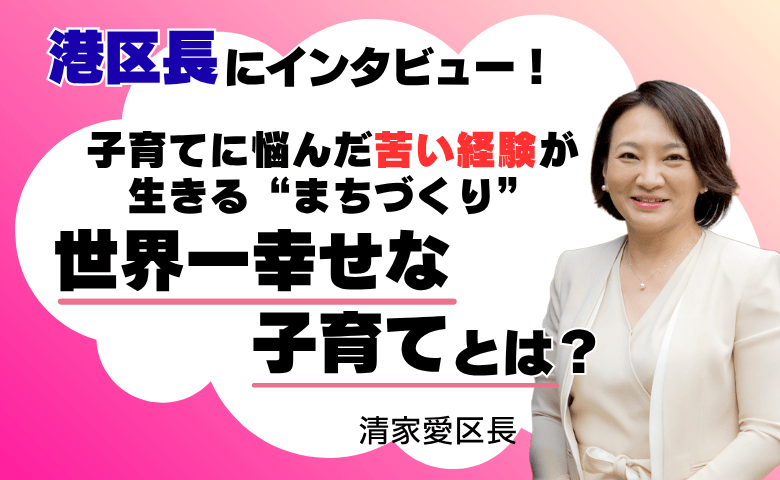「子どもの声は騒音ではない」ドイツの事例をヒントに、地域と歩んだ保育園の結末
──「子どもの声は騒音か?」という保坂区長のSNS投稿が話題になっていましたが、その投稿にはどのような背景がありましたか?
保坂展人区長(以下、保坂さん):区長宛てのメールで、ある保育園に連日「子どもの声がうるさい」という苦情が住民から寄せられていたことがわかりました。
その対応として、園側は「午後は園庭を使わない」という覚書を住民と交わしており、さらには防音壁の設置にも数百万円の予算が投じられる予定でした。
保育園も区の担当者も、非常に難しい立場に置かれていました。苦情に対応しなければならない一方で、子どもたちの健やかな成長も守らなくてはいけない。先生方も相当悩まれていたと思います。
でも、これは単なる騒音問題ではなく、地域が子どもをどう受け止めるかという“社会の在り方”が問われていると感じたのです。午後の外遊びを制限するということは、子どもたちの「遊ぶ権利」を大人が奪うことになる。たとえ住民の声でも、おかしいものはおかしいと伝えなければならない。そこで私は、どうしたら子どもを健やかに育てられる地域になるかを考えるにあたり、他国の事例を調べることから始めました。
するとドイツのハンブルクでも同様の問題が起きていたんです。幼稚園が騒音規制に抵触し、閉鎖の危機にあったのですが、保護者たちが抗議活動をおこない、「子どもの声は騒音ではない」と訴えました。この声が届き、ベルリン市では「子どもの声を騒音の対象から除外する」という法改正がおこなわれました。日本とは真逆の動きです。
振り返れば、私たちが子どものころは、外で大声を出して遊ぶのが当たり前でした。でも今は、自由に遊べる場所がどんどん減っている。そんな中で「声がうるさい」と言われてしまえば、子どもたちはどこで育てばいいのでしょうか。
子どもを健やかに育てることは、社会全体の責任です。子どもが育たなければ、社会保障や経済だって持ちません。
そこで世田谷区は、2015年に「子ども・子育て応援都市宣言」をおこない、「子どもは地域の宝であり、未来の希望」と明記しました。この宣言は、職員たちへの後押しにもなりますし、地域の理解を得るためのメッセージでもあります。
──「子どもの声がうるさい」という苦情に対しては、どのような対策を取られましたか?
保坂さん:住民に向けて何度も説明会を開きました。10回、15回、20回…2年ほどかけて丁寧に対話を重ね、子どもの声の大切さや保育園の役割を伝えました。
結果として、住民の皆さんが保育園の行事に関わってくださるようになり、子どもたちの声の印象そのものが変わっていったのです。
──保育園の「騒音問題」は一定の解決をしましたが、そもそもなぜこのような問題が起こるのでしょうか?
保坂さん:根底にあるのは、子育て世代と地域社会の分断です。特に都市部では、子育て家庭が孤立しやすく、周囲とのつながりが希薄になっています。この分断を乗り越えるには、若い世代が地域に根を張って暮らせるような環境づくりが必要です。それが、結果的に少子化の抑制にもつながると考えています。
進む少子化、止めるには?保坂区長が語る「異次元の少子化対策」
──少子化を止めるために、自治体や国に必要なことは何でしょうか?
保坂さん:最も重要なのは「安心して暮らせる住まい」の確保です。今の若い世代が、結婚や子育てを前向きに考えられるようにするには、公的な住宅環境の整備が不可欠だと思います。
かつては国が積極的に公営住宅を供給していましたが、25年ほど前からこの役割を民間に委ねるようになりました。その結果、住宅費が高くなり、若い世代にとっては大きな負担となっています。これは韓国とも共通する課題です。韓国も、家を借りるにも買うにも多額の初期費用がかかるため、結婚や出産をためらう要因になっている。そうした構造を変えなければ、少子化は止まりません。
人口が減れば、労働力も減り、医療や福祉はもちろん、日常のサービスすら維持が難しくなるでしょう。移民政策という選択肢もありますが、他国では文化や価値観の違いによる摩擦が起きています。
だからこそ、今こそ公的な責任として、若者が「ここで暮らしていける」と思える住宅政策を進めるべきです。少子化対策を「個人の努力」だけに押しつけるのではなく、社会全体の基盤として支えることが必要なのです。

大胆な対策は“国主導”でこそ意味がある
──子育て支援として、住環境の整備が重要とのことですが、それは国と自治体、どちらの役割でしょうか?
保坂さん:本気で少子化を食い止めたいのなら、大胆な対策を市区町村レベルだけに任せるのではなく、国が中心となって進めるべきだと思います。まずは、若い世代が安心して暮らせる「住まい」を国の責任で整備し、経済的不安を減らすことが最優先です。住宅問題が解決されないままでは、結婚や出産に踏み出せない人は多いでしょう。
もちろん、自治体が独自にできることもありますが、限界があります。だからこそ、国が柱となって住環境を整備し、自治体はそこに独自の支援を上乗せする形が、最も効果的だと考えています。
◇◇◇◇◇◇◇◇
「子どもは地域の宝であり、未来の希望」世田谷区が掲げたこの宣言は、一地方自治体のスローガンにとどまらず、社会全体への問いかけでもあります。子どもの声を“騒音”と捉えるのか、“未来への希望”と受け止めるのか。その価値観の違いが、日本の社会の在り方を大きく左右するのではないでしょうか。
次の世代を育てる責任は、決して親だけのものではありません。地域、自治体、そして社会全体が一体となって子どもたちを支えていくことが求められています。
世田谷区のような取り組みは、全国の自治体にとってもひとつのヒントになるはずです。人口減少や地域の活力低下が懸念される今、子どもや子育て世代をどう支えていくかは、すべての自治体に共通する重要な課題です。
子育てしやすい街を目指す挑戦は、地域の未来を守る挑戦でもあります。しかし、真の変革を実現するには、自治体の努力だけでは限界があります。国全体が子どもや若者を支える社会づくりに本気で向き合い、制度と予算の両面で支援していく。その覚悟こそが、これからの日本に必要とされているのではないでしょうか。