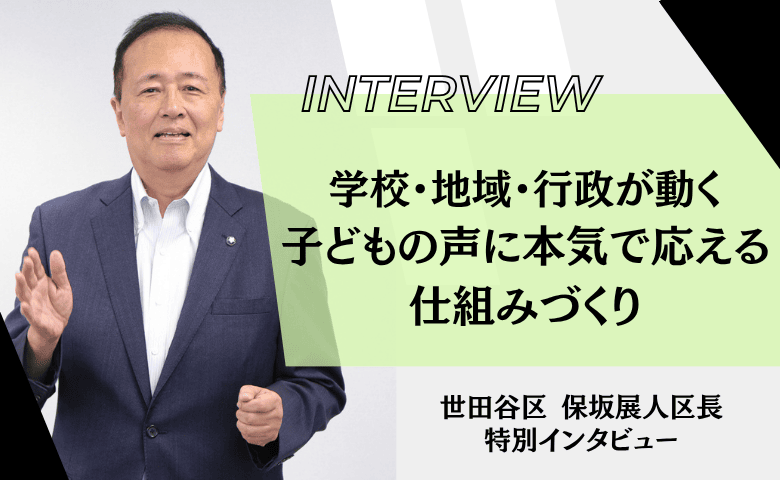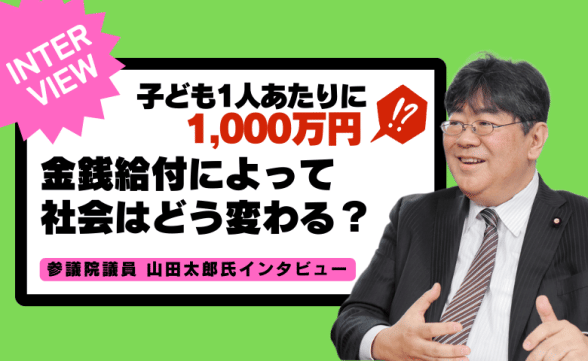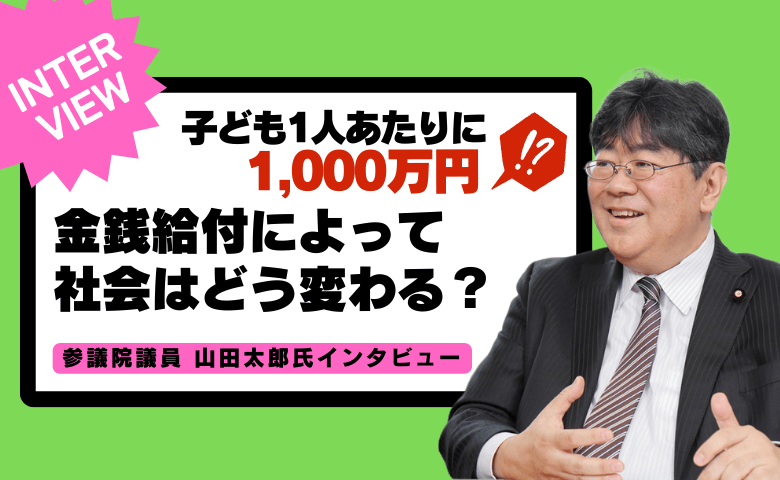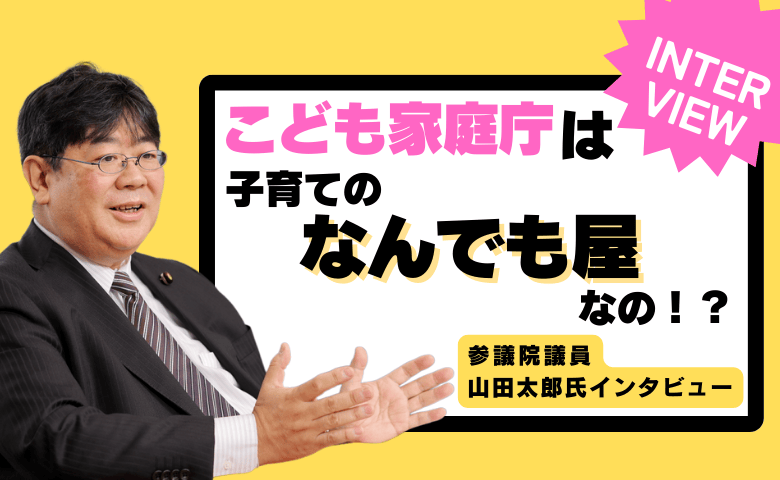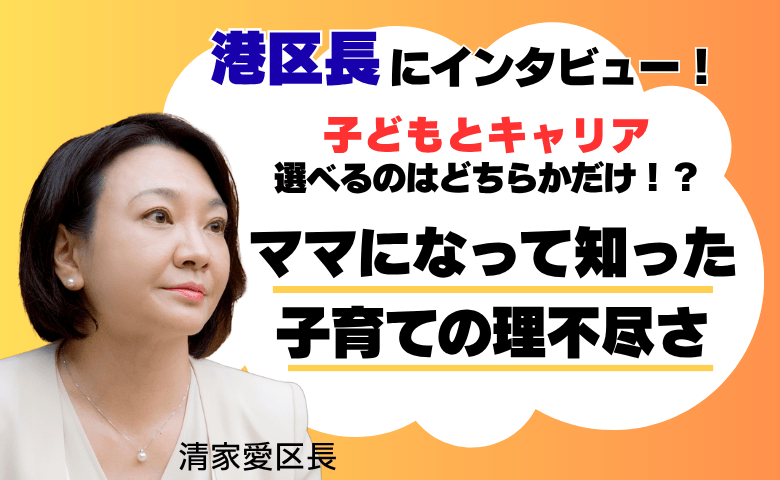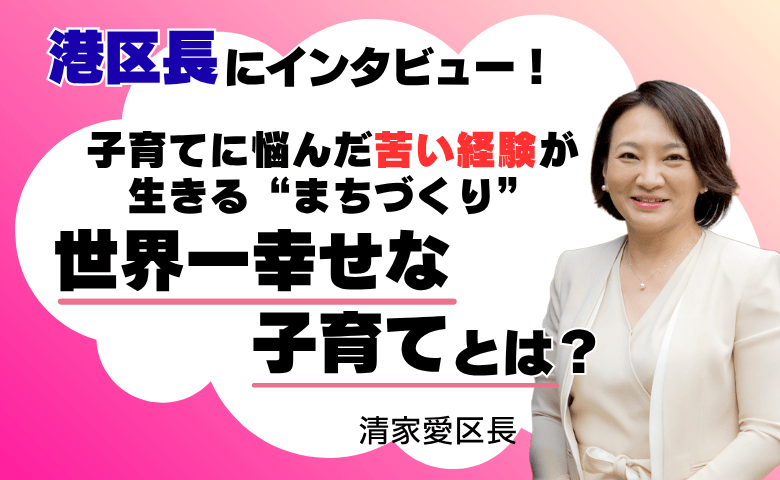「せたホッと」は単なる相談窓口ではなく大人が本気で動くための仕組み
──「せたホッと」がどのような経緯で立ち上げられたのか、設立の背景や仕組みを教えていただけますか?
保坂展人区長(以下、保坂さん):私が教育ジャーナリストとして活動していた1980年代から90年代にかけて、校内暴力やいじめが深刻な社会問題になりました。子どもたちは学校や家庭で抱えたストレスを暴力やいじめという形で発散してしまうことが多く、問題の根はとても深かったんです。
そのころ、子ども向けの電話相談システムとして、留守番電話を活用した仕組みが生まれました。子どもがまず留守電に悩みを吹き込み、それに対して後日、ラジオ形式で回答を返すという形です。この方法が予想以上に支持され、電話が鳴り止まないほどの反響がありました。それだけ多くの子どもたちが、声を聞いてほしいと願っていたのだと痛感したのです。
しかし本来は「直接会って話す」ことが大切。でも現実には対応が追いつかない。その解決策を探る中で、私はイギリスに渡り、「チャイルドライン」という民間による相談システムを取材しました。ここで学んだのは、相談者を“癒やす”だけでなく、“問題の根を断つ”支援のあり方でした。
私が区長になるとき、「子どもの立場に立って、いじめや暴力といった人権侵害の声を聴く」と公約していました。その思いを形にするため、区内の中高生を対象に意識調査を実施。その結果をふまえて、「せたホッと」の設立に踏み切りました。
単なる相談窓口ではなく、子どもがひとりで抱え込まずに済むよう、大人が本気で動くための仕組み。それが「せたホッと」の原点です。2025年で12年目を迎えますが、今も子どもたちの声に耳を傾け、具体的な行動に結びつける姿勢は変わっていません。

「せたホッと」はどう利用されている?子どもを支える仕組みと今後の課題
──「せたホッと」には、子どもたちからどのように相談が寄せられているのでしょうか?
保坂さん:もっとも多いのは、ハガキでの相談です。固定電話を置いていない家庭も増えており、特に低学年の子どもたちにとっては、電話はハードルが高いのかもしれません。そのため、ハガキのほか、対面や電話による相談も用意していますが、手紙(ハガキ)が今でも主な手段です。
──子どもたちに「せたホッと」はどれくらい認知されていますか?
保坂さん:以前の調査では、小学校低学年で約45%、高学年では約78%、中学生では74%と、かなり高い認知度を示しています。
──具体的に「せたホッと」は、どのような形で問題解決に関わっているのでしょうか?
保坂さん:大きな特徴は、「相談を聞くだけで終わらない」という点です。子どもの権利擁護委員が相談内容を精査し、必要と判断した場合は、学校現場に介入します。臨床心理士ら専門職2名以上でチームを組み、担任や校長と面談し、どうすれば問題を解決し、日常を取り戻せるかを一緒に考えます。
必要であれば、やりとりを何度も重ねて改善を図り、最終的には学校で「いじめ防止授業」を実施するところまでサポートします。これは「子どもの話を聞いて終わり」ではなく、大人が本気で動き、信頼を回復するプロセスそのものです。
──年間の相談件数の変化や実際に解決につながった事例などありますか?
保坂さん:2024年度の新規相談件数は362件と、設立以来2番目に多い問い合わせがありました。相談の内容は対人関係の悩みやいじめ、学校・教職員等の対応、心身の悩み、家庭・家族の悩みなどです。
設立当初は「せたホッと」ってどんなところだろう、と思いながら相談してきた相談者が多かったのですが、最近では誰かに話をしたいので「せたホッと」に電話をした、手紙を書いたという子どもたちが増えています。
相談者の中で「せたホッと」は安心して話を聴いてもらえるところ、という認識が広がってきたんだなと感じています。
──せたホッとの支援が入ったことで、学校の対応や雰囲気に変化は見られましたか?
保坂さん:今では「せたホッと」が間に入って相談支援や対応、関係調整することを歓迎する動きが広がっています。特に保護者と学校が対立しているケースでは、往々にして子どもの意見が置きざりにされることが少なくありません。
「せたホッと」が間に入り、あらためて子どもの最善の利益の視点から問題解決を図ることで、保護者・学校間の対立を回避することもできるため、公的な第三者機関としての「せたホッと」の役割に期待されていることも多くなっています。
──そこまで踏み込む理由は何でしょうか?
保坂さん:私が教育ジャーナリストだったころ、「自分なんか生まれてこなければよかった」「いじめられる自分が悪いんだ」と語る子どもに何人も出会いました。そんな考えを子どもに持たせてしまう社会ではいけない。すべての子どもはかけがえのない存在です。
だからこそ、「せたホッと」は相談の秘密を守り、子どもたちの信頼を最優先にしながら、大人が行動する姿を通じて、「大人は信じていい存在」だと感じてもらうことを大切にしています。

学校と地域が手を組むには?「せたホッと」に見る介入と協働の実践
──学校側は外部機関が入ることに、抵抗はなかったのでしょうか?
保坂さん:もちろん、最初から快く受け入れられたわけではありません。特に公立校は「せたホッと」の介入を拒否しませんが、私立校は努力義務にとどまるため、初期は慎重な反応もありました。
それでも活動を積み重ねていくうちに、学校と保護者間ではなかなか解決できなかったトラブルが解決に向かった事例が増え「せたホッとがあってよかった」と言っていただけるようになりました。今では学校側から相談や支援依頼が寄せられることもあります。
──10年以上の運用の中で、今後の課題はどこにあると感じていますか?
保坂さん:これからの課題は、「家庭」という一種の密室のような「社会」で起こる親子間のトラブルを適切な手段で解決していくことです。
親子間のトラブルは外からは見えにくく、解決も難しい問題のひとつです。
世田谷区では2020年に児童相談所を設置し、現在は約170人の職員が対応にあたっています。また、区内5カ所にある子ども家庭支援センターでも相談を受け付けており、必要に応じて連携する体制を整えています。
さらに、学童や児童館には約300人、区立保育園まで含めると約1,000人が子育てに直接関わっており、教育関係者も含めれば約7,000人が、互いに情報を共有しながら対応しています。
どこに相談しても、すぐに関係部署に情報が届く体制です。ですから、困ったことがあれば、話しやすい相手に、話しやすい方法で相談していただければ大丈夫です。
◇◇◇◇◇◇◇◇
「せたホッと」は、子どもの声を受け止め、大人が実際に動くことを前提とした相談システムです。話を聞いて終わるのではなく、問題の解決までつなげる、その仕組みを、保坂区長は12年前に世田谷で立ち上げました。その結果、子どもを中心に据え、学校と地域が連携する流れが少しずつ根づいてきています。
現在、世田谷区では約8,000人の保育・教育関係者が情報を共有しながら支援にあたっています。悩みを抱える子どもを社会全体で支える体制づくりは、どの自治体でも求められる課題です。
「大人は信じられる存在であること」。その確信を、仕組みとして見える形にすることが、今求められています。
そして子どもたちのSOSは、決して「誰か」の問題ではありません。私たち一人ひとりが“自分ごと”として耳を澄まし、声をつないでいく。その連鎖こそが子どもたちを守る最大の力になるのではないでしょうか。子どもの声に耳を澄まし、子どもが安心して暮らせる社会になるように願います。