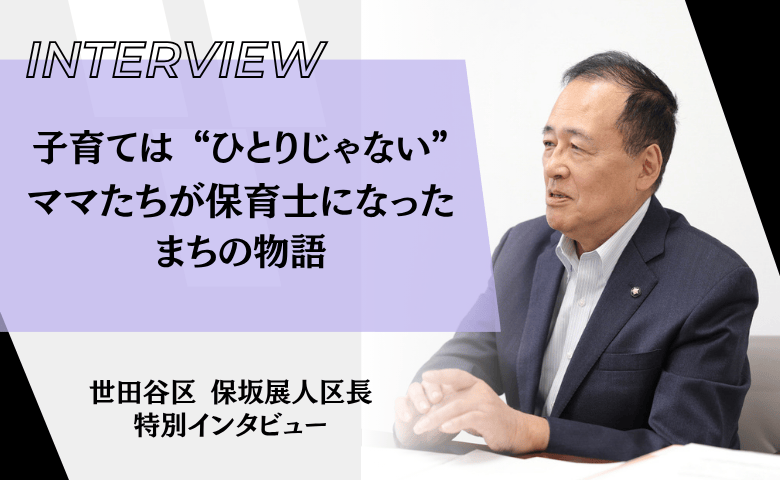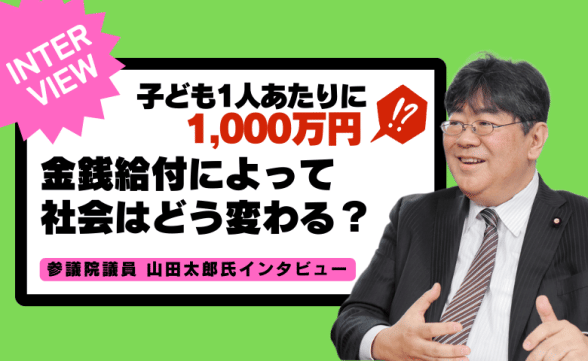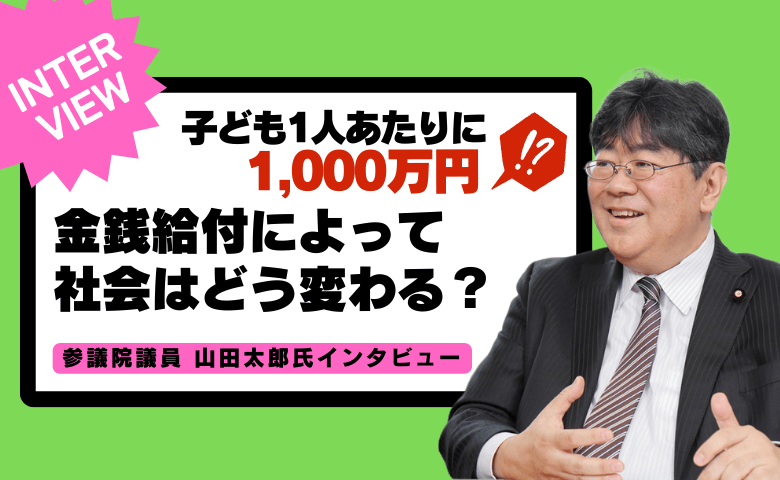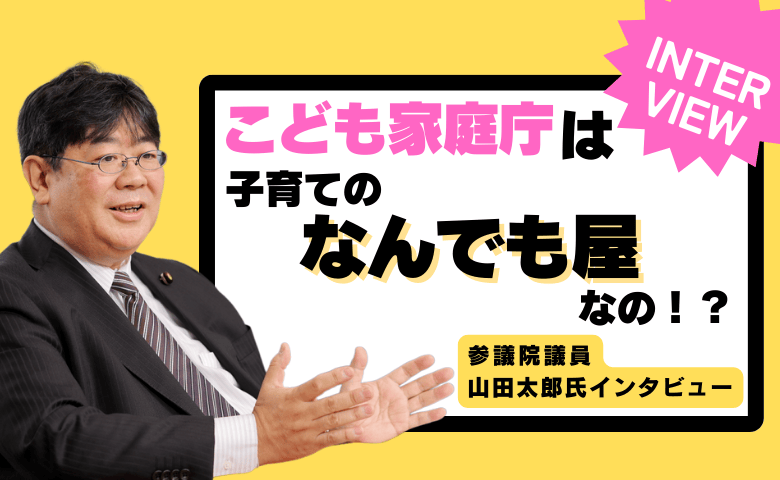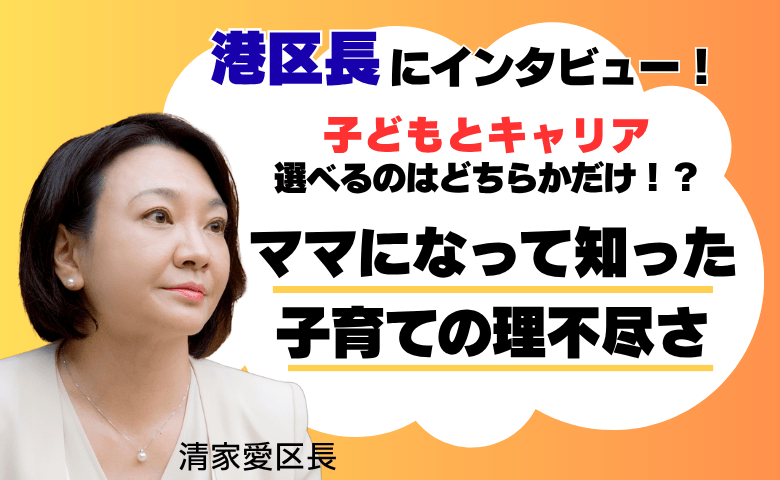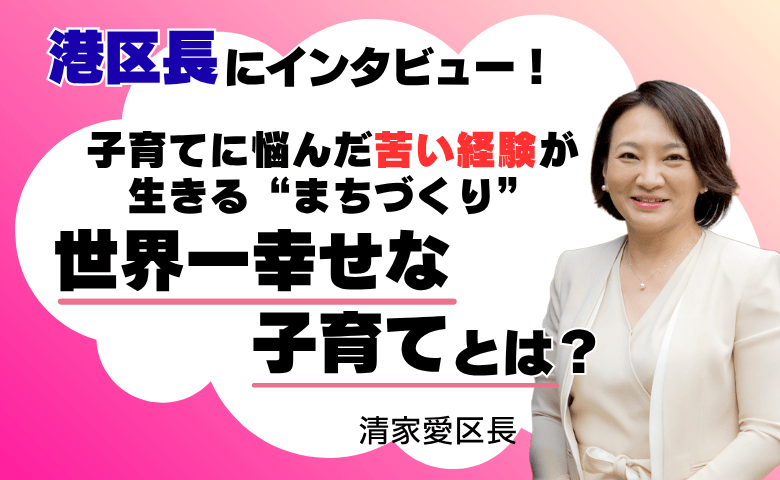保育施設を増やすだけじゃない。世田谷区の“人”に根ざした子育て支援
──世田谷区では「待機児童対策」だけでなく「保育の質」の両立を目指していると伺いました。保育園はたしかに増えていますが、保育士はどのように確保していますか?
保坂展人区長(以下、保坂さん):世田谷区では、子育て中のママたちが保育士として活躍するケースも珍しくありません。というのも子育てが孤立しがちな今、「自分たちも動こう」という意識が住民の間に芽生えつつあるのです。
行政の支援を待つだけでなく、自ら保育士資格を取得して働き始める人や、子育てが一段落した有資格者に声をかけるなど、地域の中で自然と人材の輪が広がっています。これは行政が主導したものではなく、地域に根ざした自発的な動き。その結果、世田谷区では現在、深刻な保育士不足には至っていません。
──区として、人材確保のためにどのような支援をおこなっていますか?
保坂さん:国・東京都・世田谷区の三者が連携し、保育施設運営者に対し、保育士の宿舎にかかる家賃を最大で月8万2,000円まで補助する制度を設けています。家賃の約7/8を公費で支援し、事業者の負担は1/8に抑えられています。
この制度は待機児童が多かった2015年より継続している取り組みで、同制度の導入以降、世田谷区では143の私立保育園が開園しました。
また保育士への支援が手厚いため、幼稚園教諭から保育士資格を取得して転職される方も増えており、今後は幼稚園関係者への支援についても検討すべき課題と捉えています。
保育の質ガイドラインを「子ども目線」で刷新! 視点を変えて課題を解決
──保育にかかわる人材の「質」はどのように担保されていますか? たとえば補助金目当ての事業者が参入すると、保育の質が下がる可能性が考えられます。
保坂さん:世田谷区では、保育の質を守るために独自の「保育の質ガイドライン」を策定し、2025年3月に改訂をおこないました。改訂には区職員だけでなく有識者の意見も反映されており、現場の実情に即した形でアップデートされています。
このガイドラインの大きな特徴は、子ども自身が「自分は守られるべき、大切な存在なんだ」と思える支援をおこなうことです。きっかけは、かつて区内で発生した痛ましい保育施設での事故でした。同じ過ちを繰り返さないため、子どもの尊厳と権利を中心に据えた「子どもファースト」の保育を軸にしています。
そのため、たとえ区内に土地を保有していても、厳しい指導や管理中心の方針をとる事業者は保育事業に参入できません。待機児童が多かった当時、「土地があるのに保育園をつくらないのはおかしい」との声もありましたが、私たちは一貫して「子どもの安全と保護者の安心は、なによりも優先されるべき」と考えてきました。
このガイドラインは、保育園だけでなく、子どもに関わるすべての施設・機関・事業や地域が対象です。世田谷で子育てをするすべての家庭が安心できるように、そして子どもたちが健やかに育つ環境を守るために、徹底して運用しています。

「数」と「質」の両立を実現──世田谷区の子育て支援は“声”から生まれる
──区民の声は、どのように集めているのでしょうか?
保坂さん:世田谷区では、誰でも区長に直接意見を送ることができる「区長へのメール」という仕組みがあります。寄せられた声は、私自身と関係部署の職員がすべて目を通し、原則4開庁日以内に回答するようにしています。
──その声から、実際に施策が生まれた例はありますか?
保坂さん:たとえば、フルタイムの保育園だけでなく「一時的に預けたい」というニーズがあることに、メールを通じて気づかされました。これを受け、短時間の保育サービスの導入につながりました。
他にも、きょうだいで別々の保育園に通うケースや、保護者が病気になったときの支援が欲しいという声もあり、順次対応を進めています。
特に印象的だったのは、「“待機児童”という言葉がうらやましい」という、医療的ケアが必要なお子さんを持つ保護者からの2通のメールでした。当時は、医療的ケアが必要な子どもを受け入れられる保育園が区内に存在せず、制度の枠外に置かれたままのご家族がいたのです。待機児童としてすらカウントされない、制度の“隙間”にいる親御さんの切実な声でした。
そこで杉並区が試験的に導入していた医療的ケア対応保育施設を視察し、世田谷区でも早急に導入を決定。現在では、区立保育園5か所で、医療的ケアを必要とするお子さんの受け入れ体制が整っています。
◇◇◇◇◇◇◇◇
保育の「量」と「質」は、本来トレードオフの関係にあるようにも思えます。待機児童を減らすために施設を増やせば、保育士不足や保育の質の低下を招くおそれがある。この難題にどう向き合い、両立を図るかは、すべての自治体に共通する大きな課題です。
地域の保護者が自ら保育士資格を取得し、現場を支え合う動き。家賃補助などを通じた人材確保の仕組み。そして何より子どもが事故に遭ったり、傷付いたりはさせないという決意から「子ども視点」に立った保育の質ガイドラインを整備する取り組みも進められています。
また医療的ケアが必要な子どもを持つ保護者から寄せられた切実な声に応え、受け入れ体制を整備した自治体も出てきました。制度の“隙間”に取り残された声に耳を傾けることこそ、本当の意味での子育て支援と言えるのかもしれません。
子どもたちがのびのびと成長できる環境づくり。それは、単に施設を増やすことではなく、一人ひとりの子どもの尊厳と権利に丁寧に向き合う姿勢から始まります。こうした取り組みは、今後の子育て政策にとって重要なヒントとなるはずです。そして、地域全体で子どもを見守り、保育が“自分ごと”として根づく社会が広がることを願っています。