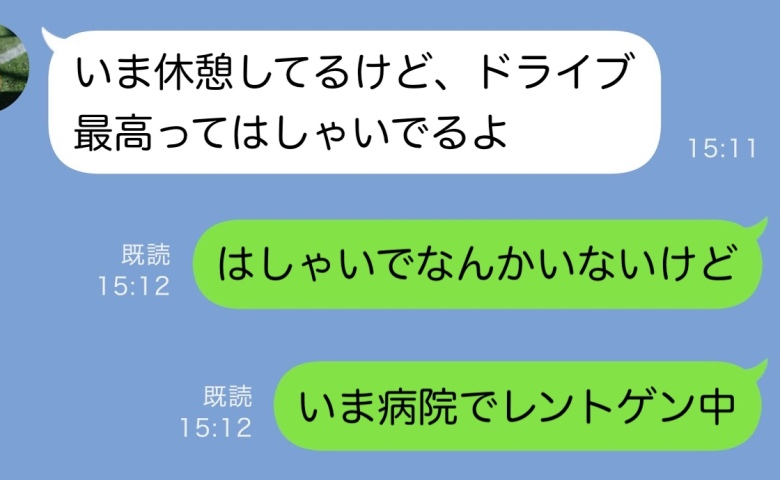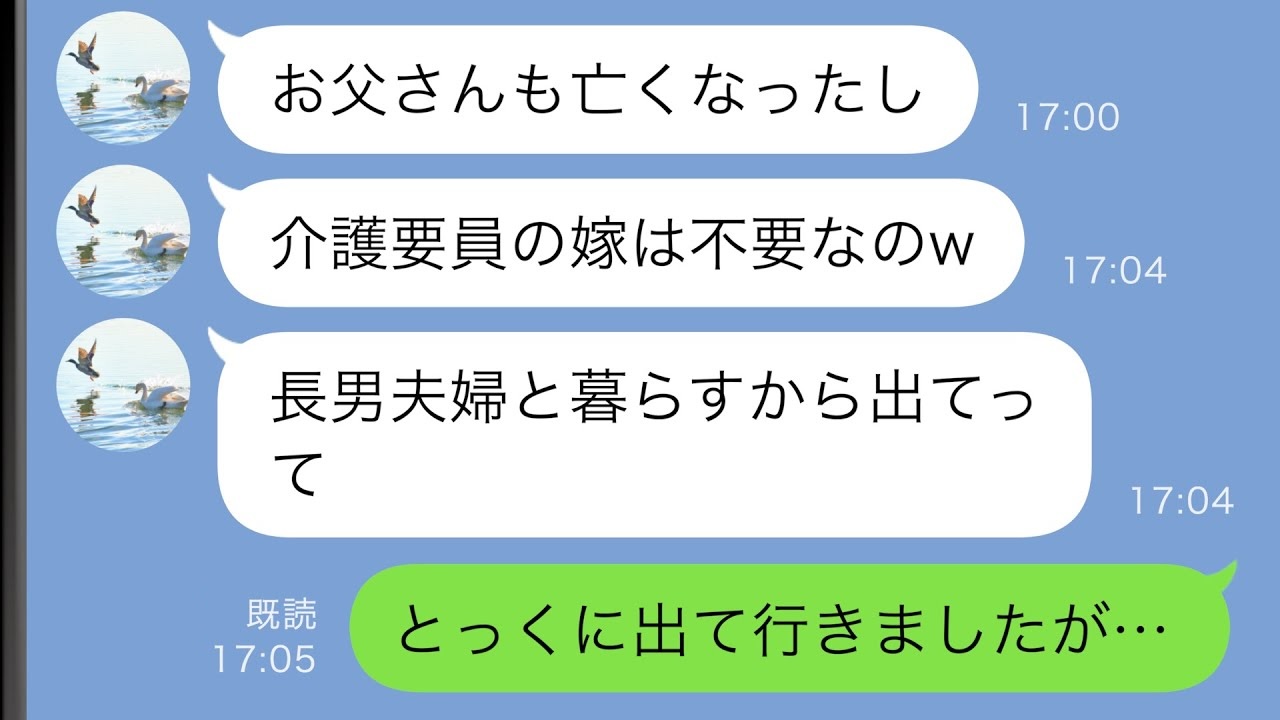自分は期待されていない…悟ったワケは
「今年は優秀な5人と……無能な彼か」部長の低い声が会議室に響きました。たしかに、一緒に入社した同期5人は、みな自分よりもいい大学を卒業しています。そして、最後の一枠は私ではなく、別の人の名前が呼ばれました。
「自分が採用されたのは何かの間違いだったのか?」「研修中に何か失敗したかな?」――そんな考えが頭をよぎったそのとき、隣にいた同期のひとりが「まあ、優秀な人材をみんな欲しがるよね。僕みたいなね? それに比べて君は……」と鼻で笑いながら言いました。その瞬間、社内に自分の居場所はないと悟り、退職を決意しました。
退職後、スーパーで働き始めると…!?
転職活動で採用されたのは、地域密着型のスーパーでした。少しずつ仕事を覚え、開店前には売り場で黙々と棚を整えます。缶詰は“使う場面”別、パスタは“ゆで時間”順。POPは目立つように配置し、商品へ自然と目線が流れるように工夫を凝らしました。いろいろな仕事を任せてもらえるため、やりがいを感じています。
すると、背後で小さく息をのむ音がしました。「すごい……これ、全部あなたが?」声をかけてきたのは、同じフロアの女性スタッフ・Aさんでした。まっすぐな賞賛の言葉に少し照れくさくも、久しぶりに褒められてうれしく、思わず笑顔になってしまいました。
仕事に慣れ、お客さまから「商品が見つけやすくなった」「POPがわかりやすい」といった声が届き始めた矢先、前の会社の新規出店が近隣に決定。なんと、店舗の責任者は、あのとき自分を鼻で笑った“同期”でした。
視察と称してやって来た元同期は、わざと聞こえるような声で言いました。「こいつ、俺たちに成績で勝てないから逃げ出したんですよ。ねえ、あなた。こいつと同じ職場じゃ苦労も多いでしょ? よかったら、うちで働きませんか?」Aさんが言葉を失うと、過去の屈辱がよみがえりました。
しかし、彼女はすぐに微笑み、「私はここで、お客さまや◯◯さん(私の名前)と一緒に、いいお店をつくりたいです」と言ってくれました。元同期はおもしろくなさそうにしていましたが、そのひと言で、私はなんとか踏みとどまることができました。
元同期が担当する店がオープンすると…
やがて、前の会社の店舗が華々しくオープンしました。しかし、思うように客が入らなかったのか、ある日、元同期が「なにかズルい手を使ってるんだろう!」と怒鳴り込んできたのです。私が言葉に詰まっていると、Aさんが一歩前に出て「ズルなんてしていません。彼は毎日、陳列やお客さまの導線を考え続けています。見てわからないなら、あなたの視線が甘いだけです」と言いました。すると元同期は顔を真っ赤にし、「覚えてろ」と吐き捨てて去っていきました。
ところが数週間後、店の客足が急に落ちました。近くの交差点では元同期の店のセールチラシが配られ、さらに、私が働くスーパーについて「接客が冷たい」「掃除が行き届いていない」といった耳障りな噂まで広がったのです。根も葉もない話に、私もAさんも、そして他の仲間たちも肩を震わせました。
閉店後、私は店舗を再度見直し、スタッフ全員で細かい部分までチェック。お客さまが買い物しやすいように売り場を工夫し、掃除や整理整頓を徹底的におこなうなど、改善を重ねていきました。
改善を重ねた結果…再び現れたのは!?
あるときから元同期の店の客足は再び減り、こちらの店には開店前から行列ができるようになりました。視察に来た元同期がまた「なにをした!」と詰め寄ってきたため、私は「ファミリー層や高齢の方が困らないことを最優先に、レイアウトを一新しただけです」と伝えました。
そこへ、重い足音が響きました。前の会社の部長が、複数の社員を連れて現れたのです。「売り上げが芳しくないので視察に来てみれば……他店に難癖をつけて迷惑をかけるとは何事か!」同期が言い訳を探す間もなく、「この店の“接客が冷たい”“掃除が行き届いていない”といった噂を流したのは君だと聞いた。話は会社で聞こう」と言われ、連れて行かれる元同期の背中を見送りました。すると部長は、私のほうを向いて言いました。
「君のような人材を失ったのは、会社の損失だ。あのときは申し訳なかった。戻ってくる気はないか?」私は常連のお客さまたちの顔を思い浮かべながら答えました。「申し訳ありません。僕はここで仕事を続けたいんです」
部長は静かに手を差し出し、「立派になったな。健闘を祈る」と言ってくれました。私は拾ってもらったこの場所で、これからも精一杯頑張ろうと心に誓いました。そして……Aさんともう少し仲良くなりたいと思っています。
◇ ◇ ◇
どんなに悔しい思いをしても、努力を続けていれば、必ず見てくれる人がいますよね。パワハラまがいの言動が目立った以前の会社では、自分の力を発揮できなかったかもしれません。転職して本当によかったですね。
【取材時期:2025年9月】
※本記事は、ベビーカレンダーに寄せられた体験談をもとに作成しています。取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。