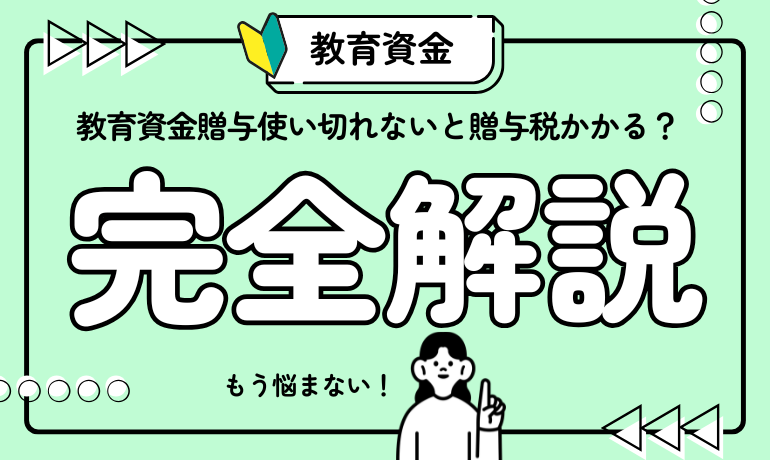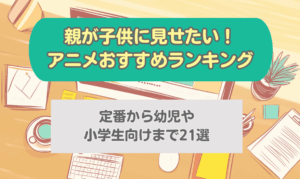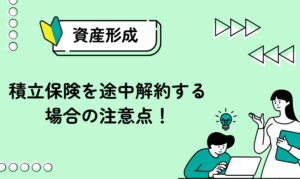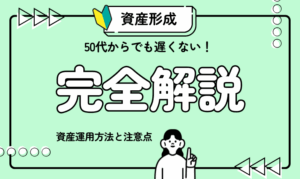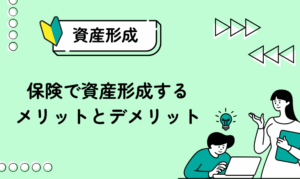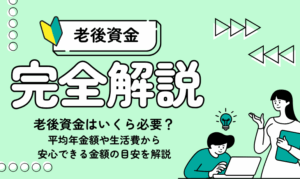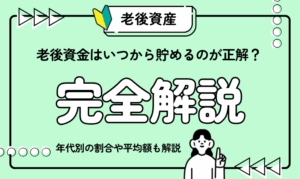「祖父母から孫へ」といった形で、子や孫の教育資金を支援する目的で利用される「教育資金贈与」。最大1,500万円までが非課税になるため、教育費の負担を軽減できる非常に有効な制度です。
しかし、この制度を利用している方の中には、「贈与されたお金を使い切れないかもしれない……」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。特に、もうすぐ30歳になる方や、学校を卒業して今後大きな教育費がかかる予定がない方は、「残ったお金はどうなるの?」「税金がかかるって本当?」といった疑問をお持ちかもしれません。
この記事では、教育資金贈与が使い切れない場合にどうなるのか、贈与税が課税されるケースやその税率、必要な手続き、そして課税を避けるための対策について、詳しく解説していきます。この記事を読めば、あなたの不安が解消され、適切に対処できるようになるはずです。
教育資金贈与の使いきれないお金は課税対象になる?
まずは、教育資金贈与制度の基本的な仕組みと、使い切れなかった場合に贈与税が課税される原則について確認していきましょう。
教育資金贈与とはどんな制度?
教育資金贈与(正式名称:教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置)とは、30歳未満の子や孫(受贈者)が教育資金に充てるために、その直系尊属である親や祖父母(贈与者)から金融機関等との契約に基づき金銭の贈与を受けた場合に、一括で贈与された資金のうち最大1,500万円まで贈与税が非課税になる課税制度上の特例です。
通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、この制度を利用すれば、将来必要になる教育費をまとめて非課税で渡すことができます。受け取った資金は専用の口座で管理され、教育費として引き出す際には、その都度金融機関に領収書などを提出する必要があります。
この制度は、子や孫の将来を想う祖父母世代などから、次世代への資産移転をスムーズにし、教育機会の充実を図ることを目的としています。
原則として30歳までに使い切らないと贈与税がかかる
この制度の最も重要なポイントは、原則として受贈者(お金をもらった側)が30歳に達した時点で契約が終了し、その時に使い切れずに残っていた金額(残額)が贈与税の課税対象になるという点です。
例えば、祖父から1,000万円の教育資金贈与を受け、30歳になったら専用口座に300万円が残っていたとします。この場合、この300万円が贈与税の計算対象となります。
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、残額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。しかし、上記の例のように残額が110万円を超えている場合は、超えた部分に対して贈与税が課せられます。
30歳を迎える前に契約を解約した場合も同様で、その時点での残額から教育費として支払った額を差し引いた金額が贈与税の対象となります。
使いきれないからと他の用途に使っても贈与税がかかる
「残高が余りそうだから、車や旅行など、教育以外のことに使ってしまおう」と考える方もいるかもしれませんが、それはできません。
教育資金贈与の口座から引き出したお金を、定められた教育目的以外に使用した場合、その支出は「目的外支出」とみなされ、その年に目的外支出した金額の合計が贈与税の課税対象となります。
なぜバレるのか?
教育資金贈与の使い道の対象項目一覧
では、具体的にどのような費用が「教育資金」として認められるのでしょうか。その範囲は細かく定められています。
【学校等に対して直接支払われる金銭】(上限1,500万円)
- 入学金、授業料、施設設備費、入園料、保育料など
- 対象となる学校:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校、高等専門学校、一定の外国人学校など
- 学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など(学校が必要と認めたもの)
【学校等以外に対して直接支払われる金銭】(上限500万円)
- 学習塾や習い事の月謝
- 例:進学塾、予備校、そろばん、習字、水泳、ピアノ、絵画、英会話教室など
- 通学定期券代、留学渡航費など
【よくある質問:これは対象になる?】
パソコン購入費:
自動車学校の費用:
大学の下宿代や生活費:
このように、対象となる使い道は具体的に決まっています。判断に迷う場合は、安易に自己判断せず、必ず契約している金融機関に問い合わせることが重要です。
贈与税を払ったら残ったお金は自由に使用できる
30歳到達時に残額があり、それに対して贈与税をきちんと納税した場合、残ったお金は完全に受贈者個人の資産となります。そのため、その後は教育目的に縛られることなく、貯金や生活費、趣味など、自由に使うことができます。
使い切れないお金は贈与者に返金できない
「使い切れなかった分は、贈与してくれた祖父母に返せば税金はかからないのでは?」と思うかもしれませんが、それはできません。
教育資金贈与は、贈与者と受贈者、そして金融機関の三者間で契約を結ぶものです。一度贈与が完了した資金は受贈者の財産となるため、贈与者に返金するという選択肢は基本的にありません。使い切れなかった場合は、贈与税を支払って自分のお金にする必要があります。
教育資金贈与を使いきれなくても贈与税が発生しないケース
原則として30歳で残額に課税される教育資金贈与ですが、いくつかの例外的なケースでは贈与税がかからない、または課税が先延ばしになることがあります。
30歳の時点で学校に在籍している
受贈者が30歳に達した時点で大学院に在籍しているなど、学校に在学中の場合は契約を終了せず、そのまま継続することができます。この場合、延長の手続きを金融機関で行うことで、卒業する年(またはその年の年末)まで非課税期間を延ばすことが可能です。
ただしこの延長措置には上限があり、受贈者が40歳に達した時点で契約は強制的に終了となります。
※注意点
40歳までに卒業して卒業時点で残高がない
上記の延長措置を利用した場合でも、40歳に達すると契約は終了します。その時点で残高があれば、その全額が贈与税の課税対象となります。40歳になるまでに計画的に資金を使い切り、卒業時点で残高がゼロになっていれば、贈与税がかかることはありません。
23歳以上か学校卒業後に贈与者が死亡した
教育資金贈与の契約期間中に、贈与者(祖父母など)が亡くなってしまった場合は、少し複雑なルールが適用されます。この場合、残額は贈与税ではなく相続税の対象として扱われる可能性があります。
税制改正により、このルールは変更が加えられています。原則として、贈与者が死亡した時点での残額は、受贈者が相続または遺贈で取得したものとみなされ、相続税の課税対象財産に加算されます。
しかし、以下のいずれかに該当する場合は、相続税の課税対象から除外されます。
- 受贈者が23歳未満である場合
- 受贈者が学校等に在学している場合
- 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
つまり、例えば大学生である20歳の孫が、祖父から受けた教育資金贈与の残額がある状態で祖父が亡くなったとしても、その残額は相続税の対象にはなりません。一方で、社会人になった25歳の孫が、23歳以上で学校も卒業している状況で贈与者死亡の知らせを受けた場合、残額は相続財産に加算されることになります。
この制度は、駆け込みでの生前贈与による相続税対策を防ぐ目的で設けられています。
教育資金贈与の使い切れないお金にかかる税率
では、実際に贈与税がかかる場合、税額はいくらになるのでしょうか。ここでは具体的な税率と計算方法を見ていきましょう。
使い切れなかった残額にかかる贈与税は、「暦年課税」という方法で計算されます。親や祖父母(直系尊属)からの贈与の場合、「特例贈与財産」として一般の贈与よりも税率が少し優遇された「特例税率」が適用されます。
計算式は以下の通りです。
【贈与税の速算表(特例贈与財産用)】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
<計算例>
- ケース1:30歳時点の残額が300万円だった場合
- 課税価格を計算:300万円 – 110万円(基礎控除) = 190万円
- 税率と控除額を確認:課税価格が200万円以下なので、税率は10%、控除額は0円
- 贈与税額を計算:190万円 × 10% – 0円 = 19万円
- ケース2:30歳時点の残額が600万円だった場合
- 課税価格を計算:600万円 – 110万円(基礎控除) = 490万円
- 税率と控除額を確認:課税価格が600万円以下なので、税率は20%、控除額は30万円
- 贈与税額を計算:490万円 × 20% – 30万円 = 98万円 – 30万円 = 68万円
このように、残額が大きくなるほど税率も高くなり、税金の負担も大きくなります。
教育資金贈与を使いきれなかったときの手続き方法
万が一、教育資金を使い切れずに贈与税の支払いが必要になった場合、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。ここでは、その流れを解説します。
1. 金融機関での契約終了手続き
受贈者が30歳に達するなど、契約の終了事由に該当した場合、まずは契約している信託銀行などの金融機関で手続きを行います。
通常、契約終了の時期が近づくと金融機関から案内が届きます。その案内に従って、口座を解約し、残額を受け取るための手続きを進めます。この時点で、金融機関は税務署に提出するための「教育資金管理契約の終了に関する調書」を作成します。
2. 贈与税の確定申告
残額が基礎控除額である110万円を超えた場合、受贈者自身が確定申告(贈与税の申告)を行う必要があります。
- 申告期間:
贈与税の申告は、契約が終了した年(30歳に達した年など)の翌年2月1日から3月15日までの間に行います。 - 申告場所:
申告書は、受贈者(お金をもらった人)の住所地を管轄する税務署に提出します。 - 申告方法:
- 税務署の窓口で提出:直接持参して提出します。
- 郵送で提出:信書便で税務署に送付します。
- e-Taxで申告:国税庁のウェブサイトから電子申告も可能です。マイナンバーカードなどが必要になります。
- 納税:申告期限と同じく、翌年の3月15日までに金融機関や税務署の窓口、e-Taxなどを利用して納税を済ませます。
申告を忘れたり、期限を過ぎてしまったりすると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があるため、必ず期限内に手続きを完了させましょう。
教育資金贈与に課税されないための対策
最後に、教育資金贈与を使い切れずに贈与税が課される事態を避けるための対策をいくつかご紹介します。
1. 将来の教育プランを立て、計画的に利用する
最も基本的な対策は、贈与を受ける時点から将来を見据え、計画的にお金を使うことです。
大学院への進学や海外留学:
社会人向けの講座や資格取得:
早い段階で将来のキャリアプランや学習計画を立て、それに合わせて資金を利用していくことが重要です。
2. 最初から使い切れる金額だけを贈与する
教育資金贈与は、非課税限度額の1,500万円を必ず一括で贈与しなければならないわけではありません。最初に500万円だけ贈与し、後から必要に応じて追加で資金を贈与する(口座に入金する)ことも可能です。
子や孫がまだ幼い場合、将来どれくらいの教育費がかかるか正確に予測するのは困難です。まずは大学進学までにかかる費用など、ある程度見通しの立つ金額だけを贈与し、その後の状況に応じて追加贈与を検討するのが、使い残しを防ぐ賢い方法と言えるでしょう。
3. 他の贈与制度と組み合わせる
教育資金贈与にこだわりすぎず、他の非課税制度の利用も視野に入れるのも有効な対策です。
暦年贈与:
結婚・子育て資金の一括贈与:
必要な都度、教育費を支払う:
どの制度が最適かは、各家庭の資産状況や家族構成、将来のプランによって異なります。
まとめ
教育資金贈与は、子や孫の未来を応援するための素晴らしい制度ですが、使い切れない場合には贈与税が課される可能性があることを理解しておく必要があります。
- 原則として、30歳になった時点で残っているお金には贈与税がかかる。
- 教育目的以外に使うと、その分が課税対象になる。
- 30歳時点で在学中であれば、最大40歳まで非課税期間を延長できる。
- 贈与者が亡くなった場合、残額が相続税の対象になるケースがある。
- 贈与税がかかる場合は、翌年に確定申告と納税が必要。
使い残しによる課税を避けるためには、将来の教育プランをしっかりと立て、計画的に資金を利用することが何よりも大切です。また、最初から多額の資金を贈与するのではなく、必要な金額を見極めたり、暦年贈与など他の制度と組み合わせたりすることも有効な対策となります。
もし教育資金贈与の利用や手続きに関して不安な点があれば、まずは契約している金融機関に相談してみましょう。また、税金に関する専門的な判断が必要な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。制度を正しく理解し、賢く活用していきましょう。