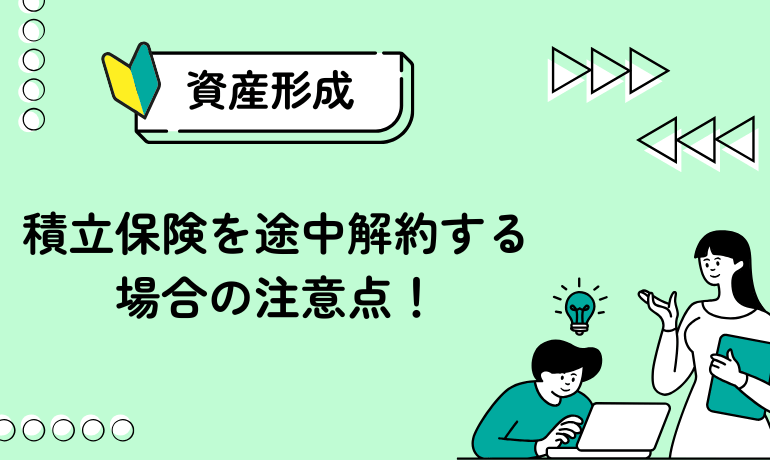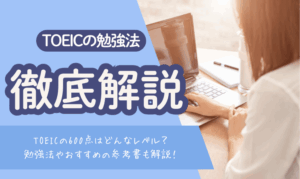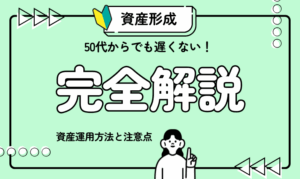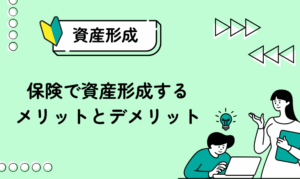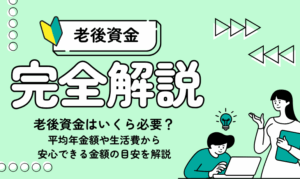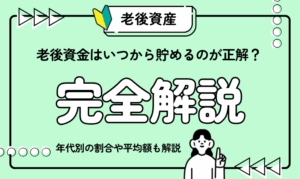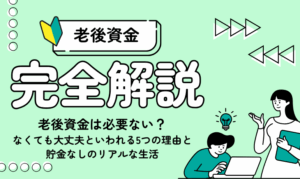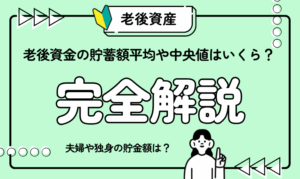積立型の生命保険(終身保険・養老保険・学資保険・個人年金保険など)は、貯蓄性を持つ保険商品です。本来は長期契約を前提として設計されていますが、「保険料の支払いが厳しくなってきた」「ほかに入りたい保険ができた」などの理由で、途中解約を検討する方もいるでしょう。契約者本人が手続きをすればいつでも解約自体は可能ですが、途中解約にはデメリットが伴う場合が多いため慎重な検討が必要です。本記事では、積立型保険を解約する際の注意点や適切なタイミングから、解約せずに資金を用意する方法まで幅広く解説します。ぜひ参考にしてください。
積立保険の途中解約はできるが損する可能性がある
積立型の生命保険は、契約者の意思で途中解約することができます。生命保険は法律上でも契約者がいつでも契約を解除できる権利が認められており、保険会社が正当な理由なくそれを拒めなくなっています。したがって、極端に言えば契約直後でも解約は可能であり、解約したことで違約金のようなペナルティが発生することも基本的にありません。
しかし、だからといって安易に解約してよいわけではありません。積立型保険を途中で解約すると、多くの場合払込保険料総額より少ない金額しか戻ってこないため、損失(元本割れ)が発生しやすい点に注意が必要です。また、一度解約してしまうとその保険で備えていた保障(死亡保障や医療特約など)もすべて失われます。同じ内容の保険に再加入しようと思っても、年齢や健康状態の変化により以前より条件が悪くなってしまうケースが多いです。つまり、積立保険の途中解約はいつでもできるものの、契約者にとって大きなデメリットを伴う可能性が高いのです。
ポイント: 積立型保険の解約は契約者の自由だが、タイミング次第では経済的損失や保障の消失といった不利益が生じる。解約を決断する前に、以下で述べる注意点やベストな解約時期を押さえておこう。
積立保険を途中解約するときの注意点
積立型の生命保険を途中で解約する場合、契約者側に生じるリスクやデメリットがいくつかあります。主な注意点として、以下の5つが挙げられます。
元本割れする可能性が高い
積立保険を満期前などに途中解約すると、それまでに払い込んだ保険料の総額よりも解約返戻金のほうが少なくなる可能性が高いです。いわゆる元本割れのリスクで、特に契約から日が浅い保険料払込期間中の解約ではほぼ確実に発生します。積立型保険の保険料の一部は保障の維持や事務手数料等のコストに充てられているため、短期間で解約してしまうとその分が差し引かれた額しか戻らないからです。満期まで継続すれば受け取れるはずだった利益も放棄することになるので、解約時期によっては大きな損失につながります。
早期解約だと返金されないことがある
契約して間もない早期解約の場合、払い込んだ保険料が一切返ってこない ケースもあります。例えば、契約から1年未満などごく短期間で解約すると、解約返戻金がゼロという商品も存在するのです。また、一部の保険商品(低解約返戻金型や無解約返戻金型の特約など)では、契約後一定期間は解約返戻金が発生しない仕組みになっています。過去の商品では、まとめて先払いした保険料の未経過分が返金されない規定があった例もあります。いずれにせよ、契約してすぐ解約すると保険料を払い損になってしまう可能性が高い点に注意しましょう。
解約払戻金に税金がかかることがある
解約によって受け取る解約返戻金の金額によっては、税金の問題も生じます。受け取った解約返戻金がそれまでに支払った保険料総額を上回る場合、その差額は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。例えば払込保険料合計100万円に対し解約返戻金が120万円だった場合、20万円が一時所得です。一時所得には50万円の特別控除があるため、他に一時所得がなく差額が50万円以下であれば課税されません。しかし差額が大きい場合は税負担が発生し、会社員の場合年末調整では精算できないため自分で確定申告が必要になるケースもあります。また、契約者と解約返戻金の受取人が異なる場合は、贈与税の対象となります。解約時には、税金面で損をしないかも確認しておきましょう。
全ての保障が受けられなくなる
積立型の生命保険を解約すると、当たり前ですがその契約に付帯していたすべての保障が消滅します。主契約の死亡保障だけでなく、付加していた特約(医療保障やがん保障など)もまとめて失われる点に注意が必要です。例えば終身保険に医療特約やがん特約を付けていた場合、解約すると死亡保障だけでなく入院給付金等の保障も二重で失うことになります。途中解約を検討する際は、その保険で確保していた保障内容を改めて見直し、保障がなくなって困らないか冷静に判断しましょう。なお、保険会社によっては主契約は継続したまま特約のみ解約することも可能ですが、主契約を解約して特約だけ残すことはできません。
再加入したくても条件が悪くなる
一度解約した保険に後から入り直したいと思っても、元の契約と同じ条件で再加入することはほぼ不可能です。生命保険の保険料は加入時の年齢や健康状態によって決まるため、解約後に年齢が上がれば保険料が割高になりますし、期間中に病気になっていれば新たな審査で加入を断られる恐れもあります。仮に再び加入できたとしても、以前と同額の保障を得るには以前より高い保険料を払う必要が出てくるでしょう。「また必要になったら入ればいい」と安易に考えると、いざというとき再加入できない・コスト増大などのリスクに直面しかねません。
以上のように、積立保険の途中解約には経済的な損失と保障の消失という大きなデメリットがあります。解約の判断は、こうした注意点を十分理解した上で行うことが大切です。
積立保険を損せず解約できるタイミングはいつ?
「では、解約するならいつが良いのか?」と悩む方も多いでしょう。なるべく損をしないタイミングは、ズバリ解約返戻金が払込保険料の総額に近づいたか上回った時です。解約時に戻ってくるお金の割合を示す指標として返戻率がありますが、この返戻率が100%(払込総額と同額)を超えていれば元本割れの心配はありません。返戻率100%を超えるのは、多くの保険商品で保険料払込期間終了時や契約満了時です。そのため、急いで解約する必要がないのであれば、返戻率が100%を超えるまで待つのが理想的と言えます。
もっとも、保険の種類によっては返戻率100%になる前に契約を終えるものもありますし、そこまで待てない事情もあるでしょう。その場合でも、できるだけ解約返戻金と払込保険料総額の差額が小さくなった時期を選んで解約することをおすすめします。返戻率の推移は契約時にもらった「解約返戻金の例表」などに5年後・10年後といった目安が記載されている場合があるので確認してみてください。不明な場合は、保険会社や担当の代理店に問い合わせれば教えてもらえます。
参考までに、ある終身保険(払込期間20年)の返戻率シミュレーション例を挙げます。
| 経過年数 | 解約返戻率の目安(払込保険料に対する割合) |
| 5年経過 | 約50%(払込総額の半分程度) |
| 10年経過 | 約80%(元本割れだがかなり差は縮小) |
| 15年経過 | 約100%(払込総額とほぼ同額) |
| 20年経過 | 約110%(払込総額を上回り利益が出る) |
※上記は一例です。実際の返戻率は、商品や契約内容によって異なります。
契約から年月が経つほど返戻率は上がっていき、元本割れのリスクは低減します。ただし、外貨建て保険や変額保険など市場変動の影響を受ける商品では、為替手数料や解約控除が差し引かれて思ったほど返戻率が伸びない場合もあるため注意が必要です。また、解約返戻金が大きく増えてプラスが出る場合には、前述の通り税金の問題も出てきます。単に返戻率だけでなく、税負担も含めて手取りで損がないかを確認することも忘れないようにしましょう。
積立保険の保険料が負担なら解約した方がいい?
毎月の保険料の支払い負担が大きく、「このままでは払い続けられない」と感じた場合、真っ先に解約を考える人もいるでしょう。しかし、保険料負担が理由ですぐに解約してしまうのはおすすめできません。前述の通り、途中解約すると元本割れなどの損失が発生しやすく、保障も失われます。経済的に厳しいからといって、解約した方がいいとは一概に言えないのです。
積立保険には、保険料の負担を軽減しつつ解約せずに契約を継続できる方法がいくつか用意されています。保険会社も契約者に長く契約を続けてもらいたいので、途中で支払いが難しくなった場合の救済策を用意しているのです。解約を決断する前に、以下で紹介するような支払い負担を減らす工夫を検討してみましょう。それでも状況が改善しない場合に、初めて解約を選んでも遅くはありません。
積立保険を解約せずに継続する5つの方法
ここでは、積立型保険を途中解約せず維持するための代表的な方法を5つ紹介します。経済的理由で解約を考えている方は、これらの対策を実行できないか検討してみましょう。
保険料を減額する
現在の契約を活かしつつ保険料負担を下げる方法の一つに、保障内容の一部を減額する方法があります。具体的には、主契約の保険金額や付帯している特約の保障額を減らすことで、月々の保険料を引き下げることが可能です。例えば死亡保障額を半分に減額すれば、それに比例して保険料も大幅に軽減されます。保険商品によっては、減額した分について「一部解約」と見なして解約返戻金が受け取れる場合もあります。ただし減額には最低保険金額の制限があり、契約内容によっては希望通り減額できないこともあるので注意が必要です。また一度減額すると元の保障額に戻すことは基本的にできないため、将来の保障ニーズも考慮して慎重に判断しましょう。
払済保険に変更する
今後ずっと保険料を払っていくことが難しい場合は、契約を払済保険に変更する方法があります。払済保険とは、それまで積み立てた解約返戻金を原資として以後の保険料支払いをストップし、契約をそのまま存続させる制度です。変更後は保険料の払込は不要になりますが、保障は一生涯または契約満了まで継続されます。ただし、保険料を払わない分保険金額(保障額)は減少し、付帯していた特約はすべて消滅します。例えば、もとの契約が死亡保険金1000万円だったものが払済後は500万円に減る、といったイメージです。これは、保障額は下がっても構わないので保険自体は残したいという場合に有効な方法です。元の契約によって払済保険への変更可否や条件が異なるため、希望する場合は保険会社に問い合わせてみましょう。
延長保険に変更する
延長保険も、保険料負担なしで保障を継続するための手段です。延長保険への変更では、解約返戻金を用いて一時払の定期保険(期間限定の保障)に切り替える形を取ります。特徴は、保険金額(保障額)は変えずに契約を存続できる点です。つまり、現在と同じ保障額のまま、新たに保険料不要の定期保険に契約し直すイメージです。ただし保険料を払わない分、保障が継続する期間は短縮されます。具体的な保障継続期間は解約返戻金の額によって決まり、返戻金が多ければそれだけ長い期間保障が続きますが、永続的ではありません。また、延長保険への変更でも特約は全て消滅し、積み立て型の機能はなくなる(解約返戻金はゼロになる)点に留意しましょう。将来的に保障期間が終了すると無保険状態になるため、それまでに新たな保険への加入を検討する必要があります。
自動振替貸付制度を利用する
一時的に保険料の支払いが難しくなっただけで、将来的には払える見込みがある場合には、自動振替貸付制度の利用が有効です。自動振替貸付とは、保険料の払い込みが滞り猶予期間を過ぎてしまった際に、解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に不足分を立て替えてくれる制度です。保険会社からの自動ローンで、保険料を払い続けることができます。これを利用すれば、一時的に現金がなくても保険契約が失効せずに継続できます。ただし、立て替えられた保険料相当額は貸付金として扱われ、あとで返済が必要になる点に注意してください。返済せず放置すると利息がつき、貸付金が解約返戻金を上回ると契約は失効してしまいます。あくまで一時しのぎの措置ですので、経済状況が回復したらできるだけ早めに返済し、通常の保険料支払いに戻すことが望ましいでしょう。
契約者貸付を利用する
急にまとまったお金が必要になった場合や、保険料支払いの資金繰りがどうにもつかない場合には、契約者貸付制度を利用して乗り切る方法もあります。契約者貸付とは、契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社からお金を借り入れできる制度です。わかりやすく言えば、今解約すれば戻ってくるお金を担保に低利でお金を借りるイメージです。借りられる上限額は解約返戻金の70~90%程度が一般的で、保険会社や商品によって異なります。審査も簡易で融資までの時間も早いことが多く、緊急の資金ニーズに対応しやすいメリットがあります。貸付を受けても契約は継続され、保障もそのままです。ただし、借りたお金には所定の利息がかかり、返済しないまま長期間放置すると利息が膨らんでしまいます。最終的に死亡保険金や解約返戻金から未返済額が差し引かれることになりますので、必要最低限の利用に留め、早めの返済を心がけましょう。
以上、解約を避けて契約を維持するための方法を5つ紹介しました。保険料が負担だからといって即解約するのではなく、減額や払済への移行など代替手段を検討することで、保障を残しつつ家計の負担を軽減できる可能性があります。どうしても難しい場合を除き、ぜひ一度これらの制度を活用できないか確認してみてください。
積立保険を解約する手続き
最後に、実際に積立保険を解約する場合の一般的な手続きの流れを確認しておきましょう。生命保険の解約は、基本的に以下のような手順で行います。
- 保険会社に連絡して解約の申し出をする
契約している保険会社の担当者やコールセンターに電話し、「解約したい」旨を伝えます。最近では、インターネット上の契約者ページから解約手続きを開始できる会社もあります。まずは、解約に必要な書類の郵送を依頼しましょう。
- 解約書類を受け取り、記入する
保険会社から、解約請求書など所定の書類が送られてきます。書類に契約者本人が必要事項を記入し、押印(または署名)しましょう。併せて、本人確認書類(運転免許証のコピーなど)や保険証券など指示された書類も用意します。
- 書類一式を保険会社に返送する
記入済みの解約書類と必要書類を同封し、保険会社指定の送付先に郵送します。保険会社に書類が届いてから解約手続きが進み、内容に不備がなければ解約が成立します。
- 解約返戻金が指定口座に振り込まれる
解約手続き完了後、契約者が指定した金融機関口座へ解約返戻金が支払われます。振込までの期間は保険会社によって異なりますが、書類到着から1週間前後で入金されるケースが一般的です(金融機関や契約内容によっては多少前後します)。
以上で、解約の手続きは完了です。解約返戻金を受け取ったら契約は消滅し、以後の保障もなくなります。解約後に「やはり続けておけば良かった…」と後悔しても契約を元に戻すことはできませんので、手続きを進める前に本当に解約するかどうか最終確認することをおすすめします。
今回は、積立型の生命保険の途中解約について、その注意点からタイミング、さらに代替手段や手続き方法まで解説しました。繰り返しになりますが、積立保険は途中解約しないことを前提に設計された商品です。解約すると経済的なデメリットや保障の消失といった大きな影響があるため、安易に契約を手放さずよく検討することが大切です。もし「解約すべきか迷っている」「他の保険に乗り換えたいが損をしたくない」といった場合は、一人で悩まずに保険の専門家やFPに相談してみるのも良いでしょう。適切な知識を基に賢い選択をして、大切な保障とお金を守ってください。