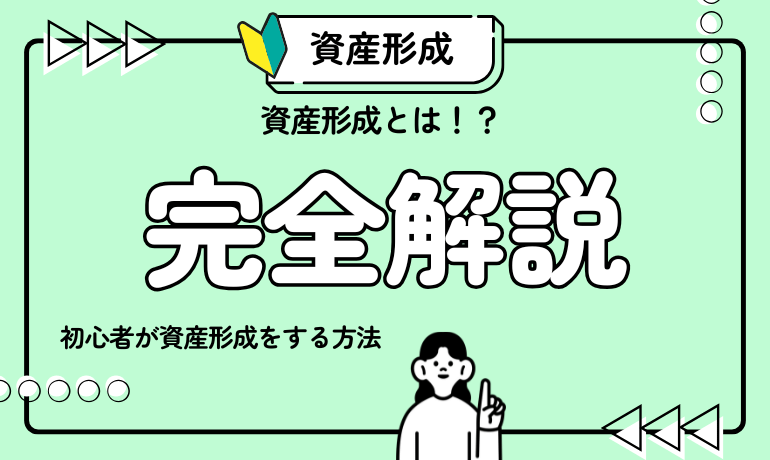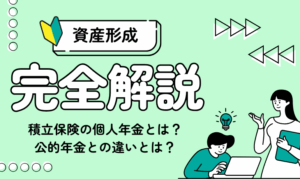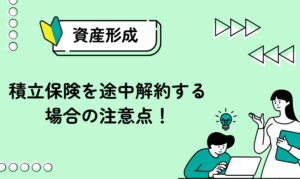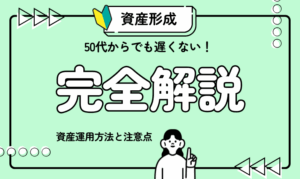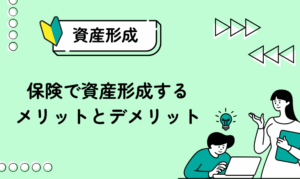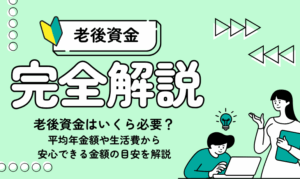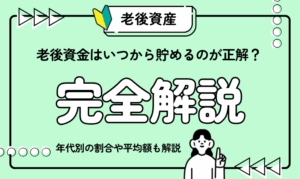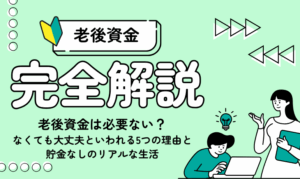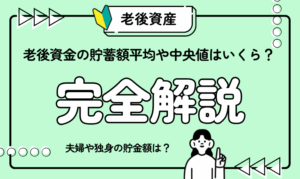資産形成という言葉を最近よく耳にするけれど、具体的に何をどうすればいいのか分からないという初心者の方も多いでしょう。本記事では、「資産形成とは何か」を簡単にわかりやすく解説するとともに、資産形成の具体的な方法や種類、それぞれのメリット・デメリットについて紹介します。さらに、初心者が資産形成を始める方法や20代・30代・40代・50代と年代別の資産形成のコツも解説します。将来に向けて効率よくお金を増やしたい方は、ぜひ参考にしてください。
資産形成とは何?なぜ必要?簡単にわかりやすく解説!
資産形成は将来に向けてお金を増やすこと
資産形成とは、将来必要になる資金や財産を計画的に増やしていくことです。たとえば、子どもの教育費や老後の生活費、マイホーム購入資金など、人生のライフイベントに備えてお金を貯めたり増やしたりすることを指します。つまり「将来のためにお金を増やす」行為全般が資産形成の意味です。そのため、資産形成を始める際にはまず目的(何のために、いつまでに、いくら貯めたいのか)を明確に決めることが重要です。目的をはっきりさせることで、資産形成の計画が立てやすくなり、モチベーション維持にもつながります。
資産形成というと一般的に「投資でお金を増やす」イメージを持つ人が多いかもしれません。しかし、将来に備えてお金を増やす手段には預金・貯蓄も含まれます。銀行預金などでコツコツと貯金するのも立派な資産形成の一つです。実際、銀行口座にお金を預けている人は、多かれ少なかれ「貯蓄」という資産形成方法を実践していることになります。このように、資産形成には投資だけでなく貯蓄も含まれる点を押さえておきましょう。
資産形成と資産運用の違い
資産形成とよく似た言葉に「資産運用」があります。この二つは混同しがちですが、意味合いが少し異なります。資産形成がゼロから資産を作り上げていくこと(お金を貯め増やすこと自体が目的)であるのに対し、資産運用はある程度まとまった資産を持っている人が、その資産を元手にさらに増やしていく行為(手段)を指します。つまり資産形成という大きな目的の中に、投資によって手持ちの資産を増やす資産運用という手段が含まれるイメージです。
例えば、資産形成の段階では収入から節約や貯金をしつつ、ときには積極的な投資によって資産を1から築いていきます。一方、資産運用の段階では既に持っている資産を減らさないよう守りながら運用し、効率よく増やすことに重点を置きます。一般的には、まとまった金融資産(目安として1,000万円以上)を保有できたら、資産形成フェーズから資産運用フェーズに移行すると言われます。
- 資産形成:
お金を貯めること自体が目的。貯金や節約、小額からの投資などでゼロから資産を築く段階。 - 資産運用:
今ある資産を増やすための手段。ある程度まとまった資産を元に、リスクを管理しつつ投資で効率的に増やす段階。
なお、資産形成期の方が「資産を増やしたい」という目的が強いため、場合によってはリスクを取った積極的な投資にも挑戦することがあります。一方、資産運用期の方は「今ある資産を減らさず守る」意識が強く、安定重視で比較的低リスクの商品を選ぶ傾向があります。自分が今どの段階にいるかを認識し、適切な方法を選ぶことが大切です。
資産形成が必要な理由
資産形成はなぜ必要なのでしょうか?主な理由をいくつか挙げます。
将来の大きな出費に備えるため:
公的年金や退職金だけに頼れないため:
インフレや低金利に対応するため:
このような背景から、資産形成の重要性は増しています。また国も個人の資産形成を後押しする動きを強めており、金融庁は「貯蓄から投資へ」というスローガンのもと、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった有利な制度を整備して私たちの資産形成を支援しています。将来に備えて早めに資産形成に取り組むことが、安心できる生活につながると言えるでしょう。
資産形成の種類とメリット・デメリット
一口に資産形成といっても、その方法にはさまざまな種類があります。大きく分けると、預金や保険など貯蓄型の方法と、株式や投資信託など投資型の方法に分類できます。それぞれリスクやリターンの特徴が異なりますので、代表的な方法とメリット・デメリットを押さえておきましょう。
貯蓄型の資産形成方法
貯蓄型の資産形成とは、元本割れのリスクがほとんどない安全性重視の方法です。銀行預金や貯蓄型の保険商品などが該当し、堅実にお金を貯めていきたい人に向いています。ただしリスクが低い分リターン(増える率)も低いため、大きく増やすことは難しい点は念頭に置きましょう。
預貯金
預貯金は銀行や信用金庫などにお金を預けて貯蓄する方法です。預けた元本が目減りする心配がなく、安全性が極めて高いのが特徴です。また預金には利息(利子)がつくため、わずかではありますが預けておくだけでお金が増えます。リスクを一切取りたくない初心者にとって、まず預貯金でコツコツ貯めることは基本と言えるでしょう。
メリット:
デメリット:
積立保険
積立保険は貯蓄機能を備えた生命保険を活用した資産形成方法です。万一の保障を得ながらお金を積み立てていける点が特徴で、例えば終身保険などでは解約時に解約返戻金を受け取ることができます。商品によっては長期間契約を続ければ、支払った保険料総額より多い解約返戻金が受け取れるケースもあります。保障と貯蓄を両立させたい人に向いている方法です。
メリット:
デメリット:
投資型の資産形成方法
投資型の資産形成とは、株式や債券、不動産など資産運用によってお金を増やす方法です。リスクはありますが、貯蓄型よりも高いリターンが期待できます。資産形成を長期的に考えるなら、預貯金だけでなく投資型商品も上手に組み合わせて運用することがポイントです。ここでは代表的な投資型の方法を紹介します。
NISA(少額投資非課税制度)
NISA(ニーサ)は、株式や投資信託などの運用益が非課税になるお得な制度です。通常、投資で得た利益や配当金には20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税金がかかりますが、NISA口座での運用なら所定の非課税枠内で税金がゼロになります。その分、効率よく資産を増やせるため、初心者にも人気の制度です。証券会社等で専用のNISA口座を開設すれば誰でも利用できます。
なお2024年からNISA制度が拡充され、年間および生涯で利用できる非課税投資枠が大幅に増えました。将来に向けて長期・積立投資をするなら、まずNISAの活用を検討するとよいでしょう。
メリット:
デメリット:
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)は、自分で積み立てる年金制度で、公的年金にプラスして老後資金を作るための個人型確定拠出年金です。掛金を拠出して運用し、原則60歳以降に受け取ります。iDeCo最大の特徴は税制優遇が非常に大きいことです。毎月拠出する掛金が全額所得控除の対象となるため、その分所得税・住民税が軽減されます。さらに運用で得た利益も非課税扱いとなり、税金面でメリットが多い制度です。
メリット:
デメリット:
債券
債券は国や企業が資金調達のために発行する有価証券で、債券を買うことは発行体へお金を貸すイメージです。債券を保有すると定期的に利息収入が得られ、満期(償還時)には額面の元本が戻ってきます。日本国債や社債、地方債など様々な種類があり、一般に債券は価格変動が株式ほど大きくなく、比較的安定した運用が可能です。
メリット:
デメリット:
投資信託
投資信託は、多数の投資家から集めた資金を元に、運用のプロである運用会社が株式や債券など複数の資産に分散投資して運用してくれる金融商品です。1本の投資信託を買うだけで簡単に分散投資が行えるため、初心者がまとまった資金がなくても幅広い資産に投資できるメリットがあります。国内外の株式や債券、不動産(REIT)など投資対象によって様々な種類の投資信託があるので、自分の目的やリスク許容度に合った商品を選べます。
メリット:
デメリット:
株式投資
株式投資は、企業の発行する株式(株券)を購入して、その企業のオーナー(株主)になることで利益を狙う方法です。株価は日々変動し、買ったときより株価が上がればキャピタルゲイン(売却益)を得られます。また企業によっては配当金や株主優待が定期的に受け取れるため、値上がり益以外のリターンも期待できます。個別株の売買はハイリスク・ハイリターンな資産形成方法ですが、うまくいけば大きく資産を増やせる可能性があります。
メリット:
デメリット:
FX(外国為替証拠金取引)
FX(外国為替証拠金取引)は、米ドルやユーロなど異なる通貨の売買によって為替差益を狙う投資手法です。証拠金を業者に預けてレバレッジを利かせ、少ない元手で大きな金額の通貨を売買できる点が特徴です。為替レートの変動によって利益を得る仕組みで、24時間リアルタイムで取引できる機動性があります。うまくいけば短期間で利益を上げることも可能ですが、その反面リスクも非常に高いです。
メリット:
デメリット:
不動産投資
不動産投資は、マンションやアパート、一戸建て、土地などの不動産物件に投資して収益を得る方法です。主に、不動産を購入して賃貸に出し家賃収入(インカムゲイン)を得る方法と、購入した物件を後に売却して値上がり益(キャピタルゲイン)を得る方法があります。立地の良い物件を適正価格で取得できれば長期間安定した収入が期待でき、将来的に地価が上昇すれば大きな売却益も狙えます。
メリット:
デメリット:
コモディティ
コモディティ投資とは、金(ゴールド)や銀、プラチナ、原油、小麦やトウモロコシなどの商品先物や現物資産に投資する方法です。特に金は代表的なコモディティで、「有事の金」と呼ばれるように経済不安やインフレ時に資産価値を保ちやすい傾向があります。インフレ局面では商品の価格が上昇しやすいため、インフレヘッジ(物価上昇への備え)としてコモディティに投資する意義があります。
メリット:
デメリット:
何から始める?初心者が資産形成する方法
資産形成の方法や商品には様々な種類がありますが、初心者の方は具体的に何から手を付ければ良いのでしょうか。ここでは、資産形成をこれから始める人に向けてまず実践したいポイントやコツを紹介します。
家計管理をして先取り貯金をする
資産形成の第一歩は、毎月の収支を把握して家計管理をしっかり行うことです。収入が入ったら使い切ってしまう生活では貯蓄に回すお金が残りません。そこで有効なのが「先取り貯金(先取り貯蓄)」という方法です。具体的には、給料日など収入が入ったタイミングであらかじめ一定額を貯蓄用口座に移し、残ったお金で生活するようにします。たとえば「手取り収入の○割を貯蓄に回す」と決めてしまい、その分は最初からなかったものとして生活費をやりくりするのです。毎月の貯金額を先に確保することで、強制的にお金が貯まり資産形成の元手を着実に増やせます。
先取り貯金を成功させるには、日々の支出を見直して貯蓄に回せる余裕を作ることも大切です。特に通信費や保険料、サブスク料金などの固定費の見直しは効果的です。一度見直せば以降ずっと支出を削減できるため、浮いたお金をそのまま貯蓄に回しましょう。家計を管理し無理のない範囲で先取り貯金を習慣づけることが、初心者にとって堅実な資産形成のスタートになります。
ライフプランを立てる
資産形成を効率よく進めるには、将来の見通しを立てて計画的に貯蓄・運用することが重要です。そこでライフプランを立てることをおすすめします。ライフプランとは、自分や家族の今後の人生設計を描き、いつどんなライフイベント(結婚、出産、住宅購入、子どもの進学・独立、自分の退職など)があり、それぞれにいくらくらいの資金が必要かを書き出したものです。
人によって人生設計や金銭的な状況は様々ですから、まずは今後5年、10年、20年で起こり得るイベントと必要なお金をリストアップしてみましょう。「○年後にマイホーム購入資金○○万円」「子どもが18歳になるまでに教育資金○○万円」など具体的に数値目標を定めると、自ずと毎月どれくらい貯蓄・運用すればよいか見えてきます。目的別に貯蓄計画を立てることで資産形成のモチベーションも高まり、日々の節約や運用にも身が入るでしょう。
ライフプランは一度作ったら終わりではなく、ライフステージの変化に応じて見直すことも大切です。定期的に計画と実績をチェックし、必要に応じて軌道修正しながら進めていきましょう。
分散投資で長期的に運用する
資産形成を成功させるには、長期的な視点でリスクを抑えて運用することがポイントです。よく「資産形成の基本は長期・積立・分散」と言われますが、まさに初心者の方はこの基本原則を意識しましょう。
まず分散投資についてです。先に述べた通り、資産形成の方法には預金だけでなく株式や債券、不動産など様々な選択肢があります。ひとつの資産や地域に偏って投資すると、その対象に何かあったとき資産全体に大きな影響が及びます。そこで、異なる値動きをする資産にバランスよくお金を配分することでリスクを軽減できます。例えば「預貯金+投資信託+株式」のように金融商品を組み合わせたり、「国内資産+海外資産」のように地域を分散させたりするのが効果的です。また時間の分散も有効で、一度にまとまった額を投じるより積立投資(ドルコスト平均法)で定期的に買い付けていけば、購入価格を平均化して高値掴みのリスクを下げられます。
次に長期投資の重要性です。投資で得られた利益は再投資することでさらに利益を生むという複利効果が働きますが、この効果は運用期間が長いほど大きくなります。短期的に大儲けしようとすると高いリスクを伴いますが、10年、20年といった長期スパンでコツコツ積み立てていけば、途中相場の上下があっても時間と複利の力で資産を増やしやすくなります。実際、過去のデータでも長期保有するほど年平均リターンが安定する傾向が示されています。
したがって、資産形成を行う際は焦らず長期的な視野で運用することが大切です。日々の価格変動に一喜一憂せず、月々の積立や定期的なリバランス(資産配分の調整)を地道に続けましょう。「卵は一つのカゴに盛るな(=分散せよ)」という格言と「ローマは一日して成らず(=長期戦で挑め)」という心構えを持って資産形成に取り組むと、リスクを抑えながら着実にお金を増やすことができます。
年代別の資産形成のコツ
資産形成の具体的な方法は、人それぞれの状況によって異なりますが、一般的に年代ごとに直面するライフイベントや経済状況が変わるため、資産形成のポイントも年代によって変化します。ここでは20代・30代・40代・50代それぞれの年代における資産形成のコツや注意点を紹介します。自分の年代に合わせた戦略で、無理なく効果的に資産形成を進めましょう。
20代が資産形成するコツ
20代は社会人としての収入がまだ多くなく、貯蓄や投資に回せるお金が限られる一方で、これから結婚・出産・マイホーム購入などさまざまなライフイベントに備えていきたい年代です。また時間的な余裕(運用期間)が最も長く取れる年代でもあります。この時期に資産形成の習慣を身につけておくことが将来の大きな差につながります。
20代の方は、まず万一に備える生活防衛資金を準備しておきましょう。目安として生活費の3ヶ月分程度を預貯金で確保しておくと、病気や失業など不測の事態でも当面は生活を維持できます。そのうえで、余裕資金が少額でも構わないので積立投資をスタートしてみることをおすすめします。たとえば毎月1万円でも良いので投資信託やつみたてNISAでコツコツ積み立ててみましょう。若いうちから投資の経験を積んでおくことには大きな意味があります。長期投資なら多少リスクを取った商品でも時間をかけてリカバリーしやすく、複利効果で将来大きく育つ可能性があります。20代は「資産形成は早く始めるほど有利」というメリットを最大限活かし、無理のない範囲で貯蓄と投資を並行して始めてみてください。
30代が資産形成するコツ
30代になると、結婚や出産、住宅購入などライフイベントが本格化し始める時期です。お子さんがいれば教育費を貯め始める必要がありますし、マイホームを買えば住宅ローンの返済も始まります。収入は20代より増えているかもしれませんが、その分支出も増える傾向にあるため、計画的に資産形成を行うことが大切です。
まず引き続き生活防衛資金(生活費数ヶ月分)は常にキープしておきましょう。そのうえで、目的別に貯蓄・運用を分けて考えるのが30代のコツです。例えば、「5年後に住宅頭金○百万円貯める」「18年後(子どもが大学進学時)までに教育資金○○万円用意する」「老後資金として60歳までに○○万円積み立てる」など、それぞれのゴールと期間を定めます。そしてゴールの時期に合わせて適切な資産形成方法を選びましょう。子どもの教育資金のように期限が決まっている資金は、安全性の高い商品や確実に現金化できる手段で積み立てるのがおすすめです(学資保険や安全性の高い債券・定期預金など)。一方、老後資金のように長期で準備する資金は、つみたてNISAやiDeCoを活用しつつ株式・投資信託などで積極的に運用すると効率的です。
30代はライフイベントによって一時的に大きな出費があり、せっかく貯めたお金を取り崩す場面もあるでしょう。マイホーム購入や出産などで貯蓄が減ったとしても落ち込まず、また次の目標に向けて計画を立て直すことが大切です。目的ごとにお金を貯めて使っていくライフサイクルを意識しながら、余裕ができた部分はしっかり将来の資産形成に回すよう心掛けましょう。
40代が資産形成するコツ
40代は収入が安定し働き盛りの年代ですが、その反面子どもの教育費負担が本格化し家計支出も多くなる傾向があります。また自分自身の老後も現実味を帯びてきて、そろそろ真剣に老後資金づくりを始めないといけない時期です。さらに親世代が70代以降になり、介護や相続など実家のことで動く機会が増え始める人もいるでしょう。40代はまさに「背伸びをすると人生の天井に手が届く」とも言われるように、現役生活と将来準備の両立が求められる難しい年代です。
資産形成のコツとしては、まず引き続き生活防衛資金はしっかり確保し、万が一に備えておきます。そのうえで、もしお子さんがいる場合は子どもが中学校を卒業する頃(15歳前後)までに教育費の目処を付けられるよう意識しましょう。高校・大学と進むにつれて教育費はピークに達するため、可能な限り早め早めに準備を進めておくことが大切です。学資保険の満期金や積立投資の解約時期を、進学時期に合わせて計画しておくと安心です。
そして40代になったら、本格的に老後資金の形成をスタートしたいところです。50代以降は教育費の負担が減るケースも多いので、子どもの教育資金の積立が一段落したら、その分を老後資金の積立にスライドさせましょう。例えば今まで毎月積み立てていた学費分を、今度はiDeCoや積立投資信託に回すといった具合です。老後まで残り20年前後ありますから、長期積立投資でじっくり増やしていけばまだ十分間に合います。また親の介護問題など将来的な出費に備えて、少し多めに緊急予備資金を積んでおくのも40代から必要になるかもしれません。
総じて40代は、教育費と老後資金という二大テーマに直面する年代です。家計に余裕が出てきたら生活レベルを上げすぎず、その分を将来のための資産形成に振り向ける意識が大切です。
50代が資産形成するコツ
50代は定年退職が現実的に見えてくる年代で、資産形成の総仕上げをする時期と言えます。50代前半は一般的に収入が最も高い時期ですが、企業によっては55歳前後で役職定年を迎えて収入が減るケースもあります。また子どもが大学生であれば教育費がピークを迎えているでしょう。さらに40代に続き親の介護や相続問題が発生する人もいます。一方で、そろそろ自分自身の老後生活を具体的にイメージし始め、住居のローン残債や年金受給見込み額なども気になる頃です。
50代の資産形成では、まず老後資金準備のラストスパートをかけましょう。収入があるうちにできるだけ多く貯蓄・投資に回し、退職までに少しでも資産を厚くしておくことが大事です。生活防衛資金として生活費3〜6ヶ月分は確保しつつ、それ以上の余裕資金は積極的に老後のための資産形成に充てます。iDeCoは60歳まで掛金拠出できますし、50代からでも遅すぎることはありません。可能な範囲で最大限活用し、所得控除による節税メリットも享受しましょう。
また、もし住宅ローンなど負債が残っている場合は、定年までに完済できるよう計画を立てます。繰上返済を検討し、退職後にローン返済が残らない状態にしておくのが理想です。住居費の負担がなくなれば、年金生活になっても家計がぐっと楽になります。保有資産の運用方針も見直す時期です。退職金の運用先や年金受給までの生活費など、直近で使う予定のお金はリスクの低い商品で置いておくなど、安全重視にシフトしていきます。ただしあまりに守りに入りすぎて長い老後に資金が目減りしてしまっては本末転倒です。寿命が延びている今、60代以降も適度に運用を続けることも視野に入れ、資産の一部は引き続き投資信託や株式で運用するといったバランスも検討しましょう。
このように、50代では目前の定年とその後の人生を見据えた資産形成がポイントになります。収入があるうちにできる準備は全てやり切るつもりで、最後の貯めどき・増やしどきを逃さないようにしましょう。そして何より健康第一で働き続けられることが資産形成では重要です。無理のない範囲で収入アップや継続就業も検討しつつ、万全の態勢で豊かな老後を迎えられるよう備えてください。
どの年代においても、資産形成は将来の安心のために欠かせない取り組みです。早いうちから計画的に始めるに越したことはありませんが、たとえスタートが遅くなっても決して手遅れではありません。自分のライフステージに合わせてできることから始め、長期・積立・分散の基本を忘れずにコツコツ続けていけば、きっと将来の大きな財産となって返ってくるでしょう。さっそく今日からできる範囲で資産形成を始めてみてはいかがでしょうか。