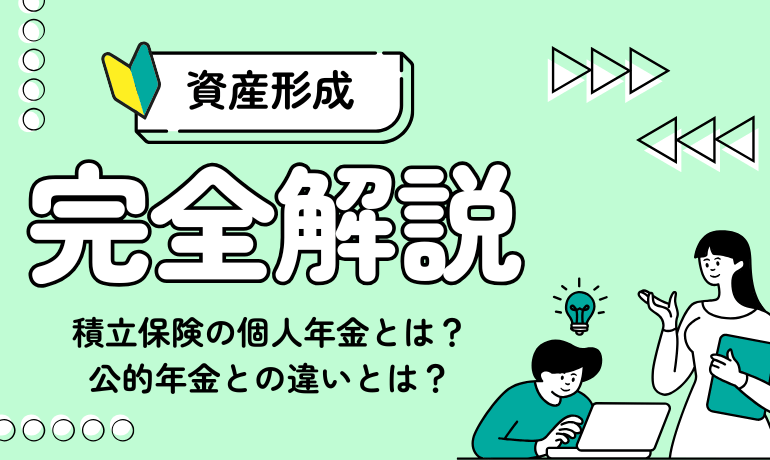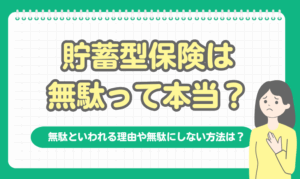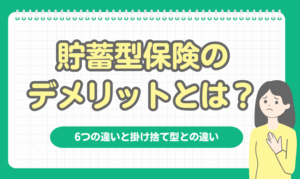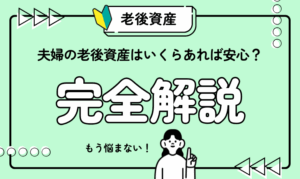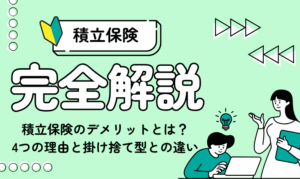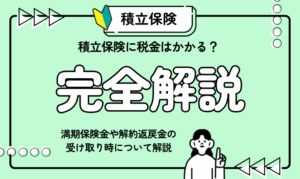積立保険の個人年金(個人年金保険)とは?
老後資金を準備するための年金保険
「個人年金保険」とは、老後の生活資金を計画的に準備するための積立型の保険です。若いうちから毎月一定の保険料を積み立て、契約時に決めた一定の年齢(例えば60歳や65歳など)から年金形式で受け取れるようにした商品です。貯蓄型の保険の一種であり、学資保険や終身保険などと同様に「積立保険」と呼ばれるカテゴリーに属しますが、個人年金保険は特に老後資金づくりに特化したものです。
個人年金保険の保険料の払込方法には「分割払い(積立払い)」と「一括払い(一時払い)」があります。分割払いでは月払いや年払いでコツコツ積み立て、無理なく長期間続けることができます。一方、一括払いでは契約時にまとまった保険料を一度に払い込みます。まとまった資金を預ける必要がありますが、分割払いよりも支払総額を抑えられ返戻率(受取率)が高くなるというメリットがあります。また契約形態によっては、一括で全期間分を前払いする「全期前納」という形も存在します。自身の資金計画に合わせ、月々の積立か一括払いかを選択できるのも個人年金保険の特徴です。
なお、個人年金保険は保険の商品であるため、契約者が年金受取開始前に亡くなった場合には死亡給付金(それまでに払い込んだ保険料相当額など)が受け取れるのが一般的です。あくまで老後資金準備を目的とした保険なので、死亡保障額は定期保険などと比べると大きくありませんが、万一の場合でも払込保険料分が無駄にならない仕組みになっています。
公的年金との違い
老後の収入源となる公的年金(国民年金・厚生年金)と、今回テーマの私的年金(個人年金保険など)には明確な違いがあります。公的年金は日本に住む人全員が原則加入する制度で、20歳から60歳まで保険料を納め、65歳以降に終身で年金を受け取る「国民の基礎的な保障」です。一方、個人年金保険は民間の保険会社が提供する任意加入の保険商品で、公的年金を補完するために自分で加入するオプションの老後資金準備手段です。
公的年金と個人年金保険の主な違いは以下のとおりです。
加入の義務:
給付の期間・方式:
役割:
財源とリスク:
このように、公的年金は必ず受け取れる土台、個人年金保険は自分で準備する上乗せという位置づけです。公的年金だけでは将来の生活に不安がある場合に、個人年金保険などの私的年金で備えることで、より安心して老後を迎えられるようにするのが目的となります。
積立保険の個人年金のメリット
将来に向けて計画的に老後資金を用意できる
個人年金保険に加入する大きなメリットは、計画的に老後資金を貯められる点です。給与など収入があるうちに毎月一定額を強制的に積み立てていくことで、着実に資金形成ができます。保険料は口座振替で自動的に引き落とされるため、「先取り貯蓄」の仕組みとして機能し、貯金が苦手な方でも無理なく続けやすいでしょう。預貯金のように簡単に引き出せないため、「あると使ってしまう」という人でも途中で取り崩すことなく老後資金を確保できるのが特徴です。
また、定額型の個人年金保険であれば契約時に将来受け取れる年金額が確定しています。そのため、「60歳時点で○○万円の年金原資を用意する」といった具体的な目標額に向けて計画を立てやすく、人生設計(ライフプラン)がしやすくなります。将来受取額があらかじめわかっている安心感と、コツコツ積み立てる強制力によって、計画的な老後資金準備が可能になります。
個人年金保険料控除が受けられる
個人年金保険に加入し保険料を払っていると、税制上の優遇措置を受けられる場合があります。それが「個人年金保険料控除」です。年末調整や確定申告の際に、支払った個人年金保険の保険料に応じて所得税・住民税の控除を受けることができます。具体的には、所定の条件を満たした契約であれば所得税で最大年間4万円、住民税で最大年間2万8千円が課税所得から控除されます。例えば、新制度の対象契約で年間8万円の保険料を支払った場合、所得税の控除額は計算式(支払保険料等×1/4+20,000円)に基づき4万円、住民税の控除額は上限である2万8,000円となります 。このように控除額は支払保険料に応じて段階的に決まります。
ただし、個人年金保険料控除を適用するには契約時に「個人年金保険料税制適格特約」を付加し、以下のような所定の条件を満たす必要があります。
- 保険料払込期間が10年以上あること(短期の一時払い契約などは対象外)
- 年金受取人が契約者本人またはその配偶者であること
- 年金受取開始年齢が60歳以上であること など
これらを満たした契約には税制適格特約が付与され、支払保険料が「個人年金保険料控除」として計上できます(条件を満たさない場合でも「一般の生命保険料控除」として一定の控除は可能です)。個人年金保険料控除の枠は一般の生命保険料控除とは別枠なので、生命保険とは別に個人年金保険にも加入すれば控除枠が増え、節税効果を享受できます。毎年の保険料負担が税金の軽減という形で一部戻ってくるため、家計の助けにもなります。長期で見ると数十万円単位で税負担が減るケースもあり、見逃せないメリットです。
健康状態の告知無しで加入できる保険が多い
個人年金保険は健康状態に不安がある方でも加入しやすい商品です。多くの個人年金保険では契約時の健康告知や医師の診査が不要とされています。これは個人年金保険が貯蓄性を主体とした保険であり、死亡保障額がそれほど大きくない(基本的には払込保険料の範囲内の給付が多い)ためです。被保険者の健康リスクによって保険会社が大きな支払いをする可能性が低いため、健康状態に関係なく広く受け入れられています。
その結果、「持病があるけど老後資金のために保険で備えたい」「他の生命保険は健康上の理由で断られた」という方でも、個人年金保険であれば契約可能なケースが多々あります。実際、各社の個人年金保険の商品パンフレット等にも「健康状態にかかわらず加入できます」と明記されているものが見られます。ただし一部の商品では職業告知など別の告知項目がある場合もありますので、申込時の必要事項は確認しましょう。総じて「ノーガイド(無選択型)」に近い緩やかな引受基準の商品が多いため、健康面の不安から老後準備を諦めていた方にも利用しやすいのがメリットです。
保険料を上回る年金を受け取れる可能性がある
個人年金保険は長期間にわたり保険料を積み立てて運用するため、将来受け取る年金額が、払い込んだ保険料総額を上回る可能性があります。これは預けた保険料が保険会社による運用益や利息によって増えることが期待できるからです。特に変額型の個人年金保険の場合、契約者が選んだ投資信託などで積極的に運用するため、市場の運用成果が良ければリターンも大きくなり、受取総額が元本(払込総額)を大きく超えることもあり得ます。また外貨建ての個人年金保険も、海外金利の高さを活かして円建てより高い利回りを得られる可能性があります。
定額型の個人年金保険でも、契約時に予定利率が適用されるため、支払った保険料に利息がつく形で年金原資が積み立てられていきます。低金利下では利息分は小さいですが、過去には予定利率が高かった時期の契約で返戻率が120%超になるようなケースもありました。現在でも商品によっては保険料総額よりも多い年金額を受け取れる設計になっているものがあります。例えば、一括払いで契約した場合や据置期間(保険料払込後、年金受取開始まで運用を継続する期間)を設けた場合に受取額が増える商品などが該当します。
このように、単純な貯金よりも有利に働く可能性がある点もメリットと言えます。ただし運用成果は将来の市場環境によるため、確実に元本超過のリターンが得られるとは限りません(定額型でも予定利率が低ければ受取総額がほぼ払込総額と同程度になる場合もあります)。それでも「うまくいけば増やせる」というチャンスがあることは、資産形成策として魅力の一つでしょう。
払込み免除の特約がある
個人年金保険には万一の場合に保険料の支払いが免除される特約を付加できる商品があります。一般的に「保険料払込免除特約」と呼ばれるもので、契約期間中に契約者(被保険者)が所定の高度障害状態になったり、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)や重度の要介護状態になった場合、それ以降の保険料の払い込みが不要になる保障です。この特約を付けておけば、例えば契約者が働けなくなるような重病になったとしても、その後の保険料負担なしで契約を継続でき、将来の年金受取権を確保できます。
保険料払込免除特約は会社や商品によって名称や対象となる条件が多少異なりますが、多くは三大疾病や所定の重度障害状態をカバーしています。例えば「がんと診断確定されたとき」「急性心筋梗塞または脳卒中で60日以上の入院または所定の手術を受けたとき」などに保険料免除が適用されるケースが典型です。個人年金保険は長期契約ですので、その間に思わぬ病気・障害で収入が途絶えるリスクもゼロではありません。そうした場合でも老後資金の積立計画を中断させないための安全網として、払込免除特約は有用です。
この特約を付けると保険料は多少上乗せになりますが、家庭の働き手に万一のことがあっても老後の備えだけは守られるという安心感があります。公的年金にはこうした「払込免除」はありませんから、保険商品ならではのメリットと言えるでしょう。契約時に特約付加を検討してみる価値があります。
積立保険の個人年金のデメリット
途中解約すると元金割れするリスクがある
個人年金保険で注意すべき最大の点は、途中で解約すると損失(元本割れ)が発生しやすいことです。契約から年金受取開始まで長期間ありますが、その途中で解約(契約をやめて解約返戻金を受け取る)すると、戻ってくるお金は払い込んだ保険料総額よりも少なくなるケースがほとんどです。なぜなら、支払った保険料の全額が積立金になるわけではなく、一部は保険会社の経費や保障のための費用に充てられているためです。特に契約後数年以内の解約では、解約返戻金がほとんどゼロに近いか、あってもごくわずかという場合も珍しくありません。
例えば毎月2万円ずつ10年間積み立てる予定の個人年金に加入していても、3年目で解約したら解約返戻金がそれまで払った72万円より大幅に少ないといったことが起こり得ます(場合によっては解約返戻金が全く出ない契約もあります)。このように中途解約に厳しいペナルティがあるのは、保険会社が契約時の初期費用や維持費用を先に差し引いているためです。長期運用を前提とした商品なので、早期にやめられてしまうと会社側もコストを回収できず、解約返戻金に反映できないという事情があります。
従って、個人年金保険に加入する際は「途中で解約しないこと」が大前提になります。ライフプランの変更や急な出費でどうしても解約せざるを得ない事態も考えられますが、その場合は元本割れを受け入れる覚悟が必要です。そうならないよう、最初から家計に無理のない保険料設定にしておくことが重要です。「毎月の支払いが苦しくて続けられない」という事態は避けるべきです。また契約前に商品パンフレットや設計書で解約返戻金の推移を確認し、何年目で元本に追いつくか(多くは払込終了時点か据置を経てようやく100%超になる)などシミュレーションを把握しておくと良いでしょう。
利率が低いとインフレで価値が目減りする
定額型の個人年金保険においては、インフレに弱いというデメリットがあります。契約時に将来の受取額が確定して安心な反面、その金額は将来的に物価が上昇しても増えないため、実質的な購買力が低下する恐れがあるのです。インフレとは物やサービスの価格が上がりお金の価値が下がる現象です。例えば現在100円の飲み物が将来200円になっていた場合、同じ1,000円でも買える本数が10本から5本に減ってしまいます。このように物価が上がるとお金の実質価値は半減します。
現在は長らく低インフレ・低金利が続いていますが、将来経済状況が変わりインフレ率が上昇すると、固定利率で積み立てた年金額の価値が目減りします。定額型個人年金では契約時点の予定利率で積立が進みますが、日本の予定利率は景気に応じて見直されるため、低金利期に契約した人は低い利率のままです。その結果、物価が上昇しても受取額は契約時点の想定額から増えず、将来的には「思ったより生活の足しにならない」という事態も起こり得ます。
一方、変額型はインフレに強い(市場が好調なら資産も膨らみやすい)と言われますが、その分リスクもあります。定額型については、「決まった額がもらえる安心感」と表裏一体で「インフレリスク」が存在する点を理解しておきましょう。特に若いうちに契約し長期で固定利率を適用する場合、将来の物価変動まで見通せないため、このリスクは頭に入れておく必要があります。
投資のような大きなリターンが期待できない
個人年金保険は安全性や計画性に優れる半面、高いリターン(利益)はあまり期待できないという性質があります。基本的に定額型は保険会社が国債や社債など堅実な運用で利回りを提供するため、現在のような低金利環境では運用益も僅かです。払込保険料総額に対する受取総額の割合(返戻率)を見ると、最近の円建て定額個人年金では100~110%程度に落ち着く商品が多く、「長期間預けてほんの少し増える」程度の利回りです。変額型や外貨建てでうまく運用できればもう少し高いリターンも可能ですが、それでもプロの金融商品であり、運用関係費用や保険関係費用が差し引かれる分、全額自分で投資する場合と比べて利回りが抑えられる傾向があります。
具体的に、同じ積立をするにしてもつみたてNISAやiDeCoなどで株式や投資信託に投資した場合、大きな利益が出る可能性があります(もちろん損失リスクもありますが)。それに対し個人年金保険は保険会社によるコントロール下で運用され、元本の安全性を重視する分リターンは限定的です。また保険商品である以上、事務コストや保障部分のコストが差し引かれるため、純粋な投資商品より効率が落ちる側面もあります。「老後資金を確実に貯める」ことが目的なので、大きく増やすことは二次的なのです。そのため「できればお金を増やしたい」と考える人にとっては物足りなく感じるでしょう。
特に若年層で長期間運用できる人は、保険よりも積極運用の方がリターンが高くなる可能性があります。個人年金保険は元本保証や最低保証がある安心感と引き換えに高収益は追求しない商品設計と言えます。「大きく殖やす」より「確実に貯める」を優先する人向けであり、もし高い運用益を狙いたいのであれば別途リスク商品への投資も検討する必要があるでしょう。
積立保険の個人年金の種類
個人年金保険は様々なタイプがありますが、大きく「運用方法」「運用通貨」「受取期間」の違いで分類できます。それぞれの観点から主な種類と特徴を説明します。
運用方法別の種類
個人年金保険は運用の仕組みにより「定額型」と「変額型」に分けられます。
定額個人年金保険
定額型の個人年金保険は、契約時に将来受け取る年金額が確定しているタイプの保険です。保険会社が主に安全性の高い資産で運用を行い、契約者にはあらかじめ決まった予定利率を適用して積立を行います。契約時に「年金原資○○円、年金年額○○円」といった形で将来の受取額が約束されるため、老後の資金計画を立てやすく安全性が高いのがメリットです。保険期間中、景気変動に関係なく最低保証があるので、元本割れの心配なく積立てることができます(※ただし途中解約しなければ、という前提です)。
定額型では利率が固定されているため、現在のような低金利下では受取額も相対的に抑え目になります。例えば予定利率0.5%の契約では、長年積み立てても増える額はわずかです。またインフレ局面に弱い(前述の通り、お金の価値が下がるリスク)というデメリットがあります。加えて、契約した時期によって有利不利が生じることもあります。例えば予定利率が低い時期に契約した人は、高い時期に契約した人に比べて同じ年金額を得るための保険料負担が大きくなりがちです。
総じて定額個人年金は「増やす」というより「確実に備える」ことに重きを置いた商品です。元本確保を優先したい人や、将来額をはっきり決めておきたい人に向いています。
変額個人年金保険
変額型の個人年金保険は、保険料を投資信託などで運用し、その運用成果によって将来受け取る年金額が変動するタイプの保険です。契約者は保険会社が用意した特別勘定(複数の投資ファンド)から運用先を選択し、保険会社はその特別勘定で資産運用を行います。運用実績が良ければ契約者の積立金が増え、将来の年金額も大きくなります。しかし運用が悪化すれば積立金が目減りし、年金額が元本を下回る(元本割れ)リスクもあります。年金額や解約返戻金、死亡給付金などが市場の動向で日々変動するため、契約時には具体的な受取額は定まりません。
変額個人年金保険のメリットは、運用次第で大きなリターンが期待できる点です。特に長期運用では複利効果も働き、株式市場の成長を取り込めれば老後資金を大きく増やせる可能性があります。またインフレ局面でも、資産価値が市場に連動して増えるためインフレに強いとされています(実際、物価上昇局面では株価や金利が上昇しやすく、それが資産に反映されやすい)。一方で最低保証がない商品が一般的です(保険会社によっては積立保証が付くものもありますが基本的にリスクは契約者負担)。運用がうまくいかなければ、せっかく積み立てても受取時に払込総額を下回るおそれがあります。
変額型には各種手数料や保険関係費用もかかります。投資信託の信託報酬や保険会社の管理費用などが差し引かれるため、全く同じ運用を自分でやるより費用負担分だけ利回りは低くなります。この点は「保険であることのコスト」と言えます。リスクを取りつつも専門家に運用を任せたい人、公的年金に上乗せして投資的な運用をしたい人には向いていますが、元本保証が欲しい人には不向きです。契約前に商品のパンフレットや目論見書をよく読み、運用の仕組みや諸費用、リスクの説明を十分理解することが大切です。
運用通貨別の種類
個人年金保険は運用に使う通貨によって「円建て」と「外貨建て」に分けることができます。
円建ての個人年金保険
円建ての個人年金保険は、保険料の支払いも運用も受取りもすべて日本円で行うタイプです。契約者は毎月(または年)決まった円貨額を払い込み、将来も円で年金を受け取ります。国内金利で運用されるため、日本の低金利環境では運用利回りは低めですが、為替変動による元本割れの心配はありません。受け取れる年金額は契約時または運用次第で決まりますが(定額型なら確定、変額型でも基準は円換算)、少なくとも為替レートによって変動することはないのでシンプルで分かりやすいのが利点です。
円建ては毎月の保険料も一定の円額なので、家計管理もしやすいです。為替手数料なども当然かかりません。一方で、近年の日本は超低金利のため、円建て運用では資産が大きく増えにくい傾向があります。欧米に比べ市場金利が極めて低いため、定額型の予定利率も低く抑えられますし、変額型でも投資対象が国内中心だと成長期待は高くありません。つまり安全だがリターンも小さいのが円建ての特徴です。外貨建てと比べると、物足りなさはあるものの、為替リスクを取りたくない人や円で確実に準備したい人には適した選択と言えます。
外貨建ての個人年金保険
外貨建ての個人年金保険は、米ドルや豪ドルなど外国通貨で保険料を運用するタイプの商品です。契約者は円で払込を行いますが、その都度保険会社が指定の外貨に換算して積立てます。外貨は日本より金利が高い場合が多く、高金利を活用した運用成果が期待できるメリットがあります。例えば米ドル建てなら米国債などで運用し、日本の金利より高い利回りを確保しやすいです。長期運用では僅かな金利差でも最終受取額に大きな差が出るため、外貨建ては円建てより有利な利回りになるケースが少なくありません。実際、外貨建て個人年金では最低保証利率が年1~2%程度設定されている商品もあり、日本円の予定利率(0.x%)と比べ高めです。
しかし、外貨建てには為替リスクがあります。円と契約通貨の為替レートが変動することで、受取時に円換算した金額が大きく増減します。例えば積み立て期間中ずっと1ドル=110円前後だったのが、受取時に1ドル=90円に円高になっていた場合、円ベースの受取総額は想定より約18%も目減りしてしまいます。逆に円安になれば増える利点もありますが、為替動向は予測が難しくリスク要因となります。また受取を円で行う場合は為替手数料もかかります。さらに外貨建て特有の契約コスト(為替両替コストや解約控除など)が円建てより高めに設定されている場合もあります。
このように、外貨建て個人年金保険は「高利回りだが元本保証はなく為替リスクあり」という特徴です。長期間運用すれば為替レートも上下する中で平均化されるとはいえ、受取時のレート次第では元本割れも起こり得ます。したがって、ある程度為替リスクを理解し受け入れられる人向きと言えます。ただし近年は外貨建てにも最低保証利率が付いていたり、契約時に将来の円換算額を一部ロックするオプションなど工夫された商品も登場しています。「外貨の力を借りて効率よく増やしたい」というニーズには応えられるので、円建てに比べリスク許容度が高い方は検討すると良いでしょう。
受取期間の個人年金保険
個人年金保険は年金の受取期間によっても種類が分かれます。主に「終身年金」「有期年金」「確定年金」の3タイプがあり、それぞれ特徴が異なります。
終身年金の個人年金保険
終身年金とは、契約時に定めた年齢(例:60歳)から被保険者が亡くなるまで一生涯、年金を受け取れるタイプの個人年金保険です。いわば民間版の「終身年金」で、公的年金のように長生きすればするほど多くの給付を受けられます。最大のメリットは、生存している限りお金が尽きないことです。寿命が想定より延びても、一生分の年金が約束されているため、「もし長生きして貯蓄を使い果たしたらどうしよう」という不安を和らげてくれます。老後資金が不足しがちな超高齢までカバーできるのは終身年金型の強みです。
ただし、終身年金ではもし早い段階で被保険者が亡くなった場合、支払った保険料の割に受け取る年金総額が少なくなってしまうリスクがあります。例えば60歳から受け取り開始して数年で亡くなった場合、残りの年金は原則支払われず打ち切りとなります(受取総額が払込保険料総額より少なくなる可能性)。このデメリットを補うため、ほとんどの終身年金保険には「保証期間付き終身年金」の形があります。これは「〇年間は生死にかかわらず年金を保証して支払う」という期間を定め、万一早期に死亡した場合でも残りの保証期間分の年金または一時金を遺族が受け取れる仕組みです。例えば「10年保証期間付終身年金」であれば、年金開始後10年未満で亡くなった場合でも、残りの期間の年金相当額が遺族に支払われます。保証期間を付ければ早期死亡時の損失は防げますが、その分年金額は保証なしに比べ少し低めに設定されます。
終身年金型は「長生きリスク」に備える保険本来の意義が大きいタイプです。公的年金だけでは一生の安心が足りないと感じる人や、家系的に長命の傾向があり寿命に備えたい人などに向いています。ただし保険料は同条件の有期年金より割高になりやすい点には留意が必要です。
有期年金の個人年金保険
有期年金とは、契約時に定めた一定の受取期間(例えば5年間や10年間など)にわたって、被保険者が生存している限り年金を受け取れるタイプの保険です。期間限定の終身年金のようなイメージで、受取期間中は毎年(または毎月)定額の年金を受け取ります。ただし被保険者が年金受取期間中に死亡した場合、その時点で年金支払いは終了し、残りの期間分は支払われません(遺族への給付は基本なし)。この点が確定年金との大きな違いです。「生きていればもらえるが、亡くなったら打ち切り」という条件付きの期間年金と言えます。
有期年金のメリットは、生存している限り受け取れる点と期間を限定することで年金額をある程度高く設定できる点です。例えば10年間の有期年金であれば、終身年金よりも保険会社にとって支払い期間が限定されるぶん、同じ保険料でも年金額が高めに計算されることがあります。言い換えれば「もし早く亡くなれば保険会社は支払いをしなくて済む」ため、その分加入者にとってはリスクを取る代わりに見返りとして年金額が増えるイメージです。長生きした場合は最大○年間受け取れるので、その期間を超えて生きたらそこで給付終了となります。
有期年金にも保証期間を付けられる商品があります(「保証期間付有期年金」)。保証期間内であれば、生死問わず年金を支払うため、途中で亡くなった場合でも残りの保証期間分は遺族が受け取れます。保証期間を過ぎた後は被保険者が生存していれば支払い続行、死亡すれば終了となります。
有期年金型は「一定期間だけ年金が欲しい」というニーズにマッチします。例えば「60~70歳の10年間、公的年金に上乗せしてゆとりを持ちたい」や「子どもの独立から自分の年金開始までの5年間を補いたい」など、ライフプランに合わせて期間を設定できます。また終身より保険料負担を抑えつつ長生きにも一定備えたい人にとって妥協点となる商品です。ただし期間以上に長生きすると給付が止まってしまうため、その後の生活は別途考えておく必要があります。
確定年金の個人年金保険
確定年金とは、被保険者の生死に関わらず契約時に定めた一定期間の年金が必ず支払われるタイプの保険です。例えば「10年確定年金」であれば、年金受取開始から10年間は被保険者が生存していても亡くなっていても、年金または残余の一時金が支払われます。極端な話、年金開始後すぐに亡くなってしまっても、遺族が残り期間の年金相当額を受け取れるため、払ったお金が無駄になりません。
確定年金のメリットは、受取総額が確定している安心感と遺族に資金を遺せる可能性があることです。契約時に「○年間で合計○○万円受け取る」ことが約束されるため、自分の老後資金計画はもちろん、万一自分に何かあった場合でも家族にそのお金を遺せます。言い換えると「自分の貯蓄を分割で取り崩す」のに近い商品で、保険というより積立貯蓄の受取方法を決めたものとも言えます。
一方で、確定年金は被保険者が長生きしても定められた期間以上は給付がないという点に注意です。例えば15年確定年金なら、受取開始から15年分受け取ったらそれで終了し、16年目以降はもう年金は出ません。生きている間ずっともらえる終身年金とはこの点が異なります。そのため、確定年金は「ある程度寿命より短めの期間」に設定されることが多く、公的年金開始までのつなぎや退職後数年間の生活補填など目的を限定して使われるケースが多いです。
確定年金型は「元本を無駄にせず受け取りきりたい」というニーズに合致します。「せっかく積み立てたのに自分が早死にしたら損」という心配が強い方には向いているでしょう。ただし長生きリスクに備えるという保険本来の目的から見ると弱いため、公的年金や他の資産と組み合わせて期間満了後に困らないよう計画しておくことが大切です。
個人年金がおすすめの人と入らない方がいい人
個人年金保険はメリットも多い反面、万人に必要というものではありません。「それぞれの家庭や資産状況によって向き不向きがある」商品です。以下に、個人年金保険が特におすすめできる人と、逆に加入をあまりおすすめしない人の特徴を挙げます。
おすすめできる人の特徴:
貯蓄が苦手な人
元本割れを避けたい人
個人事業主・フリーランスの人
入らない方がいい(おすすめできない)人の特徴:
保険料を支払える経済的余裕がない人
自分で資産運用したい人
すでに十分な老後資金を確保している人
以上のように、個人年金保険は「老後資金を確実に作りたい人」には向いていますが、「積極的に増やしたい人」「資金に余裕がない人」には向きません。インターネット上のQ&Aサイト(例えばYahoo!知恵袋など)でも「個人年金保険は入らない方がいい?」といった質問が見られるように、向き不向きを見極めることが大切です。自分の将来の年金見込みや現在の家計状況と照らし合わせて、必要性を判断しましょう。
月いくら必要?積立保険の個人年金シミュレーション
具体的に、個人年金保険でどのくらい積み立てるとどの程度の年金が受け取れるのか、いくつかシミュレーションしてみます。条件によって結果は異なりますが、一例として30歳から積立を開始した場合のケースを考えます(年金受取開始は60歳とし、そこから10年間の確定年金を受け取るプランを想定)。以下の表に加入ケースごとの保険料と受取額の目安をまとめました。
| 例 | 加入時年齢 | 月額保険料 | 保険料払込期間 | 年金受取開始年齢 | 年金月額(目安) | 年金総受取額(目安) |
| 例1 | 30歳 | 5,000円 | 30年間(~60歳) | 60歳から開始 | 約1.7万円/月 | 約200万円(10年合計) |
| 例2 | 30歳 | 15,000円 | 30年間(~60歳) | 60歳から開始 | 約5.0万円/月 | 約600万円(10年合計) |
| 例3 | 40歳 | 15,000円 | 20年間(~60歳) | 60歳から開始 | 約3.3万円/月 | 約400万円(10年合計) |
※上記は利率や契約条件を仮定した概算例です。実際の受取額は加入する商品や運用利回り等によって異なります。
例1では、30歳から毎月5千円を60歳まで30年間積み立てたケースです。総払込保険料は約180万円ですが、据置や運用利息により、60歳から毎月約1.7万円(年間約20万円)を10年間受け取れると仮定すると、総受取額は約200万円となります。払込総額よりやや多い金額を手にするイメージです。月々5千円という少額でも、30年コツコツ積めば老後に年間20万円程度の年金を得られる計算になります。
例2は、同じく30歳開始で月額1万5千円に増やした場合です。払込総額は約540万円となり、60歳から毎月約5万円(年間約60万円)を受け取れる想定とすると、10年総額で約600万円受け取れます。毎月の年金額5万円は、公的年金に上乗せするにはかなり心強い額と言えます。現役時代に月1万5千円の負担でこれだけの老後収入を確保できるのは、個人年金保険の有効な活用例でしょう。
例3は、開始年齢を40歳に遅らせたケースです。40歳から月1万5千円を20年間積み立てると、払込総額は約360万円です。受取開始は同じ60歳ですが、積立期間が短いため増やせる金額も少なくなります。この場合、60歳からの年金は毎月約3.3万円(年間約40万円)程度となり、総受取額は約400万円にとどまるシミュレーションです。例2と比べると、開始を10年遅らせただけで受取額がだいぶ減ってしまうことが分かります。「積立は早く始めた方が有利」という典型例です。開始が遅い分、同じ年金額を確保しようと思えば月々の保険料負担をもっと上げる必要があります。
上記のシミュレーションはあくまでモデルケースですが、個人年金保険で思い描く老後年金額から逆算して月いくら積めばよいかの参考になります。例えば「老後に毎月プラス5万円の年金が欲しい」と思ったら、30代のうちから1~2万円台の積立が必要、開始が遅れるならさらに高額の積立が必要、という具合です。各社の個人年金保険には試算ツールやシミュレーション表がありますので、自分の目標額に合わせて計算してみると良いでしょう。
積立保険の個人年金おすすめランキングTOP3
老後に向けた個人年金保険は多数の商品がありますが、その中から特に人気・実績のある商品をピックアップして紹介します。ここではおすすめの個人年金保険トップ3として、国内大手生保や専門会社の代表的な商品を挙げます。それぞれ特徴やおすすめポイント、基本情報をまとめますので、自分に合った商品選びの参考にしてください。
TOP1:日本生命「みらいのカタチ 年金保険」
日本生命の「ニッセイ みらいのカタチ 年金保険」は、国内最大手の日本生命が提供する個人年金保険です。「みらいのカタチ」シリーズの一商品として位置づけられており、公的年金制度と連動した分かりやすい設計や、契約後の柔軟性が特徴です。将来必要な資金を計画的に準備できるよう、月々5,000円からという少額保険料からスタートでき、長期の積立に無理なく取り組めます。契約時に年金受取開始年齢や受取期間を決めますが、後から年金開始時期や受取期間を変更できる点が他社にないメリットです。たとえば「当初65歳開始予定だったが継続雇用で70歳まで働くことになったので70歳開始に延期」などの調整が可能です。また受取期間も、契約時は10年確定年金にしておいて後に15年確定に変更する、といったことができます(※変更には所定の条件・手続きが必要です)。
さらに、ニッセイみらいのカタチ年金保険は「保険料払込免除特約」を付加することもできます。所定の3大疾病や重度障害状態になった場合、以後の保険料払込が免除されるため、長期契約でも安心感があります。大手生保の商品らしく、充実したオプションと堅実な設計で、貯蓄性と保障のバランスが取れた個人年金保険と言えるでしょう。日本生命の信頼性や全国規模のアフターフォロー網も大きな安心材料です。
- 契約年齢:
満7歳~満65歳まで契約可能(幅広い年齢で加入可。子どもの将来資金準備として親が契約するケースも対応) - 年金受取方法(種類):
5年・10年・15年の確定年金、または10年保証期間付終身年金から選択 - 保険料払込方法:
月払い・年払い・一時払いに対応(月払いの場合月額5,000円から設定可能) - 主な特約:
保険料払込免除特約(3大疾病・重度状態保障)など付加可能 - 個人年金保険料控除:
適格特約付加で対象(条件を満たせば契約者の税控除可)
おすすめポイントとして、「将来の変化に柔軟に対応できる」ことと「大手ならではの安定感」が挙げられます。長期契約中に状況が変わっても年金開始時期をずらせるのは、公的年金の繰下げ受給のような感覚で心強いです。また日本生命は2025年から返戻率を引き上げる改定を行い、契約者にとってさらに有利な条件となりました(予定利率上乗せにより受取率アップ)。堅実に貯めたい人にまず検討してほしい一社です。
TOP2:三井住友海上プライマリー生命「あしたのゆとり」
「あしたのゆとり」は、三井住友海上プライマリー生命保険が提供する個人年金保険です。MS&ADインシュアランスグループの一員で、銀行窓販などで広く販売されている商品となります。この商品は、積立利率が市場金利に連動して毎月見直される「利率変動型」です。そのため、金利上昇局面では高いリターンが期待できる一方、金利が低下すれば利率も下がります。外貨建てのため、為替変動のリスクも伴います 。したがって元本が増える期待値が高い商品と言えます。
「あしたのゆとり」は生存保障重視型と銘打っている通り、長生きすればしっかり年金を受け取れる設計になっています。具体的な年金受取方法として、確定年金(5年または10年)や保証期間付終身年金(10年保証付の終身)などから選択でき、ライフプランに応じたプラン設定が可能です。終身で受け取れるコースを選べば、家族に資産を残しながら自分も生涯年金を受け取るようなことも実現できます(例えば保証期間経過後は終身年金で、死亡時には残余の死亡一時金が出るタイプ)。利率変動型とはいえ、契約時に将来の年金開始日までは積立利率が決まる仕組みで、市場金利に連動して毎月利率が見直されつつも一定の範囲(指標金利±○%)で運用されます。専門的な細かい仕組みはありますが、平たく言えば「外貨の高金利を取り入れつつも、最低利率保証で下支えしている個人年金」です。
外貨建てゆえ為替リスクは伴いますが、その点は契約者の選択次第です。受取時に契約通貨(例:ドル建てのまま)で受け取ることもできますし、円で受け取る場合は為替レートによって円換算額が変動します。円安になれば有利、円高だと不利ですが、そのリスクを負える人には魅力的な商品でしょう。また毎回の保険料は円で一定額払い込みますが、その時の為替で外貨額が決まるため、円安時には同じ円でも少ない外貨額しか積み立てられないという点にも注意が必要です(逆に円高時には多くの外貨を買えるので有利)。とはいえ、長期にわたってドルコスト平均的に購入する形になるため、極端な偏りは平準化されます。
- 契約年齢:
おおむね満16歳~満70歳くらいまで(契約プランによって上限年齢は異なるが、幅広い年齢層が加入可能) - 年金受取方法:
5年確定年金、10年確定年金、10年保証付終身年金 など商品内で複数のプラン設定あり - 運用通貨:
米ドル建て・豪ドル建て等(契約時に選択) - 保険料払込方法:
月払い(円貨で払込、最低月額5千円~)・一時払い 等を用意 - 予定利率(積立利率):
契約時の市場金利をもとに決定(定期的に見直しあり)※最低保証利率あり - 個人年金保険料控除:
契約形態が所定条件を満たせば対象(税制適格特約付加で控除可)
「あしたのゆとり」は、「もうひと頑張り資産を殖やしたい」という層におすすめです。公的年金に上乗せのゆとりを持たせたいけれど、国内の低利回りでは物足りない……という場合に、外貨の力を借りて効率的に積立てる選択肢となります。特に現在のように米ドル金利が高水準の局面では、その恩恵を享受しやすいでしょう。大手損保系の生保であり、銀行や証券会社経由で相談・加入できる手軽さもあります。ただし為替変動リスクを許容できるか、自分の老後資金の性格(安全第一か成長重視か)を考えて選ぶことが大切です。
TOP3:ソニー生命「SOVANI(そばに)」
ソニー生命の「変額個人年金保険 SOVANI(そばに)」は、変額年金の分野でトップクラスの人気を誇る商品です。累計契約件数が100万件を突破するなど、多くの契約者に選ばれています。SOVANI最大の特徴は、非常に柔軟で使い勝手の良い積立商品であることです。まず月々3,000円からという超少額から加入でき、小口スタートが可能です。さらに家計状況に応じて保険料の増額・減額、払込の一時停止・再開が自由に行えます。例えば「子育てで出費が多い間は払込を停止し、落ち着いたら再開」「ボーナス時に追加で一時払い投入」といった調整もOKです。このように契約者のライフステージに寄り添った柔軟性が、商品名「そばに」に込められているのでしょう。
運用面では、特別勘定(ファンド)を16種類も用意しており、国内外の株式・債券・バランス型・短期金融市場型など多彩な運用スタイルから最大8つまで組み合わせて資産配分できます。つまり、自分のリスク許容度や運用方針に合わせてポートフォリオを構築できるわけです。これは投資信託で自分で運用するのと近い感覚ですが、SOVANIの場合は一度選んだ後の運用管理はプロに任せられます。特別勘定の運用成績に応じて将来の年金額や解約返戻金が増減しますが、運用次第では大きなリターンも期待できる点が魅力です。実際、ソニー生命は「人生100年時代の資産形成に対応する商品」としてSOVANIを開発しており、長期の積極運用で資産を増やす目的に合致しています。
保障に関しては、変額保険ですので基本的に死亡給付金などの保障は最低限(積立金相当額など)に抑えられ、運用部分に重きを置いています。言い換えると無駄なコストを保障に割かず、運用に集中させているため、変額年金としての効率が良いとも言えます。なお無告知型(健康状態の告知不要)で加入できるので、健康面のハードルもありません。SOVANIは受取開始後も運用が続くタイプで、年金をもらいながらも残りの積立金は特別勘定で運用されます。「運用しながら取り崩す」を自動で実現してくれるので、セカンドライフ中も資産寿命を延ばす効果が期待できます。
- 契約年齢:
満16歳~満70歳まで(契約者/被保険者の年齢条件。幅広い年齢層に対応) - 保険料:
月払い(口座振替等)月額3,000円~上限100万円まで自由に設定可。一時払いプランもあり - 払込方法の柔軟性:
増額・減額、払込停止(最大一定期間)、再開が可能 - 運用特別勘定:
全16種類(国内株式、外国株式、債券、バランス、短期など)から選択(最大8ファンドまで組合せ可) - 年金受取方法:
年金支払開始時に確定年金や有期年金等から選択(例:5年確定年金、10年確定年金など※その時の積立金額で年金額計算) - 諸費用:
ご契約の維持・管理に必要な「保険関係費用」や、特別勘定の運用にかかる「運用関係費用(信託報酬など)」が積立金から控除されます。り - 個人年金保険料控除:
契約形態によって対象となる場合あり(税制適格特約付加で可能)
SOVANIのおすすめポイントは、とにかく柔軟で続けやすいことと資産運用の自由度が高いことです。「保険料3,000円~」は学生や新社会人でも始められるハードルの低さで、途中で金額変更や休止もできるため長い人生の中で無理なく継続できます。これは他の個人年金保険にはなかなか無い利点です。また「せっかくお金を貯めるなら増やしたい」というニーズに応えて、自分好みの運用プランを組めるのも魅力です。過去の実績では多くの契約者が投資感覚で利用しており、契約件数100万件超・預かり資産残高1兆円突破(2023年発表)という規模からも人気の高さがうかがえます。変額年金は元本保証こそありませんが、長期分散投資を保険の形で実践したい人にはピッタリでしょう。
なお、変額保険ゆえに元本割れリスクや各種手数料には注意が必要です。特別勘定の運用結果次第では、払込保険料総額より少ない年金額しか得られない可能性もあります。また保険関係費用として毎日少しずつ積立金から差し引かれるコストもあります。それでも、リスクを取れる方にとってはSOVANIほど使い勝手の良い商品は他にないかもしれません。「貯蓄+投資+保険のハイブリッド」を求める方に強くおすすめできる商品です。
以上、積立型の個人年金保険についてその特徴からメリット・デメリット、おすすめ商品まで解説しました。老後資金の準備方法は人それぞれですが、個人年金保険は計画性・確実性という点で優れた選択肢です。公的年金だけでは不安だという方は、自身のライフプランに合わせてぜひ検討してみてください。将来の安心のために今からできる備えを少しずつ始めていきましょう。