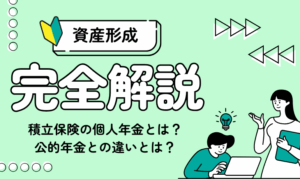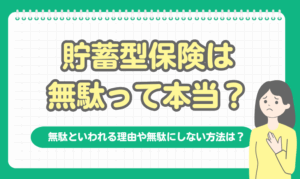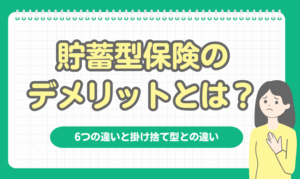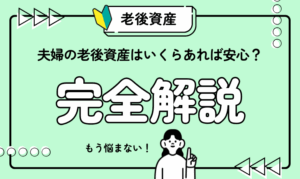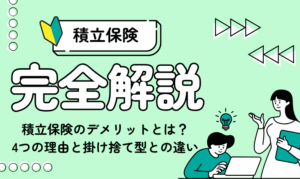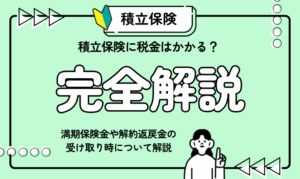「将来のために備えたいけど、何から始めればいいかわからない」
「保険には入りたいけど、ただお金を払うだけなのはもったいない気がする」
このように、保険への加入を検討し始めたばかりの方は、さまざまな疑問や不安をお持ちではないでしょうか。特に、保険には多くの種類があり、自分に合ったものがどれなのかを見極めるのは難しいと感じるかもしれません。
そんな保険初心者の方向けに、この記事では「貯蓄型保険」について徹底的に解説します。
貯蓄型保険は、万が一の事態に備える「保障」と、将来のためにお金を貯める「貯蓄」の2つの機能を兼ね備えた保険です。この記事を読めば、貯蓄型保険がどんな保険なのか、自分に必要なのかどうかが明確になります。
この記事でわかること
- 貯蓄型保険の基本的な仕組みと加入目的
- 掛け捨て型保険との明確な違い
- 代表的な貯蓄型保険の種類とそれぞれの特徴
- 貯蓄型保険のメリット・デメリット
- あなたに貯蓄型保険が向いているかどうかの判断基準
保険選びは、あなたのライフプランを大きく左右する重要な決断です。ぜひ最後までお読みいただき、後悔のない保険選びの第一歩を踏み出してください。
貯蓄型保険とは貯蓄と保障を両立できる保険
まず、「貯蓄型保険とは何か?」という基本的な部分から見ていきましょう。
貯蓄型保険とは、その名の通り、万が一の際の「保障」機能と、将来に向けた「貯蓄」機能をあわせ持った生命保険のことです。
保険と聞くと、病気やケガ、死亡といったリスクに備える「掛け捨て」のイメージが強いかもしれません。しかし、貯蓄型保険は、支払った保険料がただ消えていくのではなく、その一部が積み立てられていきます。
そして、保険期間が満了した際には満期保険金として、途中で解約した際にも解約返戻金として、これまで積み立てたお金を受け取れるのが大きな特徴です。もちろん、保険期間中に死亡したり、高度障害状態になったりした場合には、保険金が支払われるという保障機能もしっかりと備わっています。
つまり、貯蓄型保険は「万が一の保障を得ながら、同時にお金も貯められる」一石二鳥の金融商品と考えることができます。
貯蓄型保険の加入目的
では、人々はどのような目的で貯蓄型保険に加入するのでしょうか。主な目的は以下の通りです。
- 老後資金の準備: 公的年金だけでは不安だという方が、セカンドライフの生活資金を計画的に準備するために活用します。
- 教育資金の準備: 子どもの大学進学など、将来必ず必要になるまとまった教育資金を着実に貯めるために利用されます。
- 万が一の際の死亡保障: 自身に何かあった場合に、遺された家族が生活に困らないようにするための資金(生活費、葬儀費用など)を確保します。
- 特定の目的のための資金準備: 住宅購入の頭金や、起業資金など、人生の特定のイベントに向けた資金作りの手段としても選ばれます。
このように、貯蓄型保険は「保障」と「貯蓄」という2つの側面から、人生のさまざまなライフイベントに備えるための有効な手段となり得るのです。
貯蓄型保険と掛け捨て型保険の違いとは
保険を検討する際、貯蓄型保険と必ず比較されるのが「掛け捨て型保険」です。両者の違いを理解することは、自分に合った保険を選ぶ上で非常に重要です。
まず、掛け捨て型保険とは、貯蓄性をなくし、「保障」機能に特化した保険のことです。保険期間中に死亡したり病気になったりした場合には手厚い保障が受けられますが、満期保険金や解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。その分、月々の保険料が貯蓄型保険に比べて割安なのが特徴です。
両者の違いを分かりやすく表にまとめました。
| 比較項目 | 貯蓄型保険 | 掛け捨て型保険 |
| 貯蓄性 | あり | なし(またはごくわずか) |
| 満期保険金 | あり | なし |
| 解約返戻金 | あり | なし(またはごくわずか) |
| 保険料 | 割高 | 割安 |
| 主な目的 | 保障+将来の資産形成 | 万が一の大きな保障 |
| 向いている人 | ・貯金が苦手な人 ・保障と貯蓄を両立したい人 | ・保険料を抑えたい人 ・保障は保険、貯蓄は別で行いたい人 |
どちらのタイプが良い・悪いということではありません。保険に何を求めるかによって、最適な選択は変わってきます。
例えば、「子どもが独立するまでの20年間、万が一のことがあったときのために大きな死亡保障が欲しい。でも、毎月の保険料はできるだけ安く抑えたい」という方であれば、掛け捨て型の定期保険が適しているでしょう。
一方で、「万が一の保障も確保しつつ、将来のために半ば強制的にでもお金を貯めていきたい。貯金が苦手だから、仕組みで解決したい」という方であれば、貯蓄型保険が有力な選択肢となります。
このように、ご自身の価値観やライフプラン、経済状況に合わせて、どちらのタイプが自分に合っているかをじっくり検討することが大切です。
代表的な貯蓄型保険の種類
貯蓄型保険と一言でいっても、その中にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や得意な目的が異なります。ここでは、代表的な4つの貯蓄型保険について、詳しく解説します。
終身保険(生命保険)
終身保険は、その名の通り保障が一生涯続く死亡保険です。被保険者が亡くなった際に、遺族が死亡保険金を受け取ることができます。
最大の特徴は、解約しない限り保障が一生涯続くという点です。そのため、いつか必ず訪れる「死」というリスクに備えることができます。また、貯蓄性も備えており、途中で解約した場合には解約返戻金を受け取れます。一般的に、保険料の払込期間が終了した後の解約返戻金は、払込保険料の総額を上回ることが多く、これを老後資金などに活用することも可能です。
- どんな保険?: 一生涯の死亡保障があり、解約すれば解約返戻金が受け取れる保険。
- 加入目的: 葬儀費用の準備、遺族への生活資金、相続対策など。
- どんな人向け?:
- 一生涯の保障を確保したい人
- お葬式代などで家族に迷惑をかけたくないと考えている人
- 相続税対策をしたい人(死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があるため)
養老保険
養老保険は、「保障」と「貯蓄」のバランスが取れた保険と言われます。保険期間があらかじめ定められており、その期間内に被保険者が死亡した場合は死亡保険金が、無事に満期を迎えた場合は死亡保険金と同額の満期保険金が受け取れる仕組みです。
生きていても、亡くなっても、いずれの場合でも保険金が受け取れることから、「生死混合保険」とも呼ばれます。終身保険が「いつか必ず支払われる」のに対し、養老保険は「決まった時期にまとまったお金を作る」という目的意識がより強い保険です。
- どんな保険?: 保険期間中に死亡しても、満期まで生きていても、同額の保険金が受け取れる保険。
- 加入目的: 10年後、20年後といった特定の時期に必要な資金(老後資金、住宅資金など)の準備と、その期間中の死亡保障の両立。
- どんな人向け?:
- 「〇年後に〇〇〇万円」という明確な目標金額と時期がある人
- 保障を確保しながら、着実にお金を貯めたい人
個人年金保険
個人年金保険は、公的年金に上乗せする形で老後の生活資金を準備することに特化した保険です。
契約時に定めた年齢(60歳や65歳など)まで保険料を払い込み、その後、一定期間(5年、10年など)または一生涯にわたって、年金形式で保険金を受け取ることができます。保障機能は他の貯蓄型保険に比べて限定的で、一般的には保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合、それまでに払い込んだ保険料に相当する額が死亡給付金として支払われます。
- どんな保険?: 老後のための私的年金を計画的に準備する保険。
- 加入目的: ゆとりあるセカンドライフを送るための老後資金の確保。
- どんな人向け?:
- 公的年金だけでは将来が不安な人
- 計画的に老後資金を積立てたいと考えている人
- 自営業者やフリーランスで、厚生年金がない人
学資保険
学資保険は、その名の通り、子どもの教育資金を準備するための保険です。
子どもの進学時期(高校入学、大学入学など)に合わせて、お祝い金や満期保険金が受け取れるように設計されています。最大のメリットは、契約者である親に万が一のこと(死亡・高度障害など)があった場合、それ以降の保険料の払込みが免除される点です。払込みが免除された後も、保障は継続され、予定通りお祝い金や満期保険金を受け取ることができます。
これにより、「親に何かあっても、子どもの教育資金だけは必ず確保できる」という安心感を得られます。
- どんな保険?: 子どもの教育資金を計画的に準備するための保険。契約者に万が一のことがあった際の保険料払込免除機能がある。
- 加入目的: 大学の入学金や授業料など、将来必要となる教育資金の確保。
- どんな人向け?:
- 子どもの将来のために、着実にお金を貯めたい親
- 自分に何かあっても、子どもの進学の夢を諦めさせたくないと考えている人
貯蓄型保険のメリットとは
ここまで貯蓄型保険の概要や種類を見てきましたが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。主な4つのメリットを詳しく解説します。
満期保険金や解約返戻金がある
貯蓄型保険の最大のメリットは、支払った保険料が掛け捨てにならず、将来的に満期保険金や解約返戻金として戻ってくる点です。
掛け捨て型保険は、何もなければ支払った保険料は戻ってきません。それに対して貯蓄型保険は、保障を得ながらも、支払った保険料が積み立てられていくため、「保険料がもったいない」と感じることが少ないでしょう。
満期まで継続したり、一定期間以上払い込んだりすれば、支払った保険料総額よりも多くの金額が戻ってくる(返戻率が100%を超える)商品も多く、資産形成の一環として活用できます。
計画的に資産形成ができる
「毎月コツコツ貯金しようと思っても、ついつい使ってしまう…」という方は多いのではないでしょうか。
貯蓄型保険は、毎月決まった日に口座から自動的に保険料が引き落とされるため、半ば強制的に貯蓄を続ける仕組みを作ることができます。給料が入ったら先に貯蓄分を取り分けてしまう「先取り貯金」と同じ効果があり、貯金が苦手な人でも計画的な資産形成が可能です。
意思の力に頼らず、仕組みでお金を貯めたい人にとって、これは非常に大きなメリットと言えるでしょう。
生命保険料控除を利用できる
貯蓄型保険の保険料は、生命保険料控除の対象となります。
生命保険料控除とは、1年間に支払った保険料の一定額をその年の所得から差し引くことができる制度です。所得が低くなることで、所得税や住民税の負担が軽減されます。
利用できる控除枠には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があり、例えば個人年金保険に加入すれば、「個人年金保険料控除」を活用できます。
保障や貯蓄の機能に加えて、税制上の優遇措置を受けられる点も、貯蓄型保険の魅力の一つです。
契約者貸付がある
急な出費でお金が必要になったとき、保険を解約するのは避けたいものです。そんな時に役立つのが「契約者貸付」制度です。
これは、その時点での解約返戻金の一定範囲内(一般的には7〜9割程度)で、保険会社からお金を借りることができる制度です。保険を解約することなく、一時的に資金を調達できるため、保障は継続したまま急な出費に対応できます。
銀行のカードローンなどに比べて金利が低い傾向にあり、手続きも比較的簡単なため、いざという時のセーフティネットとして機能します。
貯蓄型保険のデメリットとは
多くのメリットがある一方で、貯蓄型保険には注意すべきデメリットも存在します。契約してから後悔しないよう、デメリットもしっかりと理解しておきましょう。
掛け捨て型より保険料が高くなる
貯蓄型保険は、保障機能に加えて貯蓄機能も備えているため、同じ保障内容の掛け捨て型保険と比較すると、月々の保険料はどうしても割高になります。
例えば、30歳男性が死亡保障3,000万円を確保する場合、掛け捨ての定期保険なら数千円の保険料で済みますが、貯蓄型の終身保険では数万円になることも珍しくありません。
家計に占める保険料の負担が大きくなりすぎると、生活を圧迫してしまう可能性もあります。自分の収入やライフプランに対して、無理のない保険料設定にすることが非常に重要です。
途中解約すると元本割れで損をすることが多い
貯蓄型保険は、長期的に継続することを前提に設計されています。そのため、契約から早い段階で解約してしまうと、解約返戻金がそれまでに支払った保険料の総額を下回る「元本割れ」を起こす可能性が非常に高いです。
特に契約から数年間は、解約返戻金がほとんどない、あるいはまったくないケースもあります。
「保険料の支払いが厳しくなったから解約しよう」となると、結果的に大きく損をしてしまうリスクがあるのです。加入する際には、将来にわたって保険料を払い続けられるかどうかを慎重に判断する必要があります。
インフレに弱い
貯蓄型保険は、契約時に将来受け取る満期保険金や年金額が確定している「固定金利」の商品がほとんどです。これは計画が立てやすいというメリットがある一方で、インフレ(物価の上昇)に弱いというデメリットがあります。
例えば、「30年後に500万円を受け取る」という契約をしたとします。しかし、もし30年の間に物価が2倍になっていたら、その500万円の実質的な価値は現在の250万円分にまで目減りしてしまいます。
将来のインフレリスクを考えると、貯蓄型保険だけで資産形成を行うのではなく、投資信託などインフレに強いとされる他の金融商品と組み合わせて資産を準備することも検討すると良いでしょう。この点が、保険で貯蓄をしてはいけないと言われることがある理由の一つです。
貯蓄型保険への加入がおすすめの人とは
これまで見てきたメリット・デメリットを踏まえて、どのような人に貯蓄型保険が向いているのか、また、むしろ掛け捨て型保険を選んだ方が良いのはどのような人なのかをまとめました。
貯蓄型保険がおすすめの人
以下のような方は、貯蓄型保険への加入を検討する価値が高いと言えます。
- 貯金が苦手で、仕組みで計画的にお金を貯めたい人: 半強制的に貯蓄ができるため、着実に資産形成を進められます。
- 保障と貯蓄を一つの商品でまとめて管理したい人: 手間をかけずに「備え」と「貯蓄」を両立できます。
- 生命保険料控除などの税制メリットを活用したい人: 節税効果も期待できます。
- 長期的に安定して保険料を支払える経済的余裕がある人: 途中解約のリスクを避けられるため、貯蓄型保険のメリットを最大限に活かせます。
- 投資などのリスクは取りたくないが、銀行預金よりは高い利回りを期待したい人: 元本割れのリスクはありますが、投資に比べるとリスクは限定的です。
掛け捨て型保険の方がおすすめの人
一方で、以下のような方は、掛け捨て型保険の方がニーズに合っている可能性が高いです。
- できるだけ保険料を抑えて、大きな保障を確保したい人: 特に、子育て世代など保障ニーズが高い時期に効率的に備えられます。
- 貯蓄や資産運用は、保険とは別に自分で行いたいと考えている人: 「保障は保険」「貯蓄は預金」「資産運用は投資信託(NISAやiDeCoなど)」と、目的別に商品を使い分けたい人。
- ライフステージの変化に合わせて、保険を柔軟に見直したい人: 掛け捨て型は保険期間が短いものが多く、その時々の状況に合わせて保障内容を最適化しやすいです。
- 現時点で経済的な余裕があまりない人: まずは最低限の保障を割安な保険料で確保することを優先すべきです。
貯蓄型保険は無駄だという意見もありますが、それはあくまで「貯蓄と保険を分けたい」という価値観に基づいたものです。ご自身の性格や考え方、経済状況によって、どちらが「必要」かは変わってきます。
貯蓄型保険の選び方とは
もし、あなたが貯蓄型保険への加入を前向きに検討するのであれば、次に考えるべきは「どのように選ぶか」です。後悔しないための選び方のポイントを3つご紹介します。
- 加入する「目的」を明確にする
まず最も大切なのは、「何のために保険に入るのか」という目的をはっきりさせることです。- いつまでに: 65歳までに、子どもが18歳になるまでに
- いくら: 老後資金として2,000万円、教育資金として500万円
- どんな保障が: 一生涯の死亡保障、大学在学中の教育資金
- 目的が明確になれば、選ぶべき保険の種類(終身保険なのか、学資保険なのか)が自ずと見えてきます。
- 保証と保険料のバランスを考える
目的が決まったら、次に「必要な保障」と「無理なく払い続けられる保険料」のバランスを考えます。手厚い保障や高い返戻率を求めると、保険料は高くなります。逆に、保険料を抑えようとすると、保障が不十分になったり、貯蓄性が低くなったりします。
家計の状況をしっかりと把握し、長期的に見て負担にならない保険料はいくらなのか、現実的なラインを見極めることが重要です。 - 返戻率を比較検討する
貯蓄性を重視する場合、「返戻率(へんれいりつ)」は必ずチェックしたい指標です。返戻率とは、支払った保険料の総額に対して、将来受け取れる満期保険金や解約返戻金がどれくらいの割合になるかを示したものです。
$$$$$$返戻率 (%) = \\frac{受け取る保険金の総額}{支払う保険料の総額} \\times 100 $$
$$$$返戻率が100%を超えれば、支払った保険料よりも多くのお金が戻ってくることを意味します。この数値が高いほど、貯蓄性が高い商品と言えます。複数の保険商品を比較する際には、保障内容と合わせて返戻率もしっかりと確認しましょう。
まとめ:自分に合った保険を選び、賢く将来に備えよう
今回は、「貯蓄型保険とは何か」をテーマに、その仕組みから種類、メリット・デメリット、選び方までを詳しく解説しました。
この記事のポイント
- 貯蓄型保険は、「保障」と「貯蓄」の2つの機能を兼ね備えた保険。
- 掛け捨て型との大きな違いは、解約返戻金や満期保険金の有無と、保険料の水準。
- 終身保険、養老保険、個人年金保険、学資保険などが代表的な種類で、それぞれ得意な目的が異なる。
- メリットは、計画的な資産形成ができ、税制優遇も受けられる点。
- デメリットは、保険料が割高で、途中解約すると元本割れのリスクがある点。
- 選ぶ際は「目的の明確化」「保険料とのバランス」「返戻率の比較」が重要。
貯蓄型保険は、貯金が苦手な方や、保障と貯蓄をシンプルにまとめたい方にとって、非常に心強い味方となります。一方で、保険料の高さや途中解約のリスクといったデメリットも存在するため、その特性を十分に理解した上で加入を検討することが不可欠です。
保険選びに絶対的な正解はありません。大切なのは、ご自身のライフプランや価値観に合った商品を、納得して選ぶことです。
もし、「自分一人で選ぶのは難しい」「もっと専門的なアドバイスが欲しい」と感じた場合は、保険のプロであるファイナンシャルプランナーなどに相談してみるのも良いでしょう。