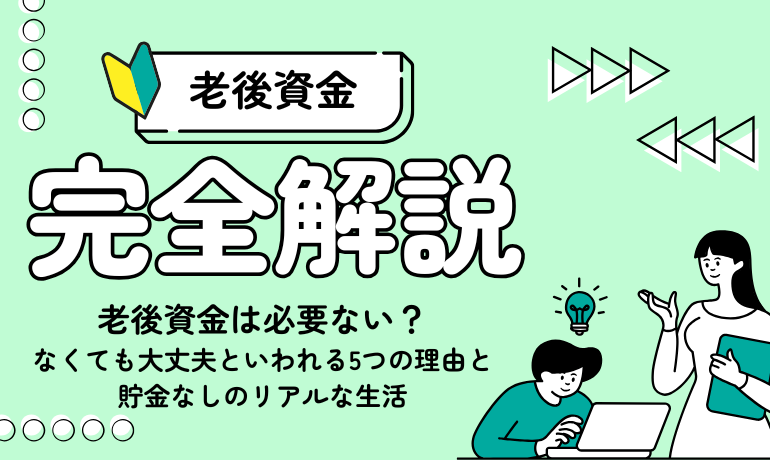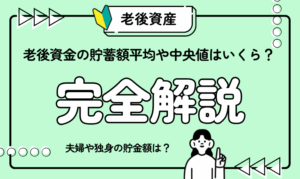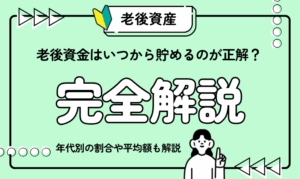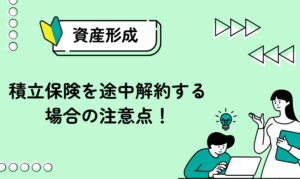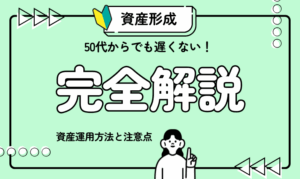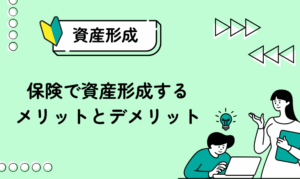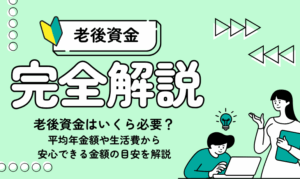「老後資金は2000万円必要」「いや、もっと必要だ」といった話を耳にするたびに、漠然とした不安に駆られていませんか?
「そんな大金、とても貯められない…」
「今の生活で精一杯で、老後のことまで考えられない」
そう感じている方も少なくないでしょう。中には「老後資金は必要ない」という声もあり、一体どちらを信じれば良いのか分からなくなってしまいますよね。
この記事は、まさにそのような悩みを抱えるあなたのために書きました。
老後資金を貯めたいけれど思うように貯められない方、貯金がなくて将来が不安な方に向けて、「老後資金は必要ない」といわれる理由を深掘りしつつ、一方で貯金なしで迎える老後のリアルな生活についても具体的に解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたが老後とどう向き合い、今から何をすべきか、その道筋がきっと見えてくるはずです。
老後資産は2000万円もいらないって本当?
多くの人が老後資金について考えるとき、頭に浮かぶのが「2000万円」という数字ではないでしょうか。この「老後2000万円問題」は、2019年に金融庁の報告書がきっかけで社会的な注目を集めました。しかし、この数字は本当に今も妥当なのでしょうか?
結論から言うと、「老後2000万円」という数字は、もはや絶対的な指標ではありません。なぜなら、この金額は特定のモデルケースに基づいて算出されたものであり、すべての人の老後に当てはまるわけではないからです。
「老後2000万円問題」とは何だったのか?
まず、この問題の前提を正しく理解することが重要です。金融庁の報告書で示されたのは、「高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)が、年金などの収入だけでは毎月約5.5万円の赤字になり、30年間生きると仮定すると約2000万円の金融資産の取り崩しが必要になる」という試算でした。
計算式:約5.5万円(毎月の赤字) × 12カ月 × 30年 = 1980万円
この試算は、あくまで当時の平均的な高齢者夫婦の家計をモデルにしたものです。しかし、この「2000万円」という数字だけが独り歩きし、「誰でも老後に2000万円の貯蓄が必要だ」という誤った認識が広まってしまいました。
なぜ「2000万円も必要ない」といわれるのか?
この試算がおかしい、あるいは「もう古い」といわれる理由はいくつかあります。
- ライフスタイルが多様化しているから
持ち家か賃貸か、都市部か地方か、趣味や交際費にどれくらいお金をかけるかなど、人によって生活スタイルは全く異なります。毎月5.5万円も赤字にならない世帯もあれば、もっと多くの不足額が出る世帯もあるでしょう。必要な金額は、一人ひとりのライフプランによって大きく変わるのです。 - 収入の状況が異なるから
上記のモデルは「無職世帯」を前提としていますが、現在では65歳以降も働き続ける人が増えています。定年後も収入があれば、年金収入だけを前提とした計算は成り立ちません。また、受け取れる年金額も、現役時代の働き方(厚生年金か国民年金か)や加入期間によって個人差が非常に大きいのが実情です。 - 資産状況が考慮されていないから
この計算には、退職金や個人年金保険、その他の金融資産などが考慮されていません。すでに保有している資産があれば、新たに準備すべき金額は当然少なくなります。
つまり、「老後2000万円問題」は、あくまで「こういうモデルケースだと、これくらい不足する可能性がある」という一つの警鐘であり、すべての人に当てはまる絶対的な目標金額ではないのです。だからといって「老後資金はまったく必要ない」ということにはなりませんが、「2000万円という数字に過度に怯える必要はない」ということは、まず理解しておきましょう。
老後資金はゼロでも大丈夫?必要ないといわれる5つの理由
「老後資金は必要ない」と主張する人たちがいます。貯金がなくて不安な方にとっては、少し希望が持てる言葉かもしれません。では、なぜ彼らは「大丈夫」だと言うのでしょうか。その論理を5つのポイントから見ていきましょう。
(※ここでは、あくまで「大丈夫」という意見の根拠を紹介するものであり、これらの理由だけで本当に安心できるかを保証するものではありません。)
理由1:贅沢しなければ年金だけで生活できる
「老後資金は必要ない」という意見の最大の根拠は、「公的年金」の存在です。現役時代にきちんと保険料を納めていれば、原則65歳から生涯にわたって年金を受け取ることができます。
総務省統計局の「家計調査報告(家計収支編)2023年(令和5年)平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の実収入(主に社会保障給付)は月額244,550円、消費支出は250,948円となっています。
このデータを見ると、毎月の赤字は約6,398円です。年間で約7.7万円の赤字となり、30年間で計算すると約230万円の不足となります。2000万円に比べれば、はるかに少ない金額です。
また、65歳以上の単身無職世帯の場合、実収入は129,298円、消費支出は143,139円で、毎月の赤字は約13,841円です。
これらのデータから、「平均的な支出の範囲内で、少し切り詰めて生活すれば、年金収入だけでもなんとか暮らしていける」という考え方が生まれます。派手な旅行や高価な買い物といった贅沢を望まないのであれば、貯蓄がなくても生活は破綻しない、という論理です。
理由2:医療費や介護費用には社会保障がある
老後の大きな不安要素である医療費や介護費用。しかし、日本には手厚い社会保障制度があります。
・高額療養費制度
これは、1カ月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の上限額を超えた分が払い戻される制度です。所得や年齢によって上限額は異なりますが、例えば70歳以上で住民税課税所得が28万円〜145万円未満の方の場合、外来での上限額は18,000円(年間上限144,000円)です。これにより、急な病気や手術で高額な医療費が発生しても、自己負担は青天井にはなりません。
・介護保険制度
40歳以上の人が加入し、介護が必要になった場合にサービスを受けられる制度です。自己負担は原則1割(所得に応じて2〜3割)で、こちらも高額介護サービス費制度により月々の負担額には上限が設けられています。
これらの社会保障制度があるため、「病気や介護で貯金がすべてなくなる」という最悪の事態は避けられる可能性が高い、というのも「老後資金は必要ない」と考える理由の一つです。
理由3:定年後も仕事はできる
「定年=リタイア」という時代は終わりつつあります。高年齢者雇用安定法の改正により、企業には70歳までの就業機会を確保する努力義務が課せられました。
多くの企業で65歳までの継続雇用制度が導入されており、元気で働く意欲があれば、定年後も収入を得続けることが可能です。パートやアルバイト、シルバー人材センターの活用、あるいは経験を活かして起業するなど、働き方の選択肢も多様化しています。
少しでも収入があれば、年金の不足分を補ったり、生活にゆとりを持たせたりすることができます。年金受給開始を繰り下げて受給額を増やすという選択も可能になります。「働けるうちは働く」という前提に立てば、まとまった老後資金を事前に準備する必要性は薄れる、という考え方です。
理由4:年齢が上がれば出費も減る
一般的に、ライフステージが進むにつれて支出は減少する傾向にあります。
例えば、
- 教育費: 子どもが独立すれば、学費や仕送りなどの大きな負担がなくなります。
- 住宅ローン: 持ち家の場合、定年までに住宅ローンを完済していれば、住居費の負担は固定資産税やメンテナンス費用のみになります。
- 交際費や被服費: 現役時代に比べて人付き合いが減ったり、スーツなどを購入する必要がなくなったりして、支出が減るケースも多いでしょう。
また、年齢を重ねるとともに活動量が減り、食費や交通費、レジャー費などが自然と少なくなることも考えられます。このような支出の自然減を見越して、「現役時代と同じだけのお金は必要ない」と考える人もいます。
理由5:退職金が受け取れる
会社員や公務員の場合、退職時にまとまった退職金を受け取れることがあります。厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)の定年退職者の平均退職給付額は1,896万円です。
これだけの金額が手に入れば、それがそのまま老後資金になります。住宅ローンの残債を完済したり、家のリフォーム費用に充てたりすることも可能です。退職金が見込める場合は、「わざわざ現役時代からコツコツ貯金しなくても、退職金で何とかなる」という考え方が出てくるのも不思議ではありません。
貯金がない人の老後のリアルな生活
ここまで「老後資金は必要ない」といわれる理由を見てきました。確かに、これらの理由には一理あります。しかし、それはあくまで特定の条件が揃った場合の話です。
もし本当に貯金ゼロで老後を迎えたら、私たちの人生はどのようなものになるのでしょうか。ここでは、より現実的な視点から、2つのケースを想定してそのリアルな生活をシミュレーションしてみましょう。
ケース1:持ち家かつ厚生年金の場合
夫のAさん(68歳)と妻のBさん(66歳)夫婦。Aさんはサラリーマンとして勤め上げ、60歳で定年退職。住宅ローン完済済みの持ち家に二人で暮らしています。夫婦が受け取る厚生年金は、合わせて月額約22万円。
【生活のシミュレーション】
- 収入: 年金収入 月220,000円
- 支出(一例):
- 食費:65,000円
- 水道光熱費:25,000円
- 通信費:10,000円
- 交通費:10,000円
- 保険・医療費:15,000円
- 趣味・娯楽費:20,000円
- 交際費(孫へのお小遣い含む):20,000円
- その他雑費:20,000円
- 固定資産税・家の修繕費積立など: 35,000円
- 合計支出:220,000円
一見すると、収入と支出がトントンで、なんとか生活できているように見えます。食費を切り詰め、趣味や旅行も近場で済ませるなど、贅沢をしなければ年金だけで生活することは不可能ではありません。
【潜むリスクとリアルな現実】
しかし、この生活には「ゆとり」が全くありません。
- 急な出費に対応できない:
ある日、給湯器が壊れたら?屋根の雨漏りを修理する必要が出たら?車が故障して買い替えが必要になったら?こうした数十万円単位の臨時出費が発生した場合、対応できる貯金がありません。カードローンなどに頼らざるを得ず、借金生活に陥る可能性があります。 - 病気や介護のリスク:
夫婦のどちらかが大きな病気になった場合、高額療養費制度があっても、差額ベッド代や先進医療費、通院の交通費など、保険適用外の費用がかさむことがあります。また、介護が必要になった場合、在宅介護でも住宅改修や福祉用具のレンタルなどで費用がかかります。施設への入居を考えたくても、一時金や月額費用を捻出できません。 - 人間関係の希薄化:
友人との旅行の誘いを断ったり、冠婚葬祭への出席をためらったりと、お金がないことが原因で人付き合いが減っていく可能性があります。社会的な孤立は、心身の健康にも悪影響を及ぼします。 - 配偶者との死別:
もし夫のAさんが先に亡くなった場合、妻のBさんが受け取れるのは自分の老齢基礎年金と、Aさんの老齢厚生年金の4分の3にあたる遺族厚生年金です。年金額は大幅に減少し、一人での生活が立ち行かなくなる可能性が非常に高くなります。
持ち家と厚生年金という、比較的恵まれた条件であっても、貯金がないだけで生活は常に綱渡り状態です。「死ぬしかない」とまでは思わなくても、お金の心配が尽きない、不安な毎日を送ることになるのです。
ケース2:賃貸かつ国民年金の場合
Cさん(70歳)は、若い頃から自営業を営んできました。結婚はせず、現在も都内のアパートで一人暮らし。収入は国民年金のみで、月額約6.6万円(令和6年度満額の場合)。
【生活のシミュレーション】
- 収入: 年金収入 月66,000円
- 支出(一例):
- 家賃:50,000円
- 水道光熱費:12,000円
- 通信費:3,000円
- 食費:?
- 医療費:?
- その他:?
この時点で、すでに収入と支出のバランスが崩壊していることが分かります。家賃と最低限のインフラ費だけで収入のほとんどが消えてしまい、食費や医療費、その他の生活必需品を買うお金がほとんど残りません。
【潜むリスクとリアルな現実】
このケースは、まさに「貧困」と隣り合わせの生活です。
- 切り詰められた生活:
食費は1日数百円に抑えなければならず、栄養バランスは偏りがちになります。エアコンの使用を我慢して熱中症のリスクに晒されたり、体調が悪くても医療費を気にして病院に行くのをためらったりすることになります。趣味や娯楽など、人生の彩りとなるものに使うお金は一切ありません。 - 住居の不安:
賃貸契約の更新や、高齢を理由とした入居拒否など、常に住まいの不安がつきまといます。家賃の安い物件を探して引っ越すにも、初期費用や引越し費用を捻出できません。 - 社会的孤立と絶望感:
経済的な困窮は、精神的にも人を追い詰めます。誰にも助けを求められず、社会から孤立していく中で、「なぜこんな人生になってしまったのか」「もう死ぬしかない」という絶望感に苛まれる可能性は十分にあります。生活保護という選択肢もありますが、申請への抵抗感や手続きの煩雑さから、利用に至らないケースも少なくありません。
もちろん、これは極端な例かもしれません。しかし、現役時代に国民年金保険料の未納期間があったり、十分な貯蓄がなかったりすれば、決して他人事ではないのです。これが、貯金なしで老後を迎えた場合の、あまりにも厳しい「リアル」なのです。
安心して生活したいなら老後資金の準備は必要!
「年金だけで生活できる」「社会保障がある」といった楽観的な見方と、「貯金がないと悲惨な生活が待っている」という厳しい現実。両方を見てきて、多くの方が「やはり、ある程度の準備は必要だ」と感じたのではないでしょうか。
なくてもなんとかなる、という考え方は、数々の「もしも」のリスクを無視した非常に危険な賭けです。安心して豊かな老後を送りたいと願うなら、老後資金の準備は絶対に必要だといえます。その理由を、改めて4つの観点から確認しましょう。
理由1:年金は減る可能性が高い
私たちが老後を迎える頃、今と同じ水準の年金を受け取れる保証はどこにもありません。少子高齢化が急速に進む日本では、年金制度を維持するために、今後さらなる制度改定が行われる可能性が非常に高いからです。
具体的には、
- 支給開始年齢の引き上げ(65歳→67歳、70歳など)
- 保険料の引き上げ
- 給付額の抑制(マクロ経済スライドの強化など)
などが考えられます。将来的に、年金の支給額が実質的に目減りしていくことは避けられないでしょう。そんな未来において、「年金だけで生活できる」という前提は、あまりにも楽観的すぎます。公的年金はあくまで老後の生活の「土台」と捉え、それだけでは不十分な部分を自分で補うという意識が不可欠です。
理由2:物価上昇(インフレ)に対応できない
近年、様々なものの値段が上がっていることを実感している方も多いでしょう。これを「インフレ(インフレーション)」といいます。例えば、現在100円で買えるパンが、20年後には150円になっているかもしれません。
もしあなたの資産が現金や預貯金だけだと、物価が上昇した分、お金の価値は実質的に目減りしてしまいます。年金額も物価に合わせて多少はスライドしますが、インフレのペースに追いつかない可能性もあります。
インフレが進むと、同じ金額の年金を受け取っていても、買えるモノやサービスの量が減ってしまい、生活はどんどん苦しくなります。将来の物価上昇に負けないよう、現金だけでなく、インフレに強い資産(株式や投資信託など)を組み合わせてお金を準備しておく視点も重要になります。
理由3:上限があっても医療費・介護費は負担になる
「高額療養費制度があるから安心」と考えるのは早計です。この制度は、あくまで「保険適用の医療費」が対象です。以下のような費用は対象外となり、全額自己負担となります。
- 差額ベッド代
- 先進医療にかかる費用
- 入院中の食事代の一部
- 保険適用外の歯科治療費や医薬品
- 通院のための交通費
また、介護についても、介護保険サービスでカバーできる範囲には限界があります。より手厚いサービスを求めたり、保険適用外のサービスを利用したりすれば、その分自己負担は増えていきます。特に、有料老人ホームなどへの入居を考える場合、数百万円の一時金や高額な月額費用が必要になることも珍しくありません。
健康寿命と平均寿命の間には約10年の差があるといわれています。この「誰かの助けが必要な期間」を安心して過ごすためには、やはりある程度の資金的な備えが欠かせないのです。
理由4:生活費以外の支出に対応できない
老後の生活は、日々の衣食住だけで成り立っているわけではありません。人生を豊かにするためには、「生活費」以外の様々な支出が発生します。
- 住宅関連費: 持ち家でも、外壁塗装や水回りのリフォームなど、10〜20年周期で大きなメンテナンス費用がかかります。
- 耐久消費財の買い替え: 冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ、車など、高額な家電や自動車はいずれ寿命を迎えます。
- 冠婚葬祭・交際費: 子どもや孫の結婚、お祝い、親戚や友人との付き合いなど、予期せぬ出費はつきものです。
- 趣味・レジャー費: 旅行に行ったり、新しい趣味を始めたり、友人と食事を楽しんだり。こうした「ゆとり」のためのお金がなければ、長い老後を心豊かに過ごすことは難しいでしょう。
これらの支出に全く対応できない生活は、精神的にも大きなストレスとなります。老後資金を準備するということは、こうした様々なライフイベントを楽しみ、自分らしい人生を最期まで謳歌するための「安心」と「自由」を準備することでもあるのです。
みんなどうしてる?老後資金の平均額
では、世の中の人々は実際にどれくらいの老後資金を準備しているのでしょうか。自分自身の立ち位置を客観的に知るために、公的なデータを見てみましょう。
金融広報中央委員会が毎年実施している「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、二人以上世帯の年代別の金融資産保有額(金融資産を保有していない世帯を含む)は以下のようになっています。
| 年代 | 平均値 | 中央値 |
| 50歳代 | 1,133万円 | 300万円 |
| 60歳代 | 1,664万円 | 600万円 |
※「平均値」は、一部の富裕層が金額を大きく引き上げるため、実感よりも高くなる傾向があります。より実態に近いのは、データを小さい順に並べたときに真ん中に来る値である「中央値」です。
このデータを見ると、50代の中央値は300万円、60代では600万円となっています。老後の目前に迫った年代でも、多くの人が十分な資産を築けているわけではない、という厳しい現実がうかがえます。
一方で、退職金などを含めると、この金額は大きく変わってくる可能性もあります。大切なのは、他人と比べて一喜一憂することではありません。このデータを参考に、自分たちの家計の現状を冷静に把握し、これからの計画を立てることです。
準備しておきたい老後資金の目安
「結局、いくら準備すれば安心なの?」という疑問が湧いてきますよね。必要な金額は個々のライフスタイルによって大きく異なりますが、一つの目安となる計算方法があります。
老後に必要な資金額 = (老後の毎月の支出 - 老後の毎月の収入) × 12カ月 × 老後年数 + 予備費
この式を使って、2つのライフスタイルを例にシミュレーションしてみましょう。
(※ここでは老後年数を65歳から95歳までの30年間と仮定します)
ケース1:最低限の生活を送る場合(夫婦)
- 毎月の支出: 25万円(現在の高齢者世帯の平均的な消費支出)
- 毎月の収入: 22万円(夫婦の厚生年金)
- 毎月の不足額: 3万円
必要な資金額 = 3万円 × 12カ月 × 30年 = 1,080万円
これに、医療・介護や住宅修繕などのための予備費として300〜500万円を加えると、約1,400〜1,600万円がひとつの目安となります。
ケース2:ゆとりのある生活を送る場合(夫婦)
生命保険文化センターの調査によると、「ゆとりある老後生活費」は平均で月額約37.9万円とされています。
- 毎月の支出: 38万円
- 毎月の収入: 22万円(夫婦の厚生年金)
- 毎月の不足額: 16万円
必要な資金額 = 16万円 × 12カ月 × 30年 = 5,760万円
これは非常に大きな金額ですが、退職金や65歳以降も働くことによる収入があれば、準備すべき金額は減っていきます。
重要なのは、まず自分たちが「どのような老後を送りたいか」を具体的にイメージし、それには月々どれくらいの費用がかかるのかを試算してみることです。その上で、自分たちの年金見込額を「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認し、どれくらいの不足額が生まれそうかを把握することが、老後資金準備の第一歩となります。
老後資金を準備する方法
「やっぱり老後資金は必要だ」と分かっても、具体的にどうすれば良いのか分からない、という方も多いでしょう。ここでは、今日から始められる老後資金の準備方法を簡潔にご紹介します。
- 家計の見直し(支出の最適化)
まず取り組むべきは、家計の現状把握と見直しです。家計簿アプリなどを活用して、毎月の収入と支出を「見える化」しましょう。特に、通信費や保険料、サブスクリプションサービスなどの「固定費」を見直すことは、効果が大きく継続しやすいのでおすすめです。支出を最適化し、毎月少しでも貯蓄や投資に回せるお金を生み出すことが基本です。 - iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用
iDeCoは、自分で掛金を拠出して運用し、60歳以降に年金または一時金で受け取る私的年金制度です。「掛金が全額所得控除」「運用益が非課税」「受け取る時も控除がある」という強力な税制優遇が最大の魅力。老後資金作りに特化した、非常に有利な制度です。 - NISA(少額投資非課税制度)の活用
NISAは、毎年の非課税投資枠内で購入した金融商品から得られる利益(配当金、分配金、譲渡益)が非課税になる制度です。2024年から新NISAが始まり、非課税保有限度額が大幅に拡大され、制度も恒久化されたことで、より使いやすくなりました。iDeCoと並行して活用することで、効率的に資産形成を進めることができます。 - 個人年金保険
民間の保険会社が提供する商品で、保険料を払い込み、契約時に定めた年齢から年金形式でお金を受け取ることができます。貯蓄性は投資信託などに劣る場合がありますが、「決まった額を強制的に貯められる」「将来受け取れる金額が確定している(定額年金の場合)」といったメリットがあります。 - 資産運用(長期・積立・分散)
iDeCoやNISAを活用して、投資信託などで資産運用を行うことも有効な手段です。大切なのは「長期・積立・分散」の3つの原則を守ること。- 長期: 短期的な値動きに一喜一憂せず、長い時間をかけて資産が育つのを待つ。
- 積立: 毎月決まった額を買い続けることで、購入価格を平準化させる(ドルコスト平均法)。
- 分散: 投資対象の国や資産(株式、債券など)を一つに集中させず、複数に分けることでリスクを低減する。
これらの方法を自分のライフプランやリスク許容度に合わせて組み合わせることが、賢い老後資金の準備につながります。
まとめ
「老後資金は必要ない」という言葉は、一見すると魅力的に聞こえるかもしれません。確かに、贅沢をせず、健康で、手厚い年金や退職金が見込めるなど、特定の条件が揃えば、貯金がなくても生活していくことは可能かもしれません。
しかし、私たちの人生には、病気や介護、家の修繕、物価の上昇など、予測できない様々なリスクが待ち受けています。そうした不測の事態に対応し、何よりお金の心配に心をすり減らすことなく、安心して自分らしい豊かな老後を送るためには、やはり計画的な資金準備が不可欠です。
老後2000万円という数字に怯える必要はありません。大切なのは、自分自身の理想の老後を思い描き、現状を把握し、今日からできる小さな一歩を踏み出すことです。
この記事が、あなたの老後に対する漠然とした不安を解消し、未来に向けた具体的な行動を起こすきっかけとなれば幸いです。