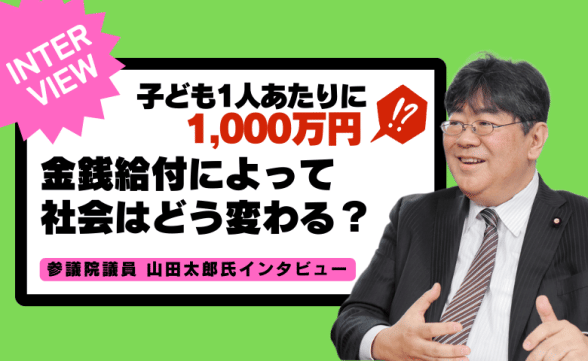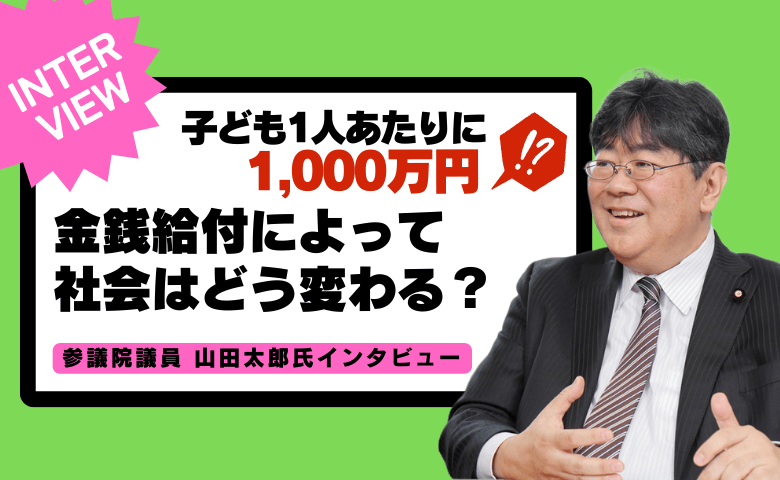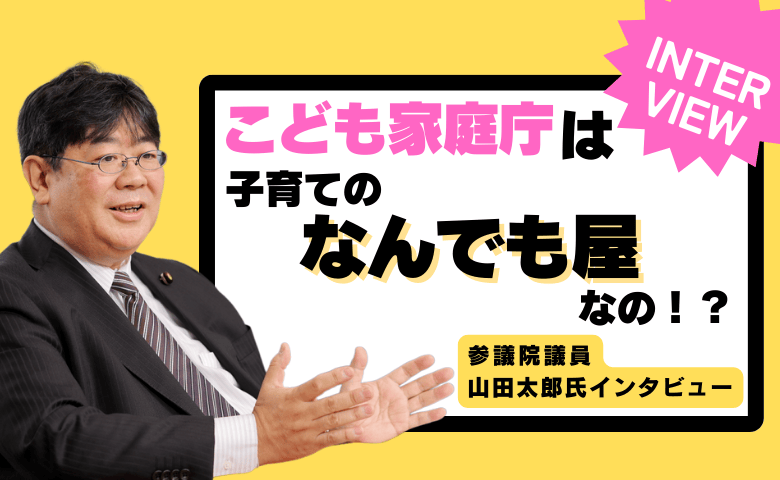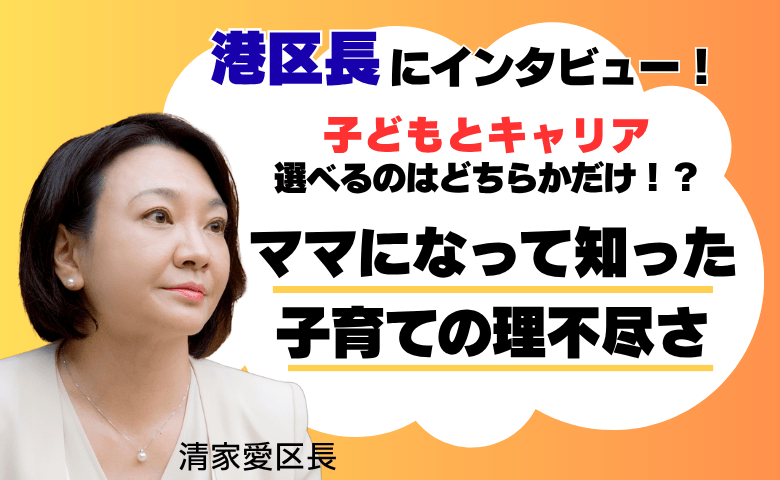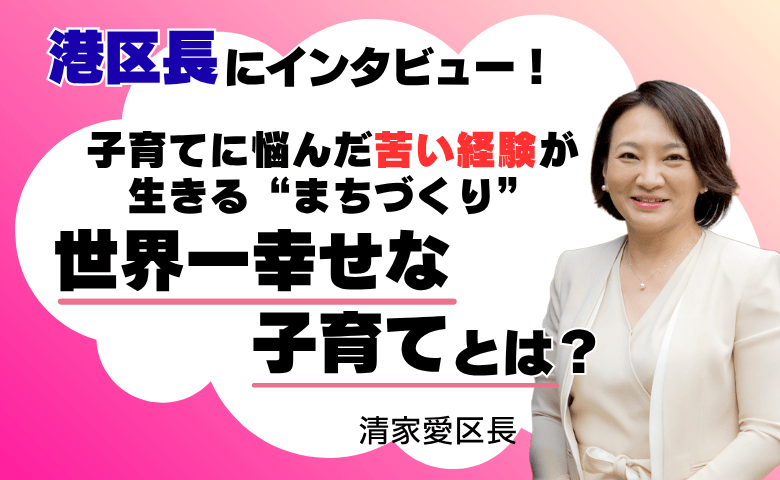野田氏も私たちと同じく、子育て真っ最中のママでいらっしゃいます。
日本の子育てがどのように移り変わってきたのか、これからどこに向かうのか。私たちの不安を解消すべく、政治の観点から、そして子どもを育てるママの観点から、たっぷりとお話を伺ってきました。
賛否両論あっていい。ようやくみんなが「子ども」の話をするようになった
―2023年にこども家庭庁が設立され「子育て政策」についてよく耳にするようになりました。日本の子育て政策は、どのように移り変わり、今どのような状況なのでしょうか?
―野田聖子氏(以下、野田さん):私が日本の子育てにきちんと策を講じないとダメだと声を挙げたのが、今から20年ほど前のことです。当時から子どもに関するあらゆる相談を、複数の窓口を訪ね回ることなく一箇所で受け付けられる、いわゆるワンストップ型の機関を作ることを推進してきました。
それがようやく目に見える形になったのが、2021年の自民党総裁選。私は候補者として「こどもまんなか社会」の公約を掲げました。子どものことをすべて受け止める機関を作るという公約だけで勝負をしたんです。残念ながら総裁には選ばれませんでしたが、新たに発足した岸田政権で、子ども政策担当大臣に任命され、念願だったこども家庭庁を発足させることができました。
正直なところ、それまでマスコミや党内の男性議員たちは、どこか子育て政策が自分ごと化しづらいところもあったと思うんです。私が議員になったころは、子どもに関することが国会やSNSなどで話題にのぼることは、ほとんどありませんでした。
子育ては個人個人がやればいいものだという風習で、少なくとも子育て施策が国にとっての重要事項だとは思っていなかったと思います。でもそれでは国が滅びると思って、私はこどもに関する省庁の設立を強く望んできた経緯があります。
何もしなかったからこそ、現在の少子化が起きている

―少子化対策については、どう思われていますか?
―野田さん:日本の少子化はおよそ50年ほど前から始まっていますが、何かが起きて少子化になったわけではありません。むしろ何もしなかったからこそ、現在のような少子化が起きている。ということは、今また何もしなければ、50年後はもっと違う未来が待っていると想像できますよね。今以上に人材が足りなくなり、仕事が成り立たなくなり、ものが売れなくなるでしょう。
これまで日本は大人を主役にした政治をおこなってきました。でもこれからは将来の担い手である子ども側から見て、たりない部分を補っていかなければならない。子どもたちの視点を取り入れ、たりない部分を補っていくために、子どもを主役にした政策を実行していく機関として、こども家庭庁は設立されました。まさに今、スタートを切ったところです。
―こども家庭庁に賛否両論あるようですが、それについてはどう思われていますか?
―野田さん:こども家庭庁を作ったことで6〜7兆円の予算が必要になり、その存在に賛否両論の議論が生まれています。「子どもを育てるのに、そんなにお金はいらないのではないか」という意見もあります。でも、タダで育った子なんていないですよね。1人の人間を育てるのには、それなりのお金が必要です。
今の日本は高齢者の割合が高く、おじいちゃんおばあちゃんにたくさんお金がいくようになっています。でも支える側の子どもたちには、社会的にお金がほとんど使われてこなかった現状がある。親の私費に頼って、子どもたちを育ててきたということです。
それを今後は「国がしっかり支え手となって、やっていこう」というのが、こども家庭庁の考えです。発足してからまだ数年しか経っていませんが、これからの子どもや親御さんの未来は過去より絶対に良くなる。その扉がすでに開いたと思っています。
SNSなどで「こども家庭庁はいらない!」という発言も見かけますが、たとえネガティブな内容であっても子育て支援や施策が注目され、話題になったり活発な議論が生まれたりすることのほうが大事だと思っています。
少子化対策と子育て政策では目的が違う。子どもを増やすには違いを理解することから
―少子化対策について、私たちができることはあるのでしょうか?
―野田さん:まずお伝えしておきたいのは、少子化対策と子育て政策は「子どもに関わること」という点では共通していますが、実は微妙に異なるということです。少子化対策は「子どもが生まれる前」の話で、子育て政策は「子どもが生まれてから」の話なんですね。
違う政策なのに、この2つを混同している議員も多いのが現状です。子どもが生まれてからの政策を立てて「少子化政策」とうたっている人たちもいますが、それは「子育て対策」なんです。まずはそれぞれの政策の違いと目的を理解しないことには子どもは増えないのではないかと思います。
たとえば少子化の原因は人口減少で、国全体の土台を揺るがすことにつながります。子どもを生む・生まない以前に、どうにかして国の人口を増やそうとするのが少子化対策です。子どもを生んで日本人を増やす方法もある一方で、たとえば諸外国から移民を受け入れて人口を増やす方法も少子化対策と言えるわけです。
―なぜ、日本は子どもが減り続けているのでしょう?

―野田さん:ひとつの要因として、結婚する男女が減っていることが挙げられると思います。日本には「結婚しないと子どもを産んではいけない」という雰囲気があると思うんです。授かり婚などと呼ばれる結婚の形が増えてはきましたが、まだまだ「結婚してから子どもは作るもの」という圧はあります。結婚する人が減っている状況だから、当然子どもの数は減っていきますよね。
日本の婚外子(※1)は2%弱ですが、アメリカでは30%強、ヨーロッパ諸国は50〜60%以上の子どもが婚外子です。このような現状を受け、まずは日本も「子どもを産むために結婚しなければならない」というハードルを下げる必要があると考えています。
※1:婚姻していない男女間に生まれた子どものこと。非嫡出子とも呼ばれる。
親と苗字が違うと子どもがかわいそう? まずは結婚へのハードルを下げる
―そのハードルを下げる条件のひとつに「選択的夫婦別姓」があるのではないかと
―野田さん:現在の日本では、結婚したらどちらかが姓を変えなければいけません。特に女性側が姓を変えるものだという風潮がまだまだあると思います。でも女性が自分の苗字のまま結婚できるという選択肢があってもいいと思うんですよ。それにより結婚というハードルが下がるカップルが一定数いるんです。
選択的夫婦別姓に関して「親と子どもの苗字が違うのはかわいそう」といった意見もありますが、子どもがかわいそうかどうかという議論以前に、当の子どもが生まれていないんです。少子化対策においては、結婚する人が減っている、そして子どもが生まれていない。まずはそのことを心配しなければいけないんです。
個人的には、選択的夫婦別姓は子どもを産みたくなる環境整備のひとつにすぎないと考えています。
選択的夫婦別姓は賛否両論が分かれていますが、賛否があるのはいいことだと思っています。毎日のように子どものことや子育て施策が話題にのぼることはとても大事なことです。
以前は、子どものことはどこかオブラートに包まれていて、公の場で語る話ではないという雰囲気がありました。そういう意味でも、こども家庭庁の設立や、夫婦別姓について、連日のようにSNSなどで議論されていることは大きな一歩になっていると思います。
―野田さんの周りの政治家にも、何か変化がありましたか?
―野田さん:20年ほど前、私が「人口が減少すると日本の元気も失われていくから、子育て施策をやろう」と言っても、男性議員からは「女性議員はその程度だな」という反応をされることが多々ありました。でも今は男性議員もこぞって、少子化対策をやろう、子どもの政策を充実させようと言い始めている。20年間、子育て施策をやろうと吠え続けてきてよかったなと思います。
子どもを産むって幸せなことだと思えるママを増やしたい
―今後特に力を入れていきたいことは?
―野田さん:子どもを産むことが喜びにつながる社会の雰囲気を作っていきたいですね。これまで社会が子育てに無関心であり続けてきた結果、「子育ては大変」「子育てはお金がかかる」などの印象が広まってしまった側面があると思います。政治において、子どもに必要な予算を捻出するためにやったことが、結果的にネガティブキャンペーンになってしまった。その現状をひっくり返したいと思っています。
♢ ♢ ♢ ♢
野田さんが政治家人生をかけて、ようやく実現に至った「こどもまんなか社会」のシステム。具体的な取り組みは始まったばかりで、すぐに結果が出ることばかりではないかもしれません。これから大人になる子どもたちが「いい世の中になったね」と言い合えるように。今私たちにできることを考えながら、今後の政府の取り組みにも注目していきたいと思います。
次回は、野田さん自身の子育て経験についてお話をうかがっていきます。医療的なケアが必要な、いわゆる医療的ケア児の息子さんを育ててこられた野田さん。そのご経験から、医療的ケア児の現状と法案についてお話をしていただく予定です。