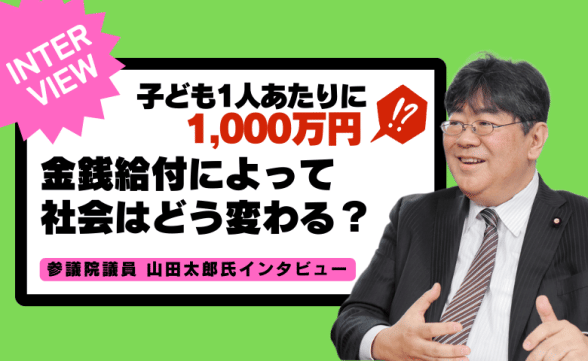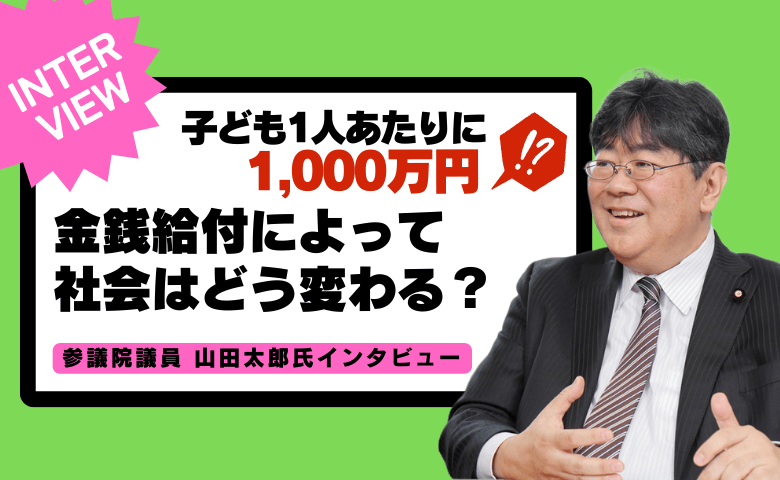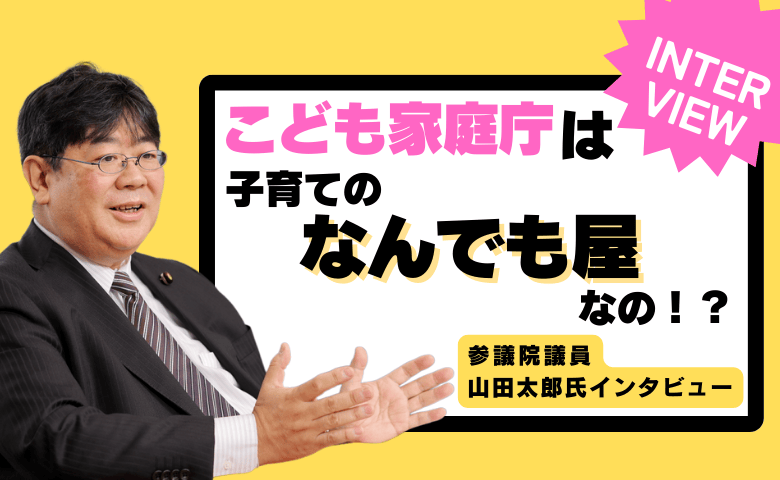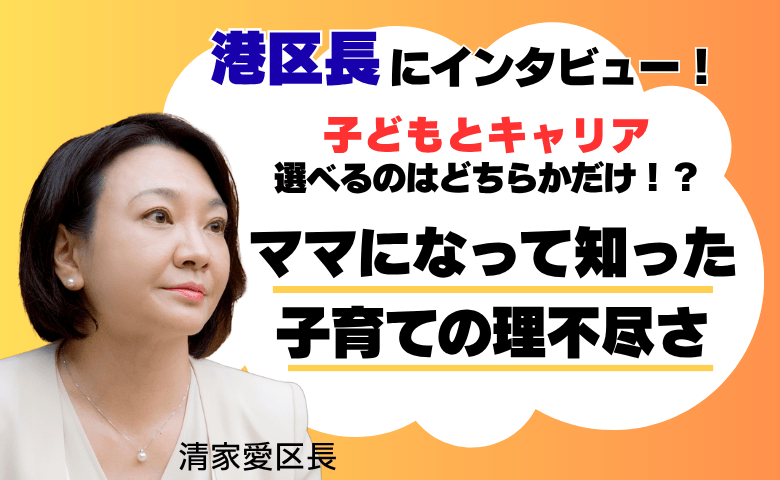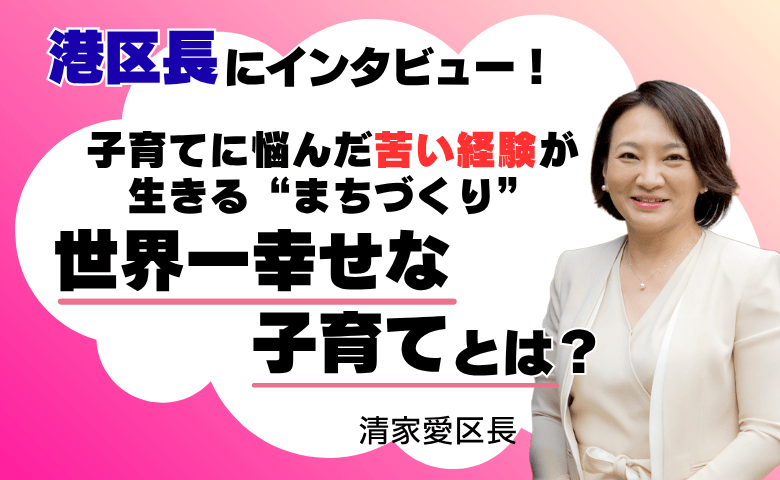息子さんが法律づくりに貢献。福祉と医療が手を繋ぐことで生きられる命
―野田さんご自身、医療的ケア児の息子さんの子育てをされていますが、日本の医療的ケア児支援の現状をどのように感じていらっしゃいますか? また医療的ケア児の受け入れ体制を整えるために、どのような理解や環境整備が必要なのでしょうか?
―野田聖子氏(以下、野田さん):これまで「医療的ケア児」と呼ばれる子どもたちは、社会的な認知が十分ではありませんでした。一般的に「障害児」とは、身体的または知的な障害を持つ子どもを指します。
一方、医療的ケア児は、医学の進歩を背景として、NICUなどに長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童です。つまり医療的ケア児は、福祉と医療の両方の支援が常に必要であり、従来の障害児支援の枠組みだけでは十分なサポートを受けられない状況にあります。
これまで日本では、福祉分野と医療分野はあまり関わりを持ってきませんでした。でも、うちの息子のような医療的ケア児は、障害者枠に入れておいても生きていけません。従来の障害者支援の枠組みだけでは必要なサポートを受けることが難しいからです。
そこで同じ医療ケア児を持つ仲間たちと協力し、医療的ケア児とその家族を支える法律を作ることにしました。
―息子さんの存在がダイレクトに新しい法律へと繋がったのですね
―野田さん:今でこそ、呼吸器をつけたり点滴の管をつけていたりしている子どもたちを「医療的ケア児」と呼ぶのだという理解が進んできましたが、当時は国会議員でさえ、医療的ケア児のことをよく知らないという現状がありました。
それで法律を作る際に、医療的ケア児がどんな状態の子どもたちを指すのかわからないから「ビジュアル画像がほしい」という話になったことがあって。でも人権やプライバシーの問題があるから、なかなか実際の医療的ケア児の画像が手に入らないでしょ。そこでうちの息子にひと肌脱いでもらったんです。
私も医療的ケア児を正しく知ってもらうためには、言葉で説明しても伝わらないと思っていたところがあったので。息子のために、いちばんかわいいパンツを探して履かせてね。体の喉(気管)に穴が開いていて、人工呼吸器や点滴の管が入っているとわかるような写真を撮って提出しました。
ところが「これは不適切な画像じゃないか」と指摘されて、理事会が紛糾したらしいんです。せっかくわが子の写真を提供したのに、その話を聞いてショックを受けたこともありましたね。
―まさに息子さんがひと肌脱いだのに、思いもよらない反応があったんですね
―野田さん:そうやって息子が公式な医療的ケア児のモデル第1号になったんです。ただ当時は税金の無駄使いをしているなどの心無い言葉をかけられることもありました。でもうちの子はこうやって法律を作ることに貢献してくれている現状もある。
だから「あなたは日本の社会を変えることに役に立っているよ」って話して聞かせていました。息子本人にはわからないかもしれませんけどね。
政治の世界より、子育てのほうがよっぽど理不尽なことばかりだった
―ご自身がママになったことで、心境の変化がありましたか?
―野田さん:政治の世界はなかなかストレスフルで「この人、どうしてこんなことを言うのだろう」ということも日常茶飯事です。でもいざ子どもを産んでみると、息子との生活のほうがよっぽど理不尽なことが多いと気づきました。
14歳になった今は、成長とともに悪い言葉を使うようになってきていて、ときには私のことを「ばばあ」呼ばわりするんですよ。それに対して、仕事では、なんだかんだちやほやされているなあと。あれだけ理不尽だと思っていたのに、息子が生まれてからは見え方が変わりましたね。
世間では「子育ては大変だ」というネガティブな印象ばかりが広がっています。でも実際に子育てをしている身からすると、そんなこともないんじゃないかと思うのです。もちろん、うちの息子は障害を持っていることもあって、一般的な子育て以上に手間がかかるところはあります。
そんななかでも、子育てを通して感じられる日々の幸せがたくさんあるんです。そんな苦悩と幸せの毎日が私たち親を育ててくれていると感じますね。
「無理して育てなくても」のドクターの言葉にくだした決断は……

―息子さんの障害がわかったとき、どういう状況だったのでしょうか? ご夫婦として、お子さんの障害をどう受け入れてこられましたか?
―野田さん:息子がおなかにいるときに、健診のエコーで「おそらく赤ちゃんに異常があります。浮腫が出ていて、障害の可能性がある」と言われました。大きく肝臓が飛び出ていて、心臓の位置がちょっとおかしくて……。おかしくなかったのは手足と頭くらいだったと思います。
障害児になるかどうか以前に、生きていられるかどうかという状態で。母体に負担がかかる可能性も否めないから、次の健診までに今後のことをご夫婦で話し合ってきてください、と。
でも私は次の健診まで、夫に子どもの状況を一切話さなかったんです。だって話し合ったら、夫は無理だって言うに決まっているじゃないですか。だから夫には相談をせずに、次の健診の際にお医者さんに「産みます」と返事をしました。
―息子さんに障害があると知ったときのご主人の反応は?
―野田さん:夫は政治と無縁の人で、障害に関しての知識もないひとりの男性です。お医者さんから「お子さんに障害があります」と聞いたときは真っ青になって、「僕には無理だ」と言っていました。障害児の親を経験してきた人が周りにいなかったので、当然の反応ですよね。
一般的な子育てであっても、周りに子育てをしてきた知り合いがいなかったら、自分にできるのか不安になると思います。それでも今は、夫が主になって息子を育ててくれています。
♢ ♢ ♢ ♢ ♢
障害のある息子さんの誕生をきっかけに、医療的ケア児とそのご家族を支える法律づくりに乗り出した野田さん。前例にないところに法律を作る道のりは、たやすいものではなかったと思います。しかし野田さんと息子さんとでタッグを組んで取り組んだ結果、たくさんの親子を支える法律が整備されました。
先輩ママの勇気ある行動のおかげで、次世代の親子が安心して生きられる未来が広がる。そう思うと、私たち一人ひとりにも何かできることがあるのかもしれないという気持ちにさせられます。
次回の記事では、息子さんを授かるために不妊治療を経験されたご経験をもとに、日本の不妊治療について思うことについてお話をうかがいます。