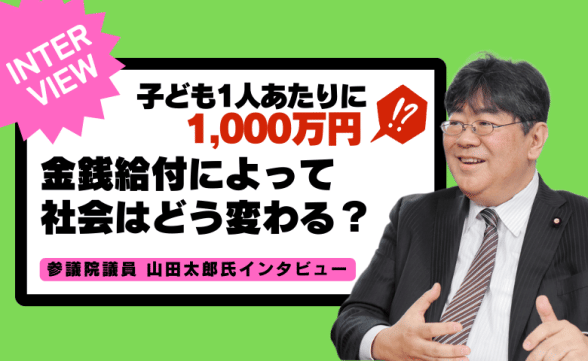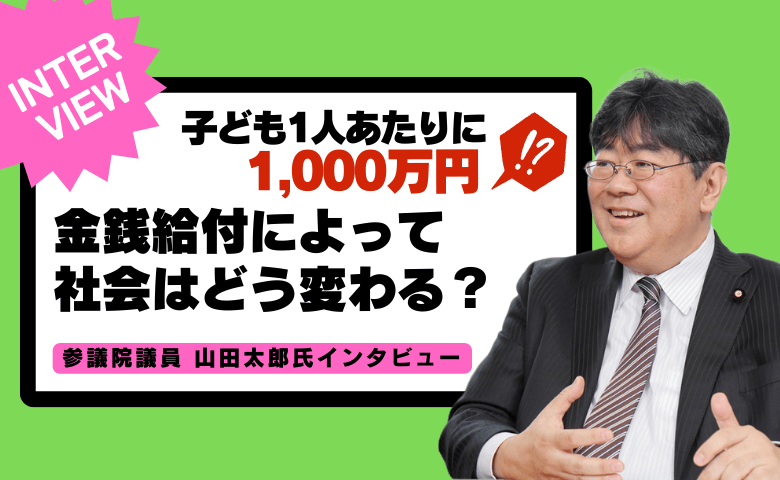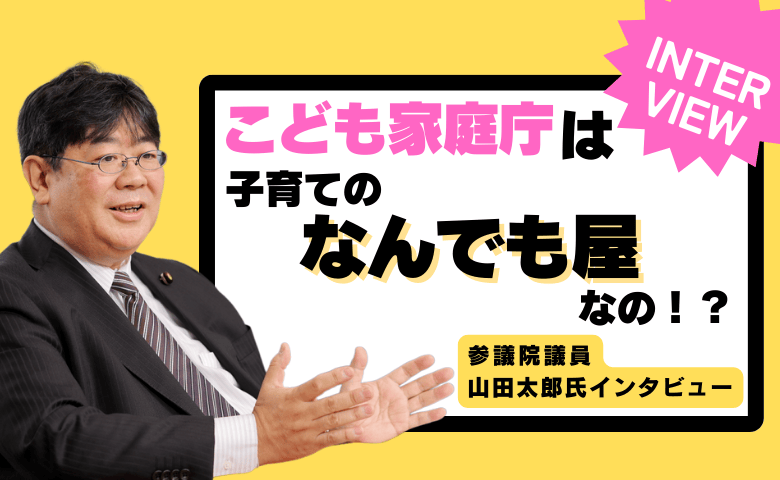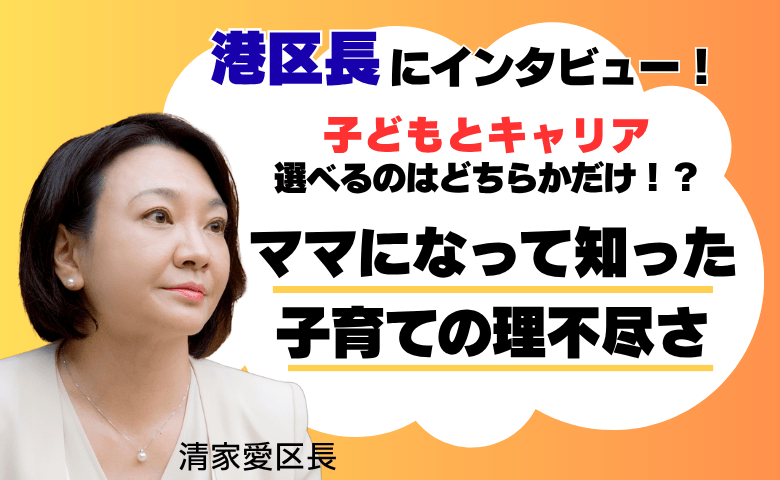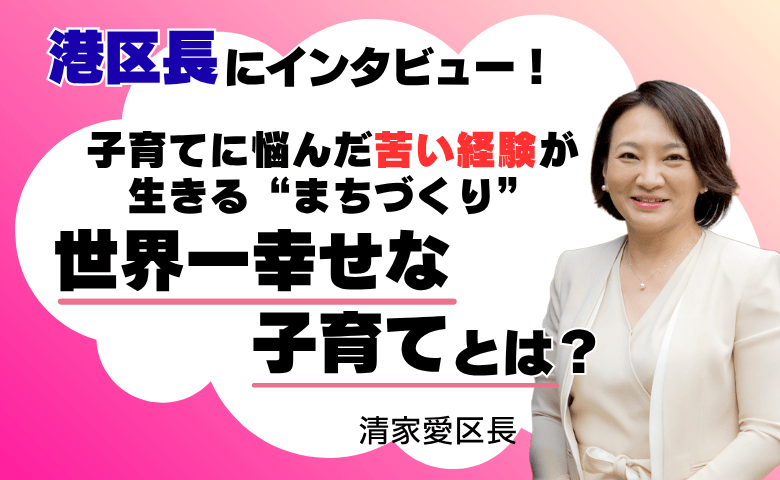不妊治療を経験して「努力しても報われることばかりじゃない」と気づいた
―ご自身の不妊治療の経験を通して、今、妊娠・出産・子育てに迷う女性たちに知っておいてほしいことや、やっておいた方が良いと思われることは何ですか?
―野田聖子氏(以下、野田さん):女性の体には個人差がありますが、たとえ閉経しても、私のように第三者の卵子をもらうことでママになれる人もいます。私の場合は50歳で出産しましたが、お世話になったエージェントの話によれば、70歳で子どもを産んだ女性もいるのだそうです。
私が自分の不妊治療の経験をカミングアウトするのは、不妊治療が恥ずかしいことではないと知ってほしいからです。一方で不妊治療はエンドレスになりやすい側面もあるので、やめどきを考えることも大事。
「努力すれば報われる」と私たちは学校で教わってきました。しかし、不妊治療を経験してこの言葉が嘘だったと思い知らされました。卵胞を育てるためのホルモン治療は、連日の注射の痛みだけでなく精神的なつらさも伴います。個人的には不妊治療は一番しんどい治療なんじゃないかと考えていたくらいです。
それなのにこれほどのつらさを乗り越えても容赦なく生理が訪れ、すべてがリセットされてしまうのです。つまり、努力しても必ずしも結果に結びつかない、それが不妊治療なんです。
今は若い男女が将来のライフプランを考えて日々の生活や健康と向き合う「プレコンセプションケア」が厚生労働省によって推進されています。パパやママ自身の健康はもちろん、次世代を担う子どもの健康にもつながるとして注目されているヘルスケアの考え方です。
今すぐ結婚や妊娠を考えていなくても、5年後10年後のことを見据えて、今から日々の生活や健康と向き合う習慣を作っていくことは大切だと思います。
自然に妊娠できない私は、完璧ではない…?

―不妊治療をするなかで、実際の治療以外でつらかったことは何ですか?
―野田さん:私の時代は、まだ不妊治療が「隠しごと」のような扱いでした。自然に妊娠できない私は完璧じゃないのだから、それを人に言う必要はないという風潮もあって。
政治の世界は年配の男性が多いこともあって職場の人に「子どもができないから不妊治療に行っています」なんて言える環境ではありませんでした。妊娠できないなんて言おうものなら「やり方を間違ってるんじゃないか」という人がいるくらい、ひどい環境だったんです。あのころがメンタル的にはいちばんきつかったですね。
不妊治療で生まれた子どもの親は誰なのか。必須だった法整備
―妊娠出産について、野田さんがこれまでやってこられたこと、また今後叶えたい政策はありますか?
―野田さん:自分の不妊治療の経験を経て、不妊治療を合法化する取り組みをしてきました。私が不妊治療をしていた当初、不妊治療はまだ法律に明記されてない治療法だったんです。でも不妊は誰にでも起きる可能性があって、それに対しての治療を受けることは合法であるとしたのです。
そして次のステップとして取り組んだのが、不妊治療の末に生まれた子どもの親権をどうするのかという問題でした。精子や卵子を提供してもらったとき「親が誰なのか」という部分が曖昧になっていたので、「民法の特例」というものを作りました。
それにより、精子を提供して生まれた子どもの場合は精子をもらった人が父親、卵子提供者ではなく卵子をもらって分娩をした人が母親と、法律で親子関係が明確に定められました。 親子関係を明確にしないと、財産相続や子の扶養義務など、さまざまな法的問題が発生するんです。
精子や卵子の提供を日本のスタンダードにすることが目標

―代理母については、どうお考えですか?
ー野田さん:代理母(依頼者の不妊などが理由で、依頼者の代わりに受精卵や卵子の提供を受け、妊娠し出産に至る女性)については現時点での日本の法律においては難しいと思います。ただ法律は常に変わっていかなくてはいけないものです。まずは精子や卵子を提供してもらうことがもっと普及し、この国のスタンダードになることを目標としています。
それが普通になってきたら、たとえば元々子宮のない方や、いろいろな子宮の病気を抱えている方がママになれる流れも生まれてくるかもしれません。精子提供や卵子提供の次の段階が、代理母にまつわる法整備になってくると思っています。そのための共通理解が必要で、今そこに取り組んでいるところです。
あとは実際に不妊治療をやってみて、やっぱり金銭的に高かったんですよね。若い人が気軽に治療を受けられる金額ではありませんでした。そこで不妊治療を保険適用にしました。当初はそんな不妊治療に保険適用なんてと叩かれたりもしましたね。実際、子どもができるかどうかが断言できない治療ではあります。でも自費だったらとてもじゃないけど不妊治療なんてやってられない。だから保険適用はマストだったと思います。
♢ ♢ ♢ ♢ ♢
日本における不妊治療の土台を築いてこられた野田さん。保険適用となったことで、チャレンジしてみようという女性や夫婦が増えたことは間違いありません。大切な命のことだからこそ、暗闇でおこなわれない世の中に。子どもを授かりたいママたちの望みを叶えるために、法律の整備が必要なのだということが深く理解できたインタビューでした。
次回は、仕事と子育てを両立されている野田さんに、女性の仕事と働く環境についてお話をうかがっていきます。