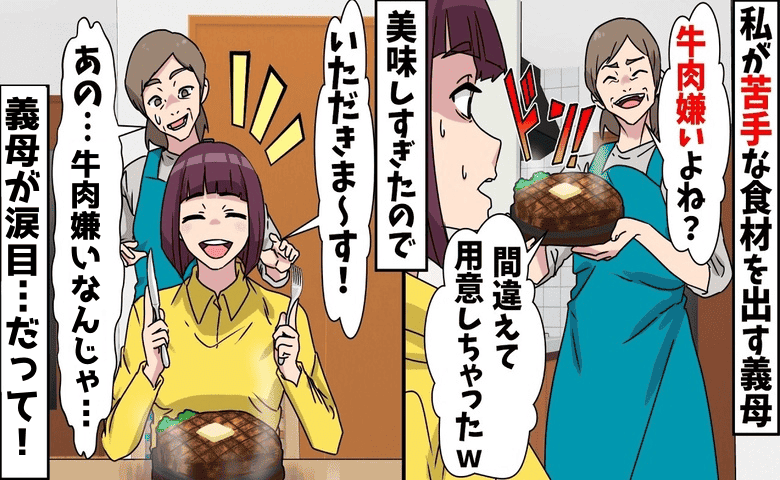小さいころ、苦しいときや泣きたい夜、そばにいてくれたのは姉だけでした。
見知らぬ中年夫婦の視線
ある日の仕事の帰り道、最寄り駅を出たあたりで、見知らぬ中年夫婦とすれ違いました。
写真を手に持ち、私の顔をちらちらと見て、こそこそ話している様子。なんだか気味が悪くて、急いで帰宅しました。
その夜、うちに寄った姉にこの話をしてみると、ぽつりとこう言いました。
「たぶん、その人たち、私たちの“親”じゃないかな」
「前に、施設の職員さんが言ってた。両親が私たちのことを探してるって」
まさか、今になって何の用があるのか。
私は用心して戸締まりを確認し、その夜は少し緊張しながら眠りにつきました。
玄関に立っていたのは
数日後の週末、家のチャイムが鳴りました。インターホンをのぞくと、そこに映っていたのは、あの中年夫婦。どうやらあの日、家を知られてしまったようです。
「久しぶり~!(名前)ちゃんよね? 私、お母さんよ。おなかを痛めて産んだわが子に、ずっと会いたかったのよ〜!」
満面の笑み。でも私は、まったくその顔に見覚えがありません。懐かしい気持ちはまったくありませんでした。記憶にあるのは、いつも手を引いてくれた姉の姿だけです。
両親のまさかの要望
「今さら何の用ですか?」
私がそう告げると、相手の表情が一変しました。
「私たち、お金がないのよ! ここで同居するから面倒みなさい」
「産んでもらった恩があるだろ? これからは恩返してくれ」
いきなり見知らぬ中年夫婦が現れて同居しろだなんて、到底理解できません。本当に両親だとしても、受け入れるつもりはありませんでした。
「恩なんてありません。同居はお断りします。私の家族は姉と夫、息子だけですから」
「これ以上騒ぐなら、警察を呼びます」
スマホを手に取ると、ふたりは逃げるように去っていきました。
姉の忠告、その後
その夜、姉に話すと苦笑いしながら言いました。
「昔、あの人たちに『もう絶対に近づくな』、『次、近づいたら法的に対応する』って言ったの」
姉はずっと、影で私を守ってくれていたのです。それ以来、両親の訪問はありません。
血が繋がっていたとしても、大切にされた記憶もなく、自分たちの都合がいいように使おうとしてくる「親」は、今の私たち姉妹にとって必要のない存在です。これからも家族と姉と平穏に過ごしていけたらと、願っています。
※本記事は、実際の体験談をもとに作成しています。取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。