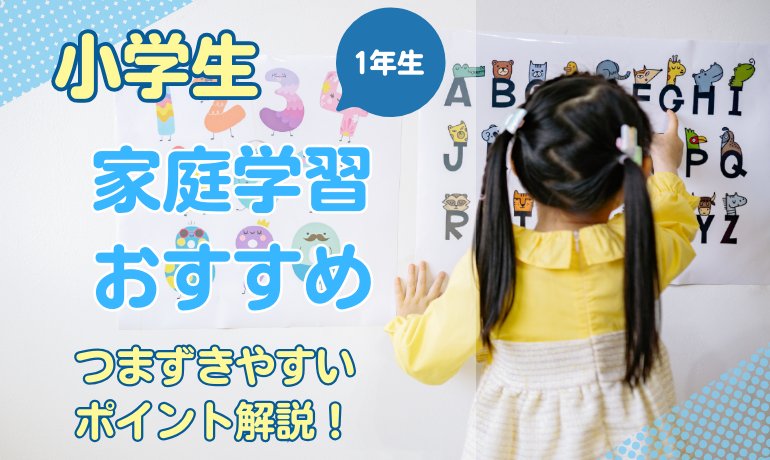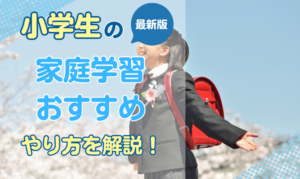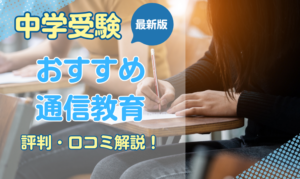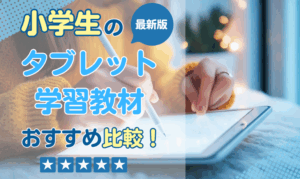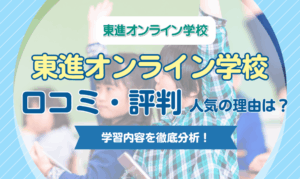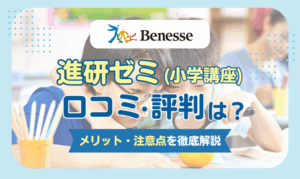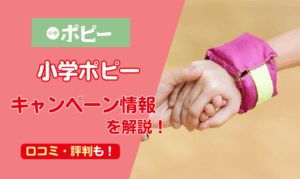ベビーカレンダー教育マガジン編集部
月間1,000万人以上が利用する医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報サイト「ベビーカレンダー」の妊娠・子育てお役立ちアイテムご紹介するベビーカレンダーマガジンです。
厳選した教育サービスをアンケート結果や編集部が定義した評価基準を元にしたランキングや口コミなどでご紹介しています。
小学1年生のうちから家庭学習を始めたいと考えていても、どのように取り組めばよいか悩んでいる保護者は多いのではないでしょうか。家庭学習には、子どもが学習習慣を身に付けたり自信を付けたりするなどのメリットがあります。
家庭学習の方法には紙学習やタブレット学習などがあるほか、家庭学習に活用できる教材もさまざまです。子どもに合った家庭学習を取り入れたいと思っていても、具体的にどの方法にするか決められないという方もいるでしょう。
本記事では小学1年生から家庭学習に取り組むメリットやつまづきやすいポイント、おすすめの家庭学習方法を解説します。おすすめの学習教材も紹介するため、子どもの家庭学習について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
小学1年生の学習内容
文部科学省によると、小学校1年生の各教科の授業時間数は以下のとおりです。
- 国語:306時間
- 算数:136時間
- 生活:102時間
- 音楽:68時間
- 図画工作:68時間
- 体育:102時間
- 道徳:34時間
- 特別活動:34時間
上記のとおり、最も時間数が多いのは国語です。国語で学ぶ文字の読み書きなどは、文章を読んだり、自分の考えを言葉にして表現するために欠かせません。日常生活においても必要な知識を学ぶ国語に重点的に取り組んでいることが分かります。
また、国語の次に時間数が多いのが算数です。算数も日常生活のなかで必要な知識である数の大小や足し算・引き算などの計算を学ぶ教科です。
小学1年生で国語と算数に取り組むことで、2年生以降の学習に必要な知識や読解力などが身につき、スムーズに学習できるようになります。
小学1年生から家庭学習を取り組むメリット
小学1年生から家庭学習に取り組むメリットには、主に以下が挙げられます。
- 学習習慣が身に付く
- 子どもの好奇心につながる
- 子どもの自信が付く
それぞれどのようなメリットなのか解説します。
学習習慣が身に付く
小学1年生から家庭学習をすることで、子どもに学習習慣を身に付けられます。
小学校に入学すれば、小学校、中学校、高校……と、これから勉強を続けていかなければなりません。そのなかで、学習習慣が身についていないと学校の勉強についていけず、勉強が嫌いになる可能性があります。
早い段階で学習習慣を身に付けると、学年が上がってからも自主的に勉強に取り組めるようになります。自ら学ぶ姿勢を持つことは、学校の勉強だけではなく、大人になってからも必要です。
小学1年生の場合はまだ勉強への苦手意識が少ないことが多く、家庭学習を身に付けやすい時期です。小学校1年生のうちから家庭学習に取り組み、学習習慣を身に付けることで、今後の勉強にも前向きに取り組めるようになるでしょう。
子どもの好奇心につながる
子どもの好奇心につながることも、家庭学習に取り組むメリットの一つです。家庭学習でさまざまな学びを得ることで、子どもの好奇心を刺激できます。
好奇心を持つことは、さまざまな事柄を自ら学ぶために欠かせない要素です。学校での勉強にはあまり興味がなく積極的に取り組めなくても、自分の興味関心があることであれば前向きに取り組める可能性があります。勉強とゲームを組み合わせるなど、子どもが関心を持っているものと勉強を組み合わせることで、子どもの好奇心を刺激できます。
家庭学習ではさまざまな勉強方法を取り入れやすいため、子どもの好奇心を刺激し育みやすいでしょう。
子どもの自信が付く
家庭学習で学力が身に付くことで、子どもが自信を付けることにもつながります。
家庭学習で学校で習った内容を復習することで、授業の内容が定着し、理解度を上げられます。授業の内容がしっかりと理解できていれば、授業が進んでも定着している知識を活用して理解できるようになります。
「授業内容を理解できる」という体験を繰り返すことで、子どもは自分に自信が持てるようになるでしょう。自信が付けば勉強に対して前向きに取り組めるようになり、さらに学力向上につながる、という良いサイクルにつながります。
小学1年生がつまずきやすいポイント
小学1年生がつまずきやすいポイントは、教科によって異なります。ここでは、以下2教科でつまずきやすいポイントを解説します。
- 国語
- 算数
それぞれどのようなポイントでつまずきやすいのか見てみましょう。
参照:ベネッセ教育情報
国語
国語では「わ」と「は」のように同じ音で異なる言葉の使い分けが、つまづきやすいポイントとして挙げられます。
大人であれば難なくできるかもしれませんが、読み書きを習い始めたばかりの小学1年生にとってはどのように使い分ければよいか分からず戸惑うことは少なくありません。「〜は」「〜を」「〜へ」を適切に使用し、「わ」「お」「え」と書き分けるには、助詞のルールを理解する必要があります。
「〜は」「〜を」「〜へ」は文章のなかで名詞の後にくっつけて使用するため、くっつき言葉と呼ばれます。くっつき言葉のルールを理解するには、さまざまな文章をもとに、文章の意味が通じるか、読んでもおかしくないかなどを考えて使い分ける方法を学ぶことが大切です。
算数
算数でつまずきやすいポイントは、くり上がり・くり下がりのある計算です。
答えが1〜10までの計算では指を使って視覚的に足し算や引き算ができますが、10以上の数字になると計算できなくなってしまうことがあります。くり上がり・くり下がりを克服するには、10のまとまりを作ったり分解したりができるようになることが大切です。
たとえば、まずは「6と4」「8と2」のように10の分解を理解します。10だと理解しづらい場合は5を「3と2」「4と1」のように分解できるようにしましょう。こうした数字を分解する考え方をもとに「8+5」の答えを求める場合、5を「3と2」に分解し、8と2を合わせて10を作ります。そして残りの3を10と足すと、13という答えが出せます。
こうした計算を繰り返して取り組むことで、くり上がり・くり下がりのある計算を克服できるでしょう。
小学1年生にはタブレット学習?紙学習?
小学1年生に家庭学習をさせたいけれど、タブレット学習と紙学習ではどちらが良いか悩んでいる保護者は多いのではないでしょうか。それぞれのメリット・デメリットには主に以下が挙げられます。
| メリット | デメリット | |
| タブレット | ・動画や音声なども活用できて理解しやすい・コンテンツが豊富 | ・タブレットが故障すると取り組めない・ゲームばかり取り組む可能性がある |
| 紙 | ・書く力が養われる・書くことで記憶に定着しやすい・親も一緒に取り組みやすい | ・教材がかさばりやすい・飽きてしまいやすい |
タブレットの場合、動画や音声なども活用した教材に取り組めるため、子どもが理解しやすいのがメリットです。さらに、国語や算数などのほかに、プログラミングや英語なども学べる教材が多く、幅広い分野のコンテンツに取り組めます。
さまざまな角度から子どもの興味関心を刺激できるため、子どもが自主的に取り組めるでしょう。一方で、タブレットが故障すれば学習できなかったり、ゲーム要素のあるコンテンツばかり取り組んだりといったデメリットもあります。
紙の教材では、勉強するうえで欠かせない書く力を養うことができるほか、親が一緒に取り組みやすいのがメリットです。子どもがどこにつまずいているかが見えるため、サポートしやすいでしょう。ただし、教材がかさばって保管場所に困ったり、子どもが飽きやすかったりといったデメリットがあります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、子どもの好みや勉強への姿勢などをもとに、子どもに合った学習方法を選びましょう。
小学1年生におすすめの家庭学習方法は?
小学1年生の家庭学習では、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 学習時間の設定
- 子どもに合わせた難易度・分量
- 勉強のルールを決める
- 目標を決める
- しっかり褒める
それぞれのポイントを解説します。
学習時間の設定
家庭学習を行う際は、あらかじめ学習時間を設定しておきましょう。小学1年生の場合、あまり長時間は集中が続かないケースが多いため、短時間での家庭学習がおすすめです。
無理に長時間勉強させようとすると、子どもは勉強が嫌いになる可能性があります。無理をさせるのではなく、短い時間で家庭学習に取り組む習慣を身に付けましょう。
子どもに合わせた難易度・分量
子どもに合わせた難易度や分量の学習に取り組むことも大切です。小学1年生で習うのは、勉強の基礎となる文字の読み書きや足し算・引き算といった基本的な計算方法などです。これらが十分に身についていないと、今後の勉強にも影響しかねません。
そのため、子どもの理解度に合わせた難易度の問題に取り組み、基礎的な勉強を定着させることが大切です。無理に難しい問題に取り組ませようとしても、子どもは理解ができず勉強への苦手意識を持ってしまうおそれがあります。
また、一度に多くの勉強をしようとするのも、集中が続かない可能性があります。子どもが負担なく取り組めるよう、子どもの理解度に合わせた難易度や分量での家庭学習を心がけましょう。
勉強のルールを決める
家庭学習では、勉強のルールを決めることも大切です。「○時には宿題をする」「〇〇を見た後は勉強する」のように、勉強するタイミングなどをルールとして決めておくことで、習慣化しやすくなります。
ルール通りに勉強できていないときは、保護者が声をかけて勉強を促しましょう。1〜2カ月程度ルール通りに取り組むことで、家庭学習の習慣が身に付くことが期待できます。
目標を決める
家庭学習を継続して行うために、あらかじめ目標を決めておきましょう。目標を決めておくと、目標達成のために積極的に取り組めるようになります。
目標が決まっていないと、勉強へのモチベーションが続かず、途中で飽きたり後回しにしたりする可能性があります。モチベーションを保てるよう、魅力的なゴールを設定してあげましょう。
たとえば、「終わったらゲームができる」「〇〇ができたら夕飯に好きなおかずを作ってあげる」など、子どものやる気につながるような目標がおすすめです。子どもの好みにあわせて、目標を設定しましょう。
しっかり褒める
家庭学習では、子どもができたことをしっかりと褒めることも大切です。保護者に褒められることで、勉強へのモチベーションを保ちやすくなります。
「宿題を間違えずに取り組めた」「集中して勉強できた」など、できたことを褒めると、子どもは自信が持てるようになります。正解した問題に花丸を書いたりシールを貼ったりするのも、子どもにとっては喜ばしいことです。
こうした成功体験を積み重ねることで、子どもの勉強に対するモチベーションを高めることができます。日頃から些細なことでも褒めるように意識しましょう。
初めての家庭学習には進研ゼミ小学講座
家庭学習で学校の宿題以外の教材を活用したいなら、進研ゼミ小学講座がおすすめです。
進研ゼミ小学講座は株式会社ベネッセが提供している通信教育教材で、概要は以下のとおりです。
| 料金 | 3,250円/月(12カ月一括払い) |
| 特徴 | 豊富なコンテンツとエデュトイなどを活用し、子どもの知的好奇心を刺激しながら学べる |
| 科目(コース) | 国語・算数・英語・プログラミング学習 |
| 使用教材 | ・紙のワーク・タブレット |
| カリキュラム | 国語・算数をメインに、書く力や読解力、知的好奇心などを育む |
| サポート体制 | 赤ペン先生の添削やまなびアドバイザーによるサポートなどが受けられる |
紙のワークが中心の「チャレンジ1ねんせい」とタブレット学習が中心の「チャレンジタッチ1ねんせい」があります。どちらも「書いて学ぶ」ことを重視しており、書く力を伸ばすことができます。
また、タブレット学習ではゲーム感覚でプログラミング学習ができるのも魅力です。約1,000冊の電子書籍が読める機能もあるため、子どもの知的好奇心を刺激できるでしょう。
サポート体制も充実しており、まなび相談窓口では勉強の進め方などを相談できます。困ったことがあれば相談できるため、安心して家庭学習に取り組めるでしょう。
まとめ|小学1年生におすすめの家庭学習方法とは?
小学1年生は、国語や算数で今後の学習に必要な基礎的な勉強を行います。2年生以降の勉強をスムーズに取り組めるようにするには、1年生で習った内容をしっかりと定着させることが大切です。そのために、家庭学習の習慣を身に付けさせましょう。
家庭学習をする際は、子どもが負担なく取り組めるように工夫する必要があります。勉強時間や分量などをあらかじめ決めておくほか、目標を決めたりできたことをしっかりと褒めたりしてモチベーションを保てるようにしましょう。
また、家庭学習で活用する教材は子どもに合ったものを活用することも大切です。進研ゼミ小学講座は紙のワークやタブレットを活用し、国語・算数以外に英語やプログラミング学習なども勉強できます。進研ゼミ小学講座のような教材も活用しながら、無理なく家庭学習を続けられるように工夫しましょう。

ベビーカレンダー教育マガジン編集部
月間1,000万人以上が利用する医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報サイト「ベビーカレンダー」の妊娠・子育てお役立ちアイテムご紹介するベビーカレンダーマガジンです。
厳選した教育サービスをアンケート結果や編集部が定義した評価基準を元にしたランキングや口コミなどでご紹介しています。