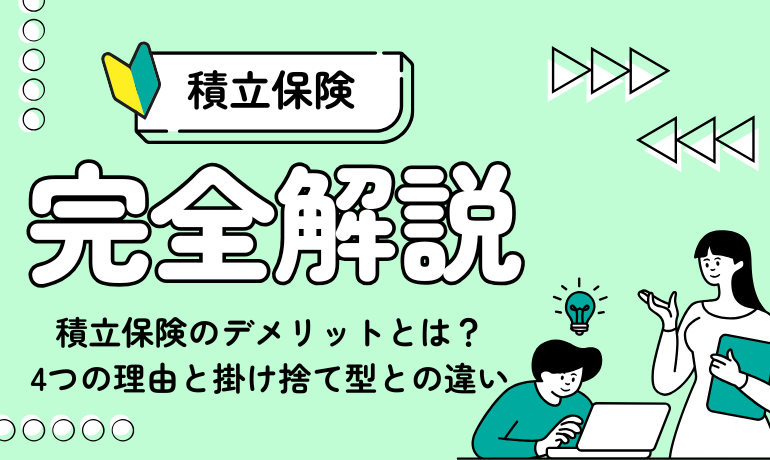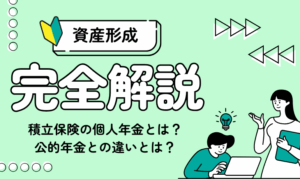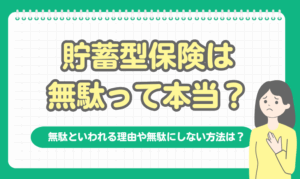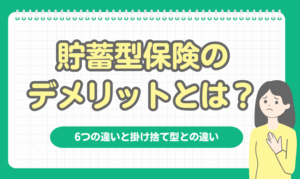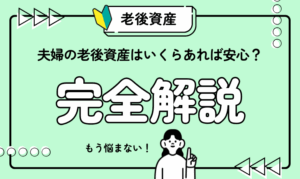「将来のために備えたいけど、貯金は苦手…」「保障も貯蓄もできる積立保険って便利そうだけど、本当に自分に合っているのかな?」
万が一の事態に備えながら、計画的に資産形成ができる「積立保険」。一見すると非常に魅力的な金融商品ですが、加入を検討する際には、そのデメリットにもしっかりと目を向ける必要があります。インターネット上では「積立保険はいらない」「保険で貯蓄をしてはいけない」といった声も聞かれ、不安に感じている方も少なくないでしょう。
この記事では、積立保険の加入を検討している方や掛け捨て型保険との違いがわからず悩んでいる方に向けて、積立保険が「いらない」といわれる4つの大きなデメリットを徹底的に解説します。
さらに、デメリットだけでなくメリットや掛け捨て型保険との違い、そしてどのような人が積立保険に向いているのかまで詳しくご紹介します。この記事を読めば、あなたが本当に積立保険に加入すべきか、後悔しない保険選びのヒントが見つかるはずです。
積立保険のデメリットとは?いらないといわれる4つの理由
積立保険は、死亡保障や医療保障といった万が一への備えと、将来のための貯蓄機能を兼ね備えた保険の総称です。具体的には、子どもの教育資金を準備する「学資保険」、老後B資金を備える「個人年金保険」、保障と貯蓄を両立する「養老保険」や「終身保険」などが含まれます。
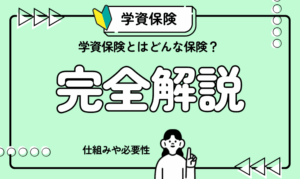
保障と貯蓄がセットになっている手軽さから人気がありますが、その仕組みゆえに看過できないデメリットが存在します。まずは、なぜ積立保険が「いらない」といわれるのか、その代表的な4つの理由を詳しく見ていきましょう。
1. 積立型は掛け捨て型より保険料が高い
積立保険の最大のデメリットとして挙げられるのが、掛け捨て型の保険に比べて月々の保険料が高額になる点です。

【なぜ保険料が高いのか?】
理由はシンプルで、保険料の内訳にあります。
つまり、積立保険の保険料は「保障コスト+貯蓄コスト」で構成されているため、同じ保障内容の掛け捨て型保険と比較すると、どうしても割高になってしまうのです。
【具体的にどれくらい違うのか?】
例えば、30歳男性が死亡保障300万円の保険に加入する場合を考えてみましょう。
これはあくまで一例ですが、保障内容は同じでも、保険料には数倍から10倍以上の差がつくことも珍しくありません。
この「保険料の高さ」は、家計に大きな影響を与えます。特に、収入が不安定な時期や子育て世代で支出が多い時期には、高い保険料が負担となり、支払いを続けるのが困難になるケースも考えられます。
「保障も貯蓄も」というメリットの裏側には、「保険料が高い」というデメリットがあることをまず理解しておくことが、積立保険を検討する上での第一歩です。貯蓄型保険の仕組みを正しく理解し、ご自身の家計状況と照らし合わせて、無理なく支払いを続けられるかを慎重に判断する必要があります。
2. 資産運用目的にするには利率が低い
「保険で貯蓄ができるなら、銀行預金より良いのでは?」と考える方もいることでしょう。しかし、純粋な資産運用の観点から見ると、積立保険の利率(予定利率)は決して高いとは言えません。これが「保険で貯蓄をしてはいけない」といわれる大きな理由の一つです。
【なぜ利率が低いのか?】
積立保険で支払った保険料のすべてが、そのまま貯蓄に回るわけではありません。支払った保険料からは、まず死亡保障などのための「保障コスト」や、保険会社の運営経費である「事業経費(手数料)」が差し引かれます。その残りの金額が、予定利率で運用される仕組みです。
- 支払保険料 - (保障コスト + 事業経費) = 積立金
このように、運用に回る前に各種コストが引かれるため、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)といった他の金融商品と比べて、実質的な利回りは低くなる傾向にあります。
【返戻率で見る積立保険の実力】
積立保険の貯蓄性を判断する指標に「解約返戻率」があります。これは、支払った保険料総額に対して、将来受け取れる満期保険金や解約返戻金が何%になるかを示す数値です。
例えば、返戻率105%の積立保険の場合、保険料を総額300万円支払うと、満期時に315万円(300万円 × 105%)が受け取れる計算になります。
一見すると「お金が増えるなら良いのでは?」と感じる人もいるでしょう。しかし、注意すべきは「期間」です。この105%という数字は、10年、20年、30年といった長期間をかけてようやく到達するケースがほとんどです。年利に換算すると1%にも満たないことが多く、資産「運用」と呼ぶには物足りない水準と言わざるを得ません。
近年では、低金利の影響を受け、返戻率が100%をわずかに超える程度、あるいは100%を下回る(元本割れする)積立保険も増えています。「いつでも100%以上のお金が戻る積立保険」は、現在では非常に少なくなっているのが実情です。
貯蓄や資産形成を主な目的とするのであれば、保障は割安な掛け捨て保険で確保し、積立保険に支払うはずだった差額分を、より利率の高いNISAやiDeCoなどで運用する方が、効率的に資産を増やせる可能性があります。
3. 途中解約は元本割れのリスクが高い
積立保険のデメリットとして、最も注意すべき点の一つが「途中解約による元本割れリスク」です。
「貯蓄型の保険なのだから、いつでも支払った分くらいは戻ってくるだろう」と安易に考えていると、思わぬ損失を被る可能性があります。
【なぜ元本割れするのか?】
積立保険を途中で解約した際に払い戻されるお金を「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」といいます。この解約返戻金の額は、多くの場合、払込期間が短いほど、支払った保険料の総額を大きく下回ります。つまり「元本割れ」してしまうのです。
その理由は、先ほども触れた保険料の仕組みにあります。支払った保険料からは、まず保険会社の運営経費や保障コストなどが「初期費用」として優先的に差し引かれます。そのため、加入して間もない時期は、貯蓄に回るお金が非常に少ない状態です。
上のグラフのように、解約返戻金が払込保険料総額を上回る(返戻率が100%を超える)までには、一般的に10年以上の長い期間が必要となります。特に、加入から数年以内の解約では、解約返戻金がほとんどない、あるいは全くないケースもあります。
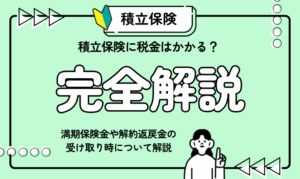
【ライフプランの変化に対応しにくい】
人生には、結婚、出産、転職、住宅購入など、さまざまなライフイベントが訪れます。それに伴い、家計の状況も変化し、保険料の支払いが厳しくなることもあるでしょう。
そんな時に、掛け捨て保険であれば、比較的気軽に保障内容を見直したり、解約したりすることが可能です。しかし、積立保険の場合は、途中解約すると元本割れしてしまうため、「損をしたくない」という思いから解約に踏み切れず、家計を圧迫し続ける…という悪循環に陥ってしまうリスクがあります。
積立保険に加入するということは、「長期間、保険料を払い続ける」という強いコミットメントが求められます。ご自身の将来のライフプランを慎重に考え、本当に最後まで払い続けられるかを見極めることが極めて重要です。
4. 利率固定型だとインフレに弱い
積立保険の多くは、契約時の「予定利率」が満期まで固定される「利率固定型」の商品です。契約時には魅力的に見えた利率でも、将来の経済状況の変化、特に「インフレーション(インフレ)」によって、その価値が実質的に目減りしてしまうリスクを抱えています。
【インフレとは?】
インフレとは、モノやサービスの値段(物価)が継続的に上昇し、相対的にお金の価値が下がることです。
例えば、現在100円で買えるリンゴが、20年後にはインフレによって200円出さないと買えなくなるとします。これは、20年後の200円の価値が、現在の100円の価値と同じになった、つまり「お金の価値が半分になった」ことを意味します。
【利率固定型の保険がインフレに弱い理由】
積立保険は、20年後、30年後といった遠い将来に、契約時に定められた金額(例えば300万円)を受け取る、という約束です。
もし、年率2%のインフレが30年間続いた場合、物価は約1.8倍になります。つまり、30年後に受け取る300万円の価値は、現在の価値に換算すると約167万円(300万円 ÷ 1.8)にまで目減りしてしまうのです。
このように、利率が固定されている金融商品は、インフレが進行すると、将来受け取るお金の購買力が著しく低下してしまうという大きな弱点を持っています。
将来のインフレ率を正確に予測することは誰にもできません。しかし、長期にわたる契約である積立保険を検討する際には、このインフレリスクの存在を必ず念頭に置いておく必要があります。お金の「額面」だけでなく、「実質的な価値」がどうなるかという視点を持つことが大切です。
積立保険のメリット3つ
ここまで積立保険のデメリットを詳しく見てきましたが、もちろんメリットも存在します。デメリットとメリットの両方を理解した上で、自分にとって最適な選択をすることが重要です。
ここでは、積立保険が持つ代表的な3つのメリットをご紹介します。
1. 保障を得ながら計画的にお金が貯められる
積立保険の最大のメリットは、万が一の死亡保障や医療保障を確保しながら、将来のための資金を計画的に準備できる点です。
【貯金が苦手な人の強い味方】
「毎月コツコツ貯金しよう」と決意しても、ついつい使ってしまってなかなか貯まらない…という経験はありませんか?
積立保険は、毎月決まった日に、指定した口座から保険料が自動的に引き落とされます。これは、意識せずとも半強制的に貯蓄が実行される仕組みと言えます。貯金が苦手な人にとっては、この「強制力」が、着実にお金を貯めていくための大きな助けとなるでしょう。
【「もしも」と「将来」を同時に準備】
積立保険は、2つの安心を同時に手に入れられる点が魅力です。
このお金を、子どもの大学進学費用や自分たちのセカンドライフ資金など、ライフプランに合わせた目的に活用できます。
このように、「保障」と「貯蓄」という人生における重要なお金の準備を一本化できる手軽さは、積立保険ならではのメリットと言えるでしょう。
2. 所得控除で節税ができる
積立保険に加入して保険料を支払うと、「生命保険料控除」という制度の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。
【生命保険料控除とは?】
生命保険料控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った保険料の額に応じて、その年の所得から一定額を差し引くことができる制度です。所得が低くなることで、課税対象額が減り、結果として所得税や住民税が安くなります。
控除の種類は、加入した保険の契約時期や保障内容によって「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに分かれています。積立保険は、その種類(終身保険、養老保険、個人年金保険など)に応じて、これらのいずれか、または複数の控除の対象です。
【どれくらい節税できる?】
例えば、2012年1月1日以降に契約した保険の場合、各控除の限度額は以下の通りです。
| 年間払込保険料 | 所得税の控除額 |
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 20,001円~40,000円 | 支払保険料 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,001円~80,000円 | 支払保険料 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,001円以上 | 一律40,000円 |
| 年間払込保険料 | 住民税の控除額 |
| 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 12,001円~32,000円 | 支払保険料 × 1/2 + 6,000円 |
| 32,001円~56,000円 | 支払保険料 × 1/4 + 14,000円 |
| 56,001円以上 | 一律28,000円 |
仮に、年間8万円以上の保険料を支払っている場合、所得税で最大4万円、住民税で最大2万8千円が課税所得から控除されます。所得税率が10%の人であれば、年間で約6,800円(所得税4,000円+住民税2,800円)の節税につながります。
会社員の方であれば年末調整で、自営業の方などは確定申告で手続きをすることで、この控除を受けることが可能です。
利率の低さがデメリットとして挙げられる積立保険ですが、この節税効果を実質的な利回りの一つとして捉えることもできるでしょう。
3. 契約者貸付が利用できる
急な出費でお金が必要になった時、積立保険を解約すると元本割れしてしまう可能性があることは先述の通りです。しかし、そんな時に活用できる便利な制度が「契約者貸付」です。
【契約者貸付とは?】
契約者貸付とは、その時点で貯まっている解約返戻金の一定の範囲内(一般的には7~9割程度)で、保険会社からお金を借りることができる制度です。
【解約との違いとメリット】
途中解約と比べて、契約者貸付には以下のような大きなメリットがあります。
・保障が継続される:最大のメリットは、お金を借りている間も保険契約は有効であり、万が一の際の保障はそのまま継続される点です。解約してしまうと保障はなくなりますが、貸付であれば安心です。
・手続きが簡単でスピーディー:一般的なカードローンなどの審査に比べて手続きが簡単で、比較的早くお金を借りることができます。
・返済の自由度が高い:返済期間や毎月の返済額を比較的自由に設定できる場合が多く、自分のペースで返済していくことが可能です。もちろん、利息は発生しますが、カードローンなどと比較すると金利は低めに設定されていることが一般的です。
もし満期や解約を迎えるまでに返済が終わらなかった場合は、受け取る保険金や解約返戻金から借入額と利息が差し引かれます。
「保障は続けたいけれど、一時的にお金が必要…」という状況に陥った際に、解約という最終手段を取らずに済むセーフティーネットとして、契約者貸付制度は非常に心強い存在と言えるでしょう。
積立保険と掛け捨て保険の違い
ここまで積立保険のメリット・デメリットを見てきましたが、ここで改めて「掛け捨て保険」との違いを整理しておきましょう。どちらのタイプが自分に合っているかを判断するために、それぞれの特徴を正しく理解することが大切です。
| 比較項目 | 積立保険(貯蓄型保険) | 掛け捨て保険 |
| 貯蓄性 | あり満期保険金や解約返戻金がある。 | なし満期保険金や解約返戻金は、ないか、あってもごくわずか。 |
| 保険料 | 高い保障コスト+貯蓄コストのため。 | 安い保障コストのみのため。 |
| 保障内容 | 保障は一生涯続く「終身型」が多い。 | 一定期間のみ保障する「定期型」が多い。 |
| 途中解約 | 元本割れのリスクが高い。 | 元本割れのリスクはほぼないが、払った保険料は戻らない。 |
| 柔軟性 | 途中での見直しがしにくい。 | ライフステージに合わせて見直しやすい。 |
| メリット | ・保障と貯蓄を兼ねられる・計画的に貯蓄できる・生命保険料控除がある・契約者貸付が利用できる | ・保険料が安く、大きな保障を得やすい・家計への負担が少ない・貯蓄と保険を分けて考えられる |
| デメリット | ・保険料が高い・利率が低い・途中解約で元本割れする・インフレに弱い | ・貯蓄性がない(お金は戻ってこない)・更新時に保険料が上がることがある |
| 代表的な保険 | 終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険 | 定期保険、収入保障保険、医療保険、がん保険 |
【ポイントのまとめ】
・積立保険:『保障』と『貯蓄』のハイブリッド型。保険料は高いが、万が一の備えと将来の資金準備を同時に行える。貯金が苦手な人に向いている。
・掛け捨て保険:『保障』に特化したシンプル型。保険料は安いが、支払った保険料は戻ってこない(掛け捨て)。保険と貯蓄は分けて考えたい人、保険料を抑えたい人に向いている。
どちらが良い・悪いということではなく、それぞれの特性を理解し、ご自身の価値観やライフプランに合った方を選ぶことが重要です。
積立保険への加入がおすすめの人とは
これまでの内容を踏まえ、どのような人が積立保険に向いていて、どのような人が掛け捨て保険に向いているのかを具体的に見ていきましょう。
積立保険がおすすめの人
以下のような考え方や状況に当てはまる方は、積立保険のメリットを活かせる可能性があります。
☑ 貯金が苦手で、半強制的にでもお金を貯める仕組みが必要な人
毎月の給料から天引きされる感覚で、着実に将来の資金を準備したい方。「貯金」という意識だとつい使ってしまうが、保険料として引き落とされるなら続けられるというタイプの人には最適です。
☑ 保障と貯蓄の管理を一本化して、シンプルにしたい人
「保障はA社の掛け捨て保険、貯蓄はB銀行の積金とC証券のNISAで…」と、複数の金融商品を管理するのが面倒だと感じる方。一つの契約で万が一の保障と将来の資産形成をまとめて管理したいというニーズに応えられます。
☑ 教育資金や老後資金など、使う時期と目的が明確に決まっている人
「15年後の子どもの大学入学資金として300万円」「65歳からのセカンドライフ資金として500万円」といったように、具体的な目標がある場合、その時期に合わせて満期を設定できる積立保険は有効な手段です。目標達成に向けた計画的な資金準備ができます。
☑ 途中解約の可能性が低く、長期的に保険料を払い続けられる経済的余裕がある人
積立保険の最大のリスクは途中解約です。今後、収入が安定しており、長期にわたって保険料を無理なく支払い続けられる見通しが立っていることが加入の前提条件となります。
掛け捨て保険がおすすめな人
一方で、以下のような方は、掛け捨て保険の方が合理的な選択となるでしょう。
☑ とにかく月々の保険料を安く抑えたい人
家計に占める固定費をできるだけ減らしたい方。特に子育て世代など、出費がかさむ時期には、安い保険料で大きな保障を確保できる掛け捨て保険が適しています。
☑ 保険は万が一の保障、貯蓄は貯蓄として、分けて効率的に運用したい人
「保障は保険、貯蓄はNISAやiDeCo」というように、目的ごとに最適な金融商品を使い分けたいと考える方。保険で保障を確保しつつ、浮いたお金をより高い利回りが期待できる投資に回すことで、効率的な資産形成を目指せます。
☑ ライフステージの変化に合わせて、保障内容を柔軟に見直したい人
結婚、出産、子どもの独立など、ライフステージによって必要な保障額は変化します。掛け捨て保険は解約や見直しがしやすいため、その時々の状況に応じて最適な保障を確保したいというニーズに柔軟に対応できます。
☑ 保険についてある程度の知識があり、自分で資産運用ができる人
金融商品に関する知識があり、自身で投資先を選んで資産を増やしていくことができる方にとっては、手数料が高く利率の低い積立保険は魅力的に映らないでしょう。
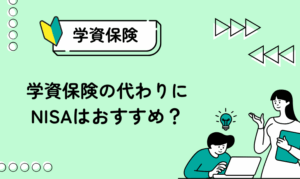
後悔しない積立保険の選び方
もし、あなたが積立保険に加入する方向で検討を進めるのであれば、後悔しないために押さえておくべきポイントがいくつかあります。勢いで契約してしまう前に、以下の点を確認しましょう。
・加入の目的を明確にする
まず、「なぜ積立保険に加入するのか?」を自問自答しましょう。「老後資金のため」「子どもの教育資金のため」「万が一の死亡保障を兼ねた貯金のため」など、目的を具体的にすることが保険選びの第一歩です。目的が明確になれば、必要な保障額、満期の時期、目標金額(満期保険金額)が見えてきます。
・払込期間と保証期間を確認する
保険料をいつまで支払うのか(払込期間)、保障がいつまで続くのか(保障期間)は必ず確認しましょう。例えば「10年満期」の養老保険や、60歳まで払い込んで保障が一生涯続く「終身保険」など、種類はさまざまです。ご自身のライフプラン(定年退職の時期など)と照らし合わせて、無理のないプランを選びましょう。
・返戻率を必ずチェックし、比較検討する
設計書(提案書)を見せてもらったら、必ず「返戻率」を確認してください。支払う保険料総額に対して、満期時や解約時にいくら戻ってくるのかを示す重要な指標です。複数の保険会社から同じような条件で見積もりを取り、返戻率を比較することが大切です。「A社は105%、B社は108%」といった具体的な数字で比較すれば、より有利な商品を選ぶことができます。
・保障内容が自分に合っているか吟味する
積立保険といっても、「終身保険」「養老保険」「個人年金保険」など種類によって保障内容は異なります。死亡保障がメインなのか、生存している場合の貯蓄がメインなのかなど、主たる目的と保障内容が合致しているかを確認しましょう。また、医療特約や先進医療特約など、付加できるオプションについても検討が必要です。
・契約者は誰にするか検討する
保険の契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保障の対象になる人)、受取人(保険金を受け取る人)を誰にするかは非常に重要です。特に税金面で違いが出てくるため、安易に決めず、FP(ファイナンシャルプランナー)や保険代理店の担当者とよく相談して決めましょう。
積立保険は、一度契約すると長期間にわたって付き合っていく商品です。店舗やオンライン相談などを活用し、専門家の意見も聞きながら、納得のいくまで検討を重ねることが後悔しない保険選びにつながります。
おすすめの積立保険はこちらをチェック!
この記事では、積立保険のデメリットを中心に、メリットや掛け捨て保険との違い、そして後悔しない選び方まで詳しく解説してきました。
積立保険は、保険料の高さや利率の低さといったデメリットがある一方で、計画的な資産形成を助けてくれる心強い味方にもなり得ます。大切なのは、その特性を正しく理解し、ご自身のライフプランや価値観に合っているかどうかを見極めることです。
もし、この記事を読んで「自分には積立保険が合っているかもしれない」「もっと具体的な商品を知りたい」と感じた方は、さまざまな保険商品を比較検討してみることをおすすめします。ゆうちょや明治安田生命をはじめ、各社から多様な積立保険が提供されています。積立生命保険ランキングなどを参考にしながら、ご自身の目的に合った保険を探してみてはいかがでしょうか。
あなたの保険選びが、より良い未来への備えとなることを心から願っています。