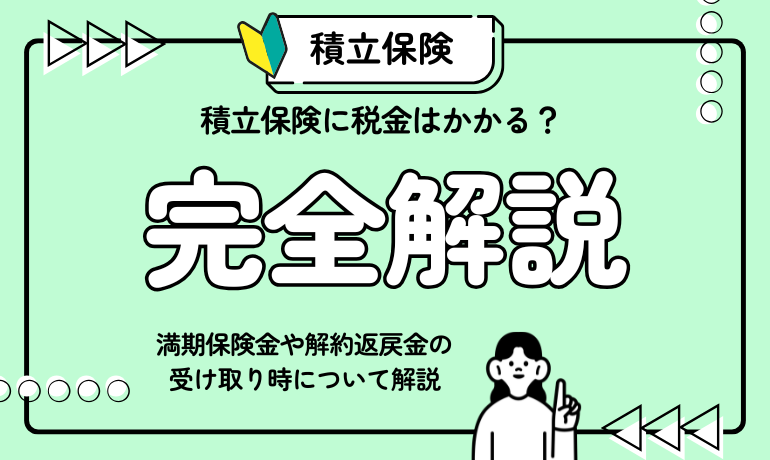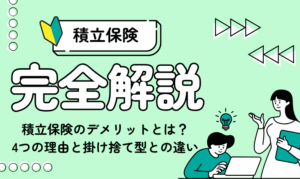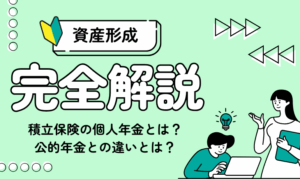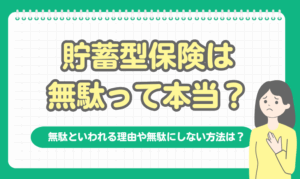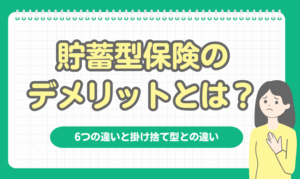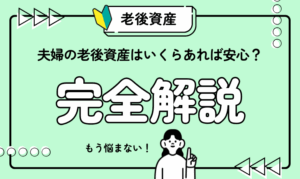積立保険を受け取る際、多くの方が気になるのが税金の問題です。長年コツコツと保険料を支払い続けてきた積立保険。満期を迎えて保険金を受け取る時や、途中解約して解約返戻金を受け取る時に、どのような税金がかかるのでしょうか。
結論から申し上げると、積立保険の受け取りには原則として税金がかかります。しかし、実際には各種控除があるため、税金が発生しないケースも少なくありません。本記事では、積立保険にかかる税金について、受取人や受け取り方法による違い、具体的なシミュレーション、確定申告の必要性、税金対策としての活用方法まで、詳しく解説していきます。
積立保険の満期保険金や解約払戻金の受け取りには税金がかかる?
積立保険の満期保険金や解約返戻金を受け取る際は、原則として税金の対象となります。ただし、必ずしも税金を支払う必要があるわけではありません。なぜなら、各種控除が適用されるため、実際には税金が発生しないケースも多いからです。
税金の種類や金額は、契約者と受取人の関係、受け取り方法(一括か年金形式か)によって大きく変わってきます。例えば、契約者と受取人が同じ場合は所得税の対象となりますが、契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象となります。
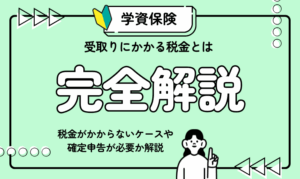
積立保険と一口に言っても、その種類は様々です。代表的なものとして、養老保険、学資保険、個人年金保険などがあります。これらの保険は、死亡保障を備えながら貯蓄性も持つ商品で、満期時や解約時にまとまったお金を受け取ることができます。
また、保険料を支払い続けてきた期間や、受け取る金額によっても税金の取り扱いは異なります。途中解約した場合の解約返戻金や、一部引き出しをした場合も同様に税金の対象となる可能性があります。
重要なのは、税金がかかるかどうかは「利益」が出ているかどうかによるということです。支払った保険料の総額よりも受け取った金額が多い場合、その差額が利益となり、この利益部分に対して税金がかかることになります。
積立保険の受取人による税金の種類
積立保険にかかる税金は、契約者と受取人の関係によって大きく異なります。ここでは、それぞれのケースでどのような税金がかかるのか、詳しく見ていきましょう。
契約者と受取人が同じ:所得税(一時所得)
契約者と受取人が同じ場合、つまり保険料を支払った人が保険金を受け取る場合は、所得税の対象となります。具体的には、「一時所得」として扱われます。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得のことです。
一時所得の計算式は以下のとおりです。
一時所得の金額 = 総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円)
さらに、課税される一時所得の金額は、上記で計算した一時所得の金額の2分の1となります。
満期保険金300万円を受け取り、支払った保険料の総額が200万円だった場合:
この25万円が他の所得と合算されて、所得税が計算されることになります。
所得税の税率は、課税される所得金額に応じて以下のように定められています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
契約者と受取人が違う:贈与税
契約者と受取人が異なる場合、例えば夫が保険料を支払い、妻が保険金を受け取るようなケースでは、贈与税の対象となります。これは、保険料を負担していない人が経済的利益を受けることになるため、贈与とみなされるからです。
贈与税の計算は、暦年課税の場合、以下の式で行います。
贈与税額 = (贈与財産の価額 – 基礎控除額110万円)× 税率 – 控除額
贈与税の税率は、一般贈与財産と特例贈与財産で異なります。特例贈与財産とは、18歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産のことです。
一般贈与財産の税率表:
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産の税率表:
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
積立保険の受け取り方による税金の種類
積立保険の受け取り方には、大きく分けて「一括受取」と「年金形式での受取」の2種類があります。どちらを選択するかによって、税金の取り扱いが変わってきます。
一括で受け取る場合
一括で保険金を受け取る場合の税金の取り扱いは、先ほど説明した受取人による違いと同様です。
契約者と受取人が同じ:所得税(一時所得)
契約者本人が一括で保険金を受け取る場合は、一時所得として所得税の対象となります。計算方法は前述のとおりで、受け取った保険金から支払った保険料を差し引いた利益部分に対して、50万円の特別控除を適用し、さらにその2分の1が課税対象となります。
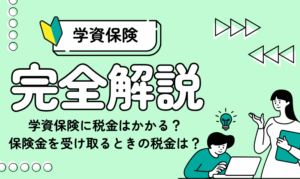
この方法のメリットは、50万円の特別控除があることと、課税対象が2分の1になることです。そのため、利益が50万円以下であれば、実質的に税金はかからないことになります。
契約者と受取人が違う:贈与税
契約者以外の人が一括で保険金を受け取る場合は、贈与税の対象となります。この場合、受け取った保険金の全額が贈与財産となり、110万円の基礎控除を差し引いた金額に対して贈与税が課されます。
年金形式で受け取る場合
年金形式で受け取る場合は、一括受取とは税金の取り扱いが異なります。
契約者と受取人が同じ:所得税(雑所得)
契約者本人が年金形式で保険金を受け取る場合、毎年受け取る年金は「雑所得」として所得税の対象となります。
雑所得の計算式は以下のとおりです。
雑所得の金額 = その年の年金の収入金額 – 必要経費
必要経費は、以下の式で計算します。
必要経費 = その年の年金の収入金額 × 払込保険料の総額 ÷ 年金の受取総額
例えば、払込保険料の総額が300万円で、年金の受取総額が400万円、年間の年金収入が40万円の場合:
この10万円が他の所得と合算されて、所得税が計算されることになります。
契約者と受取人が違う:贈与税と所得税(雑所得)
契約者以外の人が年金形式で保険金を受け取る場合は、少し複雑になります。年金受給権を取得した時点で贈与税の対象となり、その後毎年受け取る年金については雑所得として所得税の対象となります。
つまり、最初に年金受給権の評価額に対して贈与税がかかり、その後は毎年の年金収入に対して所得税がかかるという二重の課税が発生することになります。
源泉分離課税の対象になる積立保険
積立保険の中には、源泉分離課税の対象となるものがあります。源泉分離課税とは、他の所得と合算せずに、支払いの際に一定の税率で源泉徴収することで課税関係が完結する課税方式です。
源泉分離課税の対象となる積立保険は、主に「金融類似商品」と呼ばれるものです。これらは、保険の機能よりも貯蓄の機能が強い商品で、以下の条件を満たすものが該当します。
これらの保険から生じる差益(満期保険金や解約返戻金から払込保険料を差し引いた金額)に対しては、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収されます。
源泉分離課税の計算例:
・満期保険金:150万円
・払込保険料:100万円
・差益:50万円
・源泉徴収税額:50万円 × 20.315% = 101,575円
この場合、101,575円が源泉徴収され、残りの1,398,425円を受け取ることになります。源泉分離課税の場合は、確定申告の必要がないというメリットがあります。
積立保険の受け取りで税金がかからないケース
ここまで積立保険にかかる税金について説明してきましたが、実際には税金がかからないケースも多くあります。以下、主なケースを紹介します。
契約者と受取人が同じ場合:
1.利益が50万円以下の場合
一時所得の特別控除額が50万円あるため、受け取った保険金から支払った保険料を差し引いた利益が50万円以下であれば、税金はかかりません。
2.他に一時所得がない場合で利益が90万円以下の場合
一時所得は2分の1が課税対象となるため、利益が90万円の場合、特別控除50万円を差し引いた40万円の2分の1である20万円が課税対象となります。基礎控除48万円の範囲内であれば、実質的に税金はかかりません。
3.解約返戻金が払込保険料を下回る場合
途中解約などで解約返戻金が払込保険料の総額を下回る場合は、利益が発生していないため税金はかかりません。
契約者と受取人が違う場合:
1.受取金額が110万円以下の場合
贈与税の基礎控除額が110万円あるため、受け取った保険金が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
2.配偶者からの贈与で2,000万円以下の場合(配偶者控除の特例)
婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与の場合、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除できる特例があります。
積立保険の税金シミュレーション
ここでは、実際に積立保険を受け取った場合の税金について、具体的な金額でシミュレーションしてみましょう。
100万円を受け取ったときの税金
まずは、100万円を受け取ったときの税金から見ていきます。
契約者と受取人が同じ場合
一括で100万円の満期保険金を受け取り、払込保険料の総額が70万円だった場合:
この場合、利益が特別控除額の50万円以下のため、税金はかかりません。
仮に払込保険料が40万円だった場合:
この5万円が他の所得と合算されて所得税が計算されます。他の所得が300万円の場合、305万円に対する税率10%が適用され、追加の所得税は5万円 × 10% = 5,000円となります(復興特別所得税を含めると5,105円)。
契約者と受取人が違う場合
100万円の満期保険金を受け取った場合:
- 贈与税の課税価格 100万円 – 110万円(基礎控除) = 0円
基礎控除額の110万円以下のため、贈与税はかかりません。
300万円を受け取ったときの税金
続いて、300万円を受け取った場合に税金がどうなるのか見ていきましょう。
契約者と受取人が同じ場合
一括で300万円の満期保険金を受け取り、払込保険料の総額が200万円だった場合:
1.利益の計算 300万円 – 200万円 = 100万円
2.一時所得の計算 100万円 – 50万円(特別控除) = 50万円
3.課税対象額 50万円 × 1/2 = 25万円
この25万円が他の所得と合算されて、所得税が計算されます。他の所得が400万円の場合、425万円に対する税率20%が適用され、追加の所得税は25万円 × 20% = 50,000円となります(復興特別所得税を含めると51,050円)。
契約者と受取人が違う場合
300万円の満期保険金を受け取った場合:
1.贈与税の課税価格 300万円 – 110万円(基礎控除) = 190万円
2.贈与税額(一般贈与財産の場合) 190万円 × 10% = 19万円
したがって、贈与税として19万円を納付する必要があります。
500万円を受け取ったときの税金
ここでは、500万円を受け取った場合の税金について解説していきます。
契約者と受取人が同じ場合
一括で500万円の満期保険金を受け取り、払込保険料の総額が350万円だった場合:
・利益の計算 500万円 – 350万円 = 150万円
・一時所得の計算 150万円 – 50万円(特別控除) = 100万円
・課税対象額 100万円 × 1/2 = 50万円
この50万円が他の所得と合算されて所得税が計算されます。他の所得が500万円の場合、550万円に対する税率20%が適用され、追加の所得税は50万円 × 20% = 100,000円となります(復興特別所得税を含めると102,100円)。
契約者と受取人が違う場合
500万円の満期保険金を受け取った場合:
したがって、贈与税として53万円を納付する必要があります。
積立保険の払い戻しを受けたら確定申告が必要?
積立保険の満期保険金や解約返戻金を受け取った場合、確定申告が必要かどうかは状況によって異なります。
確定申告が必要な場合:
1.一時所得の金額が20万円を超える場合
給与所得者で年末調整を受けている人でも、一時所得を含む給与所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
2.複数の一時所得がある場合
積立保険の満期保険金以外にも一時所得がある場合は、合計額で判断する必要があります。
3.年金形式で受け取っている場合
雑所得として毎年確定申告が必要になる可能性があります。
4.贈与税の対象となる場合
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。
確定申告が不要な場合:
1.源泉分離課税の対象となる場合
金融類似商品として源泉徴収されている場合は、確定申告は不要です。
2.利益が特別控除額以下の場合
一時所得の場合、利益が50万円以下であれば確定申告は不要です。
3.贈与税の基礎控除以下の場合
受取金額が110万円以下の場合は、贈与税の申告は不要です。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告が必要にもかかわらず申告しなかった場合、以下のようなペナルティが課される可能性があります。
- 無申告加算税
納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。
- 延滞税
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。
- 重加算税
仮装・隠蔽があった場合は、35%または40%の重加算税が課される可能性があります。
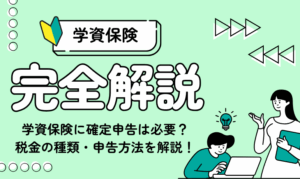
税務署は保険会社から支払調書を受け取っているため、申告漏れは発覚する可能性が高いです。必要な場合は、必ず確定申告を行いましょう。
積立保険は税金対策になる?
積立保険は、適切に活用すれば税金対策として有効な手段となります。特に、生命保険料控除を活用することで、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
生命保険料控除とは
生命保険料控除は、1年間に支払った生命保険料に応じて、一定の金額を所得から控除できる制度です。平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)の場合、以下の3つの区分があります。
・一般生命保険料控除:生存または死亡に起因して支払う保険金・給付金に係る保険料
・介護医療保険料控除:入院・通院等に伴う給付に係る保険料
・個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料
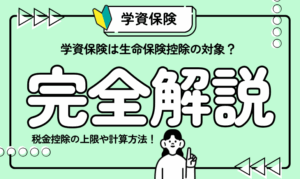
各控除の限度額は以下のとおりです。
所得税の生命保険料控除額
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 20,001円〜40,000円 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
| 40,001円〜80,000円 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
| 80,001円以上 | 一律40,000円 |
3つの控除を合わせて、最大12万円の所得控除が可能です。
住民税の生命保険料控除額
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
| 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 12,001円〜32,000円 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
| 32,001円〜56,000円 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
| 56,001円以上 | 一律28,000円 |
3つの控除を合わせて、最大7万円の所得控除が可能です。
税金控除の対象となる積立保険
生命保険料控除の対象となる主な積立保険は以下のとおりです。
・養老保険:一般生命保険料控除の対象となります。
・学資保険:一般生命保険料控除の対象となります。
・個人年金保険:個人年金保険料税制適格特約を付加している場合は、個人年金保険料控除の対象となります。
・終身保険:一般生命保険料控除の対象となります。
具体的な節税効果
年収500万円の会社員が年間8万円の養老保険料を支払っている場合:
所得税率を10%、住民税率を10%とした場合:
このように、生命保険料控除を活用することで、年間数千円から数万円の節税効果を得ることができます。
その他の税金対策としての活用方法
1.相続税対策
生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があるため、相続税対策として活用できます。
2.贈与税対策
暦年贈与の基礎控除110万円を活用して、毎年保険料相当額を贈与し、受贈者が保険契約者となることで、計画的な資産移転が可能です。
3.法人での活用
法人が契約者となる積立保険は、保険料の一部を損金算入できる場合があり、法人税の節税対策として活用できます。
まとめ
積立保険の満期保険金や解約返戻金を受け取る際の税金について、詳しく解説してきました。重要なポイントをまとめると、以下のとおりです。
・積立保険の受け取りには原則として税金がかかりますが、各種控除により実際には税金が発生しないケースも多くあります。
・契約者と受取人が同じ場合は所得税(一時所得)、異なる場合は贈与税の対象となります。
・一括受取の場合と年金形式での受取では、税金の取り扱いが異なります。
・金融類似商品に該当する場合は、源泉分離課税の対象となります。
・確定申告の必要性は、受け取った金額や利益の額によって判断する必要があります。
・生命保険料控除を活用することで、所得税・住民税の節税効果が期待できます。
積立保険は、将来の資金準備として有効な手段ですが、受け取り時の税金についても事前に理解しておくことが大切です。特に、契約者と受取人の設定や、受け取り方法の選択によって税負担が大きく変わることがあるため、契約時から計画的に検討することをおすすめします。
また、税制は改正されることがありますので、実際に保険金を受け取る際は最新の税制を確認し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することも重要です。適切な知識を持って積立保険を活用することで、効果的な資産形成と税金対策を両立させることができるでしょう。