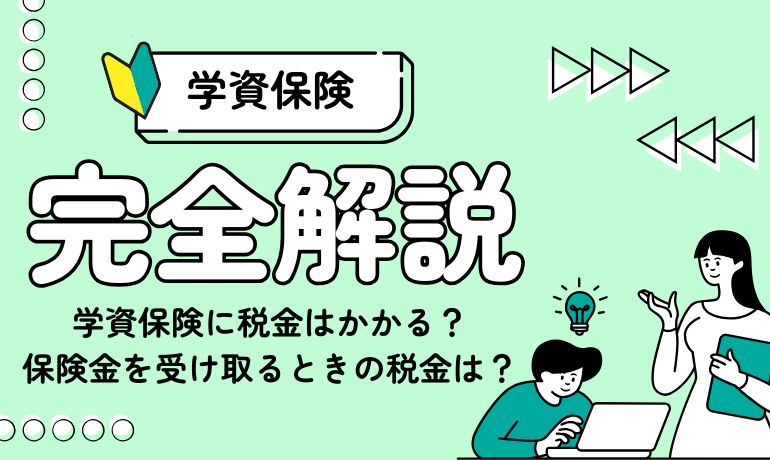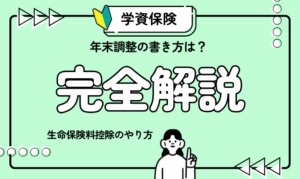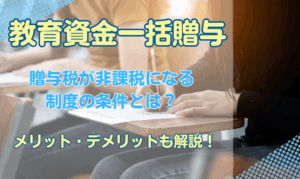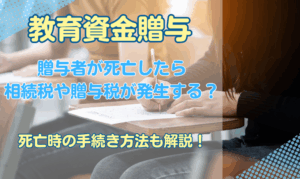子どもの教育資金を準備するために、学資保険に加入している方も多いでしょう。しかし、いざ祝金や満期保険金を受け取る際に気になるのが「税金はかかるのか」という点です。学資保険の保険金受け取りには税金がかかる場合とかからない場合があり、受け取り方や契約形態によって税金の種類も変わってきます。
この記事では、学資保険の保険金にかかる税金の種類から具体的な計算方法、確定申告の必要性まで詳しく解説します。学資保険を有効活用するためにも、税金の仕組みを正しく理解しておきましょう。
学資保険の受け取りには税金がかかる?
学資保険の保険金を受け取る際、多くの方が「税金取られるのか」「どのくらいの負担になるのか」と心配されるでしょう。結論から申し上げると、学資保険の受け取りには税金がかかる場合とかからない場合があります。
受け取った学資金は税金の対象になる
学資保険で受け取った学資金は、課税対象となります。ただし、金額やその他の収入などによって実際に税金が発生するかは変わってきます。
重要なポイントは、受け取った金額全体に税金がかかるわけではなく、利益の部分にのみ税金がかかるということです。さらに、受け取り方によっては特別控除もあるため、利益すべてが税金の対象になるわけではありません。
つまり、下ろす時やもらう時に自動的に税金が発生するわけではなく、利益額と控除額の関係によって税金の有無が決まります。
元本割れの場合は税金がかからない
学資保険が元本割れしている場合、つまり支払った保険料総額よりも受け取る保険金が少ない場合は、利益が出ていないため税金はかかりません。これは契約者と受取人が同じ場合に限ります。
返戻金が支払った保険料を下回り、返戻率が100%未満の場合は、利益や利息が発生していないため課税対象外となります。
受取り方や受取人によって税金の種類や金額も変わる
学資保険にかかる税金は、利益額だけでなく受取り方法や受取人によっても異なります。一括で受け取るか分割で受け取るか、契約者が受け取るか子どもが受け取るかによって、適用される税金の種類や計算方法が変わってくるのです。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険にかかる税金の種類
学資保険の保険金にかかる税金には、主に4つの種類があります。それぞれどのようなケースで課税されるのかを見ていきましょう。
所得税
所得税は、契約者と受取人が同じ場合にかかる税金です。学資保険の保険金を受け取った際の利益部分が所得として扱われ、所得税の対象となります。
一括で受け取る場合は「一時所得」として、分割で受け取る場合は「雑所得」として課税の対象です。所得税は国税であり、確定申告によって納税します。
住民税
住民税は、所得税と連動して課税される地方税です。学資保険の受け取りで所得税が発生する場合、同時に住民税も課税対象となります。住民税の税率は、一般的に10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)です。
贈与税
贈与税は、契約者と受取人が異なる場合にかかる税金です。例えば、祖父母が契約者となって保険料を支払い孫が受取人となっている場合や、親が契約者で子どもが受取人の場合などが該当します。
贈与税には基礎控除額があり、年間110万円以下の贈与であれば税金はかかりません。また、親から18歳以上の子への贈与は「特別贈与」として税率が優遇されます。
相続税
相続税は、契約者が亡くなった場合に適用される税金です。契約者の死亡により保険金が支払われる場合、その保険金は相続財産として扱われ、相続税の対象となります。
ただし、相続税には基礎控除額があり、「3000万円+600万円×法定相続人の数」までは非課税となります。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の保険金にかかる税金の計算方法
学資保険の税金計算は、契約形態や受け取り方法によって異なります。ここでは、具体的な計算方法を詳しく見ていきましょう。
契約者と受取人が同じ場合
契約者と受取人が同じ場合、受け取る保険金は所得税の対象となります。受け取り方法によって「一時所得」または「雑所得」として扱われます。
一括で受け取る場合:一時所得
満期保険金や祝金を一括で受け取る場合は、一時所得として課税されます。一時所得の計算式は以下の通りです。
一時所得の計算式
一時所得 = (受取保険金総額 – 支払保険料総額 – 特別控除額50万円)× 1/2
具体的な計算例を見てみましょう。
計算例1
- 支払保険料総額:300万円
- 受取保険金総額:350万円
- 利益:50万円
一時所得 = (350万円 – 300万円 – 50万円)× 1/2 = 0円
この場合、利益が50万円なので特別控除額50万円以下となり、一時所得は0円となります。つまり税金はかかりません。
では、利益がもっと大きい場合を見てみましょう。
計算例2
- 支払保険料総額:500万円
- 受取保険金総額:600万円
- 利益:100万円
一時所得 = (600万円 – 500万円 – 50万円)× 1/2 = 25万円
この場合の所得税額を計算してみます(他に所得がなく、所得税率が5%の場合)。
所得税額 = 25万円 × 5% = 12,500円
上記の計算から、学資保険により12,500円の所得税が発生することになります。
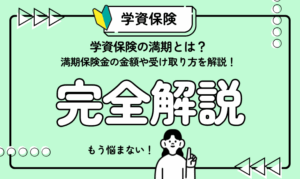
年金で受け取る場合:雑所得
学資保険を分割受取で受け取る場合は、雑所得として課税されます。雑所得の計算式は以下の通りです。
雑所得の計算式
雑所得 = 年間受取金額 – 年間受取金額×(支払保険料総額 ÷ 受取金額総額)
具体的な計算例を見てみましょう。
計算例
- 支払保険料総額:400万円
- 受取保険金総額:450万円
- 受取期間:5年間
- 年間受取金額:90万円
雑所得 = 90万円 – 90万円×(400万円÷450万円) = 10万円
この雑所得10万円に対して、所得税がかかります。所得税率を5%とすると、年間の所得税額は5,000円でます。
学資保険の雑所得がない場合の所得税と比較すると、年間5,000円の税負担が発生することになります。
契約者と受取人が違う場合
契約者と受取人が異なる場合は、贈与税の対象となります。贈与税は「一般贈与」と「特別贈与」に分かれ、それぞれ税率が異なります。
一般贈与の場合
一般贈与は、夫婦間や親と未成年の子、祖父母と孫などの間で行われる贈与です。
一般贈与の税率表
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
計算例
受取保険金が200万円の場合:
贈与税 = (200万円 – 110万円)× 10% = 9万円
特別贈与の場合
特別贈与は、祖父母や父母から18歳以上の子や孫への贈与に適用される優遇税制です。
特別贈与の税率表
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
計算例
受取保険金が300万円の場合:
贈与税 = (300万円 – 110万円)× 10% – 10万円 = 9万円
同じ金額でも、一般贈与と特別贈与では税負担が異なることがわかります。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
5つのケース別:学資保険の税金
学資保険は長期間に渡るケースが多いので、その中で契約状況が変わる場合も少なくありません。ここでは5つのケース別に、学資保険で発生する税金について紹介していきます。
学資保険を途中解約した場合
解約返戻金が発生し、その金額が払込総額を超えていれば、超過分に対して一時所得課税がかかります。解約返戻金が元本を下回っている場合は課税されません。
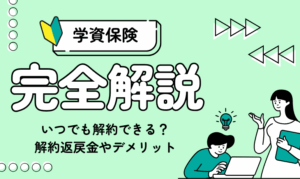
契約者が死亡した場合
「払込免除特約」付きの学資保険に入っていて契約者が死亡した場合、保険料の払込が免除されます。この時点で学資保険の保険金を受け取ることはないので、特に税金はかからないと思われがちです。しかし契約者と受取人が同じ場合は、受取人を変更する必要があります。その結果、配偶者や子供に保険金を受け取る権利が移転するため、相続税の対象となることがあります。
学資保険の名義変更した場合
離婚などで契約者を変更した場合、それまでの貯蓄分が移転されたとみなされ、贈与税がかかるケースがあります。
満期保険金を据え置きにした場合
据え置き期間中に発生した利息部分については、雑所得として課税対象になります。利息も所得として課税される点に注意が必要です。
学資保険の配当金を受け取った場合
学資保険の配当金は、基本的には課税対象になっていません。しかし受け取るタイミングによっては課税対象となるケースもあります。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
税金はいくら?学資保険の税金のシミュレーション
以下に、一括で受け取った場合の一時所得と税額の例を示します(契約者と受取人が同じ場合、年収300万円、特別控除50万円を適用)。
| 受取金額 | 払込保険料 | 利益 | 課税対象(一時所得) | 税金目安(所得税10%) |
| 100万円 120万円 | 80万円 80万円 | 20万円 40万円 | (20万−50万)×1/2=0円 (40万−50万)×1/2=0円 | 0円 0円 |
| 150万円 | 80万円 | 70万円 | (70万−50万)×1/2=10万円 | 1万円 |
| 200万円 | 100万円 | 100万円 | (100万−50万)×1/2=25万円 | 2.5万円 |
| 300万円 400万円 | 150万円 150万円 | 150万円 250万円 | (150万−50万)×1/2=50万円 (250万−50万)×1/2=100万円 | 5万円 10万円 |
| 500万円 | 200万円 | 300万円 | (300万−50万)×1/2=125万円 | 12.5万円 |
※実際の税率は所得に応じて変動します。また、住民税(約10%)も別途発生します。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の税金は確定申告しなかったらばれる?
一時所得・雑所得の金額が大きい場合や、保険会社から税務署に支払調書が提出されている場合、申告漏れが税務調査で発覚する可能性があります。意図的でなくても過少申告加算税や延滞税が発生することもあるため、必ず必要に応じて確定申告を行いましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
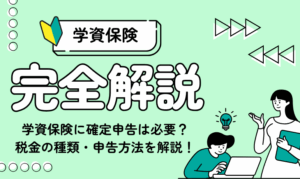
学資保険の保険料は税金控除の対象になる
学資保険の保険料は、「生命保険料控除」の対象です。毎年の年末調整や確定申告で最大4万円(旧契約なら5万円)まで控除できます。
生命保険料控除を受ける際は、以下のように就業形態に合わせて申告を行う必要があります。
・会社員 → 年末調整で申告
・個人事業主 → 確定申告で申告
控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽減されます。ただし学資保険に複数加入している場合でも、控除の上限は合算で計算される点に注意してください。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
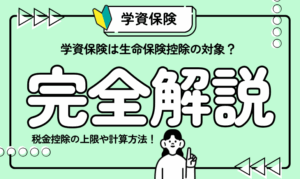
まとめ
- 学資保険の受け取りには税金がかかるケースがあるが、条件次第で非課税となる
- 税金の種類には一時所得・雑所得・贈与税・相続税がある
- 契約者と受取人、受け取り方によって課税内容が異なる
- 税額は控除や課税方法によって大きく変わるため、事前のシミュレーションが重要
- 確定申告を怠るとペナルティが課せられる可能性あり
- 学資保険の保険料は生命保険料控除の対象になる
正しく学資保険の税務知識を身につけて、損をしない資金計画を立てましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!