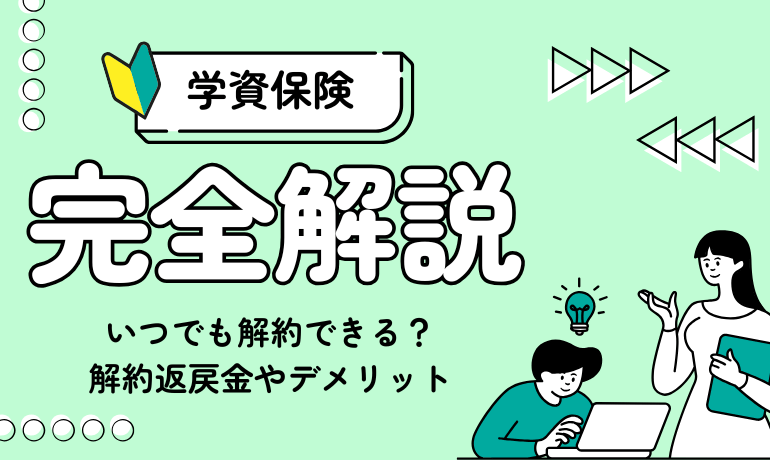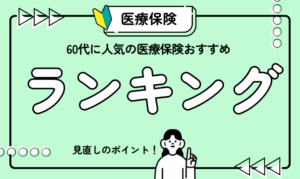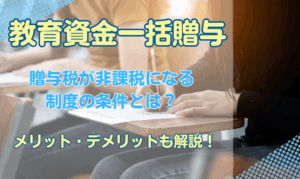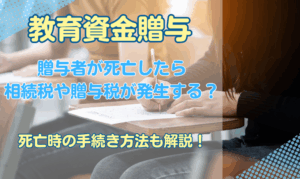学資保険に加入したものの、離婚や家計の事情で保険料の支払いが困難になり、解約を検討している方は少なくありません。学資保険は子供の教育資金を計画的に準備するための重要な保険ですが、やむを得ない事情で解約せざるを得ない場合もあります。
この記事では、学資保険の解約について知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。解約の可否から解約返戻金、デメリット、手続き方法まで、解約を検討している方が知っておくべき情報を包括的にお伝えします。
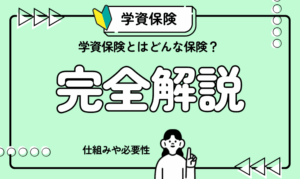
学資保険はいつでも解約できる!
学資保険は契約期間の途中解約が可能です。多くの方が「一度加入したら満期まで続けなければならない」と思い込んでいますが、実際には契約者の意思でいつでも解約することができます。
学資保険の途中解約は、子供の教育資金を準備するという本来の目的を果たせなくなるため推奨されませんが、家計の状況や生活環境の変化によってやむを得ない場合があります。離婚、収入減少、失業、病気など、さまざまな理由で保険料の支払いが困難になった際は、解約という選択肢があることを覚えておきましょう。
途中解約しても違約金や手数料は必要なし
学資保険を途中解約する場合、違約金や解約手数料などのペナルティは基本的に発生しません。これは多くの生命保険に共通する特徴で、契約者が解約を希望すれば、追加の費用負担なく手続きを進めることができます。
ただし、違約金がないからといって解約にデメリットがないわけではありません。途中解約には様々な不利益が伴うため、解約前にそれらを十分理解した上で判断することが重要です。特に、支払った保険料に対して解約返戻金が少なくなる「元本割れ」のリスクは大きなデメリットの一つです。
解約を検討する際は、違約金がかからないことに安心せず、総合的な損失を考慮して慎重に判断しましょう。
解約返戻金を受け取れることも多い
学資保険を解約した場合、多くのケースで解約返戻金を受け取ることができます。解約返戻金とは、これまで支払った保険料の一部が返還されるお金のことです。
解約返戻金の額は、加入からの経過期間、支払った保険料の総額、契約内容などによって決まります。一般的に、加入期間が長いほど解約返戻金は多くなる傾向にありますが、支払った保険料の総額を下回ることが多いのが現実です。
返金されるお金がいくら戻るかは、契約している保険会社や商品によって異なります。一部の契約では、特に加入初期の解約の場合、解約返戻金がゼロまたは非常に少額になることもあります。解約を検討する際は、事前に保険会社に連絡して、現時点での解約返戻金の概算額を確認することをおすすめします。
期間によって戻ってくるお金の割合は大きく変わるため、解約のタイミングも重要な要素となります。
解約できるのは契約者本人か委任状がある代理人のみ
学資保険の解約手続きができるのは、原則として契約者本人のみです。契約者以外の人が解約手続きを行うことはできません。これは、保険契約の重要性と契約者の権利を保護するための措置です。
ただし、契約者本人以外でも解約手続きが可能なケースがあります。それは、契約者から正式な委任状を受けた代理人による手続きです。委任状には契約者の署名・押印が必要で、代理人の身分証明書の提出も求められます。
契約者が病気で動けない場合、海外に長期滞在している場合、その他の事情で本人が手続きできない場合は、委任状による代理人手続きを検討しましょう。ただし、保険会社によって委任状の書式や必要書類が異なるため、事前に確認が必要です。
離婚するなら名義変更して続けることもできる
離婚が原因で学資保険の解約を検討している場合、解約以外に名義変更という選択肢があります。学資保険の契約者を夫から妻へ、または妻から夫へ変更することで、離婚後も保険を継続することが可能です。
離婚後の名義変更では、子供の親権者が契約者になることが一般的です。親権者が契約者になることで、子供の教育資金の管理と保険の管理を統一でき、将来的なトラブルを避けることができます。また、親権者でない方の経済状況に左右されずに保険を継続できるというメリットもあります。
別居中であっても名義変更の手続きは可能ですが、現契約者の同意が必要になります。離婚協議の際に学資保険の取り扱いについても話し合い、子供の将来のために最適な選択をすることが重要です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の解約に伴うデメリット
学資保険の解約には複数のデメリットが伴います。これらのデメリットを理解せずに解約してしまうと、後悔することになりかねません。解約を検討する際は、以下のデメリットを十分に検討した上で判断しましょう。
元金割れで損する可能性が高い
学資保険の途中解約における最大のデメリットは、元本割れによる損失です。元本割れとは、解約返戻金が支払った保険料の総額を下回ることを指します。
多くの学資保険では、契約初期の解約で大幅な元本割れが発生します。これは、保険料の一部が保険会社の運営費用や保険営業担当者への手数料として使われているためです。また、保険の保障部分にも費用が充当されているため、貯蓄部分だけでは支払った保険料を下回ってしまいます。
戻ってくるお金が支払った金額より少なくなることで、実質的に損失を被ることになります。特に加入から数年以内の解約では、解約返戻金が支払保険料の50-70%程度になることも珍しくありません。
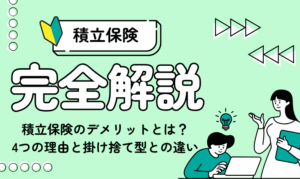
解約返戻金の計算シミュレーション
具体的な解約返戻金の計算例を見てみましょう。以下は一般的な学資保険の解約返戻金シミュレーションです。
契約条件
- 月額保険料:15,000円
- 満期保険金:200万円
- 契約期間:18年
- 保険料払込期間:10年
解約年数別の解約返戻金と返戻率
| 経過年数 | 払込保険料累計 | 解約返戻金 | 返戻率 |
| 3年 | 54万円 | 32万円 | 59.3% |
| 4年 | 72万円 | 48万円 | 66.7% |
| 5年 | 90万円 | 72万円 | 80.0% |
| 6年 | 108万円 | 95万円 | 88.0% |
| 7年目 | 126万円 | 118万円 | 93.7% |
| 8年 | 144万円 | 140万円 | 97.2% |
| 10年 | 180万円 | 185万円 | 102.8% |
この表からわかるように、払込完了前の解約では大幅な元本割れが発生し、特に初期の解約では損失が大きくなります。
未経過期間の保険料が返還されないこともある
学資保険の保険料は通常、月払いや年払いで前払いしています。月の途中で解約した場合、未経過期間の保険料が返還されないことがあります。
例えば、月払いの保険料を月初に支払った直後に解約した場合、その月の大部分は未経過期間となりますが、多くの保険会社では日割り計算による返還は行いません。年払いの場合も同様で、年の途中で解約しても未経過期間分の保険料は返還されないのが一般的です。
この仕組みは「払済」という概念に基づいており、支払った保険料は支払時点で保険期間分の対価として扱われます。解約のタイミングによっては、この未経過分も含めて損失となる可能性があります。
万が一のリスクに対する保証がなくなる
学資保険には、教育資金の積立機能だけでなく、契約者や被保険者に万が一のことがあった場合の保障機能も付いています。解約によってこれらの保障がすべて失われることも大きなデメリットです。
多くの学資保険には「保険料払込免除特約」が付帯されており、契約者が死亡・高度障害状態になった場合、以後の保険料の支払いが免除され、満期時には予定通り保険金を受け取ることができます。また、「育英年金特約」が付いている場合は、契約者に万が一のことがあった際に、年金形式で給付金を受け取ることができます。
これらの特約は、一家の大黒柱に万が一のことがあっても子供の教育資金を確保するための重要な保障です。解約によってこの安心を失うことは、経済的リスクの増大を意味します。
年齢によっては再加入できないも多い
一度学資保険を解約してしまうと、同じ条件での再加入は困難になります。学資保険には加入年齢の上限があり、子供の年齢が一定以上になると新たに加入することができません。
多くの学資保険では、子供の加入可能年齢は0歳から6歳程度までとなっています。それ以上の年齢になると、新規加入自体ができなくなります。また、契約者の年齢制限もあり、一定年齢を超えると加入できません。
仮に再加入が可能だったとしても、契約者の年齢上昇により保険料が高くなることがあります。また、健康状態の変化により、加入時に健康告知や医師の診査が必要になる場合もあります。
学資保険は解約した方がいい?解約のメリットとは
解約にデメリットが多いとはいえ、状況によっては解約した方が良い場合もあります。学資保険を解約することで得られるメリットも理解しておきましょう。
最大のメリットは、毎月の保険料支払いの負担がなくなることです。家計が厳しい状況では、月々15,000円から20,000円程度の保険料負担は大きな負担となります。解約によってこの負担から解放され、他の必要な支出に資金を回すことができます。
また、解約返戻金を受け取ることで、当面の生活費や急な出費に対応することも可能です。特に失業や病気などで収入が減少している場合、解約返戻金は重要な資金源となります。
もったいないと感じる方もいるかもしれませんが、より効率的な教育資金の準備方法を検討することもできます。例えば、新NISAや積立NISAを活用した投資信託での資産形成は、学資保険よりも高い利回りを期待できる可能性があります。ドル建ての投資商品なども選択肢の一つです。
ただし、これらの方法は市場リスクを伴うため、元本割れの可能性もあります。リスクとリターンを十分に理解した上で選択することが重要です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
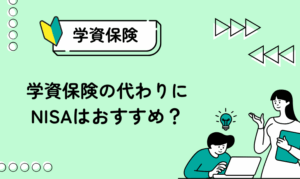
保険料が負担!解約せずに学資保険を続ける方法
保険料の支払いが困難だからといって、すぐに解約する必要はありません。学資保険を継続するための様々な方法があります。これらの方法を活用することで、無理な保険料負担を軽減しながら保険を継続することが可能です。
自動振替貸付制度を利用する
自動振替貸付制度は、保険料の支払いが困難な場合に、解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に保険料を立て替えてくれる制度です。契約者が特別な手続きをしなくても、保険料の支払期日に口座残高が不足している場合、自動的に適用されます。
この制度のメリットは、保険契約を継続できることと、手続きが不要なことです。一時的な資金不足で保険料が払えない場合でも、保険が失効することなく継続されます。
一方、デメリットもあります。立て替えられた保険料には利息が発生し、通常年3-6%程度の利率が適用されます。この利息は複利で計算されるため、長期間利用すると負担が大きくなります。また、貸付残高が解約返戻金額を超えると、保険契約が失効する可能性があります。
契約者貸付を利用する
契約者貸付は、解約返戻金の一定割合(通常80-90%)を限度として、保険会社からお金を借りることができる制度です。自動振替貸付とは異なり、契約者が能動的に申し込む必要があります。
契約者貸付を利用すれば、一時的な資金不足に対応しながら保険契約を継続することができます。借りたお金の使途は自由で、保険料の支払いだけでなく、生活費や教育費などにも使用できます。
ただし、貸付金には利息が発生し、返済しなければ保険契約が失効するリスクもあります。計画的な返済が必要な制度です。
受け取る保険金を減額する
保険金額を減額することで、毎月の保険料負担を軽減することができます。例えば、満期保険金200万円の契約を150万円に減額すれば、それに応じて保険料も下がります。
減額は部分解約と同様の扱いとなり、減額分に相当する解約返戻金を受け取ることができます。この方法なら、保険契約を完全に解約することなく負担を軽減できます。
ただし、減額により将来受け取れる保険金も少なくなるため、教育資金の準備という本来の目的を果たせなくなる可能性があります。
特約を解約する
学資保険には様々な特約が付帯されていることがあります。これらの特約を解約することで、保険料を削減することができます。
例えば、育英年金特約、医療特約、災害特約などを解約すれば、その分の保険料負担がなくなります。主契約である学資保険部分は維持しながら、付加的な保障を削ることで継続しやすくなります。
特約の解約は保障内容の変更を伴うため、本当に必要のない特約かどうかを慎重に検討する必要があります。
払済保険に変更
払済保険とは保険料の払込を中止し、その時点での解約返戻金をもとに保険期間は変えずに保険金額を下げた保険に変更することです。
この方法を利用すれば、以後の保険料負担なしで保険契約を継続することができます。保険金額は下がりますが、満期時には一定の保険金を受け取ることが可能です。
払済保険への変更は、一定の解約返戻金が蓄積されている場合のみ可能で、契約初期では利用できないことがあります。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の解約のやり方と注意点
学資保険を解約する際は、正しい手続きを踏む必要があります。手続きの流れと注意すべきポイントを詳しく説明します。
手続きのやり方と必要書類
学資保険の解約手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
1. 保険会社への連絡
まず、契約している保険会社のコールセンターに電話で連絡します。最近では、インターネットでの手続きを受け付けている保険会社も増えています。ネットでの手続きが可能な場合は、24時間いつでも申し込みができるため便利です。
2. 解約請求書類の取得
保険会社から解約に必要な書類が送付されます。郵送のほか、営業所での受け取りやホームページからのダウンロードが可能な場合もあります。
3. 必要書類の準備と提出
解約請求書に必要事項を記入し、必要書類と併せて保険会社に提出します。
一般的な必要書類
- 解約請求書(保険会社指定の様式)
- 保険証券
- 契約者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑(契約時に届け出た印鑑)
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
必要なものは保険会社によって異なるため、事前に確認することが重要です。
解約返戻金の振り込みに必要な日数
解約手続きが完了してから解約返戻金が振り込まれるまでの期間は、一般的に1週間から2週間程度です。ただし、提出書類に不備があった場合や、保険会社の審査に時間がかかる場合はさらに日数を要することがあります。
いつ振り込まれるかは、手続き完了後に保険会社から通知されます。何日かかるかは保険会社によって異なりますが、多くの場合、書類提出から10営業日以内には入金されます。
急いでお金が必要な場合は、事前に保険会社に振り込み予定日を確認しておくと安心です。
損をしない解約のタイミング
解約のタイミングによって、損失を最小限に抑えることができる場合があります。特に注意すべきポイントを以下に示します。
月の境目での解約
月払いの場合は、新しい月の保険料が引き落とされる前に解約手続きを完了させることで、余分な保険料の支払いを避けることができます。
元本割れリスクが減るタイミング
多くの学資保険では、契約してから2-3年は大幅な元本割れが発生します。可能であれば、返戻率が改善する時期まで継続することを検討しましょう。
2010年3月以前の契約の場合
2010年3月以前に契約した学資保険の中には、責任準備金の計算方法が現在と異なるものがあります。これらの契約では、月の途中で解約すると未経過分の保険料が返還されない可能性が高いため、月末での解約がおすすめです。
解約した場合の税金と確定申告
学資保険を解約した際に受け取る解約返戻金には、税金がかかる場合があります。税務上の取り扱いを正しく理解しておくことが重要です。
一時所得として課税
解約返戻金は、原則として一時所得として所得税の課税対象となります。ただし、以下の計算で求められる金額が課税対象です。
(解約返戻金 – 支払保険料総額 – 特別控除額50万円)× 1/2
この計算で求められた金額が他の所得と合算されて課税されます。
課税されないケース
多くの場合、学資保険の解約では元本割れが発生するため、実際に課税されることは少ないです。解約返戻金が支払保険料総額を下回る場合は、課税対象となる一時所得は発生しません。
確定申告の必要性
給与所得者の場合、一時所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、他の一時所得がある場合は合算して計算する必要があります。
年末調整では学資保険の解約返戻金は処理されないため、課税対象となる場合は翌年の確定申告で申告する必要があります。
贈与税に注意
契約者と解約返戻金の受取人が異なる場合は、贈与税の対象となる可能性があります。特に、夫が契約者で妻が解約手続きを行う場合などは注意が必要です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
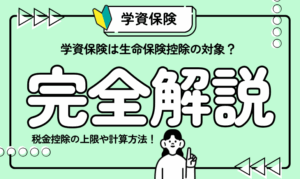
生活保護や自己破産の場合は学資保険の解約は必要?
特別な事情により生活保護を受給する場合や自己破産をする場合、学資保険の取り扱いについて知っておく必要があります。
生活保護の場合
生活保護を申請する際、学資保険などの資産は原則として処分対象となります。ただし、解約返戻金が少額の場合や、子供の将来のために必要と認められる場合は、保有が認められることもあります。
生活保護の申請前に福祉事務所に相談し、学資保険の取り扱いについて確認することが重要です。自己判断で解約してしまう前に、必ず専門機関に相談しましょう。
自己破産の場合
自己破産手続きにおいて、学資保険の解約返戻金は財産として扱われます。解約返戻金が一定額以上の場合は、破産財団に組み入れられ、債権者への配当原資となります。
ただし、解約返戻金が少額の場合や、自由財産の範囲内の場合は、保険契約を維持できる可能性があります。自己破産を検討している場合は、弁護士などの専門家に相談し、学資保険の取り扱いについて適切なアドバイスを受けることが重要です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
まとめ
学資保険の解約は可能ですが、多くのデメリットを伴います。特に元本割れによる損失は大きく、解約前に十分な検討が必要です。
保険料の支払いが困難な場合は、まず解約以外の方法を検討しましょう。自動振替貸付制度、契約者貸付、減額、払済保険への変更など、様々な選択肢があります。
どうしても解約が必要な場合は適切な手続きを踏み、税務上の取り扱いにも注意が必要です。解約のタイミングも重要な要素となるため、慎重に判断することが大切です。
学資保険は子供の将来のための重要な準備です。解約を検討する際は短期的な視点だけでなく、長期的な影響も含めて総合的に判断することをおすすめします。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!