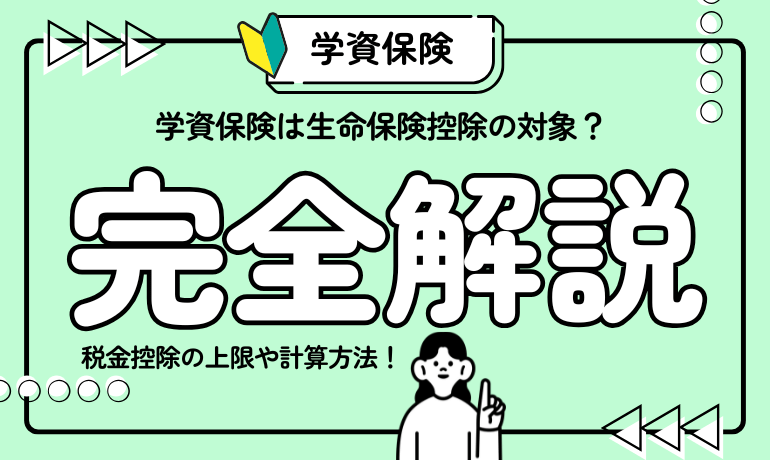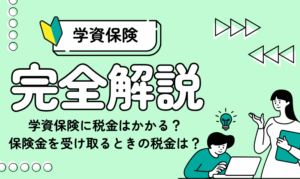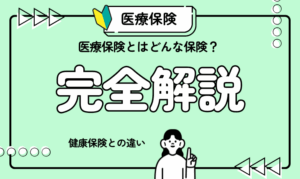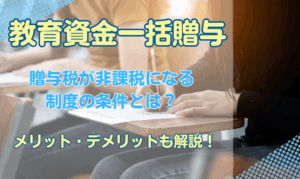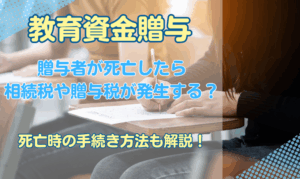子供の教育資金の準備として学資保険に加入している家庭は多いですが、学資保険の保険料が税金控除の対象になることをご存知でしょうか。適切な手続きを行うことで、所得税や住民税の負担を軽減できます。
しかし、控除の仕組みや申請方法について詳しく知らない方も多いのが現状です。そこでこの記事では、学資保険の税金控除について、初めて手続きを行う方にもわかりやすく解説します。控除の対象となる条件や控除額の計算方法、申請時の注意点まで詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
学資保険は税金控除の対象になる?
学資保険への加入を検討している方や、すでに加入している方にとって、税金控除の対象になるかどうかは重要なポイントです。結論から言うと、学資保険は生命保険料控除の対象となり、適切な手続きを行うことで税金の負担を軽減できます。
学資保険の保険料は一般生命保険料の控除対象
学資保険の保険料は、生命保険料控除の中で「一般生命保険料控除」の区分に該当します。この控除制度により、1年間で支払った学資保険の保険料の一部が所得から差し引かれ、結果として所得税と住民税の負担が軽減されます。
控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った保険料の金額です。月払いの場合は12ヶ月分、半年払いの場合は年間で支払った回数分の保険料が対象となります。
この控除制度を利用することで得られるメリットは、直接的な税金の負担軽減です。所得税は国に納める税金、住民税は都道府県や市区町村に納める税金ですが、どちらも学資保険の保険料控除により軽減されます。個人年金保険とは異なり、学資保険は一般生命保険料控除の枠組みに含まれるため、他の生命保険と合算して控除額が計算されることも重要なポイントです。
控除するには年末調整か確定申告が必要
学資保険の保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告での手続きが必要です。自動的に控除が適用されることはありませんので、必ず手続きを行いましょう。
会社員や公務員の場合、通常は年末調整で控除の手続きを行います。勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、保険会社から送付される控除証明書を添付して提出します。年末調整で適切に手続きを行えば、12月の給与や賞与で控除分が還付されるか、翌年の住民税が軽減されます。
一方、個人事業主やフリーランスの方は確定申告で控除の手続きを行います。また、会社員でも年末調整で控除の申請を忘れた場合や、年末調整後に学資保険に加入した場合は、確定申告での手続きが必要です。確定申告書の生命保険料控除の欄に必要事項を記入し、控除証明書を添付して税務署に提出します。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
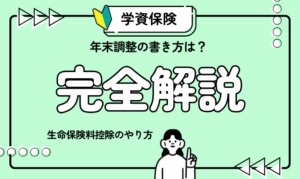
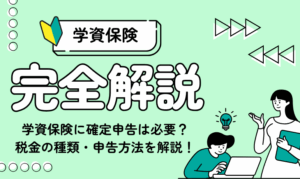
学資保険の税金の控除額はいくら?上限と計算方法
学資保険の控除額は、契約時期や支払保険料の金額によって異なります。現在の税制では、平成24年1月1日以降に契約した保険には「新制度」、それ以前に契約した保険には「旧制度」が適用されます。どちらの制度が適用されるかによって、控除額の計算方法と上限額が変わるのです。
所得税の控除額
所得税の控除額は、支払った保険料の金額に応じて段階的に設定されています。新制度と旧制度で計算方法が異なるため、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
新制度(平成24年1月1日以降契約)の場合:
- 年間支払保険料20,000円以下:
支払保険料全額 - 年間支払保険料20,001円〜40,000円:
支払保険料×1/2+10,000円 - 年間支払保険料40,001円〜80,000円:
支払保険料×1/4+20,000円 - 年間支払保険料80,001円以上:
一律40,000円(上限)
旧制度(平成23年12月31日以前契約)の場合:
- 年間支払保険料25,000円以下:
支払保険料全額 - 年間支払保険料25,001円〜50,000円:
支払保険料×1/2+12,500円 - 年間支払保険料50,001円〜100,000円:
支払保険料×1/4+25,000円 - 年間支払保険料100,001円以上:
一律50,000円(上限)
ここで、具体的な計算例を見てみましょう。新制度で年間保険料が60,000円の場合、控除額は60,000円×1/4+20,000円=35,000円となります。所得税率が10%の方であれば、35,000円×10%=3,500円の所得税が軽減されます。
住民税の控除額
住民税の控除額は、所得税よりも上限が低く設定されています。
新制度の場合:
- 年間支払保険料12,000円以下:
支払保険料全額 - 年間支払保険料12,001円〜32,000円:
支払保険料×1/2+6,000円 - 年間支払保険料32,001円〜56,000円:
支払保険料×1/4+14,000円 - 年間支払保険料56,001円以上:
一律28,000円(上限)
旧制度の場合:
- 年間支払保険料15,000円以下:
支払保険料全額 - 年間支払保険料15,001円〜40,000円:
支払保険料×1/2+7,500円 - 年間支払保険料40,001円〜70,000円:
支払保険料×1/4+17,500円 - 年間支払保険料70,001円以上:
一律35,000円(上限)
先ほどと同じく、新制度で年間保険料が60,000円の場合、控除額は上限の28,000円となります。住民税の税率は一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)のため、控除額に10%を乗じた2,800円が軽減されます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の税金控除をするときの注意点
学資保険の税金控除を申請する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらの点を理解していないと、期待していた控除を受けられなかったり、計算した控除額と実際の控除額に差が生じたりする可能性があります。
一括払いでは一度しか控除できない
学資保険の保険料を一括払い(一時払い)で支払った場合、控除を受けられるのは支払いを行った年のみです。翌年以降は保険料の支払いがないため、控除の対象となりません。
例えば、新制度で200万円を一括払いした場合、その年の控除額は上限の40,000円です。上限を超えた分の保険料は、控除の観点では無駄になってしまいます。
ただし、全期前納の場合は取り扱いが異なります。全期前納とは、将来の保険料をまとめて前払いする方法ですが、保険会社が各年度に充当する金額に応じて、毎年控除を受けることが可能です。一括払いと全期前納では控除の取り扱いが大きく異なるため、加入時に確認しておくことが重要です。
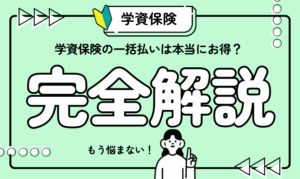
保険料を払っている人しか控除できない
学資保険の控除を受けられるのは、実際に保険料を支払っている人に限られます。契約者と保険料の支払者が異なる場合は、支払者が控除を受けることになります。
共働き夫婦のケースで、夫が契約者となり妻の口座から保険料を引き落としている場合、控除を受けられるのは実際に支払いを行っている妻です。つまり、年末調整や確定申告では妻が控除の申請を行う必要があります。
契約者と支払者が違う場合は、保険会社から送付される控除証明書の宛名が支払者名義になっているかを確認しましょう。宛名が契約者名義になっている場合は、保険会社に連絡して支払者名義での控除証明書の発行を依頼する必要があります。
未払い分は控除の対象にならない
生命保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った保険料のみです。未払いの保険料がある場合、その分は控除の対象になりません。
月払いの場合、12月分の保険料が翌年1月に引き落とされるケースがあります。この場合、12月分の保険料は翌年の控除対象となり、申請年の控除対象には含まれません。また、保険料の引き落としができずに未払いとなっている期間がある場合も、その期間の保険料は控除対象外となります。
控除証明書には、実際に支払った保険料の金額が記載されているため、この金額を基に控除額を計算することになります。
控除枠には他の保険も含まれる
学資保険は一般生命保険料控除の対象となりますが、この控除枠には他の生命保険も含まれます。終身保険、定期保険なども同じ控除枠を使用するため、複数の保険に加入している場合は合算して控除額を計算します。
例えば、学資保険で年間30,000円、終身保険で年間40,000円の保険料を支払っている場合、合計保険料は70,000円です。新制度の場合、この金額での控除額は70,000円×1/4+20,000円=37,500円となります。
すでに他の生命保険で控除上限に達している場合、学資保険の保険料を追加で支払っても控除額は増えません。加入前に、現在の保険料控除の状況を確認しておくことが重要です。
受取人が親族以外だと控除できない
学資保険の控除を受けるためには、保険金の受取人が契約者本人または配偶者、その他の親族である必要があります。親族以外が受取人に指定されている場合は、控除の対象となりません。
親族の範囲は、6親等以内の血族と3親等以内の姻族です。子供、両親、兄弟姉妹、祖父母、孫などは親族に該当しますが、友人や恋人などは親族に該当しません。
学資保険の場合、通常は子供が被保険者となり、親が契約者かつ受取人となるケースが多いためこの条件に抵触することは少ないですが、契約内容を確認しておきましょう。
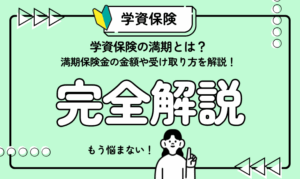
遡って控除申請できるのは5年まで
学資保険の控除申請を忘れていた場合や控除の存在を知らなかった場合でも、過去5年分まで遡って控除の申請を行うことができます。これを「更正の請求」といいます。
過去分の控除申請を行う場合は、該当年分の控除証明書が必要です。控除証明書を紛失している場合は、保険会社に連絡して再発行を依頼しましょう。多くの保険会社では、過去数年分の控除証明書の再発行に対応しています。
ただし、5年を超えた分については時効により申請できませんので、控除の申請漏れに気づいたら早めに手続きを行うことが大切です。
ふるさと納税の控除上限額が減る
生命保険料控除とふるさと納税の控除は併用できますが、生命保険料控除により課税所得が減ることで、ふるさと納税の控除上限額も減少します。
なぜなら、ふるさと納税の控除上限額は所得税率に基づいて計算されるため、生命保険料控除により所得税率が下がる場合はふるさと納税の上限額も下がるのです。また、住民税の控除により、ふるさと納税の住民税控除の基となる金額も減少します。
具体的な影響額は個人の所得状況により異なりますが、両方の制度を利用する場合は相互の影響を考慮して寄付額を検討することが重要です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の税金控除の申告方法
学資保険の税金控除を受けるための申告方法は、会社員などの給与所得者と個人事業主などで異なります。最後に、それぞれの手続きの流れと必要書類について詳しく解説します。
年末調整のやり方
会社員や公務員の方は、通常、年末調整で学資保険の控除手続きを行います。年末調整は勤務先が代行して行う所得税の精算手続きで、毎年10月から12月にかけて実施されます。
年末調整で学資保険の控除を受けるための手順は、以下の通りです。
まず、勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書」が配布されます。この書類の「一般の生命保険料」の欄に、学資保険の情報を記入します。記入項目は、保険会社名、保険等の種類(学資保険または こども保険)、保険期間、契約者氏名、保険金等の受取人氏名、続柄、年間支払保険料などです。
年間支払保険料については、保険会社から送付される控除証明書に記載されている金額を記入します。控除証明書は通常10月頃に送付されますが、年末調整の書類提出期限に間に合わない場合は、保険料の払込予定額での申告も可能です。
控除証明書は、申告書と一緒に勤務先に提出する必要があります。原本の提出が原則ですが、コピーでも認められる場合があるため、勤務先の指示に従いましょう。
また、控除証明書が届かない場合の対処法についても知っておくことが重要です。控除証明書が紛失や未着の場合は、保険会社に連絡して再発行を依頼しましょう。多くの保険会社では電話やインターネットで再発行の手続きが可能で、通常1〜2週間程度で再発行されます。年末調整の締切に間に合わない場合は、翌年の確定申告で控除を受けることもできます。
確定申告のやり方
個人事業主やフリーランスの方、年末調整で控除申請を忘れた会社員の方は、確定申告で学資保険の控除手続きを行います。
確定申告での控除手続きの流れは、以下の通りです。
まず、確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の欄にある「生命保険料控除」の項目を見つけます。ここに、一般の生命保険料として学資保険の控除額を記入します。
控除額の計算は、控除証明書に記載されている年間支払保険料を基に、前述の計算式を使用して行います。新制度か旧制度かを確認し、適切な計算式を使用することが重要です。
確定申告書には、控除証明書の原本を添付する必要があります。e-Taxで電子申告を行う場合は、控除証明書の内容を入力し、原本は自宅で保管します。ただし、税務署から提出を求められた場合は提示する必要があるため、大切に保管しておきましょう。
確定申告の期限は、翌年の2月16日から3月15日までです。この期間内に税務署に申告書を提出するか、e-Taxで電子申告を行います。控除により還付税額が発生する場合は、申告後1〜2ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
まとめ
学資保険は生命保険料控除の対象となり、適切な手続きを行うことで所得税や住民税の負担を軽減できる重要な制度です。控除を受けるためには年末調整または確定申告での手続きが必要で、自動的に適用されることはありません。
控除額は契約時期により新制度と旧制度に分かれ、支払保険料に応じて段階的に設定されています。所得税では最大40,000円(旧制度は50,000円)、住民税では最大28,000円(旧制度は35,000円)の控除を受けることができます。
ただし、一括払いでは一度しか控除できない、実際の支払者のみが控除を受けられる、他の生命保険と合算して上限が決まるなど、いくつかの注意点があります。また、ふるさと納税の控除上限額への影響についても考慮しなければなりません。
控除の申請を忘れた場合でも、5年以内であれば遡って申請することができます。学資保険に加入している方は、これらの制度を有効活用して税負担の軽減を図りましょう。控除に関して不明な点がある場合は、保険会社や税務署、税理士などに相談することをおすすめします。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!