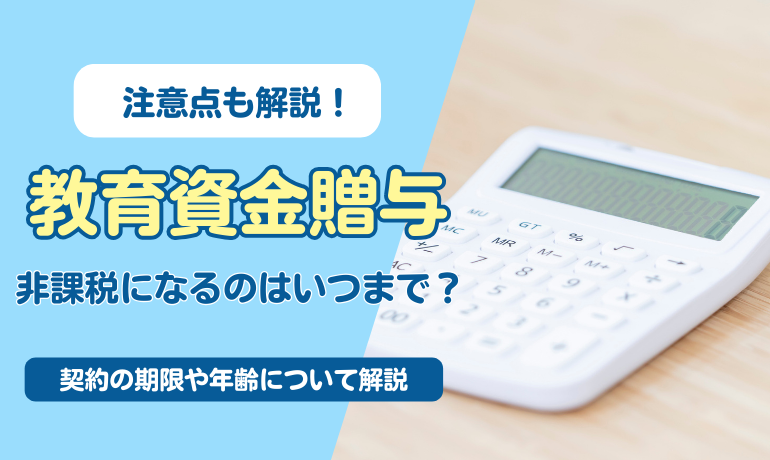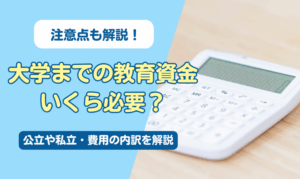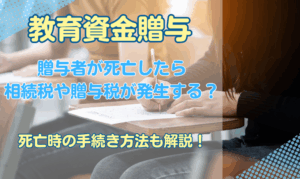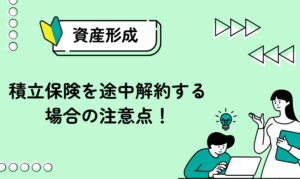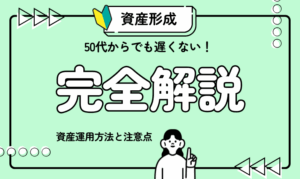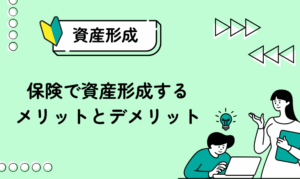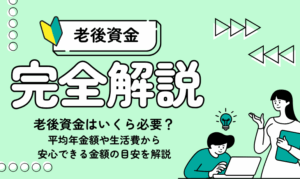お子さんやお孫さんの将来のために、大学の入学金や授業料、あるいは塾や習い事の費用など、まとまった教育資金を援助したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。そんな時に活用したいのが「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」です。
この制度を利用すれば、最大1,500万円までの教育資金の贈与が非課税になるため、子や孫の教育を力強くサポートできます。しかし、「この制度はいつまで使えるの?」「贈与を受ける子どもの年齢に制限はある?」「贈与されたお金はいつまでに使い切ればいい?」といった期限に関する疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、「教育資金贈与はいつまで?」という疑問をお持ちの方に向けて、制度の契約期限や対象となる年齢、資金の利用期限について、網羅的に解説します。制度の概要から具体的な手続きの流れ、注意点まで詳しく説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。
教育資金贈与の制度が使えるのはいつまで?
まず、教育資金贈与の非課税制度の基本的な概要と、最も重要な「制度の利用期限」について解説します。
教育資金贈与とはどんな制度か
教育資金贈与の非課税制度とは、正式名称を「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」といいます。これは、30歳未満の子や孫(受贈者)のために、その直系尊属である祖父母や父母(贈与者)が、金融機関等との教育資金管理契約に基づき教育資金を一括で拠出した場合、受贈者一人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
通常、個人から年間110万円を超える財産の贈与を受けると贈与税が課税されます。しかし、この特例を使えば、将来必要となる教育資金をまとまった金額で、かつ非課税で次世代へ移転させることが可能です。この制度は、子育て世代の経済的負担を軽減し、教育の機会を充実させること、そして高齢者世代が持つ資産を早期に若い世代へ移転させることで経済を活性化させる目的で創設されました。
贈与する側(祖父母・父母)にとっては、相続税対策としても有効な手段となり得ます。一方、贈与される側(子・孫)にとっては、学費の心配をせずに学業に専念できるという大きなメリットがあります。
非課税が適用されるのは2026年3月31日まで
多くの方が最も知りたい「この制度はいつまで利用できるのか?」という疑問ですが、現在のところ、非課税の特例が適用される教育資金管理契約の締結期限は「2026年3月31日まで」となっています。
ここで重要なのは、この「2026年3月31日」という期限が何を指すのかを正確に理解することです。これは、「贈与者(祖父母など)が金融機関に専用口座を開設し、非課税の対象となる資金の入金を完了させる期限」を意味します。つまり、この日までに契約と入金の手続きを終えれば、その資金は非課税の対象となります。
贈与された教育資金をすべて使い切る期限ではない、という点を押さえておきましょう。2026年3月31日までに契約・入金した資金であれば、その後、受贈者(子・孫)が30歳になるまで、非課税の枠内で教育費として引き出して使うことができます。
この制度は2013年4月1日に開始されて以来、何度か期限の延長が繰り返されてきました。直近では、2023年度の税制改正によって、当初の2023年3月31日から3年間延長され、現在の2026年3月31日という期限が設定されました。
2026年4月1日以降はどうなる?
では、2026年4月1日以降、この制度はどうなるのでしょうか。現時点では、再延長されるか、あるいはこのまま廃止・終了となるかは未定です。
過去の経緯を見ると、延長が繰り返されてきた実績があるため、再び延長される可能性はゼロではありません。しかし一方で、政府の税制調査会では、こうした富裕層向けの優遇措置が格差を固定化するとの指摘もあり、制度の見直しや廃止に向けた議論も行われています。
実際に、2023年度の税制改正では、贈与者が死亡した場合の相続税の取り扱いが厳しくなるなど、制度内容は少しずつ変化しています。そのため、「次も延長されるだろう」と安易に考えず、制度の利用を検討している方は、現行の期限である2026年3月31日までに手続きを完了させることを前提に、計画を立てるのが賢明です。
金融機関に入金できるのはいつまで?
制度上の契約期限は2026年3月31日ですが、注意したいのは、金融機関での手続きには時間がかかるという点です。期限である3月31日の当日に金融機関へ行っても、その日のうちに契約を完了できない可能性が非常に高いでしょう。
口座開設の申し込み、必要書類の確認、贈与契約書の作成、そして資金の入金といった一連の手続きには、数週間程度の余裕を見ておく必要があります。
そのため、多くの金融機関では、制度上の期限よりも早い日付を自社の申込受付最終日として設定しています。
「まだ期限まで時間がある」と油断していると、いざ手続きをしようとしたときには申込期間が終了していた、という事態になりかねません。この制度の利用を決めたら、できるだけ早く金融機関に相談し、具体的なスケジュールを確認しておくことが重要です。
受贈者の年齢は29歳まで
この制度を利用できる受贈者(贈与を受ける子や孫)には年齢制限があります。具体的には、金融機関と教育資金管理契約を結ぶ日において、29歳以下(30歳未満)であることが必要です。
契約日に30歳の誕生日を迎えている場合は、この制度を利用することはできません。例えば、2026年3月10日に30歳になる方が利用したい場合は、その前日の3月9日までに契約を完了させる必要があります。
なお、この年齢要件はあくまで「契約日時点」のものです。契約時に29歳であれば、その後30歳になったとしても契約自体は有効に継続されます。
30歳になっても学生なら40歳まで延長できる
原則として、この制度の契約は受贈者が30歳に達した日に終了します。しかし、これには例外的な延長措置が設けられています。
もし受贈者が30歳に達した時点で、大学院に在学しているなど学校等に在学している場合は、契約を終了せずに継続することが可能です。この場合、在学している期間中は1年ごとに契約期間を更新でき、最長で40歳に達する日まで延長することができます。
例えば、大学卒業後に大学院の博士課程に進学した場合や、社会人になってから大学に入り直した場合などがこのケースに該当します。
この延長措置を利用するためには、30歳に達した後に、在学中であることを証明する書類(在学証明書など)を金融機関に提出する手続きが必要です。自動的に延長されるわけではないため、該当する場合は忘れずに手続きを行いましょう。
贈与された教育資金はいつまでに使えばOK?
次に、贈与された1,500万円の資金を「いつまでに使い切る必要があるのか」という点について解説します。使い切れなかった場合にどうなるのかは、多くの方が気にするポイントです。
結論から言うと、「この日までに絶対に使い切りなさい」という明確な日付があるわけではありません。しかし、特定のタイミングで口座に残高があると、その残高が課税対象になってしまうケースがあります。
主に以下の2つのケースで、使いきれなかった資金に税金がかかる可能性があります。
- 受贈者が30歳に達したとき
- 契約期間中に贈与者が亡くなったとき
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
30歳になったら使い切れない分は贈与税の対象になる
前述の延長措置を利用しない限り、この制度の教育資金管理契約は、受贈者が30歳に達した日に終了します。
この契約終了時点で、教育資金口座に使い切れていない残高がある場合、その残高は「その年に受贈者が贈与者から受け取った通常の贈与」として扱われ、贈与税の課税対象となります。
【計算例】
- 30歳到達時の口座残高:500万円
- 贈与税の基礎控除:110万円
- 課税対象額:500万円 – 110万円 = 390万円
この390万円に対して、所定の税率を掛けた金額が贈与税として課税されます。この年に、他の人からも贈与を受けていれば、それも合算して計算する必要があります。
このように、30歳までに資金を使い切れないと、せっかくの非課税メリットが薄れてしまう可能性があります。受贈者の年齢や進路を考慮し、本当に必要な金額を見極めて贈与額を決めることが重要です。
贈与者が亡くなると相続税の対象になることがある
もう一つの重要な注意点が、契約期間中に贈与者(祖父母・父母)が亡くなった場合です。この場合、原則として死亡日時点での教育資金口座の残高は、贈与者の相続財産に加算され相続税の課税対象となります。
ただし、これには重要な例外があります。以下のいずれかのケースに該当する場合、贈与者が亡くなっても、口座残高は相続税の対象にはなりません。
- 受贈者(子・孫)が23歳未満である場合
- 受贈者が学校等に在学している場合
- 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる訓練を受けている場合
この例外規定は、2021年度の税制改正で設けられたものです。それ以前は、受贈者の状況にかかわらず、贈与者の死亡時には残高全額が相続税の対象とされていました。この改正により、若年層や学生への配慮がなされ、制度がより使いやすくなったと言えます。
しかし、例えば受贈者が25歳で、すでに学校を卒業して社会人として働いているような状況で贈与者が亡くなると、口座残高は相続税の対象となってしまいます。
一方で、この制度には相続税対策としてのメリットもあります。通常の生前贈与では、贈与者が亡くなる前3年〜7年以内(2024年1月1日以降の贈与から段階的に延長)に行われた贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算する「生前贈与加算」の対象となります。しかし、この教育資金贈与の特例を利用した贈与は、生前贈与加算の対象外です。
つまり、贈与者が亡くなる直前にこの制度で贈与を行ったとしても、その贈与額が相続財産に持ち戻されることはありません(ただし、死亡時の残高は上記の条件付きで課税対象)。これは、相続税対策を考える上で大きな利点と言えるでしょう。
教育資金贈与の対象になるものとは
この制度で非課税となる「教育資金」には、具体的にどのような費用が含まれるのでしょうか。対象となる範囲は細かく定められています。大きく分けると、「学校等に対して直接支払われる金銭」と「学校等以外(塾や習い事など)の者に支払われる金銭」の2種類があり、それぞれ非課税の上限額が異なります。
| 費用の種類 | 非課税限度額 | 主な具体例 |
| 学校等に支払う金銭 | 1,500万円 | 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、学用品の購入費(学校が指定・斡旋するもの)、給食費、修学旅行費、学校が徴収するPTA会費など |
| 学校等以外に支払う金銭 | 500万円 (上記1,500万円の内枠) | 学習塾や家庭教師の謝礼、そろばんやピアノ、水泳などの習い事の月謝、通学定期券代、留学のための渡航費、教科書代、参考書代など |
非課税対象となる教育資金の具体例
【学校等に支払う金銭(上限1,500万円)】
ここでの「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校、専修学校、および一定の外国人学校などを指します。これらの教育機関に直接支払う以下のような費用が対象です。
- 入学金、入園料、授業料、保育料、施設設備費、検定料 など
- 学用品費、修学旅行費、学校給食費 などで、学校側が保護者から一括して徴収し、支払うことが明らかなもの
【学校等以外に支払う金銭(上限500万円)】
学校以外に支払う教育関連費用も、最大500万円まで非課税の対象となります。ただし、この500万円は1,500万円の枠の中に含まれます。例えば、塾の費用として300万円を使った場合、学校等に支払える非課税枠は残り1,200万円となります。
対象となるのは、教育を受けるために直接必要と認められる以下のような費用です。
- 教育サービスに関する費用
- 学習塾、そろばん、習字、ピアノ、バレエ、水泳、野球、サッカーなどの指導対価
- 家庭教師への謝礼(個人契約も可)
- オンライン塾や通信教育の費用
- 物品購入に関する費用
- 教科書、参考書、問題集などの購入費
- 交通費など
- 通学定期券代
- 留学のための渡航費(片道分)
注意点として、塾や習い事の費用が対象となるのは、受贈者が29歳以下の場合に限られます。
非課税の対象にならない費用の例
一方で、教育に関連していても、この制度の対象とはならない費用もあります。判断に迷うケースも多いため、事前に確認が必要です。
- 下宿やアパートの家賃、敷金、礼金、生活費
- 留学中の滞在費や遊興費
- 大学の同窓会費
- 部活動で使うユニフォームや道具の購入費(※学校に支払う「部費」は対象となる場合があります)
- パソコンやタブレット端末の購入費(※授業で必須と学校が証明する場合は対象となる可能性があります)
- 自動車学校の費用(※運送業への就職に必須など、特定の条件を満たす場合は対象となる可能性があります)
- 奨学金の返済
これらの費用は、教育に付随するものであっても「直接的な教育費」とはみなされず、非課税の対象外となります。対象になるかどうか不安な場合は、契約する金融機関や税務署に問い合わせるのが確実です。
教育資金贈与の流れとやり方
最後に、実際に教育資金贈与の非課税制度を利用する場合の、具体的な手続きの流れとやり方を解説します。手続きが面倒に感じられるかもしれませんが、ステップごとに理解すればスムーズに進めることができます。
Step 1: 贈与者と受贈者で合意し、金融機関を選ぶ
まず、贈与者(祖父母・父母)と受贈者(子・孫)の間で、誰が、誰に、いくら贈与するのかを決め、双方で合意します。受贈者が未成年の場合は、親権者(父母など)が手続きを行います。
次に、この制度を取り扱っている金融機関を選びます。主に信託銀行、都市銀行、地方銀行、証券会社などが対応しています。金融機関によって手数料や、領収書の提出方法(アプリ対応の有無など)、提供されるサービスが異なるため、複数の金融機関を比較検討するとよいでしょう。
Step 2: 金融機関で専用口座を開設し、申告書を提出する
利用する金融機関を決めたら、受贈者(子・孫)の名義で「教育資金管理契約」を結び、専用の口座を開設します。この際、以下の書類が必要になるのが一般的です。
- 贈与契約書(金融機関所定の様式または自作のもの)
- 教育資金非課税申告書(金融機関を経由して税務署へ提出)
- 受贈者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 贈与者と受贈者の関係を証明する書類(戸籍謄本など)
- (受贈者が未成年の場合)親権者の本人確認書類
必要書類は金融機関によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
Step 3: 贈与者が専用口座に資金を一括で入金する
口座開設と契約が完了したら、贈与者はその口座に贈与する資金を一括で振り込みます。この制度は「一括贈与」が前提のため、分割での入金は認められていません。この入金をもって、非課税での贈与手続きは一旦完了です。
Step 4: 教育資金を支払い、金融機関に払い戻しを請求する
専用口座に入金された資金は、受贈者やその親権者が自由に引き出せるわけではありません。教育目的で使ったことを証明して、金融機関から払い戻しを受ける、または直接支払ってもらう必要があります。支払い方法には、主に2つのパターンがあります。
立て替え払い方式(後からの払い戻し)
直接支払い方式(振込依頼)
Step 5: 領収書等を金融機関に提出する
立て替え払いをした場合、その支払いが教育資金であることを証明するために、領収書等の提出が必須です。この領収書には、以下の項目が記載されている必要があります。
- 支払年月日
- 支払金額
- 支払いの内容(例:令和〇年度前期授業料として)
- 支払先(学校名、塾名など)
- 支払者(受贈者本人または親権者)
これらの記載がないと、教育資金として認められない場合があります。領収書を受け取る際は、必ず内容を確認しましょう。
領収書の提出には期限があり、多くの場合「支払いをした日の翌年3月15日まで」と定められています。期限を過ぎると払い戻しが受けられなくなるため、支払いをしたら速やかに提出する習慣をつけることが大切です。
近年は、手続きの面倒さを解消するため、スマートフォンアプリを使って領収書の写真をアップロードするだけで申請が完了するサービスを提供している金融機関も増えています。
まとめ:計画的な準備で教育資金贈与を有効活用しよう
今回は、「教育資金贈与はいつまで利用できるのか」というテーマを中心に、制度の契約期限、年齢要件、資金の利用期限、注意点などを詳しく解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。
- 制度の契約期限は2026年3月31日まで。 この日までに金融機関との契約・入金を完了させる必要がある。
- 受贈者は契約日時点で29歳以下である必要がある。
- 贈与された資金は、受贈者が30歳になるまでに使うのが原則。
- 30歳時点で使いきれなかった残高には贈与税がかかる。
- 贈与者が亡くなった場合、残高は条件によって相続税の対象となる。
- 非課税対象は、学校等への支払いは最大1,500万円、塾・習い事等は最大500万円(1,500万円の内枠)。
- 利用には専用口座の開設と、支払いごとの領収書提出といった手続きが必要。
教育資金の一括贈与非課税措置は、子や孫の未来を経済的に支えるための非常に有効な制度です。しかし、期限が定められており、将来的に制度が変更・廃止される可能性も否定できません。
利用を検討している方は、「まだ時間がある」と先延ばしにせず、まずは制度を取り扱っている金融機関に相談し、具体的な計画を立て始めることをお勧めします。贈与額の決定や税金に関する複雑な判断が必要な場合は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのも良い選択肢です。
この記事が、お子さんやお孫さんのための大切な教育資金計画の一助となれば幸いです。