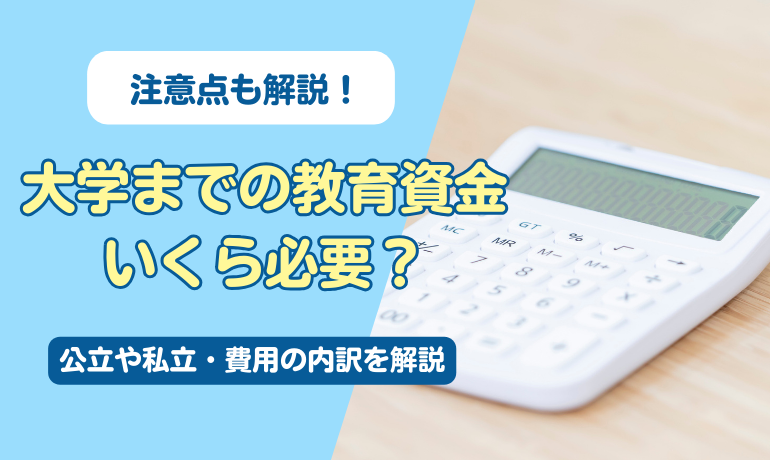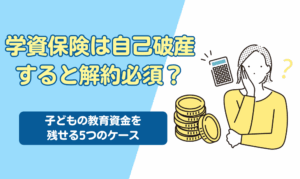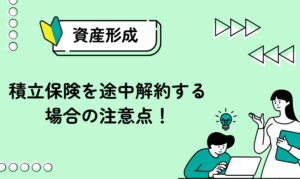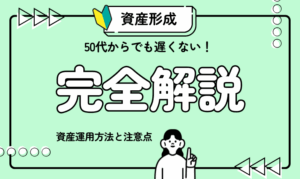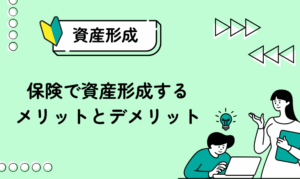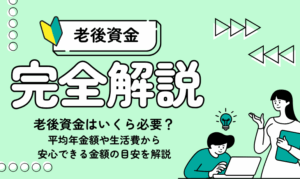「子どもの将来のために、十分な教育を受けさせてあげたい」と願うのは、親であれば誰もが抱く想いでしょう。しかし、その想いを実現するためには、まとまった教育資金の準備が不可欠です。「一体、大学卒業までにいくら必要なんだろう……」と、漠然とした不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
子どもの進路は、国公立か私立か、文系か理系か、自宅から通うのか一人暮らしをするのかによって、必要な費用が大きく変わります。しかし、事前に目安となる金額を知り、計画的に準備を始めることで、将来の選択肢を狭めることなく、子どもの夢を応援することができます。
この記事では、幼稚園から大学までにかかる子どもの学費について、公的なデータを基に詳しく解説します。公立と私立の総額比較や、各教育ステージでかかる費用の内訳、効率的な資金の貯め方、活用できる制度まで、教育資金に関するあらゆる疑問にお答えします。
ぜひ最後までお読みいただき、ご家庭に合った教育資金計画を立てるための第一歩としてお役立てください。
子どもの教育資金はいくら必要?学費総額の目安
子ども1人を幼稚園から大学まで卒業させるのに必要な教育資金の総額は、進路選択によって大きく異なります。ここでは、最も一般的な「すべて公立」と「すべて私立」の2つのコースで、学費の平均的なシミュレーションを見ていきましょう。
文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」と、日本政策金融公庫の「令和3年度 教育費負担の実態調査結果」を基に算出すると、大学卒業までにかかる学習費の総額は以下のようになります。
| 進路パターン | 幼稚園 (3年間) | 小学校 (6年間) | 中学校 (3年間) | 高校 (3年間) | 大学 (4年間) | 教育資金 合計 |
| すべて国公立 | 約67万円 | 約211万円 | 約162万円 | 約154万円 | 約538万円 | 約1,132万円 |
| すべて私立 | 約160万円 | 約995万円 | 約431万円 | 約316万円 | 約720万円 | 約2,622万円 |
※文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」、日本政策金融公庫「令和3年度 教育費負担の実態調査結果」を基に算出。
※大学の費用は、国公立大学の授業料・入学金の標準額と、私立大学(文系)の平均額を参考にしています。
※上記は学校教育費、学校給食費、学校外活動費を含んだ金額の目安です。
この表からわかるように、すべて公立の学校に進んだ場合でも、教育資金の総額は約1,132万円にものぼります。一方、すべて私立の道を選ぶと、その額は約2,622万円と、公立の2倍以上になります。その差は実に約1,500万円にもなり、進路がいかに教育費に大きな影響を与えるかがお分かりいただけるでしょう。
もちろん、これはあくまで平均的なモデルケースです。「小学校までは公立で、大学は私立文系に」「高校から私立理系に」など、ご家庭の方針や子どもの希望によって、必要な子どもの学費は千差万別です。大切なのは、これらの数値を一つの目安として捉え、ご家庭のライフプランに合わせた資金計画を立てることです。
学校ごとの子どもに必要な教育費
教育費の負担は、常に一定というわけではありません。子どもの成長に合わせて、負担が大きくなる時期と、比較的落ち着いている時期があります。ここでは、幼稚園から大学まで、それぞれのステージで年間にどれくらいの教育費が必要になるのか、その内訳と特徴を詳しく見ていきましょう。
幼稚園に必要な教育費
幼稚園の3年間で必要となる教育費の年間平均額は以下の通りです。
| 区分 | 学校教育費 | 学校給食費 | 学校外活動費 | 年間合計 |
| 公立幼稚園 | 約13万円 | 約2万円 | 約8万円 | 約22万円 |
| 私立幼稚園 | 約31万円 | 約4万円 | 約18万円 | 約53万円 |
※文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」より算出
2019年10月から「幼児教育・保育の無償化」がスタートし、3歳から5歳までの子どもの幼稚園や保育所などの利用料が原則無料になりました。しかし、上記の表を見ると、依然として費用がかかっていることがわかります。
これは、無償化の対象が「利用料(保育料)」のみであり、通園送迎バスの利用料、給食費、教材費、制服代、PTA会費、行事費などは保護者負担となるためです。また、習い事などの「学校外活動費」も家計の負担となります。特に私立幼稚園は、独自の教育プログラムや充実した施設を強みとしている場合が多く、その分、教材費や施設維持費などが高くなる傾向にあります。
小学校に必要な教育費
小学校の6年間は、公立と私立の差が大きく開き始める時期です。
| 区分 | 学校教育費 | 学校給食費 | 学校外活動費 | 年間合計 |
| 公立小学校 | 約7万円 | 約4万円 | 約24万円 | 約35万円 |
| 私立小学校 | 約96万円 | 約5万円 | 約66万円 | 約166万円 |
※文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」より算出
公立小学校の年間費用が約35万円であるのに対し、私立小学校は約166万円と、その差は約4.7倍にもなります。私立は授業料そのものが高額であることに加え、制服代、指定カバン代、寄付金などが必要になるケースも多くあります。
また、この時期から目立ち始めるのが「学校外活動費」の増加です。学校外活動費には、塾や習い事の月謝、教材費などが含まれます。特に私立小学校に通う家庭では、学校の授業の補習や更なる学力向上を目指して、塾に通う子どもの割合が高くなる傾向にあり、学校外活動費が公立の2倍以上となっています。
中学校に必要な教育費
中学校では、小学校よりもさらに公立と私立の教育費の差が広がります。学習塾に通い始める子どもが増え、部活動にかかる費用も本格化してきます。
| 区分 | 学校教育費 | 学校給食費 | 学校外活動費 | 年間合計 |
| 公立中学校 | 約14万円 | 約4万円 | 約36万円 | 約54万円 |
| 私立中学校 | 約106万円 | 約1万円 | 約37万円 | 約144万円 |
※文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」より算出
公立中学校の年間費用が約54万円に対し、私立中学校は約144万円と、その差は約2.7倍です。私立は授業料に加え、施設設備費や修学旅行の積立金などが高額になる傾向があります。
注目すべきは「学校外活動費」です。公立中学校では、年間の教育費(約54万円)のうち、約67%(約36万円)を学校外活動費が占めています。これは、高校受験に向けて塾に通う生徒が多いためです。一方、私立は中高一貫校が多く、高校受験がないためか、学校外活動費は公立とほぼ同額となっています。しかし、その分、学校教育費が公立の約7.5倍と非常に高額です。
高校に必要な教育費
高等学校の教育費は、国の「高等学校等就学支援金制度」により、授業料の負担が軽減される場合があります。しかし、それでもなお公立と私立では大きな差があります。
| 区分 | 学校教育費 | 学校外活動費 | 年間合計 |
| 公立高校 | 約31万円 | 約21万円 | 約51万円 |
| 私立高校 | 約75万円 | 約30万円 | 約105万円 |
※文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」より算出
※高校では給食がない場合が多いため、項目から除外しています。
公立高校の年間費用が約51万円であるのに対し、私立高校は約105万円と、約2倍の差があります。就学支援金制度は、世帯年収の目安が約910万円未満の家庭を対象に、授業料の一部または全部を支援するものですが、授業料以外の入学金や施設設備費、教材費、修学旅行費などは自己負担となります。
また、この時期は大学進学を見据えた塾や予備校の費用、大学入学共通テストや各大学の受験料など、「学校外活動費」が大きく膨らむ時期でもあります。子どもが希望する進路を実現するためには、学校に支払う費用以外にも、まとまったお金が必要になることを念頭に置いておきましょう。
大学に必要な教育費
教育資金の負担が最も大きくなるのが大学時代です。進学先が国公立か私立か、また文系か理系かによって、必要な学費は大きく異なります。
| 大学区分 | 入学金 | 授業料 (年間) | 施設設備費 (年間) | 初年度納付金 | 4年間の学費合計 |
| 国公立大学 | 約28万円 | 約54万円 | – | 約82万円 | 約243万円 |
| 私立大学文系 | 約22万円 | 約82万円 | 約15万円 | 約118万円 | 約408万円 |
| 私立大学理系 | 約25万円 | 約113万円 | 約18万円 | 約157万円 | 約551万円 |
| 私立大学医歯薬系 | 約108万円 | 約288万円 | 約89万円 | 約489万円 | 約2,393万円 (6年間) |
※文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」「令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額の調査結果」を基に作成。
※国公立大学は標準額を記載。医歯薬系は6年間の合計額。
国公立大学の4年間の学費総額が約243万円であるのに対し、私立文系では約408万円、私立理系では約551万円と、大きな差があります。特に私立の医歯薬系学部に進学する場合、6年間で2,000万円を超える高額な学費が必要となるため、早期からの特別な準備が不可欠です。
一人暮らしで仕送りをする場合
子どもが親元を離れて一人暮らしをしながら大学に通う場合、学費に加えて生活費の仕送りが必要になります。この仕送り額が、家計にとって大きな負担となることは少なくありません。
全国大学生活協同組合連合会の「第58回学生生活実態調査」(2022年度)によると、一人暮らしの大学生への仕送り額の平均は、月額約7.1万円です。
これを基に計算すると、
- 年間の仕送り額: 約7.1万円 × 12カ月 = 約85万円
- 4年間の仕送り総額: 約85万円 × 4年 = 約340万円
となり、学費とは別にこれだけの資金が必要になります。例えば、子どもが私立文系大学に自宅外から通う場合、4年間の学費約408万円に仕送り額約340万円が加わり、合計で約748万円ものお金がかかる計算になります。
さらに、一人暮らしを始める際には、アパートの敷金・礼金や仲介手数料、家具・家電の購入費などの初期費用として、50万円〜100万円程度が別途必要になることも想定しておかなければなりません。子どもの進路を考える際には、学費だけでなく、こうした生活費の可能性も視野に入れておくことが重要です。
子どもの教育資金はいくら貯めるべき?
ここまで見てきたように、教育資金は子どもの進路によって大きく変動します。では、具体的に「いつまでに、いくら貯める」ことを目標にすればよいのでしょうか。
一般的に、教育資金の準備における一つの大きな目標は「大学入学までに300万円〜500万円を準備する」ことです。
この金額が目安とされる理由は、大学で最もお金がかかる「入学初年度」の費用をカバーするためです。私立大学の場合、入学金や前期分の授業料などを一括で支払う必要があり、初年度納付金は文系で約118万円、理系では約157万円にもなります。
まずこの初年度納付金を準備した資金でまかない、残りの在学中の学費は、その後の家計の収入や、準備してきた資金の残額、奨学金などを組み合わせて支払っていく、という考え方が現実的です。大学入学時にまとまった資金があれば、その後の資金繰りに余裕が生まれ、精神的な安心にも繋がります。
もちろん、これはあくまで一つの目安です。すべて私立に進学する可能性を考えるなら、より多くの準備が必要になります。また、子ども2人がいる場合はどうでしょうか。単純に2倍の金額が必要になると考えがちですが、第1子と第2子の年齢差によって準備期間が異なります。例えば、年齢が近ければ負担が集中しますが、年齢が離れていれば第1子の教育費の目処が立った後に、第2子の準備に集中できます。
大切なのは、ご家庭の教育方針(「大学は国公立に進んでほしい」「子どもの希望を最優先したい」など)を基に、 realisticな目標金額を設定することです。上記のデータを参考に、ご家庭ならではの教育資金シミュレーションをしてみることをお勧めします。
子どもの教育資金を貯める方法
目標額が決まったら、次はいよいよ計画的に貯蓄を始める段階です。教育資金のような長期にわたる資金準備には、目的に合った方法を選ぶことが重要です。ここでは、代表的な貯め方とそのメリット・デメリットを解説します。
学資保険
子どもの教育資金準備の代表的な方法です。毎月決まった保険料を支払うことで、子どもの進学時期(18歳、20歳など)に合わせて、満期保険金やお祝い金としてまとまったお金を受け取れます。
メリット:
デメリット:
預貯金(定期預金・積立定期預金)
最も安全で手軽な方法です。給与振込口座とは別に教育資金専用の口座を作り、毎月決まった額を自動的に移す「積立 定期預金」などを利用すると、計画的に貯めることができます。
メリット:
デメリット:
NISA(つみたて投資枠)
2024年から新しくなったNISAは、教育資金準備の有力な選択肢として注目されています。投資信託などを毎月一定額ずつ積立購入し、得られた利益(分配金、譲渡益)が非課税になる制度です。
メリット:
デメリット:
財形貯蓄制度
勤務先にこの制度があれば、給与から天引きで貯蓄ができるため、着実にお金を貯めることができます。一般財形、住宅財形、年金財形の3種類があります。
メリット:
デメリット:
祖父母からの教育資金一括贈与
祖父母や曽祖父母から、30歳未満の子や孫へ教育資金を一括で贈与する場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になる特例制度です。
メリット:
デメリット:
どの方法が最適かは、各ご家庭のリスク許容度や貯蓄に対する考え方によって異なります。複数の方法を組み合わせて、リスクを分散しながら計画的に準備を進めていくのが賢明な方法と言えるでしょう。
教育資金の補助や減免制度
国や自治体は、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、さまざまな支援制度を設けています。これらの制度を上手に活用することで、教育資金の負担を大きく減らすことができます。
| 制度名 | 対象年齢・時期 | 制度の概要 |
| 児童手当 | 0歳〜中学校卒業まで | 子どもを養育する保護者に手当が支給される制度。所得制限がある。支給額は年齢や第何子かによって異なる(月額1万円または1万5千円)。 |
| 幼児教育・保育の無償化 | 3歳〜5歳 | 幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無料になる制度。住民税非課税世帯は0歳〜2歳も対象。 |
| 高等学校等就学支援金制度 | 高校在学中 | 国公私立を問わず、高校等の授業料に充てるための就学支援金が支給される制度。世帯年収約910万円未満が目安。 |
| 高校生等奨学給付金 | 高校在学中 | 授業料以外の教育費(教科書費、学用品費など)を支援する給付型の奨学金。住民税非課税世帯や生活保護世帯が対象。 |
| 高等教育の就学支援新制度 | 大学・短大・専門学校在学中 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に、「授業料・入学金の減免」と「給付型奨学金の支給」がセットで行われる。 |
特に、毎月支給される児童手当は、すぐに使ってしまわずに全額を貯めておくだけでも、子どもが中学校を卒業するまでに総額で約200万円になります。これは大学の初年度納付金を大きくカバーできる金額であり、非常に強力な教育資金の原資となります。
これらの制度は、申請しなければ利用できないものがほとんどです。また、所得制限などの条件が設けられている場合も多いため、お住まいの自治体のホームページや文部科学省のウェブサイトなどで、ご自身が対象となる制度がないか、こまめに情報を確認することが大切です。
それでも教育資金が不足するときに頼れる方法
計画的に準備を進めていても、想定外の出費が重なったり、思ったように貯蓄が伸びなかったりして、教育資金が不足してしまうケースも考えられます。そんな万が一の時に頼れる方法として、「奨学金」と「教育ローン」があります。
奨学金
奨学金は、経済的な理由で修学が困難な学生を支援するための制度で、学生本人が利用者となります。独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金が最もよく知られています。
給付型奨学金:
返済が不要なタイプの奨学金です。学力基準や家計基準が厳しく、誰でも利用できるわけではありませんが、対象となれば大きな助けとなります。「高等教育の就学支援新制度」の中心となる支援です。
貸与型奨学金:
返済が必要なタイプの奨学金で、無利息の「第一種奨学金」と、利息が付く「第二種奨学金」があります。卒業後、長期間にわたって学生本人が返済していくことになるため、利用は慎重に検討する必要があります。
教育ローン
教育ローンは、契約者である親が金融機関から教育資金を借り入れ、返済していくものです。借入時から返済が始まるのが奨学金との大きな違いです。
国の教育ローン(日本政策金融公庫):
民間のローンに比べて金利が低めに設定されており、ひとり親家庭や世帯年収が低い家庭には金利の優遇措置があります。審査は民間のローンよりは緩やかとされています。
民間の教育ローン:
銀行や信用金庫などが取り扱っています。国の教育ローンよりも借入限度額が高く、資金の使い道も幅広いなど、自由度が高いのが特徴です。金利やサービス内容は金融機関によってさまざまなので、複数の商品を比較検討することが重要です。
奨学金も教育ローンも、将来の家計に返済負担がのしかかる「借金」であることに変わりはありません。これらはあくまで最終手段と考え、まずはコツコツと貯蓄を進めることを基本としましょう。安易に頼るのではなく、本当に必要な金額だけを、計画的に利用することが大切です。
まとめ:計画的な準備で、子どもの未来を応援しよう
子どもの教育資金は、進路によって1,000万円から2,500万円以上と、非常に高額になることがお分かりいただけたかと思います。しかし、数字の大きさに圧倒される必要はありません。大切なのは、早い段階から計画的に準備を始めることです。
大学進学など、まとまったお金が必要になる時期から逆算し、「いつまでに、いくら」という具体的な目標を立てましょう。そして、ご家庭の状況に合った貯蓄方法を選び、コツコツと継続していくことが、子どもの夢を応援するための最も確実な道筋となります。
まずは大学入学を見据えて300万円〜500万円を目標に、児童手当を全額貯めるところから始めてみてはいかがでしょうか。そして、就学支援金やNISAなど、活用できる制度は積極的に利用し、賢く教育資金を準備していきましょう。