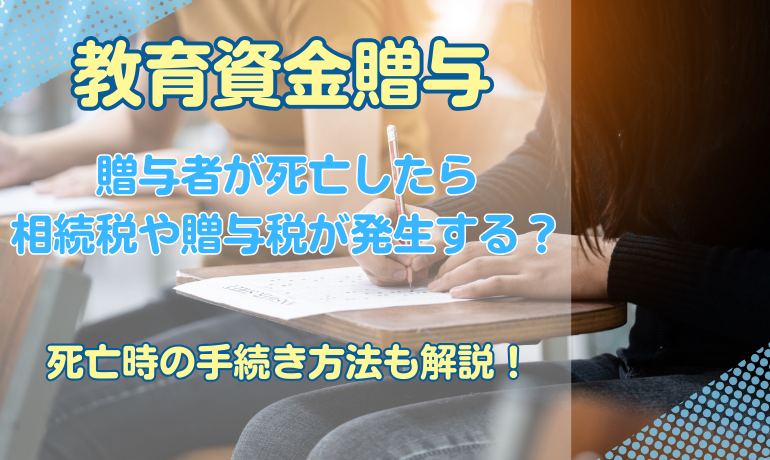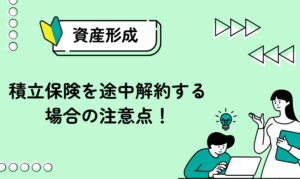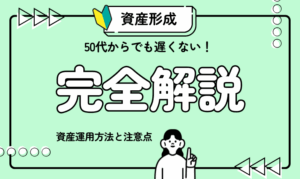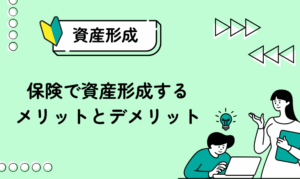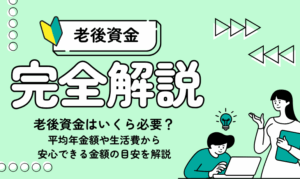「子や孫の将来のために、少しでも多くの教育資金を遺したい」
そのような想いから、教育資金贈与の制度を利用している方、または利用を検討している方は多いでしょう。
しかし、もし贈与をしてくれた祖父母や親(贈与者)が、資金を使い切れないうちに亡くなってしまったらどうなるのでしょうか。
「残ったお金(残額)に相続税や贈与税などの税金はかかるの?」
「口座は解約されてしまうの?」
「何か特別な手続きが必要?」
贈与者がご高齢の場合、このような不安は尽きません。
この記事では、教育資金贈与を受けているなかで贈与者が死亡してしまった場合に何が起こるのか、そしてどのような手続きが必要になるのかを、制度の改正点も踏まえながら詳しく解説します。いざという時に慌てないための対策として、ぜひ最後までご覧ください。
教育資金贈与は贈与者が死亡するとどうなる?
まず、贈与者が亡くなった場合に、教育資金贈与の口座残高がどう扱われるのか、基本的なルールから見ていきましょう。
そもそも教育資金贈与(正式名称:教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置)とは、30歳未満の子や孫(受贈者)へ、教育資金として使うことを目的に、金融機関の専用口座を通じて最大1,500万円までを一括で贈与しても贈与税が非課税になる制度です。
この制度を利用中に贈与者が死亡した場合、原則としてその時点での口座の残額(管理残高)が、贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。
ただし、「必ず相続税がかかる」というわけではありません。重要なのは、いつ贈与を受けたかという点です。税制改正により、贈与の時期によって扱いが大きく異なるため、注意が必要です。
残額が相続税の対象になることがある
贈与者が死亡した時点で教育資金口座に残金があった場合、その残額は相続税の対象になることがあります。しかし、これは贈与が行われた時期によってルールが異なります。ご自身の契約がいつ行われたものかを確認することが重要です。
2021年3月31日までの贈与の場合
2021年3月31日までに締結された教育資金管理契約に基づく贈与の場合、原則として贈与者が死亡しても、口座の残額は相続税の課税対象にはなりません。
たとえ贈与者が亡くなる直前(相続開始前3年以内)の贈与であっても、相続財産に加算する必要はありませんでした。この時期に贈与を受けた方にとっては、非常に有利な条件だったと言えます。
2021年4月1日以降の贈与の場合
2021年度の税制改正により、2021年4月1日以降の贈与については扱いが厳格化されました。
この期間に贈与を受けた場合、贈与者が死亡した時点で口座に残額があれば、その残額は原則として相続税の課税対象となります。
ただし、以下のいずれかの条件を満たす場合は、例外として相続税の対象にはなりません。
- 受贈者が23歳未満である場合
- 受贈者が学校等に在学している場合
- 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
つまり、贈与者が亡くなった時点で、受贈者がまだ若く、まさに教育を受けている最中であれば、残額に相続税はかからないということです。一方で、すでに学校を卒業しているなど、上記の条件に当てはまらない場合は、残額が相続税の対象となってしまいます。
受贈者が孫の場合は2割加算される
相続税には「2割加算」というルールがあります。これは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した人が、配偶者および一親等の血族(子や父母)以外の場合に、納付する相続税額が2割増しになる制度です。
教育資金贈与は、祖父母から孫へ行われるケースが非常に多いです。この場合、受贈者である孫は、贈与者である祖父母から見て「一親等の血族」ではないため、2割加算の対象となります。
したがって、贈与者の死亡によって口座の残額が相続税の課税対象となり、かつ受贈者が孫である場合、計算された相続税額からさらに2割が加算された金額を納付する必要があるため、注意が必要です。
また、2023年度の税制改正で、贈与者の相続財産が5億円を超える場合に孫などへの残額が課税対象となる特例がありましたが、このルールは撤廃され、現在は相続財産の価額にかかわらず、上記のルールが適用されます。
贈与税の対象にはならない
ここで一つ重要なポイントがあります。
贈与者が死亡し、口座の残額が相続税の対象になった場合、そのお金はもはや「教育資金」という名目での縛りがなくなります。
つまり、その残額を教育費以外の目的(例えば生活費や娯楽費など)に使ったとしても、新たに贈与税が課されることはありません。あくまで「相続財産」として扱われるためです。相続税の申告・納税さえ済ませれば、その後の使い道は自由になります。
教育資金贈与の口座は引き続き利用できる
贈与者が亡くなったと聞くと、「専用口座も解約されてしまうのでは?」と心配になるかもしれません。
しかし、ご安心ください。贈与者の死亡は、金融機関との「教育資金管理契約」が終了する事由にはあたりません。したがって、贈与者が死亡しても口座はそのまま継続して利用できます。
受贈者が30歳になる、または口座の残金がゼロになり契約終了の合意をする、といった本来の終了事由に該当するまで、引き続きその口座から教育資金を引き出して使うことが可能です。
教育資金贈与で贈与者死亡したときの手続き方法
では、実際に贈与者が亡くなった場合、具体的にどのような手続きをすればよいのでしょうか。相続税の対象になるかどうかで、必要な手続きが異なります。
相続税の対象になる場合は金融機関に死亡の届け出が必要
まず、口座の残額が相続税の課税対象になる場合は、契約している金融機関(銀行や信託銀行など)に、贈与者が死亡した旨を届け出る必要があります。
届け出が必要なケース
- 2021年4月1日以降の贈与で、贈与者死亡時に受贈者が23歳以上かつ学校等に在学していないなど、相続税の非課税措置の対象外となる場合。
届け出が不要なケース
- 2021年3月31日までの贈与の場合
- 2021年4月1日以降の贈与でも、受贈者が23歳未満であるなど、相続税の非課税措置の対象となる場合
ただし、不要なケースであっても、相続手続き全体の中で金融機関から提出を求められる可能性はあります。まずは契約先の金融機関に連絡し、指示を仰ぐのが最も確実です。
届け出の必要書類
一般的に、金融機関への死亡の届け出には以下の書類が必要となります。多くの書類は金融機関の窓口やウェブサイトで入手できます。
- 異動申告書(死亡届):金融機関所定の様式
- 贈与者の死亡の事実が確認できる書類:戸籍謄本(除籍謄本)や住民票の除票など
- 教育資金管理契約にかかわる契約者(贈与者)の地位承継に関する依頼書:相続人が口座の権利を引き継ぐ場合に必要(金融機関所定の様式)
- 相続人全員の同意書および印鑑証明書:相続人全員で合意したことを証明するために必要となる場合がある
金融機関によって必要書類は異なるため、必ず事前に問い合わせて確認しましょう。
受贈者が23歳以上で学校へ通っている場合の追加書類
贈与者が死亡した時点で受贈者が23歳以上であっても、学校等に在学中、または教育訓練を受けている場合は、相続税の非課税措置を受けられます。
この適用を受けるためには、上記の届出に加えて、その事実を証明するための追加書類が必要です。
- 在学証明書:通っている学校が発行したもの
- 教育訓練の受講を証明する書類:ハローワークなどが発行したもの
これらの書類を提出することで、口座残額が相続税の対象外であることを証明します。
相続税の基礎控除額を超える場合は相続税の申告をする
口座の残額が相続税の課税対象となった場合、次に考えるべきは相続税の申告です。
ただし、相続税は必ず発生するわけではありません。課税対象となる遺産の総額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ、申告と納税の義務が生じます。
基礎控除額の計算式
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人だった場合、基礎控除額は3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円となります。
教育資金贈与の口座残額を含めた、亡くなった贈与者のすべての遺産(預貯金、不動産、有価証券など)の合計額がこの基礎控除額を超えなければ、相続税の申告も納税も不要です。
超える場合は、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内に、被相続人(贈与者)の最後の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出し、納税を済ませる必要があります。
管理残高の計算方法
相続税の課税対象となる「管理残高」は、単なる口座の残高ではありません。正しくは、以下の計算式で算出します。
課税対象となる管理残高の計算式
ポイントは、最後の「死亡日までに支払うことが確定していた教育資金」です。
例えば、贈与者が亡くなる前に次学期の授業料の請求書が届いており、支払うことが決まっていたものの、まだ口座からは引き出していなかった、というようなケースです。この金額は、死亡日時点の口座残高から差し引くことができます。
この控除を受けるためには、授業料の請求書や振込依頼書など、支払いが確定していたことを客観的に証明できる書類が必要になります。
受贈者が23歳未満かつ2021年4月1日以降に贈与を受けた場合
このケースは、前述の通り、口座残額は相続税の課税対象にはなりません。そのため、基本的には金融機関への死亡の届け出も不要です。
しかし、相続税の申告自体は必要な場合があります。
具体的には、教育資金贈与の残額を除いた他の遺産総額が、基礎控除額を超えているケースです。
この場合、相続税の申告書に「教育資金管理契約に基づき贈与を受けた金銭のうち、死亡日までの教育資金支出額を控除した残額」を記載し、非課税の適用を受ける旨を明記して提出する必要があります。これにより、税務署に対して「この残額は非課税の対象ですよ」と正しく申告するわけです。
この手続きを失念すると、後日税務署から問い合わせが来る可能性もあるため、相続税申告が必要な場合は、税理士などの専門家に相談しながら進めるのが安心です。
まとめ:贈与者死亡時はまず「贈与日」と「受贈者の状況」を確認しよう
教育資金贈与の途中で贈与者が亡くなってしまった場合、多くの方が動揺し、不安に感じると思います。しかし、やるべきことは決まっています。慌てずに一つひとつ確認し、手続きを進めていきましょう。
【贈与者死亡時のチェックポイント】
- 贈与契約日を確認する
- 2021年3月31日以前 → 残額は原則、相続税の対象外。
- 2021年4月1日以降 → 残額は原則、相続税の対象。
- 受贈者の状況を確認する(上記1が「以降」の場合)
- 23歳未満、在学中、教育訓練中 → 例外的に相続税の対象外。
- 上記以外 → 原則通り相続税の対象。
- 相続税の対象になるか判断する
- なる場合 → 金融機関へ死亡を届け出て、相続財産全体が基礎控除額を超えるか確認。超えるなら相続税申告。
- ならない場合 → 原則手続き不要。ただし他の遺産で相続税申告が必要なら、申告書への記載は必要。
教育資金贈与の制度や相続税の計算は、税制改正も多く複雑です。特に、相続人が複数いる場合や、財産の種類が多い場合は、手続きが煩雑になりがちです。
もし少しでも不安な点や不明な点があれば、契約先の金融機関はもちろん、税理士や弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。大切な資産を正しく引き継ぎ、故人の想いを未来へ繋いでいきましょう。