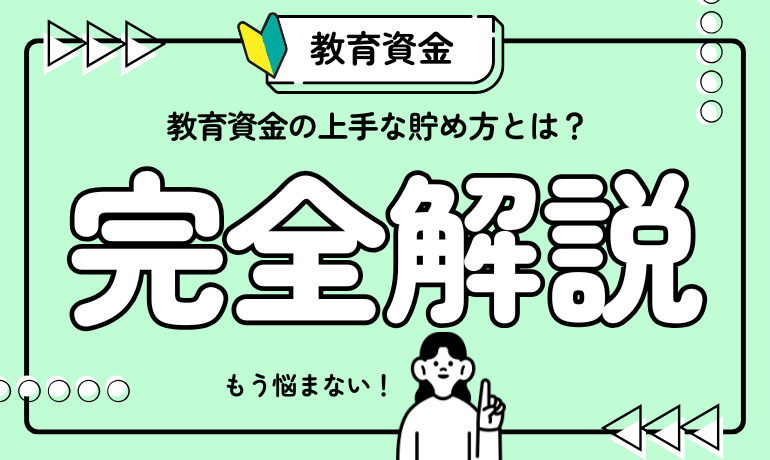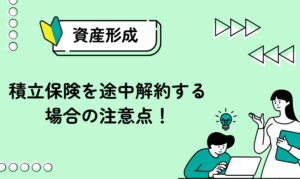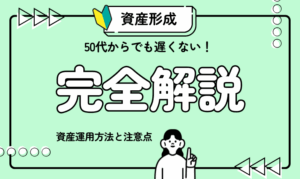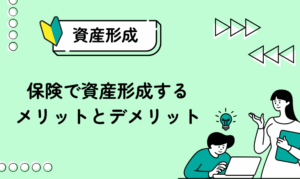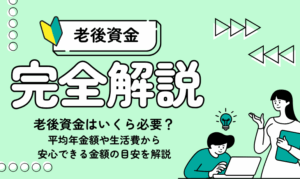「子どもの将来のため、しっかり教育資金を準備してあげたい」
多くの親御さんがそう願う一方で、「いったいいくらかかるの?」「どうやって貯めたらいいの?」と、漠然とした不安を抱えているのではないでしょうか。
教育資金の貯め方には、銀行預金や学資保険、NISAを活用した投資など、さまざまな方法があります。しかし、それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解しないまま始めてしまうと、「思ったように貯まらなかった」「もっと良い方法があったかも…」と後悔につながりかねません。
この記事では、お子さまの夢を応援したいと願うあなたのために、教育資金の基本的な貯め方から、着実に準備するためのコツ、そして目標とすべき金額の目安まで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、あなたの家庭の状況や考え方に合った最適な「教育資金の貯め方」が見つかるはずです。さあ、一緒に子どもの未来のための第一歩を踏み出しましょう。
教育資金の貯め方は主に3種類
教育資金を準備するための方法は、大きく分けて「預貯金」「保険」「投資」の3種類があります。これらはどれか一つだけを選ぶというよりも、それぞれの特徴を理解し、組み合わせて活用するのが一般的です。
まずは、それぞれの貯め方がどのようなものか、概要を解説します。ご自身の性格や家計の状況、教育資金を使うタイミングなどを考慮しながら、どの方法が自分に合っているか検討してみましょう。
- 預貯金: 最も身近で安全な方法。銀行の普通預金や定期預金などで、コツコツとお金を積み上げていきます。元本が保証されている安心感が最大の特徴です。
- 保険: 学資保険や終身保険などを活用する方法。貯蓄機能に加えて、契約者(親)に万が一のことがあった場合の保障が付いているのが特徴です。
- 投資: 投資信託などを活用し、お金に働いてもらって「増やす」ことを目指す方法。NISA(少額投資非課税制度)などを活用することで、効率的な資産形成が期待できます。
この3つの方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。次の章から、一つひとつの貯め方について、具体的な特徴や上手に貯めるコツを詳しく見ていきましょう。
預貯金で確実に貯める
最もシンプルで、多くの人が最初に思いつくのが預貯金でしょう。子ども名義の口座を開設し、毎月決まった額を貯金していく方法です。具体的には、普通預金、定期預金、積立式定期預金などがあります。
教育資金を着実に貯めるなら、給与振込口座とは別に教育資金専用の口座を作り、毎月自動で一定額が振り替えられる「自動積立定期預金」の仕組みを利用するのがおすすめです。これにより、「余ったら貯金する」のではなく、「先に貯金して残りで生活する」という貯蓄の習慣が身につきます。
預貯金で教育資金を貯めるメリット
✅ 元本保証の安心感
預貯金の最大のメリットは、銀行にお金を預けている限り、元本が減る心配がないことです。金融機関が破綻した場合でも、預金保険制度により1金融機関あたり元本1,000万円とその利息までが保護されます。着実に、安全にお金を貯めたいという方には最適な方法です。
✅ いつでも引き出せる流動性の高さ
急な出費が必要になった場合でも、預貯金ならATMや窓口ですぐに引き出すことができます。入学金や授業料の支払いなど、使う時期が明確に決まっている教育資金において、必要な時にすぐに使える流動性の高さは大きなメリットです。
✅ 始めやすさと分かりやすさ
特別な知識は必要なく、誰でも簡単に始められるのが預貯金の魅力です。口座を開設して入金するだけなので、手間がかかりません。貯まっている金額も通帳を見れば一目瞭然で、目標に対する進捗が分かりやすいのも特徴です。
預貯金で教育資金を貯めるデメリット
❌ 金利が低く、お金はほとんど増えない
現在の超低金利時代において、預貯金で得られる利息はごくわずかです。お金を大きく増やすことは期待できず、あくまで「貯めておく」という役割になります。
❌ インフレに弱い
インフレとは、物価が上昇し、相対的にお金の価値が下がることです。例えば、年2%のインフレが続くと、今ある100万円の価値は10年後には約82万円に目減りしてしまいます。預貯金の金利がインフレ率を下回っている場合、実質的にお金の価値は減ってしまうのです。将来必要となる教育費も、インフレによって現在想定している金額よりも高くなる可能性があります。
保険で万が一に備えながら貯める
次に紹介するのは、保険商品を活用して教育資金を準備する方法です。代表的なものに「学資保険」がありますが、「低解約返戻金型終身保険」なども選択肢になります。
これらの保険は、毎月決まった保険料を支払うことで、子どもの進学時期(18歳、22歳など)に合わせて満期金や祝い金を受け取れる仕組みです。単にお金を貯めるだけでなく、契約者である親に万が一のことがあった場合に、それ以降の保険料の支払いが免除されるといった保障機能が付いているのが大きな特徴です。
コツコツ貯めるのが苦手な方でも、保険料という形で半強制的に貯蓄を続けられるため、計画的な資金準備に向いています。
保険で教育資金を貯めるメリット
✅ 契約者に万一のことがあった際の保障がある
最大のメリットは、契約者(親)が死亡または高度障害状態になった場合に、以降の保険料の支払いが免除される「払込免除特則」が付いている点です。払込が免除されても、契約時に定めた満期金や祝い金は満額受け取れるため、親に何かあっても子どもの教育資金を確実に遺すことができます。この安心感は、預貯金や投資にはない大きな魅力です。
✅ 計画的に貯蓄できる
保険料は毎月口座から引き落とされるため、一度契約すれば意識せずとも貯蓄を続けられます。途中で解約すると元本割れする可能性があるため、簡単には引き出せず、結果的に着実にお金を貯めることができます。
✅ 生命保険料控除の対象になる
支払った保険料は、年末調整や確定申告で「生命保険料控除」の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減できる場合があります。
保険で教育資金を貯めるデメリット
❌ 返戻率が低く、元本割れのリスクがある
返戻率(へんれいりつ)とは、支払った保険料総額に対して、受け取れる満期金や祝い金の総額がどれくらいの割合かを示す数値です。この返戻率が100%を下回る(元本割れする)商品も少なくありません。また、契約から早い段階で解約すると、解約返戻金が支払った保険料を大幅に下回ることがほとんどです。
❌ 流動性が低い
預貯金のように、必要な時にすぐにお金を引き出すことはできません。途中でまとまったお金が必要になった場合は「契約者貸付制度」を利用できることもありますが、利息がかかります。
❌ インフレに弱い
預貯金と同様、契約時に受け取れる金額が決まっているため、将来インフレが進行した場合、お金の実質的な価値が目減りしてしまう可能性があります。
学資保険と生命保険のどちらがおすすめ?
教育資金を保険で準備する場合、主に「学資保険」と「低解約返戻金型終身保険」などの生命保険が比較検討されます。どちらが良いかは、何を重視するかによって異なります。
| 比較項目 | 学資保険 | 低解約返戻金型終身保険 |
| 目的 | 子どもの教育資金準備に特化 | 死亡保障がメイン(貯蓄性も兼ね備える) |
| 受取時期 | 18歳満期など、子どもの進学時期に合わせて設定 | 任意のタイミングで解約して解約返戻金を受け取る |
| 保障内容 | 契約者の死亡・高度障害時の保険料払込免除が主 | 契約者の死亡・高度障害時に保険金が支払われる |
| 返戻率 | 商品によるが、近年は100%を少し超える程度が多い | 保険料払込期間中の返戻率は低いが、払込満了後は上昇する傾向 |
| 自由度 | 決められた時期にしか受け取れない | 解約のタイミングは自由 |
- 学資保険がおすすめな人
- 「教育資金」という目的を明確にして、着実に準備したい人
- 子どもの進学など、お金が必要なタイミングが決まっている人
- 複雑な商品は苦手で、シンプルで分かりやすいものが良い人
- 生命保険がおすすめな人
- 教育資金だけでなく、親の万が一の死亡保障も手厚くしたい人
- 教育資金として使わなかった場合、老後資金など他の目的に活用することも検討したい人
- より自由度の高いプランを設計したい人
教育資金の準備を最優先するなら学資保険が分かりやすいですが、家計全体の保障を見直す中で、貯蓄性のある生命保険を活用するという選択肢も有効です。
投資で増やしながら貯める
3つ目の方法は、投資信託などを活用して、お金を「増やす」ことを目指す方法です。特に、少額から始められ、税制優遇のある「NISA(ニーサ)」制度の活用が一般的です。
具体的には、毎月決まった金額で投資信託をコツコツと購入していく「積立投資」を行います。長期間続けることで、複利の効果(利息が利息を生む効果)が期待でき、預貯金や保険よりも大きく資産を増やせる可能性があります。
ただし、投資には必ずリスクが伴います。元本が保証されておらず、購入した商品の価格が変動するため、時には元本割れする可能性もあることを十分に理解しておく必要があります。教育資金のように使う時期が決まっているお金を投資で準備する場合は、リスクを抑えるために「長期・積立・分散」を徹底することが重要です。
投資で教育資金を貯めるメリット
✅ 大きく増やせる可能性がある
最大のメリットは、預貯金や保険よりも高いリターンが期待できる点です。例えば、毎月3万円を18年間積み立てた場合、年率3%で運用できれば元本648万円が約851万円に、年率5%なら約1058万円になる計算です。この「増える力」は、インフレにも対抗できる大きな強みとなります。
✅ NISA活用で運用益が非課税になる
通常、投資で得た利益(運用益)には約20%の税金がかかりますが、NISA口座内で得た利益には税金がかかりません。この非課税メリットは非常に大きく、効率的な資産形成を後押ししてくれます。
✅ 少額から始められる
ネット証券などでは月々1,000円といった少額から積立投資を始められます。家計に無理のない範囲でスタートし、状況に応じて金額を調整することも可能です。
投資で教育資金を貯めるデメリット
❌ 元本保証がなく、価格変動リスクがある
投資である以上、元本割れのリスクは避けられません。世界的な経済危機などが起きた場合、資産価値が大きく減少する可能性もあります。教育資金が必要となるタイミングで暴落が起きてしまうと、予定していた金額を引き出せない事態も考えられます。
❌ 金融知識がある程度必要
どのような商品を選ぶか、リスクをどう管理するかなど、ある程度の金融知識が必要になります。何も知らずに始めると、ハイリスクな商品を選んでしまったり、価格が下がった時に慌てて売ってしまったり(狼狽売り)して、損失を被る可能性があります。
❌ 短期的な資金準備には向かない
投資は、価格の変動を乗り越えて長期的にリターンを狙うものです。数年後に必要になる資金の準備には向いていません。少なくとも10年以上の長期的な視点で取り組むことが前提となります。
教育資金の貯め方で人気なのは学資保険
これまで3つの貯め方を紹介してきましたが、実際にはどの方法が多くの家庭で選ばれているのでしょうか。
富国生命保険が2020年に行った調査によると、教育資金の準備方法として最も多かったのは「学資保険・こども保険」で58.9%、次いで「預貯金」が56.4%という結果でした。(※複数回答)
この結果から、多くの家庭が、元本が保証されている預貯金の安心感をベースにしつつ、親の万が一に備える保障機能と計画性を重視して学資保険を選んでいることがうかがえます。
投資(つみたてNISAなど)は近年注目度が高まっていますが、やはり元本割れのリスクがあるため、子どものための大切な教育資金の準備としては、より安全・確実な方法を好む傾向が強いようです。
ただし、これはあくまで一般的な傾向です。低金利が続く現代において、預貯金や学資保険だけではインフレに対応しきれないという考え方から、NISAなどを活用して積極的に「増やす」選択をする家庭も増えています。
教育資金を確実に貯めるためのコツ
教育資金は、子どもの成長に合わせて長期間にわたって準備していくものです。途中で挫折することなく、目標額を着実に貯めるためには、いくつかのコツを押さえておくことが重要です。
複数の方法で貯める
最も重要なコツは、どれか一つの方法に絞るのではなく、複数の方法を組み合わせることです。「預貯金」「保険」「投資」にはそれぞれメリット・デメリットがあります。これらを組み合わせることで、お互いの弱点を補い合い、より安定的かつ効率的に教育資金を準備することができます。
組み合わせの例:
- 基本パターン(安定重視):預貯金+学資保険
- 大学の入学金など、絶対に減らせないお金は預貯金や学資保険で確実に確保。
- 安全性を最優先したい方向けの、王道の組み合わせです。
- バランスパターン:預貯金+学資保険+NISA
- ベースは預貯金と学資保険で固めつつ、余裕資金の一部をNISAでの積立投資に回す。
- インフレ対策や、目標額以上の上乗せを目指したい方向け。
- 積極パターン(収益性重視):預貯金+NISA
- 生活防衛資金や当面の教育費は預貯金で確保する。
- 大学費用など、使うまで時間があるお金はNISAで積極的に増やすことを目指す。リスク許容度が高い方向け。
このように、ご自身のリスク許容度や家計の状況に合わせて、最適なポートフォリオを組むことが成功への鍵です。
早いうちから計画的に準備する
教育資金の準備は、「時間を味方につける」ことが何よりも大切です。子どもが生まれたら、なるべく早いうちから準備を始めましょう。
早く始めるメリットは2つあります。
- 月々の積立額を抑えられる:
例えば、18歳までに500万円を貯める場合、0歳から始めれば月々の積立額は約2.3万円ですが、10歳から始めると約5.2万円もの負担になります。 - 複利の効果を最大限に活かせる:
投資を取り入れる場合、運用期間が長いほど複利の効果は大きくなります。早く始めることで、雪だるま式に資産が増えていく効果をより享受できます。
また、教育資金には「貯めどき」と言われる時期があります。一般的に、子どもが小さく、まだ教育費があまりかからない小学校入学前と、塾や習い事の費用が落ち着く高校入学前が貯めやすい時期とされています。この「貯めどき」を逃さず、集中的に貯蓄ペースを上げることが、計画達成のポイントになります。
児童手当を教育資金用にまわす
中学校卒業まで支給される「児童手当」は、教育資金の大きな原資になります。この手当を生活費に使ってしまうのではなく、「最初からなかったもの」として全額貯蓄に回すことを強くおすすめします。
所得制限にかからなかった場合、0歳から15歳まで受け取れる児童手当の総額は、約200万円にもなります。これは、大学の入学金や初年度の授業料に相当する大きな金額です。
児童手当が振り込まれる口座を、生活費の口座とは別に教育資金専用口座に指定し、手を付けずに貯めていくだけで、教育資金準備の大きな柱を作ることができます。
投資をするならNISAを活用する
もし投資で教育資金の準備をするのであれば、NISA(少額投資非課税制度)の活用は必須です。2024年から始まった新NISAは、非課税で投資できる上限額が大幅に拡大し、制度も恒久化されたことで、長期的な資産形成に非常に使いやすい制度になりました。
特に、毎月コツコツ積み立てるのに適した「つみたて投資枠」を利用すれば、リスクを分散しながら長期的なリターンを目指すことができます。
ただし、前述の通り、投資には元本割れのリスクがあります。教育資金のすべてをNISAで準備するのではなく、あくまで預貯金や保険でベースを固めた上でのプラスアルファと位置づけるか、使うまで10年以上の時間的余裕がある資金を対象にするのが賢明です。
貯めるためには働き続けるのも大事
教育資金を貯めるためには、「節約」や「運用」も大切ですが、それ以上に重要なのが「収入を確保し続ける」ことです。特に、子どもが生まれると、働き方を見直す方も多いでしょう。
もちろん、家庭の事情は様々ですが、可能であれば共働きを続ける、あるいは一度離職しても再就職するなどして、世帯収入を維持・向上させる努力が、教育資金の確保に直結します。
収入が安定していれば、毎月の積立額を増やすことができ、目標達成までの道のりがぐっと楽になります。将来のキャリアプランも含めて、夫婦でしっかりと話し合っておくことが大切です。
幼稚園から大学まで子どもに必要な教育資金はいくら?
教育資金の準備を始めるにあたり、まず把握すべきなのが「ゴールとなる目標金額」です。子どもがどのような進路を歩むかによって、必要な教育費は大きく変わります。
文部科学省の調査によると、幼稚園から大学卒業までにかかる教育費の目安は以下の通りです。
【幼稚園から高校までの学習費総額(15年間)】
| 進路パターン | 学習費総額 |
| 全て国公立 | 約574万円 |
| 幼稚園のみ私立 | 約622万円 |
| 高校のみ私立 | 約739万円 |
| 全て私立 | 約1,830万円 |
出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
【大学4年間の学費】
| 大学の種類 | 学費総額(入学金含む) |
| 国立大学 | 約243万円 |
| 公立大学(地域内) | 約254万円 |
| 私立大学(文系) | 約408万円 |
| 私立大学(理系) | 約551万円 |
| 私立大学(医歯系) | 約2,393万円 |
出典:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」「令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額の調査結果について」を基に算出
これらのデータを基に、進路パターン別の教育資金の総額をシミュレーションしてみましょう。
【進路パターン別 教育資金総額の目安】
| 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 合計 |
| 国公立 | 国公立 | 国公立 | 国公立 | 国立 | 約817万円 |
| 私立 | 公立 | 公立 | 公立 | 私立文系 | 約1,102万円 |
| 私立 | 公立 | 公立 | 私立 | 私立理系 | 約1,440万円 |
| 私立 | 私立 | 私立 | 私立 | 私立理系 | 約2,381万円 |
このように、オール国公立でも1,000万円近く、私立大学に進学することも視野に入れると1,500万円以上の資金が必要になる可能性があります。また、子どもが2人、子ども3人となれば、その分必要額も増えていきます。
もちろん、これはあくまで平均的なデータであり、塾や習い事、一人暮らしをする場合の仕送りなどを含めると、さらに多くの費用がかかることもあります。まずは、「大学費用として少なくとも500万円を準備する」など、具体的な目標を立てることが、計画的な準備の第一歩です。
教育資金を十分に貯められないときはどうする?
計画的に準備を進めていても、家計の状況の変化などにより、どうしても教育資金が足りなくなってしまう悩みを抱えることもあるかもしれません。そんな時は、以下の方法を検討しましょう。
- 奨学金制度を利用する
最も一般的な方法が奨学金です。独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には、返済不要の「給付型」と、卒業後に返済が必要な「貸与型」(無利子の第一種と有利子の第二種)があります。大学や地方自治体が独自に設けている奨学金制度もあります。 - 教育ローンを借りる
奨学金が学生本人に貸し付けられるのに対し、教育ローンは保護者が借りるものです。国の教育ローン(日本政策金融公庫)は、民間の金融機関のローンに比べて金利が低い傾向にあります。ただし、いずれも借金であることには変わりなく、計画的な返済が必要です。 - 祖父母からの支援を受ける
祖父母から教育資金の援助を受けられる場合は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という制度を活用できる可能性があります。これは、30歳未満の子や孫へ教育資金を贈与する場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です(※適用には金融機関での専用口座開設などの要件あり)。
これらの方法は、あくまで最終的な選択肢です。まずは家計を見直し、早い段階からコツコツと準備を進めることが何よりも大切です。
まとめ:家庭に合った方法で、子どもの未来を応援しよう
本記事では、教育資金の貯め方について、「預貯金」「保険」「投資」という3つの基本的な方法から、着実に貯めるためのコツ、必要な金額の目安まで詳しく解説してきました。
【この記事のポイント】
- 教育資金の貯め方は「預貯金(安全性)」「保険(保障と計画性)」「投資(収益性)」の3種類。
- それぞれにメリット・デメリットがあるため、複数を組み合わせてリスクを分散させることが重要。
- 人気の方法は学資保険だが、家庭の方針に合わせてNISAなどを活用するのも有効。
- 成功の鍵は「早期開始」。児童手当などを活用し、「貯めどき」を逃さずに計画的に準備する。
- 目標額は進路によるが、1,000万円〜1,500万円が一つの目安。まずは具体的な目標設定から始める。
教育資金の準備は、ゴールまでの期間が長いからこそ、後回しにしてしまいがちです。しかし、早く始めれば始めるほど、月々の負担は軽くなり、選択肢も広がります。
この記事を参考に、まずはあなたの家庭に合った貯め方はどれか、夫婦で話し合ってみてください。そして、まずは専用の口座を開設する、資料請求をしてみるなど、小さな一歩から始めてみましょう。