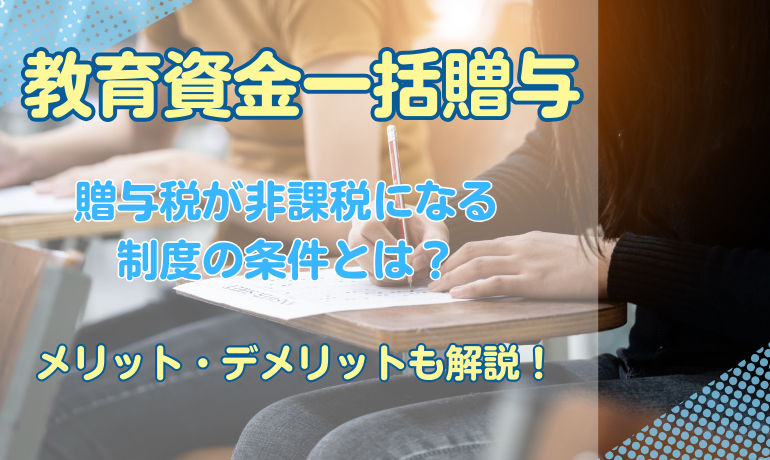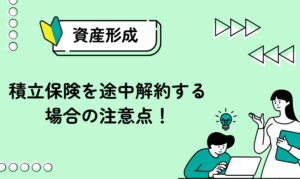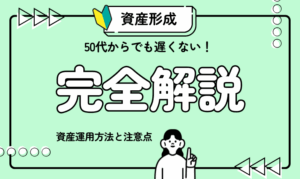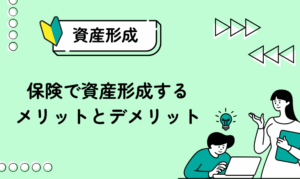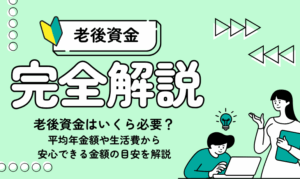「孫の将来のために、まとまった教育資金を渡してあげたい」「子どもの進学費用を早めに準備しておきたいけれど、贈与税が心配……」
お子さんやお孫さんを想う気持ちから、教育資金の援助を検討している方は多いのではないでしょうか。しかし、一度に大きな金額を贈与すると、高額な贈与税がかかってしまう可能性があります。
そんな悩みを解決するのが「教育資金一括贈与」の非課税制度です。この制度を活用すれば、最大1,500万円までの教育資金を非課税で一括贈与できます。
この記事では、教育資金の一括贈与を検討している方に向けて、制度の詳しい内容や利用条件、メリット・デメリット、具体的な手続き方法まで、わかりやすく解説します。制度を正しく理解し、大切なご家族のために最も良い方法を選択するお手伝いができれば幸いです。
教育資金一括贈与とはどんな制度?
まずは、教育資金一括贈与の非課税制度がどのようなものなのか、基本的な仕組みから見ていきましょう。
教育資金贈与が1500万円まで贈与税が非課税になる制度
教育資金一括贈与の非課税制度の正式名称は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」です。
これは、30歳未満の子や孫(ひ孫も対象)に対して、その方の祖父母や父母などの直系尊属が、金融機関に専用の口座を開設し教育資金を一括で拠出した場合、受贈者(お金を受け取る子や孫)一人あたり最大1,500万円までの金額について贈与税が非課税になる、という特例制度です。
通常、個人から年間110万円を超える贈与を受けた場合には贈与税が課税されますが、この制度を利用することで、将来必要となる教育資金を前もって、かつ税金の負担なくまとめて渡すことが可能になります。
この制度は、次世代への資産移転を促し、子育て世代の経済的負担を軽減することを目的とした期間限定の措置として創設されました。
制度の対象者
この制度を利用できるのは、以下の関係にある人たちです。
贈与者(お金をあげる人):
受贈者の直系尊属。具体的には、父母、祖父母、曽祖父母などが該当します。叔父や叔母、配偶者の親(義父母)は直系尊属ではないため、対象外。
受贈者(お金をもらう人):
贈与を受ける年の1月1日時点で30歳未満の子や孫、ひ孫。
つまり、祖父母から孫へ、あるいは親から子へ、といった形で利用できる制度です。
令和8年3月31日で終了になる
この非課税措置は、もともと平成25年(2013年)4月1日から始まった制度です。その後、何度か税制改正による延長が繰り返されてきましたが、現時点では令和8年(2026年)3月31日までに金融機関等との契約を締結したものが対象とされています。
この期限を過ぎると、原則としてこの制度は利用できなくなります。つまり、制度の廃止が予定されているということです。
また、追加で資金を信託・預入する場合も、この期限内に行う必要があります。教育資金の一括贈与を検討している方は、この期限を念頭に置いて計画を進めることが重要です。今後の税制改正で再延長される可能性もゼロではありませんが、現行制度を確実に利用するためには早めの準備をおすすめします。
教育資金一括制度を利用するための条件
この非課税制度を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件は以下の3つです。
直系尊属かつ受贈者が30歳未満であること
前述の通り、贈与者と受贈者の関係性が最も重要な要件です。贈与者は父母や祖父母などの直系尊属、受贈者は30歳未満の子や孫(ひ孫も含む)でなければなりません。
教育のための資金贈与であること
贈与された資金の使い道は、その名の通り「教育のための資金」に限定されます。どのような費用が対象になるかについては、後ほど詳しく解説します。金融機関に開設した専用口座から払い出しを行う際には、その支払いが教育目的であることを証明する領収書などの提出が必要になります。
受贈者の合計所得金額が1,000万円を超えないこと
2019年の税制改正により、新たに所得制限が設けられました。
具体的には、贈与契約を結ぶ前年の受贈者(お金をもらう子や孫)の合計所得金額が1,000万円を超える場合、この非課税制度の適用を受けることはできません。
例えば、すでに社会人として働いている20代の子や孫に贈与する場合、その方の前年の所得を確認する必要がありますのでご注意ください。
暦年贈与や相続時精算課税制度との併用も可能
贈与税に関する制度には、教育資金一括贈与の他にも「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」があります。嬉しいことに、教育資金一括贈与はこれらの制度と併用することが可能です。
暦年贈与とは?
相続時精算課税制度とは?
教育資金一括贈与は、これら2つの制度の非課税枠とは別枠で利用できます。
例えば、祖父から孫へ教育資金として1,500万円を一括贈与(非課税)し、さらに同じ年に、生活費の援助など別の目的で暦年贈与の枠を使って110万円を贈与(非課税)することも可能です。
このように、各制度をうまく組み合わせることで、より大きな金額を非課税で次世代へ移転させることができます。
教育資金一括贈与で非課税が適用される範囲
この制度で非課税となる教育資金は、支払先によって上限額が異なります。具体的には、最大1,500万円の非課税枠の中に、さらに「500万円まで」という別の枠が設けられています。
対象となる費用の範囲を正しく理解しておくことが、制度を有効活用する上で非常に重要です。
学校等に対して支払う費用(1,500万円まで)
まず、非課税限度額である1,500万円の枠をすべて使えるのは、「学校等」に対して直接支払われる費用です。
ここでいう「学校等」とは、学校教育法で定められた学校などを指します。具体的には以下のようなものが含まれます。
| 対象となる学校等の種類 | 支払われる費用の具体例 |
| 学校教育法上の学校 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校 |
| 外国の教育施設 | 日本にあるインターナショナルスクール、海外の学校(留学費用など) |
| 認定こども園・保育園 | 認定こども園、保育園、その他一定の基準を満たす認可外保育施設 |
| その他 | 自動車学校や教習所(※)、防衛大学校、気象大学校など |
これらの学校等に対して支払われる、以下のような費用が1,500万円までの非課税対象となります。
- 入学金、入園料、授業料、保育料
- 施設設備費、教育充実費
- 受験料
- 学用品の購入費(ランドセル、教科書、制服など)
- 給食費
- 修学旅行費、学校が主催する遠足費
- 学校寮の費用(下宿代)
(※)自動車学校や教習所の費用は、教育訓練給付金の支給対象となる講座など、一定の要件を満たす場合に「学校等」の費用として認められます。
塾や習い事などに支払う費用(500万円まで)
次に、「学校等以外」の教育サービスに対して支払われる費用です。これらは、上記の1,500万円の枠のうち、500万円を上限として非課税の対象となります。
具体的には、以下のような費用が該当します。
- 学習塾や予備校の授業料
- 水泳、ピアノ、書道、そろばんなどの習い事の月謝や謝礼
- スポーツ(野球、サッカーなど)や文化活動(バレエ、絵画教室など)に関する指導への対価
- 上記サービスを受けるために使用する物品の購入費
- 上記サービスを受けるための交通費(通学定期券代など)
例えば、大学の授業料として1,000万円、予備校の費用として300万円を支払う場合、合計1,300万円となり、全額が非課税となります。
しかし、大学の授業料が800万円、予備校や習い事の費用が600万円だった場合、合計は1,400万円ですが、予備校等の費用は500万円までしか非課税になりません。そのため、超過した100万円分については非課税の対象外となってしまいます。
非課税が適用されない費用
教育に関連する支出でも、この制度の対象外となるものがあります。うっかり支払ってしまうと、後から贈与税が課税される可能性もあるため注意が必要です。
以下は、非課税とならない費用の代表例です。
学校の寮費は対象ですが、個人でアパートやマンションを借りる際の家賃や敷金・礼金は対象外です。
一人暮らしの学生への仕送りは、教育費ではなく生活費と見なされるため対象外です。
留学中に観光するための費用や、部活動で使う道具でも個人的な趣味の範囲と判断される高価なものは対象外となる可能性があります。
原則として対象外です。ただし、学校からの指示で全員が購入必須となっている場合など、教育に直接必要であると証明できる場合に限り、認められるケースもあります。
教育資金を準備するための学資保険の保険料は、この制度の対象外です。贈与された資金を学資保険の支払いに充てることはできません。
学校等の費用として認められる特定の講座を除き、一般的な運転免許の取得費用は対象外です。
教科書など学校から指定された学用品は対象ですが、日常的に使うノートやペンなどの文房具は、社会通念上、教育費とは認められにくいです。
教育ローンを組んだ場合の利息分は対象外です。
これらの費用を支払う必要がある場合は、暦年贈与の枠(年間110万円)を利用するなど、別の方法を検討するのが良いでしょう。
教育資金一括贈与を利用するメリット
この制度には、贈与税の非課税以外にもいくつかのメリットがあります。
① まとまった教育資金を一度に非課税で贈与できる
② 相続税の節税対策になる
③ 贈与者の意思通りに資金を使ってもらえる
④ 暦年贈与など他の制度と併用できる
教育資金一括贈与を利用するデメリット
多くのメリットがある一方で、この制度にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。安易に利用を決めず、デメリットもしっかりと理解した上で判断することが大切です。
専用口座開設や贈与契約書など手続きが面倒
この制度を利用するためには、ただお金を渡すだけでは済みません。以下のような一連の手続きが必要となり、非常に面倒だと感じる方も少なくありません。
- 贈与者と受贈者の間で贈与契約書を作成する。
- 取扱金融機関(銀行、信託銀行、証券会社など)で、受贈者名義の専用口座を開設する。
- 金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を税務署に提出する。
これらの手続きには、戸籍謄本や本人確認書類など、複数の必要書類を準備する必要があります。
また、金融機関によっては、口座開設や管理に手数料がかかる場合があります。手数料の金額は金融機関によって異なり、数万円程度かかることもあるため、事前に比較検討することが重要です。
引き出しには領収書が必要
専用口座からお金を引き出す際、そのお金が教育目的で使われたことを証明するために、金融機関に領収書や請求書を提出しなければなりません。
引き出し方法は金融機関によって異なりますが、主に以下の2つのパターンがあります。
立て替え払い
直接支払い
いずれにせよ、支払いの都度、領収書を保管し、金融機関に提出するという手間が発生します。領収書を紛失してしまうと、口座からお金を引き出せなくなるリスクもあります。クレジットカードでの支払いも可能ですが、その場合も利用明細など支払いを証明する書類が必要です。
贈与税や相続税の対象になることがある
非課税制度といっても、どのような場合でも完全に税金がかからないわけではありません。特定の条件下では、贈与税や相続税の課税対象となってしまうケースがあります。
① 受贈者が30歳になったら残額に贈与税がかかる
受贈者が30歳に達した時点で、専用口座に使い切らなかったお金(管理残額)が残っている場合、その残額に対して贈与税が課税されます。
例えば、1,000万円の贈与を受け、30歳までに800万円を使い、200万円が残ったとします。この200万円は、30歳になった年に贈与があったものとみなされ、基礎控除110万円を差し引いた90万円に対して贈与税が計算されます。
ただし、受贈者が30歳になった時点で大学院などに在学している場合は、40歳に達する日まで契約を継続できる特例があります。
② 贈与者が死亡すると残額が相続税の対象になることがある
契約期間中に贈与者(お金をあげた祖父母など)が死亡した場合、その時点での口座の残額が相続税の課税対象になる可能性があります。これは「持ち戻し」と呼ばれます。
2023年(令和5年)の税制改正により、この持ち戻しのルールが厳しくなりました。
改正前
改正後(2023年4月1日以降の契約)
この改正により、制度の相続税対策としての効果は薄れたと言えます。これから制度を利用する方は、この点を十分に理解しておく必要があります。
③ 教育資金以外に使うと贈与税がかかる
当然ながら、口座の資金を教育目的以外(生活費や遊興費など)に使用した場合は、その支出額が贈与税の課税対象となります。税務署の調査で発覚した場合は、ペナルティが課される可能性もあります。
中途解約ができない
教育資金一括贈与の契約は、原則として中途解約ができません。
解約が認められるのは、以下の2つのケースに限られます。
- 受贈者が30歳に達した場合(または40歳に達した場合)
- 受贈者が死亡した場合
そのため、一度契約すると、贈与者側の事情(事業の悪化など)でお金が必要になっても、口座の資金を戻すことはできません。
また、家庭環境の変化にも注意が必要です。例えば、両親の離婚により親権者が変更になった場合でも、口座の管理は引き続き親権者が行うことになります。贈与者である祖父母から見て、望まない相手(元配偶者など)が資金を管理することになる可能性があり、心理的な抵抗を感じるケースも考えられます。
さらに、万が一受贈者(子や孫)が贈与者より先に死亡してしまった場合、口座に残ったお金(残額)は、受贈者の相続財産となります。これは、法定相続人(例えば、離婚した元配偶者など)に渡る可能性があることを意味します。これも贈与者にとっては意図しない結果かもしれません。
このように、一度始めると簡単にはやめられないという点は、大きなデメリットと言えるでしょう。
教育資金一括贈与のやり方
制度のメリット・デメリットを理解した上で、実際に利用したいと考えた場合の手続き方法と預金の使い方について解説します。
教育資金一括贈与の手続き方法
手続きの大まかな流れは以下の通りです。
- 取扱金融機関を選ぶ:
まずは、教育資金贈与信託(信託銀行)や教育資金贈与専用の預金口座(銀行など)を扱っている金融機関を選びます。ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行といったメガバンクや、三井住友信託銀行などの信託銀行、千葉銀行、横浜銀行、京都銀行、八十二銀行、もみじ銀行といった地方銀行、JAバンクなど、多くの金融機関が取り扱っています。手数料、サービス内容、店舗の利便性などを比較して選びましょう。金融機関の変更は原則できないため、慎重に選ぶ必要があります。 - 贈与契約を結び、必要書類を準備する:
贈与者と受贈者の間で、教育資金の一括贈与である旨を明確にした贈与契約書を作成します。同時に、金融機関での手続きに必要な書類を準備します。
【主な必要書類の例】- 贈与契約書
- 教育資金非課税申告書(金融機関で入手)
- 贈与者と受贈者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 贈与者と受贈者の直系尊属関係を証明する書類(戸籍謄本など)
- 受贈者のマイナンバーが確認できる書類
- (所得制限の確認のため)受贈者の前年の所得を証明する書類
- 金融機関で専用口座を開設し、資金を預け入れる:
受贈者が金融機関の窓口へ行き、準備した書類を提出して専用口座の開設を申し込みます。その後、贈与者がその口座へ一括で資金を振り込みます。 - 金融機関が税務署へ申告書を提出:
口座が開設されると、金融機関が納税地の所轄税務署へ「教育資金非課税申告書」を提出します。これにより、非課税の適用を受けるための手続きは完了です。受贈者自身が確定申告をする必要はありません。
預金の使い方・引き出し方法
専用口座からの資金の引き出しは、前述の通り、教育費の領収書などを金融機関に提出して行います。
- 受贈者(または親権者)が授業料などを支払う
- 支払った際の領収書を受け取る
- 金融機関の窓口や郵送で、払戻請求書と領収書を提出する
- 審査後、口座から同額が払い出される。
- 学校などから受け取った請求書を用意する
- 金融機関の窓口や郵送で、振込依頼書と請求書を提出する
- 金融機関が口座から直接、支払先に振り込む。
支払日から一定期間内に手続きが必要な場合や、領収書に記載すべき項目(支払日、金額、支払先、支払い内容など)が細かく決まっている場合があります。具体的なルールは取扱金融機関によって異なるため、問い合わせて事前に確認しておくことが重要です。
教育資金は都度贈与しても贈与税がかからない
ここまで教育資金の一括贈与制度について解説してきましたが、実は、そもそも「必要なときに必要な分だけ」教育費を渡す方法(都度贈与)であれば、贈与税はかかりません。
相続税法では、「扶養義務者から生活費又は教育費に充てるために取得した財産のうち、通常必要と認められるもの」は贈与税の対象にならないと定められています。
つまり、親が子の大学の入学金や授業料をその都度支払ったり、祖父母が孫の中学校の制服代を負担したりすることは、それが社会通念上妥当な金額であれば、贈与にはあたらないのです。
この都度贈与は、面倒な手続きや領収書の管理、資金の使途制限などが一切なく、最もシンプルで分かりやすい方法です。
では、どんな人に一括贈与がおすすめ?
都度贈与でも非課税になるなら、なぜ手間のかかる一括贈与制度を利用するメリットがあるのでしょうか。一括贈与が特におすすめなのは、以下のようなケースです。
将来の相続税が多額になりそうな人
贈与者の健康状態に不安がある人
将来の教育資金を確実に確保しておきたい人
これらのニーズがなく、都度必要な費用を援助できる状況にあるのであれば、無理に一括贈与制度を利用せず、シンプルな都度贈与を選択する方が良い場合も多いでしょう。
まとめ
教育資金一括贈与の非課税制度は、子や孫の将来を想う気持ちを形にし、次世代を力強くサポートできる有効な手段です。最大1,500万円という大きな非課税枠は非常に魅力的です。
しかし、その一方で、手続きの煩雑さや資金使途の制限、中途解約ができないといったデメリット、そして税制改正によるルールの変更など、利用する前に必ず理解しておくべき注意点も数多く存在します。
この制度の利用を検討する際は、
- 制度の期限(令和8年3月31日)はいつか?
- 非課税の対象となる費用、ならない費用は何か?
- 手続きの手間や領収書の管理は負担にならないか?
- 30歳で使い切れない場合や、贈与者が死亡した場合の課税リスクは?
- そもそも「都度贈与」ではダメなのか?
といった点を総合的に考慮し、ご自身の家庭の状況や目的に本当に合っているのかを慎重に判断することが重要です。
もし判断に迷う場合は、税理士やファイナンシャルプランナー、金融機関の専門家などに相談し、アドバイスを求めることをおすすめします。制度を正しく理解し、賢く活用することで、大切なご家族の未来を豊かに育んでいきましょう。