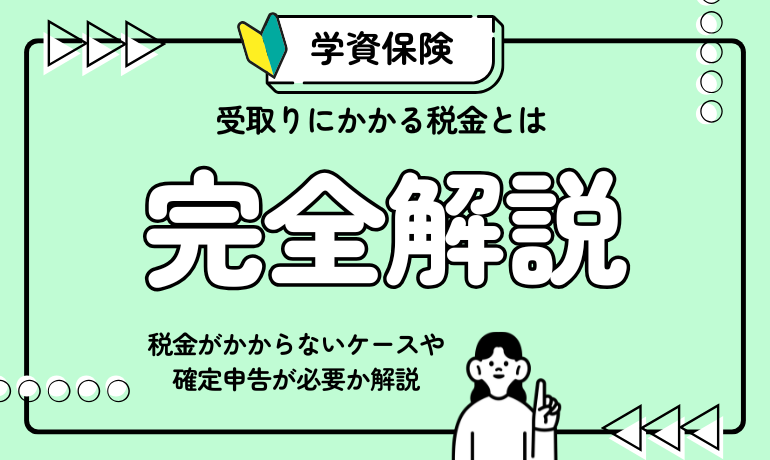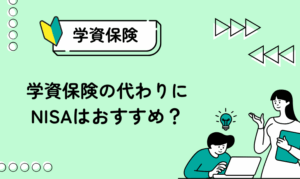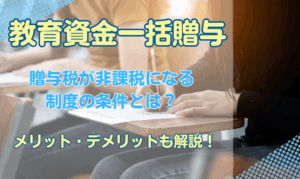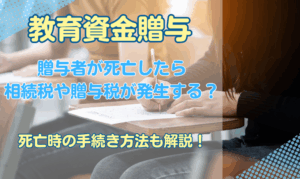学資保険から受け取るお金には、税金がかかることがあります。お子様の教育資金として積み立ててきた大切なお金を受け取る際、思わぬ税金の負担で手取り額が減ってしまうケースもあるため、事前に税金の仕組みを理解しておくことが重要です。
本記事では、学資保険の受取時にかかる税金の種類や税金がかからないケース、確定申告の必要性について詳しく解説します。学資保険からお金を受け取る予定がある方もすでに受け取った方も、ぜひ参考にしてください。
学資保険の受取りにかかる税金とは
学資保険は、お子様の教育資金を計画的に準備するための保険商品です。契約時に定めた時期に祝金や満期保険金を受け取ることができますが、その受取方法や契約形態によってさまざまな種類の税金がかかる可能性があります。
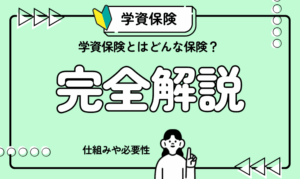
学資保険の受取時にかかる税金は、主に「所得税」「贈与税」「相続税」の3種類です。どの税金が適用されるかは、保険料の負担者(契約者)と保険金の受取人の関係、受取方法などによって決まります。
祝金の税金
祝金は、学資保険の契約期間中に、お子様の進学時期に合わせて受け取れるお金です。一般的に、小学校入学時、中学校入学時、高校入学時などのタイミングで支払われます。
祝金を受け取った場合、その対象となる税金は、保険料負担者と受取人の関係によって異なります。保険料負担者と受取人が同一人物の場合は「所得税」の対象となり、異なる場合は「贈与税」の対象です。
ただし、祝金の金額や他の所得との合計額によっては、税金がかからないケースも多くあります。特に、一括で受け取る祝金の場合、一時所得として計算され、特別控除額50万円を差し引いた後の金額が課税対象となるため、実際に税金がかかるケースは限定的です。
満期保険金の税金
満期保険金は、学資保険の契約期間が満了した際に受け取れるまとまった金額です。多くの場合、お子様が大学に進学する18歳や20歳のタイミングで受け取ることになります。
満期保険金にかかる税金も、祝金と同様に保険料負担者と受取人の関係によって決まります。同一人物の場合は所得税(一時所得または雑所得)、異なる場合は贈与税の対象です。
満期保険金は金額が大きくなることが多いため、税金の負担も大きくなりやすい傾向があります。ただし、受取方法を工夫することで、税負担を軽減できる場合もあります。
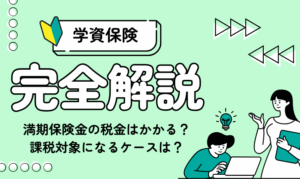
解約払戻金の税金
解約払戻金は、学資保険を途中で解約した際に受け取れるお金です。家計の事情や教育プランの変更などにより、満期を待たずに解約するケースで発生します。
解約払戻金についても、保険料負担者と受取人が同一人物の場合は所得税(一時所得)の対象となり、異なる場合は贈与税の対象となります。ただし、解約払戻金は支払った保険料総額を下回ることが多く、この場合は差益が発生しないため、実質的に税金がかからないケースがほとんどです。
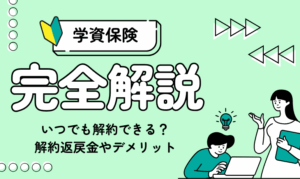

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の受取りで税金がかからないケース
学資保険から受け取るお金すべてに、税金がかかるわけではありません。受け取り方や金額、契約形態によっては、税金がかからないケースも多くあります。ここでは、税金がかからない主なケースについて、わかりやすく解説します。
一括で受取る場合
学資保険の保険金を一括で受け取る場合、保険料負担者と受取人が同一人物であれば、一時所得として計算されます。一時所得には50万円の特別控除があるため、以下の条件を満たせば税金はかかりません。
税金がかからない条件:
- 受取保険金総額 – 支払保険料総額 – 50万円(特別控除)≦ 0
例えば、300万円の満期保険金を受け取り、支払った保険料総額が260万円の場合、差益は40万円となります。この差益から特別控除50万円を差し引くと、課税対象額は0円となるため、税金はかかりません。
一方、200万円の満期保険金を受け取り、支払保険料総額が130万円の場合、差益は70万円となります。特別控除50万円を差し引いても20万円が残るため、この金額の2分の1(10万円)が課税対象です。
年金形式で受取る場合
学資保険の保険金を年金形式で分割して受け取る場合は、雑所得として計算されます。会社員の方で給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要となるため、実質的に税金がかからないケースがあります。
例えば、毎年30万円を5年間で受け取る契約で、その年に対応する支払保険料が25万円の場合、雑所得は5万円となります。他に雑所得がなければ、20万円以下のため確定申告は不要です。
ただし、年金形式で受け取る場合は毎年の所得として計算されるため、他の雑所得と合算して20万円を超えると確定申告が必要になる点に注意が必要です。
契約者と受取人が違う場合
契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合は、贈与税の対象となります。贈与税には年間110万円の基礎控除額があるため、以下の条件を満たせば税金はかかりません。
例えば、祖父母が契約者となり孫が受取人となっている学資保険で、年間100万円の祝金を受け取った場合、基礎控除額110万円以下のため税金はかかりません。
ただし、同じ年に他の贈与も受けている場合は、それらと合算して110万円を超えると贈与税がかかるため注意が必要です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の受取りでかかる税金の計算方法
学資保険の受取時に税金がかかる場合、その計算方法は税金の種類によって異なります。ここでは、それぞれの税金の計算方法と具体例を紹介します。
保険料の負担者と受取人が同じ場合
先述の通り、保険料負担者と受取人が同一人物の場合、受け取る保険金は所得税の対象となります。そして、受取方法により一時所得または雑所得として計算されます。
所得税(一時所得)
一括で保険金を受け取る場合は、一時所得として計算されます。
計算式: 一時所得 = 受取保険金総額 – 支払保険料総額 – 特別控除50万円
課税対象額 = 一時所得 × 1/2
具体例(300万円受取の場合):
・受取保険金:300万円
・支払保険料総額:220万円
・一時所得:300万円 – 220万円 – 50万円 = 30万円
・課税対象額:30万円 × 1/2 = 15万円
この15万円が他の所得と合算されて、所得税が計算されます。
具体例(200万円受取の場合):
・受取保険金:200万円
・支払保険料総額:160万円
・一時所得:200万円 – 160万円 – 50万円 = △10万円(マイナス)
・課税対象額:0円
この場合、一時所得がマイナスとなるため、税金はかかりません。
所得税(雑所得)
年金形式で保険金を受け取る場合は、雑所得として計算されます。
計算式: 雑所得 = その年の受取額 – その年に対応する支払保険料
具体例:
・年間受取額:40万円
・その年に対応する支払保険料:32万円
・雑所得:40万円 – 32万円 = 8万円
この8万円が他の雑所得と合算されて、所得税が計算されます。
契約者と受取人が違う場合
契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合、受け取る保険金は贈与税または相続税の対象となります。
贈与税
契約者が生存している状態で、受取人が保険金を受け取る場合は贈与税の対象となります。
計算式: 課税価格 = 受取保険金 – 基礎控除110万円
贈与税額 = 課税価格 × 税率 – 控除額
具体例(200万円受取の場合):
・受取保険金:200万円
・課税価格:200万円 – 110万円 = 90万円
・贈与税額:90万円 × 10% – 0円 = 9万円
贈与税の税率は、基礎控除後の課税価格によって異なり、200万円以下の場合は10%となります。
相続税
契約者が死亡し、受取人が保険金を受け取る場合は相続税の対象となります。ただし、相続税には基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)があるため、多くの場合は税金がかかりません。
計算式: 相続税の課税価格 = 相続財産総額 – 基礎控除
学資保険の保険金も相続財産に含まれますが、生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人数)の適用を受けられる場合があります。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険を受け取ったら確定申告は必要?
学資保険から保険金を受け取った場合、確定申告が必要かどうかは、受け取った保険金の種類や金額、他の所得の有無などによって異なります。
確定申告が必要なケース:
1.一時所得の場合
課税対象となる一時所得(特別控除後の金額の1/2)が発生した場合
ただし、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合は申告不要
2.雑所得の場合
雑所得が20万円を超える場合(給与所得者)
雑所得がある場合(給与所得者以外)
3.贈与税の場合
年間の贈与額合計が110万円を超える場合
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
確定申告が必要であるにもかかわらず申告しなかった場合、以下のようなペナルティが課される可能性があります。
確定申告をしなかった場合のリスク:
1.無申告加算税
納付すべき税額の15%(50万円を超える部分は20%)
2.延滞税
申告期限から実際に申告・納付するまでの期間に応じて課税
3.重加算税
悪質な所得隠しと判断された場合、35%または40%徴収
税務署は保険会社から提出される支払調書により、保険金の支払いを把握しています。そのため、申告漏れは後日必ず発覚(ばれる)することになります。
年末調整での対応:
学資保険から受け取った保険金は、年末調整では処理できません。年末調整は給与所得の源泉徴収税額の精算を行うものであり、一時所得や雑所得、贈与税については対象外となります。
したがって、確定申告が必要な場合は、翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間中に、税務署に申告書を提出する必要があります。
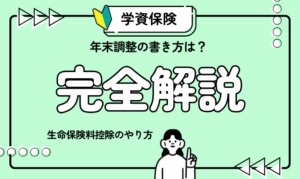

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
まとめ
学資保険の受取時にかかる税金は、契約形態や受取方法によって異なります。保険料負担者と受取人が同一の場合は所得税、異なる場合は贈与税または相続税の対象となりますが、多くのケースでは各種控除により税金がかからないか、負担が軽減されます。
特に重要なポイントは、以下の通りです。
・一括受取の場合、差益が50万円以下なら税金はかからない
・年金形式の受取で雑所得が20万円以下なら確定申告は不要(給与所得者の場合)
・贈与の場合、年間110万円までは非課税
・確定申告が必要な場合は、必ず期限内に申告する
学資保険は大切な教育資金を準備するための商品です。受取時の税金について正しく理解し、適切に申告することで、計画通りの教育資金を確保することができます。不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!