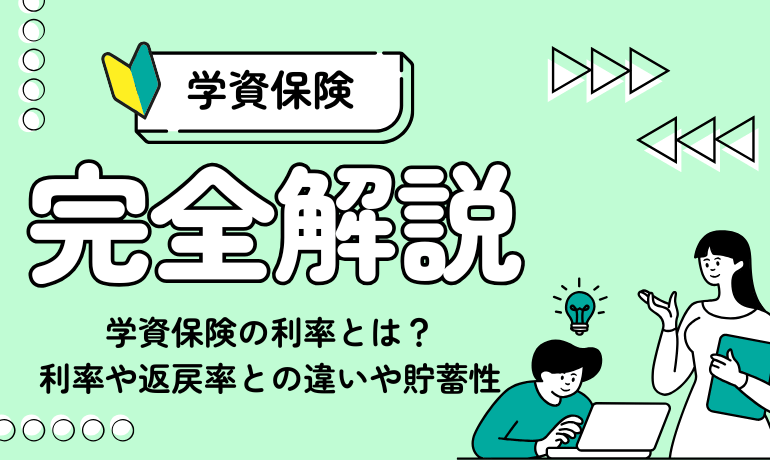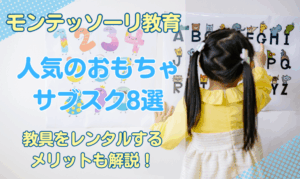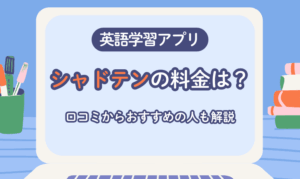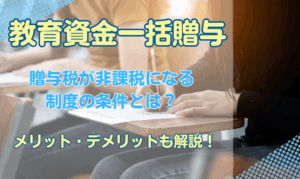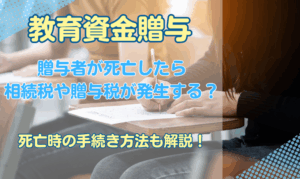学資保険の利率とは
学資保険の利率とは、契約時に保険会社が約束する運用利率(予定利率)のことです。保険会社は契約者から預かった保険料を国債などで運用し、その運用益を見込んで将来の保険金や保険料を計算します。この利率は学資保険の仕組み(からくり)の中核であり、加入時点の予定利率によって保険料や受取額が決まります。利率が高ければ運用益が多く見込めるため保険料は割安になり、逆に利率が低ければ運用益が少ない分保険料が割高になる傾向があります。
ただし、この「予定利率」はあくまで保険会社の内部で使われる指標で、加入者が直接受け取る金利とは異なります。契約時に定められた予定利率は満期まで固定され、契約後に変更されることはありません。そのため、過去に予定利率の高い時期(高金利時代)に契約された学資保険は、比較的少ない保険料で大きな満期金を受け取れる「お宝保険」と呼ばれることもあります。一方、現在は超低金利時代が続いており、予定利率も大幅に低下しています。この利率低下の影響で学資保険の返戻率(戻り率)も昔より低い水準になっているのが現状です。
学資保険の利率とは「予定利率」のこと
改めて、学資保険における利率=予定利率について解説します。予定利率とは、保険会社が契約者の支払った保険料を運用する際に見込む利率のことです。言い換えれば、保険会社が「このくらい増やせますよ」と契約者に約束している運用利回りを指します。予定利率は各社が独自に定めていますが、背景には金融庁が決める「標準利率」という指標があり、市場金利の動向に応じて各社ほぼ横並びの水準になります。
予定利率が高い時期に契約した学資保険では、その分運用益が期待できるため保険料が安く抑えられ、相対的に返戻率(戻り率)も高くなる傾向にありました。例えば1990年代の高金利期には予定利率が3~5%と非常に高く、返戻率が120%超の学資保険も珍しくなかったほどです。しかし現在のような低金利下では予定利率は1%を下回る水準となっており、学資保険の返戻率もおおむね103~105%程度に収まっています。予定利率が下がった結果、昔に比べて利率が悪い(低い)学資保険ばかりになってしまったというわけです。
なお、予定利率そのものは各社の商品パンフレット等に明示されないことも多く、一般消費者には分かりにくい指標です。実際に学資保険の「お得さ」を判断する際は、予定利率よりも返戻率を見るほうが分かりやすいため、次で詳しく説明します。
利率と利回りの違い
学資保険を語るうえで混同しがちなものに「利率」と「利回り」があります。ここで言う利率は前述の予定利率を指しますが、利回りとは実際に契約者が得られる運用成果を年率換算した数値のことです。簡単に言えば、利回り=実質的な年利であり、学資保険の場合は支払った保険料に対し満期金などで増えた利益を、運用期間で慣らして年率に置き直したものです。
利率(予定利率)は保険会社が計算上使用するもので、高ければ保険料が安くなる要因ですが、それがそのまま契約者の儲けには直結しません。一方、利回りは契約者目線での実質的な増え方を示すので、こちらのほうが「結局どれくらい得したか」を示す指標と言えます。
例えば、ある学資保険の返戻率が104%だったとしましょう。多くの方は「104%なら元本より4%増えるからお得だ」と感じるでしょうが、この104%というのはあくまで保険期間全体での増加率です。仮にこの保険期間が18年間だとすると、利回り(年利換算)に直すと約0.4~0.5%程度に過ぎません。「返戻率105%=年利5%」では決してない点に注意が必要です。学資保険では保険料を長期間かけてコツコツ払い込むため、運用期間全体では少し増えていても年単位で見るとごくわずかな利息しか付かないというケースがほとんどです。
このように、予定利率(利率)は保険会社の運用利率、利回りは契約者が得る実質利率(年利換算)と覚えておきましょう。一般に近年の学資保険では、返戻率103~105%程度の商品が多く、その場合の年利回りは0.3~0.5%前後となります。超低金利の銀行預金(金利0.001%~0.1%程度)に比べればわずかに有利ですが、かつての学資保険ほど大きなリターンは期待できないのが現状です。
利率と返戻率の違い
返戻率(へんれいりつ)とは、学資保険で支払った保険料総額に対して、受け取れる祝金・満期保険金の総額がどの程度になるかを示す割合です。計算式は以下の通りで、学資保険のパンフレットや比較サイトでもよく使われる指標です。
返戻率(%) = 受取総額(祝金・満期金) ÷ 支払総額(払込保険料) × 100
返戻率が100%なら支払総額と受取総額が同じ、100%を超えれば支払った額より多く受け取れる(※貯蓄性がある)、100%を下回れば支払額より受取額が少ない(※元本割れ)ことを意味します。例えば、ソニー生命の学資保険(大学入学一時金タイプ)で、契約者30歳・子ども0歳の場合に15年間で約382万円の保険料を払い込み、満期時に400万円を受け取れるケースでは返戻率104.62%になります。100%を上回っていれば「支払った額より多く受け取れるお得な保険」ということになり、学資保険を選ぶ際にはこの返戻率が重要な比較ポイントとなります。
しかし、返戻率は時間の要素を考慮していない点に注意しましょう。先ほどの例では104.62%の返戻率でしたが、18年間運用した利回りで見ると約0.5%に過ぎないことを述べました。返戻率はあくまで総額ベースの割合なので、長期間運用すればするほど数字上は高く見えても、実際の年利ベースでは低くなる場合があります。
まとめると、学資保険の利率(予定利率)は保険会社が設定する運用利率であり、返戻率は支払額に対する受取額の割合(増えた分の率)です。そして利回りはその増えた分を年率に均したものです。それぞれ意味が異なるので混同しないようにしましょう。
学資保険の利率の平均と推移
学資保険の予定利率(利率)や返戻率は年々低下傾向にあります。特に予定利率は、市場金利の低迷に伴ってここ数十年で大きく下がりました。日本の生命保険各社が参照する標準利率の推移を見ると、例えば1990年代前半には予定利率が4~5%もありましたが、その後1990年代後半にかけて2~3%台、2000年代以降はさらに低下し1%台から現在では1%を切る水準となっています。約30年の間に予定利率が右肩下がりで下降し続けてきたため、昔のようなお得な学資保険は今はほとんど存在しないと言われます。経済情勢の変化により、保険会社の運用利回りが約束した利回りを下回る『逆ざや』という経営上の大きな負担となりました 。
予定利率の低下に伴い、学資保険の返戻率(貯蓄性)も全体的に下がりました。かつては返戻率120%前後(払った保険料より2割多く戻ってくる)の商品もありましたが、現在では主要な学資保険でも返戻率はせいぜい105%前後が一般的です。下記は契約者30歳・子ども0歳、18歳満期(大学入学時に満期金受取)、貯蓄型プラン(祝い金なし)で試算した主な学資保険の返戻率です。
- ソニー生命(学資保険III型):約105.5%
- 明治安田生命(つみたて学資):約105.7%
- 日本生命(ニッセイ学資保険):約107.2%
いずれも100%を超えているものの、110%には届かない水準であることが分かります。大手民間保険各社の貯蓄重視型プランはほぼこの程度(105%前後)に収まっている一方、かんぽ生命など一部では短期払込プランでもやっと100%を少し超える程度の商品もあります。近年、一部の学資保険(特に保障重視型)では返戻率が90%台(元本割れ)となるケースも指摘されています。例えば医療特約付きの学資保険や、低金利下で販売された一部商品の中には返戻率80~90%台というものもあり、契約条件次第では満期時に元本割れとなり得るので注意が必要です。
このように全体的な水準だけ見ると「学資保険は昔ほど増えない」「利率が悪い」と言われがちですが、それでも銀行預金よりは有利であり、また後述するような保障面のメリットもあります。最近では世界的に金利上昇の動きもあり、将来的に標準利率が上がれば学資保険の予定利率が上がる可能性もあります。ただし現時点では金利が急上昇する兆しはなく、学資保険の利率の平均は依然として低水準です。そのため、学資保険を検討する際は単純な利率よりも返戻率や保障内容に着目して選ぶ必要があるでしょう。
返戻率から実際の利率(利回り)を計算する方法
返戻率から年利換算の利回りを求めるには「時間」の要素を考慮する必要があります。おおまかな計算方法としては、運用期間をN年とした場合に(返戻率 ÷ 100)をN乗根して求め、そこから1を引くと利回り(年平均の増加率)が算出できます。数式で書くと少し難しく感じますが、例を用いて説明しましょう。
例えば、返戻率104%で運用期間18年の学資保険があるとします。この場合、1.04(=104%)の18年根を取って年平均の増加率を求め、その値から1を引けば利回りが出ます。実際に計算すると年利約0.4%となります。先ほど例に出した返戻率104.62%・期間15年のケースでは年利約0.5%でした。このように返戻率と期間から利回りを計算すれば、「年率換算でどの程度得しているか」がわかるのです。
ただし正確に利回りを算出しようとすると、保険料の払込タイミングも考慮しなければなりません。学資保険では毎月や毎年、徐々に保険料を支払っていくため、運用に回るお金の額と期間は一定ではありません。厳密な利回り(内部収益率IRR)を求めるにはやや複雑な計算になりますが、概算としては上記のように「返戻率を期間でならす」イメージで十分でしょう。
ポイントは、返戻率を年利に直すとかなり低くなるということです。大手各社の学資保険返戻率が軒並み105%前後であることを踏まえると、それらの年利回りは0.3~0.5%程度にしかなりません。「思ったより増えないな」と感じるかもしれませんが、逆に言えば銀行預金よりは良い利率ではあります。学資保険はあくまで「堅実に教育資金を準備する」ことに重きを置いた商品なので、投資のように大きな利回りは期待せず確実性を取るという位置づけになります。
学資保険を比較検討するなら返戻率で比較しよう
以上を踏まえ、学資保険を選ぶ際には予定利率そのものを比較検討するのは難しいことがお分かりいただけたでしょう。予定利率は各社で明確に公表されていなかったり、商品ごとに異なることもあり、一般の方が直接比較するのには適しません。それよりも、各保険商品ごとの返戻率を比較するほうが実用的です。返戻率は支払額に対する戻りの割合ですから、「どの商品がより貯蓄性が高いか」を直感的に把握できます。
例えば、ある学資保険Aの返戻率が105%、学資保険Bが102%だったとします。この場合、返戻率105%のAのほうが貯蓄性が高い(より多く戻ってくる)と判断できます。ただし注意したいのは、返戻率だけでなく保障内容や払込期間も併せて考えることです。極端に返戻率が高い商品は、保障(特約)が一切付いていない純粋な積立型であるケースが多く、逆に返戻率が低めの商品は医療特約や育英年金など保障が充実している代わりに貯蓄性を犠牲にしていることがあります。
学資保険を選ぶ際はまず各商品の返戻率を比較し、次にその返戻率が実現している条件(払込期間や特約の有無など)を確認しましょう。そうすることで、「元本割れでも手厚い保障を取るか」「多少保障を削ってでも貯蓄性を優先するか」といった判断がしやすくなります。特に学資保険は目的が教育資金の準備ですから、貯蓄性重視なら返戻率の高い商品を選ぶのが基本となります。
貯蓄性が高い学資保険のおすすめランキング
貯蓄性(返戻率)が高い学資保険の中でも、特に人気・評価の高い商品をランキング形式で紹介します。学資保険選びの参考として、それぞれの特徴や返戻率、基本的な契約内容を簡潔にまとめます。
TOP1:ソニー生命の学資保険(学資保険III型)
ソニー生命の学資保険は貯蓄性がトップクラスに高いことで知られています。特にIII型(大学資金一括受取タイプ)は、祝い金を大学入学以降に集中させるプランで、条件次第では返戻率121.5%という突出した水準を公式に示しています。これは他社と比べても群を抜く高さで、ソニー生命がいかに運用益を契約者に還元しているかが分かります。ただ、これは契約者30歳・子ども0歳・保険料10年払込完了・満期22歳といった極めて有利な条件が重なった場合の理論値です 。
おすすめポイント:契約者の年齢や払込期間などを柔軟に設計でき、払込期間を短くするほど返戻率が上がる仕組みになっています。例えば5年払い・10年払い等の短期払いや一括払いにも対応しており、その分運用期間が長くなるためリターンが大きくなります。また、満期金を受け取らずに据え置いて利息を付けることもでき、大学在学中に分割受取することでさらに返戻率を高めることも可能です。保障面では他社同様に契約者(親)に万一のことがあれば以後の保険料が免除され、満期金は予定通り受け取れる仕組みになっています。貯蓄性最優先で学資保険を選びたい方に最適な商品と言えるでしょう。
基本データ(ソニー生命 学資保険III型):
- 契約者(親)の加入年齢: 満18歳~契約条件による上限あり(一般的に20~55歳程度)
- 被保険者(子ども)の年齢: 出生前(妊娠140日前)~12歳まで契約可能
- 保険料払込期間: 5年・10年・15年など短期払いから、18歳・22歳までの長期払いまで選択可
- 保険金受取年齢: 満18歳(大学入学時)または満22歳(大学卒業時)などプランにより選択
- 返戻率(目安):返戻率(目安): 約105%(一般的なプラン)~最大121.5%(※特定の好条件が重なった場合)
TOP2:明治安田生命「つみたて学資」
明治安田生命の「つみたて学資」は、名称が示す通り貯蓄性に特化したシンプルな学資保険です。教育資金の受取を大学進学時期に集中させるタイプで、祝い金(幼稚園・小中高の入学金)を一切設けずその分返戻率を高めています。一般的な条件下での返戻率は105%前後ですが、払込方法によっては返戻率が大幅に向上し、短期払で最大118.2% 、一括払では最大127%に達するプランもあります。2023年の改定で返戻率が向上し、現在では大手の中でもトップクラスの貯蓄性を誇る商品です。
おすすめポイント:払込期間や受取方法をある程度カスタマイズできますが、基本はコツコツ積み立てて18歳以降にまとめて受け取るシンプルな設計です。複雑な特約がなく、必要以上の保障を省いているため元本割れの心配が少ないのが魅力です。契約者の万一時には払込免除となる保障は付いており、教育資金を確実に準備できます。ただし契約者の年齢条件がややシビアで、例えば契約者年齢は満18~45歳までなど制限がありますので、両親や祖父母が契約する場合は年齢要件に注意が必要です。総じて「シンプルで貯蓄重視」の学資保険を探している方に向いています。
基本データ(明治安田生命 つみたて学資):
- 契約者の加入年齢: 満18歳~45歳まで(※契約者の年齢上限は比較的低めなので注意)
- 子どもの加入年齢: 出生予定日140日前~9歳まで契約可能
- 保険料払込期間: 原則子どもが18歳になるまで(契約時に短期払いオプションがある場合も)
- 保険金受取時期: 満18歳から数年間に分割受取(18歳~22歳の毎年受取などプランによる)
- 返戻率(目安): 約105%(月払いプラン)~最大118.2%(短期払いプラン)
TOP3:日本生命「ニッセイ学資保険」
日本生命の学資保険(ニッセイ学資保険)は、大手生保の安心感と安定した返戻率で人気の商品です。特に「こども祝金なし型」と呼ばれるプランは、幼児期・学生期の祝い金を省いて満期に教育資金をまとめて受け取るタイプで、貯蓄性に優れています。このプランを選択した場合の返戻率は比較的高く、さらに2025年1月2日からの保険料率改定により、特定の条件下(5年短期払いなど)では返戻率が最大約112.0%まで向上します。日本生命の調査によると、契約者の約85.7%が貯蓄重視の祝金なし型を選んでいます 。 標準的な条件での返戻率も104~105%台は確保されており、堅実に増やせる商品です。
おすすめポイント:老舗の日本生命ということで信頼性・安心感があります。特徴としては、受取方法を柔軟に選択可能なことです。大学入学時に一括で満期金を受け取る他、契約者の希望に応じて大学在学中4年間に分割して学資金(年金形式)を受け取るタイプも用意されています。さらに、兄弟姉妹で複数契約すると保険料が割引になる多契約割引制度などもあり、家計に優しい配慮があります。もちろん契約者死亡時の保険料払込免除も付帯され、保障面も万全です。大手ならではのサービスと高い返戻率のバランスが取れた商品と言えるでしょう。
基本データ(日本生命 ニッセイ学資保険):
- 契約者の加入年齢: 満20歳~50歳前後まで(親だけでなく祖父母も契約者になれる場合あり)
- 子どもの加入年齢: 0歳(出生後すぐ)~12歳頃まで契約可能
- 保険料払込期間: 子どもが18歳になるまで(※短期払込プランも選択可)
- 保険金受取時期: 満18歳時に一括受取 or 18歳~21歳もしくは22歳まで毎年分割受取(プラン選択)
- 返戻率(目安): 祝い金なし型で104%~最大約112.0%(※2025年1月2日以降の料率改定後、5年短期払いなどの場合)
学資保険の貯蓄性を高めるコツ
学資保険は契約の仕方次第で返戻率をさらに高めることも可能です。少しでも有利に積み立てるための4つのコツを紹介します。
- 保障のないシンプルなプランを選ぶ: 学資保険に医療特約や育英年金などの保障を付けると、その分保険料が保障部分に充てられ返戻率が低下します。貯蓄性最優先なら特約なしの純粋な積立型を選びましょう。必要な保障は学資保険とは別に、例えば親の死亡保障は定期保険、子どもの医療保障は共済などで準備し、学資保険は貯蓄専用にする方法がおすすめです。特約を分離しておけば後で見直しもしやすくなります。
- なるべく早く加入し、満期までの期間を長く取る: 子どもが生まれたらできるだけ早く学資保険に加入するのが有利です。加入が早いほど運用期間が長くなり返戻率が向上します。例えば0歳で加入した場合と3歳で加入した場合では、満期時の返戻率に数%の差がつくこともあります。最近は妊娠中(出産予定日の140日前)から契約できる商品も増えています。また、満期を18歳より22歳に延ばすのも効果的です。22歳満期なら運用期間がさらに長くなるため返戻率が高まります。ただし大学入学のタイミングに資金が必要になるので、18歳時に一部祝金を受け取ったり、18歳満期にして満期金を据え置いて運用継続(据え置き利息を付けて後で受取)する方法もあります。場合によっては複数の学資保険に加入し、受取時期を分散させる工夫も有効です。
- 保険料はまとめて早く払い込む: 払込方法を工夫することで返戻率を大幅に向上させることができます。一般的に月払いより年払い、年払いより前納(一括払い)のほうが返戻率は高くなります。実例として、ある商品の場合「月払い:返戻率103.5%、年払い:104.8%、10年短期払い:106.2%、一括前納:108.5%」といった具合に払込を早く終えるほど返戻率が上昇しました。一括で保険料を支払えば、保険会社は長期間まとめて運用できるため、その分契約者に還元してくれるのです。また事務コスト削減分が返戻率に反映される効果もあります。ただし一括払いの注意点として、まとまった資金が必要で家計負担が大きいこと、生命保険料控除の節税メリットが支払った年に集中してしまうこと、そして払込免除の恩恵を受けられる期間が短くなること等があります。家庭の資金計画に応じて無理のない払込方法を選びましょう。
- 契約者(親)を妻名義にする: 多くの学資保険では契約者(被保険者)の性別によって保険料が異なり、一般的に女性契約者のほうが保険料が安い設定になっています。これは統計的に女性のほうが長生きで死亡リスクが低いためです。そのため、同じ条件でも妻が契約者になったほうが返戻率が高くなるケースがあります。例えば子ども0歳・払込18年で試算すると「夫が契約者:返戻率104.5%」「妻が契約者:返戻率105.8%」という1%以上の差が生じることもあります。18年トータルで考えれば数万円以上の差になる可能性もあり、検討する価値は十分です。ただし注意したいのは、払込免除特約の適用です。契約者を妻にすると、もし夫(主な収入源)が亡くなっても保険料免除になりません(契約者である妻が健在なため)。一方、夫を契約者にしておけば夫に万一のことがあった場合に保険料免除となり教育資金が確保できます。このように返戻率を取るか保障を取るかというトレードオフがあるため、ご夫婦で話し合って決めましょう。共働きで両方収入がある場合は単純に返戻率の高いほうを契約者にする手もあります。
以上のポイントを押さえて工夫すれば、同じ学資保険でもより高い貯蓄性を引き出すことができます。学資保険は長期の契約になりますので、少しの差が大きなリターンの違いにつながります。ぜひ契約前に確認してみてください。
利率が低くても学資保険に加入するメリット
「今の学資保険は利率が低いし増えない」と言われることもありますが、利率が低くても学資保険に加入するメリットは確かに存在します。主なメリットを整理すると以下の通りです。
- 計画的に教育資金を貯められる: 学資保険に入ると毎月決まった額の保険料を払うため、半強制的に貯蓄していくことができます。銀行預金で自分で貯めようとすると、つい生活費に使ってしまうこともありますが、学資保険なら簡単に引き出せない仕組みなので確実に積み立てられます。いわば先取り貯蓄の効果があり、意志に自信がない方でも計画的に教育費を準備できるのは大きなメリットです。
- 預貯金より増える可能性が高い: 超低金利の現在、銀行に預けても利息はほとんど期待できません。その点、学資保険なら必要以上の保障を付けない限り支払った金額より多くの学資金を受け取れる可能性が高いです。先述したように利回り自体は大きくありませんが、少なくとも銀行よりは有利な利率で積み立てられるのはメリットと言えます。
- 契約者に万一のことがあっても教育資金が確保される: 学資保険は生命保険の一種でもあります。多くの学資保険には保険料払込免除特約が付いており、契約者(親)が死亡または高度障害状態になった場合、その後の保険料支払いは免除されます。そして保険料を払っていなくても満期金や祝い金は契約通り受け取れるのです。これは銀行貯金にはないメリットです。万が一の際にも子どもの教育資金を確保できる安心感は、学資保険ならではの大きな利点でしょう。
- 生命保険料控除の対象で節税効果がある: 学資保険の保険料は生命保険料控除の対象になります(一般生命保険料控除枠)。毎年払った保険料に応じて所定の控除が受けられ、所得税・住民税の負担が軽減されます。控除額は支払保険料にもよりますが、生命保険料控除は、支払った保険料に応じて所得から一定額が控除される制度であり、節税額そのものではありません。実際の節税額は「所得控除額 × 税率」で決まるため、多くの場合、年間数千円から1万円程度の負担軽減となります。新制度における所得控除額の上限は、所得税で年間4万円、住民税で年間2.8万円です 。
- 受取時の税制優遇: 学資保険の満期金などを受け取る際の税金も、契約形態によっては優遇があります。通常、満期保険金は契約者が受取人の場合「一時所得」として扱われます。一時所得には50万円の特別控除があるため、利益(受取総額 – 支払保険料総額)が50万円以下であれば課税されません 。また契約者と受取人を分けることで贈与税の非課税枠を活用する方法もあります。いずれにせよ、運用益に対して丸ごと課税される投資商品とは異なり、一定の範囲で教育資金を非課税で受け取れる点は見逃せません。
以上のように、学資保険には利率面以外のメリットが多く存在します。特に「自分で貯める自信がない」「もしものとき子どもの教育費が心配」というご家庭にとって、学資保険は有力な選択肢です。利率だけにとらわれず、保障と貯蓄のバランスを考慮して、自分たちに合った方法でお子さんの教育資金準備を進めましょう。