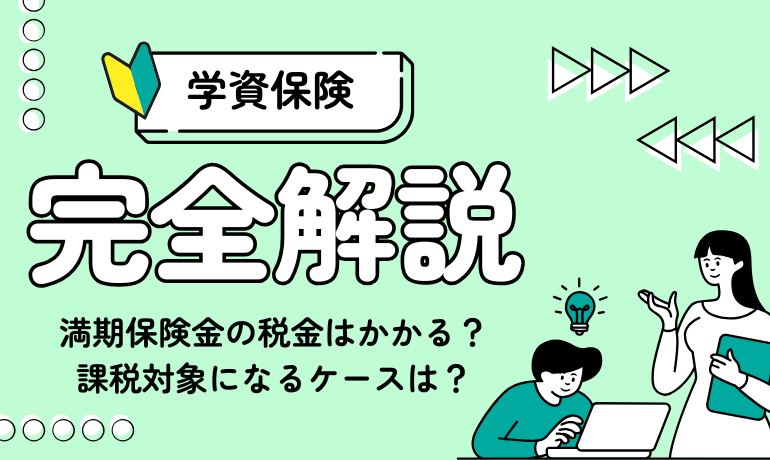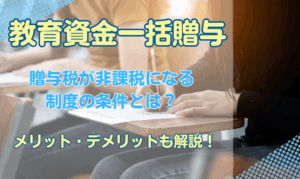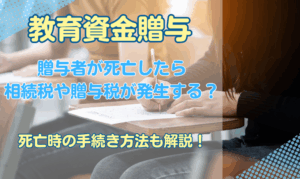学資保険は、子どもの教育資金を計画的に準備できる保険商品として多くの方に利用されています。しかし、満期を迎えて保険金を受け取る際に「税金はかかるのか」「確定申告は必要なのか」という疑問を持つ方も少なくありません。
本記事では学資保険の満期保険金にかかる税金について、課税対象となるケースや計算方法、確定申告の必要性などを詳しく解説します。満期が近づいている方やすでに満期保険金を受け取った方は、ぜひ参考にしてください。
学資保険の満期保険金に税金はかかる?
学資保険の満期保険金や祝金に税金がかかるかどうかは、受け取り方や受取人、保険金額によって異なります。税金がかからないケースもあれば、課税対象となり確定申告が必要になるケースもあります。
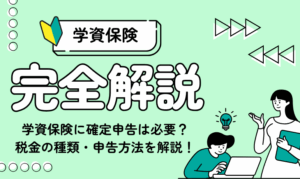
まず、学資保険の満期保険金にかかる税金の種類を整理してみましょう。
税金の種類と該当するケース
| 保険料負担者と受取人の関係 | 受け取り方 | 税金の種類 |
| 同じ(例:父が保険料を支払い、父が受け取る) | 一括受取 | 所得税(一時所得) |
| 同じ(例:父が保険料を支払い、父が受け取る) | 年金形式 | 所得税(雑所得) |
| 異なる(例:父が保険料を支払い、母が受け取る) | 一括・年金形式 | 贈与税 |
| 保険料払込免除後に受取(契約者死亡など) | 一括・年金形式 | 相続税 |
このように、保険料を負担した人と保険金を受け取る人の関係、そして受け取り方によって、かかる税金の種類が変わってきます。
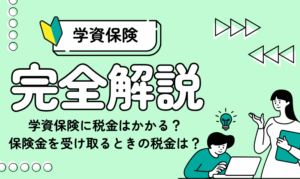
税金がかからないケースもある
ただし、すべてのケースで税金がかかるわけではありません。例えば、一時所得の場合は特別控除額50万円があり、満期保険金から支払った保険料総額を差し引いた金額が50万円以下であれば税金はかかりません。
また、贈与税の場合も基礎控除額110万円があるため、年間の贈与額が110万円以下であれば税金の対象外です。
税金がかかる場合は、原則として確定申告が必要になります。ただし、会社員の方で一定の条件を満たす場合は、年末調整で対応できることもあります。
それでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の満期保険金の税金【保険料の負担者と受取人が同じ】
保険料を支払った人と満期保険金を受け取る人が同じ場合、受け取り方によって「一時所得」または「雑所得」として所得税の課税対象となります。
一括で受け取る場合:所得税(一時所得)
満期保険金を一括で受け取る場合は、一時所得として所得税の課税対象となります。一時所得とは営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得のことです。
学資保険の満期保険金は、まさにこの一時所得に該当します。ただし、重要なポイントは、満期保険金の全額が課税対象となるわけではないということです。支払った保険料総額を差し引き、さらに特別控除額50万円を超えた部分にのみ税金がかかります。
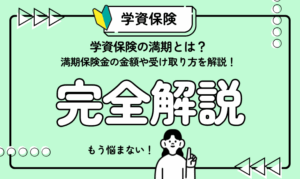
一時所得の計算方法と税率
一時所得の金額は、以下の計算式で求めます。
一時所得の金額 = (満期保険金 - 支払保険料総額 - 特別控除額50万円)
この計算で求めた一時所得の金額を、他の所得と合算して総所得金額を算出し、その1/2の金額に所得税率を適用します。
所得税の税率は、課税される所得金額に応じて以下のように定められています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
一時所得の具体例
それでは、具体的な数字を使って一時所得の計算をシミュレーションしてみましょう。
例1:満期保険金300万円の場合
・満期保険金:300万円
・支払保険料総額:240万円
・一時所得の計算:(300万円 - 240万円 - 50万円)× 1/2 = 5万円
この場合、一時所得は5万円となり、この金額が他の所得と合算されて課税されます。
例2:満期保険金200万円の場合
・満期保険金:200万円
・支払保険料総額:180万円
・一時所得の計算:(200万円 - 180万円 - 50万円)× 1/2 = 0円(マイナスのため0円)
この場合、満期保険金から支払保険料総額を差し引いた金額が50万円以下のため一時所得は発生せず、税金はかかりません。
年金形式で受け取る場合:所得税(雑所得)
学資保険の満期保険金を年金形式で受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象となります。年金形式とは、満期保険金を一度に受け取るのではなく、毎年一定額ずつ分割して受け取る方法です。
雑所得は、他の所得区分に該当しない所得の総称で、公的年金等や個人年金保険の年金などが該当します。学資保険を年金形式で受け取る場合も、この雑所得に分類されます。
雑所得の計算方法
雑所得の金額は、以下の計算式で求めます。
雑所得の金額 = その年に受け取った年金額 - その年金額に対応する支払保険料
年金額に対応する支払保険料は、以下の計算式で求めます。
その年金額に対応する支払保険料 = その年に受け取った年金額× (支払保険料総額 ÷ 年金受取総額)
雑所得の具体例
具体的な数字を使って雑所得の計算をしてみましょう。
例:満期保険金300万円を10年間の年金形式で受け取る場合
・満期保険金総額:300万円
・支払保険料総額:240万円
・年間受取額:30万円(300万円 ÷ 10年)
・年間の対応する支払保険料:24万円(30万円 × 240万円 ÷ 300万円)
・雑所得の金額:30万円 - 24万円 = 6万円
この場合、毎年6万円の雑所得が発生し、この金額が他の所得と合算されて課税されます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の満期保険金の税金【保険料負担者と受取人が違う】
保険料を支払った人と満期保険金を受け取る人が異なる場合、贈与税の課税対象となります。例えば、父親が保険料を支払い、母親や子どもが満期保険金を受け取るケースなどが該当します。
一括・年金形式で受け取る場合:贈与税
保険料負担者と受取人が異なる場合、受け取り方が一括でも年金形式でも贈与税の対象となります。贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金で、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
つまり、満期保険金が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
贈与税の計算方法と税率
贈与税の金額は、以下の計算式で求めます。
贈与税の金額 = (満期保険金 - 基礎控除額110万円)× 税率 - 控除額
贈与税の税率は、贈与を受けた金額に応じて以下のように定められています(一般贈与財産の場合)。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税の具体例
具体的な数字を使って、贈与税の計算をしてみましょう。
例1:満期保険金300万円の場合
この場合、19万円の贈与税がかかります。
例2:満期保険金100万円の場合
この場合、満期保険金が基礎控除額110万円以下のため、贈与税はかかりません。
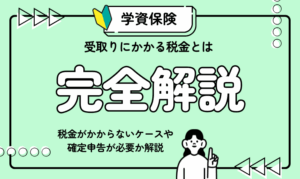
保険料の払込みが免除された場合:相続税
学資保険では、契約者(保険料負担者)が死亡した場合などに以後の保険料の払込みが免除される特約が付いていることがあります。このような保険料払込免除特約により保険料の払込みが免除された後に満期保険金を受け取る場合、相続税の課税対象となることがあります。
これは、本来支払うべきだった保険料相当額が、死亡した契約者から受取人への相続財産とみなされるためです。
相続税の計算方法と税率
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。基礎控除額は、以下の計算式で求めます。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続税の税率は、法定相続分に応じる取得金額に応じて以下のように定められています。
| 法定相続分に応じる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の具体例
具体的な数字を使って、相続税の計算をしてみましょう。
例:契約者死亡により保険料払込免除となり、満期保険金300万円を受け取る場合
・満期保険金:300万円
・払込免除となった保険料相当額:100万円
・相続財産としての評価額:300万円(満期保険金全額)
・他の相続財産と合わせて基礎控除額を超える場合に相続税が課税される
ただし、相続税は他の相続財産と合わせて計算する必要があるため、学資保険の満期保険金だけで相続税額を計算することはできません。相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の満期保険金は確定申告が必要?
学資保険の満期保険金を受け取った場合、税金がかかるケースでは原則として確定申告が必要になります。ただし、すべてのケースで確定申告が必要というわけではありません。
課税対象の場合は確定申告が必要
学資保険の満期保険金が課税対象となる場合、以下のようなケースで確定申告が必要になります。
確定申告が必要なケース
・一時所得が発生する場合
満期保険金から支払保険料総額を差し引いた金額が50万円を超える場合
ただし、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合は申告不要
・雑所得が発生する場合
年金形式で受け取り、雑所得が発生する場合
公的年金等以外の雑所得が20万円を超える場合
・贈与税が発生する場合
年間の贈与額が110万円を超える場合
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告が必要
確定申告が不要なケース
・給与所得者の特例
年末調整を受けた給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合
この場合、一時所得や雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要
・課税されない場合
一時所得の特別控除額50万円以下の場合
贈与税の基礎控除額110万円以下の場合
なお、年末調整では学資保険の満期保険金に関する税金の精算はできません。年末調整は、給与所得に関する所得税の精算を行うものであり、一時所得や贈与税などは対象外となるためです。
課税対象なのに確定申告しなかったらばれる?
学資保険の満期保険金が課税対象であるにもかかわらず確定申告をしなかった場合、税務署に発覚する可能性があります。
保険会社は、一定額以上の保険金を支払った場合、税務署に支払調書を提出する義務があります。この支払調書により、税務署は保険金の支払い状況を把握できるため、申告漏れが発覚することがあるのです。
申告漏れが発覚した場合のペナルティは、以下のとおりです。
・延滞税
納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される
年率2.4%~8.7%(令和6年の場合)
・無申告加算税
納付すべき税額の5%~20%
自主的に申告した場合は5%、税務調査により発覚した場合は15%~20%
・重加算税
悪質な隠蔽や仮装があった場合
納付すべき税額の35%~40%
このようなペナルティを避けるためにも、課税対象となる場合は必ず確定申告を行いましょう。
満期保険金の確定申告の方法
学資保険の満期保険金の確定申告は、以下の手順で行います。
・必要書類の準備
保険会社から送付される支払明細書
源泉徴収票(給与所得者の場合)
マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
・確定申告書の作成
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用
または税務署で配布される確定申告書を使用
・申告内容の記入
一時所得の場合:申告書の「一時所得」欄に記入
雑所得の場合:申告書の「雑所得」欄に記入
贈与税の場合:贈与税申告書に記入
・提出方法
e-Tax(電子申告)
郵送
税務署への直接持参
確定申告の書き方で特に注意すべき点は、収入金額と必要経費を正確に記入することです。収入金額には満期保険金の額を、必要経費には支払保険料総額を記入します。
また、一時所得の場合は特別控除額50万円を忘れずに差し引き、計算した所得金額の1/2を総所得金額に算入することも重要です。
確定申告の期限は、所得税の場合は翌年の2月16日から3月15日頃まで、贈与税の場合は翌年の2月1日から3月15日頃までとなっています。期限内に申告することで、延滞税などのペナルティを避けることができます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
まとめ
学資保険の満期保険金にかかる税金は、保険料負担者と受取人の関係、受け取り方によって異なります。保険料負担者と受取人が同じ場合は所得税(一時所得または雑所得)、異なる場合は贈与税、保険料払込免除後の受取の場合は相続税の対象となります。
ただし、一時所得の特別控除額50万円や贈与税の基礎控除額110万円により、実際には税金がかからないケースも多いです。税金がかかる場合は原則として確定申告が必要ですが、給与所得者で一定の条件を満たす場合は申告不要となることもあります。
学資保険の満期が近づいている方は、事前に税金の計算をして、必要に応じて確定申告の準備をしておくことをおすすめします。申告漏れによるペナルティを避けるためにも、課税対象となる場合は期限内に適切に申告を行いましょう。
税金に関する詳しい内容や個別の状況については、税務署や税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。適切な税務処理を行うことで、大切な教育資金を有効に活用することができるでしょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!