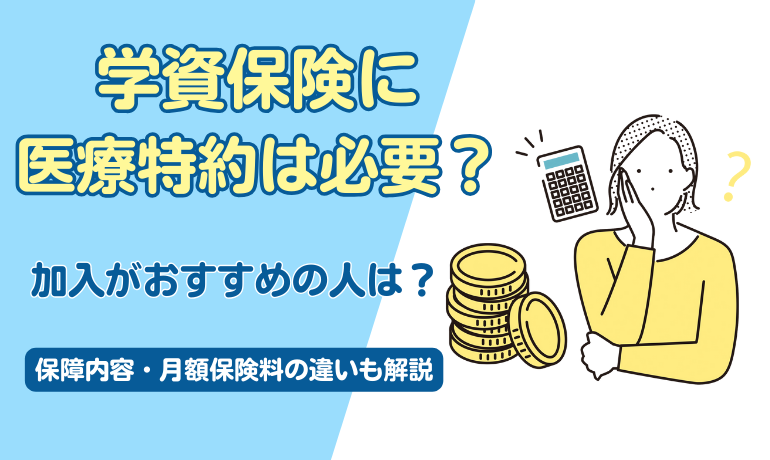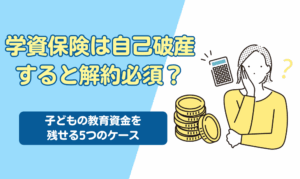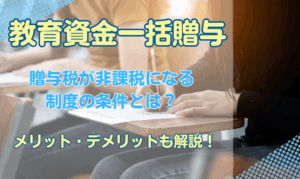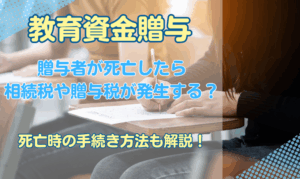お子さまの将来の教育資金を計画的に準備するための「学資保険」。その加入を検討する際に、多くの人が悩むのが「医療特約」を付けるべきか否かという問題です。
「万が一の病気やケガに備えて医療特約を付けた方が安心」と考える一方、「医療特約を付けると保険料が上がり、貯蓄性が下がるのでは?」といった不安の声も聞かれます。
この記事では、学資保険の医療特約の必要性について、さまざまな角度から徹底解説します。医療特約の保障内容やメリット・デメリット、主要な学資保険の医療特約の比較、さらには加入がおすすめな人の特徴まで詳しくご紹介。
この記事を読めば、あなたの家庭にとって学資保険の医療特約が本当に必要なのか、最適な選択をするための判断材料がきっと見つかるはずです。
医療特約付きの学資保険とは
まずはじめに、「学資保険」と「医療特約」がそれぞれどのようなものなのか、基本を理解しておきましょう。この二つがセットになった「医療特約付き学資保険」の仕組みについても解説します。
学資保険とは
学資保険は、子どもの教育資金を準備することを主な目的とした貯蓄型の保険です。契約者である親などが毎月一定の保険料を払い込むことで、子どもの進学時期に合わせて、祝い金や満期保険金としてまとまった資金を受け取ることができます。
また、多くの学資保険には、保険料の払込期間中に契約者(親など)が死亡または高度障害状態になった場合に、それ以降の保険料の支払いが免除される「払込免除」の機能が付いています。これにより、万が一のことがあっても、予定通り教育資金を確保できるのが大きな特徴です。
医療特約とは
医療特約とは、主契約である学資保険に付加(セット)することで、子どもの病気やケガによる入院や手術などに備えるための保障です。具体的には、以下のような場合に給付金が支払われます。
- 入院給付金
病気やケガで入院した際に、「入院1日あたり〇〇円」という形で給付金が支払われます。 - 手術給付金
所定の手術を受けた際に、「入院給付金日額の〇〇倍」といった形で一時金が支払われます。
いわば、学資保険という貯蓄の箱に、オプションとして医療保険の機能を追加するイメージです。これにより、教育資金の準備と子どもの医療保障を一つの契約でまとめて管理できる手軽さが特徴です。このような保険を「医療特約付き学資保険」と呼びます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険に医療特約はいらないといわれる5つの理由
「教育資金と医療保障がセットなら安心」と思える医療特約ですが、実際には「学資保険に医療特約は不要」という意見が多く聞かれます。その背景には、主に5つの理由があります。
- 医療保険の代わりとするには保障が不十分
- そもそも子どもの医療費負担が少ない
- 保険料が高くなってしまう
- 返戻率が下がり教育資金の額にも影響が出る
- 学資保険が終了すれば医療特約も解約になる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 医療保険の代わりとするには保障が不十分
学資保険の医療特約は、あくまで「特約」であり、単体の医療保険と比較すると保障内容が限定的であるケースがほとんどです。
例えば、以下のような点で保障が手薄になる可能性があります。
- 入院給付金の日額が低い・支払日数が短い
単体の医療保険なら日額5,000円や10,000円といった設定が可能ですが、特約では日額3,000円~5,000円程度で、1回の入院での支払限度日数が60日など短めに設定されていることが多いです。 - 手術給付金の対象となる手術が限られている
対象となる手術の種類が単体の医療保険よりも少ない場合があります。 - 先進医療や通院に対する保障がない
近年注目されている先進医療の技術料をカバーする保障や、退院後の通院に対する保障が付いていないことが多くあります。
あくまで学資保険の主目的は教育資金の準備であるため、医療保障は簡易的なものになりがちです。本格的な医療への備えを考えるのであれば、特約だけでは心もとないと感じるかもしれません。
2. そもそも子どもの医療費負担が少ない
「いらない」と言われる最も大きな理由が、日本国内の公的な医療費助成制度の存在です。
多くの自治体では「子ども医療費助成制度(乳幼児医療費助成制度など名称は様々)」が設けられており、健康保険証を使って医療機関にかかった際の自己負担分を、自治体が全額または一部を助成してくれます。
対象年齢や助成内容は自治体によって異なりますが、例えば東京都では、高校生(18歳になった後の最初の3月31日まで)までの子どもは、保険診療の自己負担分が原則無料です(所得制限なし。住民税非課税世帯以外は入院時の食事療養標準負担額のみ自己負担)。
このように、多くの場合、子どもの医療費は公的制度によって手厚くカバーされています。そのため、民間の保険で高額な保障を準備する必要性は、大人に比べて低いと言えるでしょう。
もちろん、助成の対象外となる費用(差額ベッド代、先進医療費、入院中の食事代の一部など)もありますが、そのために毎月保険料を払い続けるのが合理的かどうかは、慎重に判断する必要があります。
3. 保険料が高くなってしまう
医療特約を付加すれば、当然その分の保険料が上乗せされます。特約部分の保険料は、保障内容にもよりますが月々数百円から1,000円程度になるのが一般的です。
一見すると少額に思えるかもしれませんが、学資保険は10年、15年と長期にわたって払い込むものです。塵も積もれば山となり、払込期間全体で見ると大きな金額になります。
仮に、月額800円の医療特約を15年間付けたとしましょう。
- 月額の差: 800円
- 年間の差: 800円 × 12カ月 = 9,600円
- 15年間の総額: 9,600円 × 15年 = 144,000円
このシミュレーションのように、医療特約を付けることで、付けない場合と比較して14万円以上も多く保険料を支払うことになります。この金額をどう捉えるかが、判断の分かれ目となるでしょう。
4. 返戻率が下がり教育資金の額にも影響が出る
学資保険を選ぶ上で重要な指標となるのが「返戻率(へんれいりつ)」です。返戻率とは、払い込んだ保険料総額に対して、将来受け取れる祝い金や満期保険金の総額がどれくらいの割合になるかを示したものです。
返戻率が100%を超えれば、払い込んだ保険料よりも多くの金額が戻ってくることを意味し、貯蓄性が高いと言えます。
しかし、医療特約部分の保険料は基本的に「掛け捨て」です。つまり、この保険料は保障を買うためのコストであり、将来の受取額には反映されません。
そのため、医療特約を付加すると、その分だけ払い込む保険料総額が増える一方で、受け取る学資金の額は変わりません。結果として、分母である「払い込む保険料総額」が大きくなるため、返戻率は下がってしまうのです。
教育資金を効率的に貯めるという学資保険本来の目的を重視するならば、返戻率を低下させる医療特約は付けずに、その分の保険料を貯蓄や投資に回した方が合理的という考え方ができます。
5. 学資保険が終了すれば医療特約も解約になる
学資保険の医療特約は、あくまで主契約である学資保険に付随するものです。そのため、学資保険が満期を迎えて主契約が消滅すると、医療特約も同時に終了してしまいます。
多くの学資保険は、大学進学資金の準備を目的として18歳や22歳で満期を迎えます。つまり、その年齢以降は子どもの医療保障がなくなってしまうのです。
もし、満期後も子どもの医療保障を継続したいと考えるのであれば、その時点で新たに医療保険に加入し直す必要があります。しかし、その時の健康状態によっては、希望する保険に加入できない(謝絶される)リスクや、保険料が割高になる可能性も考えられます。
一生涯の保障や、若いうちに安い保険料で加入しておくメリットを重視するならば、学資保険の特約ではなく、初めから単体の医療保険を検討する方が理にかなっていると言えるでしょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
代表的な学資保険の医療特約の内容
では、実際に各保険会社はどのような医療特約を用意しているのでしょうか。ここでは、代表的な保険会社の学資保険における医療特約の有無と、その概要を一覧で見てみましょう。
| 保険会社名 | 商品名(例) | 医療特約の有無 | 医療特約の概要(有の場合) |
| かんぽ生命<br>(ゆうちょ銀行) | はじめのかんぽ | 有り | 入院・手術・放射線治療を保障する「無配当総合医療特約」などを付加可能。入院1日目から保障。 |
| ソニー生命 | 学資保険スクエア | 無し | 貯蓄性を重視し、あえて医療保障を付けないシンプルな設計。 |
| 日本生命 | ニッセイこどもの保険 | 有り | 入院、手術、放射線治療などを保障する特約を付加可能。 |
| 富国生命 | みらいのつばさ | 無し | 高い返戻率を追求するため、保障をシンプルにしている。別途、同社の医療保険への加入は可能。 |
| 明治安田生命 | つみたて学資 | 無し | 貯蓄機能に特化し、シンプルな商品性で分かりやすさを重視。 |
| 第一生命 | こども学資保険 | 有り | 入院・手術などを保障する「こども新総合医療特約」などを付加可能。 |
| JA共済 | こども共済 | 有り | 入院、手術、通院などを保障する「医療共済」をセットで考えることが可能。保障内容が手厚いのが特徴。 |
※上記は2025年8月時点での一般的な情報です。商品改定などにより内容は変更される可能性があります。詳細は各社の公式サイトやパンフレットでご確認ください。
このように、保険会社によって方針は大きく分かれます。
- かんぽ生命、日本生命、第一生命、JA共済など
貯蓄と保障をセットで提供する選択肢を用意している伝統的な大手生保に多いタイプです。 - ソニー生命、富国生命、明治安田生命など
「教育資金の準備」という目的に特化し、高い返戻率を実現するためにあえて医療特約を付けていないタイプです。
この違いは、各社の学資保険に対する考え方を反映していると言えるでしょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の医療特約への加入がおすすめの人とは
ここまで、学資保険の医療特約は不要とする意見を中心に解説してきましたが、もちろん全ての人にとって不要なわけではありません。以下のような考え方や状況に当てはまる人にとっては、医療特約への加入が有効な選択肢となる場合があります。
1. 貯蓄と保障を一つの契約でシンプルに管理したい人
「教育資金の準備もしたいし、子どもの医療保障も気になる。でも、いくつも保険契約を管理するのは面倒」と感じる人にとっては、学資保険に医療特約を付けることで、保険の管理を一本化できるメリットがあります。保険料の引き落としも一つにまとまるため、家計管理がシンプルになります。
2. 公的な医療費助成制度だけでは不安を感じる人
子どもの医療費助成制度は非常に手厚いですが、対象外の費用も存在します。
- 差額ベッド代
個室や少人数の病室を希望した場合にかかる費用。 - 先進医療の技術料
公的医療保険の対象外となる先進的な治療にかかる費用。 - 入院中の食事代の一部(食事療養標準負担額)
- その他雑費
パジャマやタオルのレンタル代、テレビカード代、家族が病院に通うための交通費など。
こうした自己負担費用に対して、どうしても不安が残るという方もいるでしょう。特に、長期入院になった場合などは、これらの費用も積み重なります。医療特約からの給付金を、こうした助成対象外の費用や、親が看病のために仕事を休んだ際の収入減少の補てんに充てたいと考えるのであれば、加入を検討する価値はあります。
3. 健康状態に不安があり、将来医療保険に入れないリスクに備えたい人
確率は低いものの、子どもが生まれつきの病気を持っていたり、幼少期に大きな病気にかかったりした場合、将来的に単体の医療保険に加入するのが難しくなる可能性があります。
学資保険の医療特約であれば、主契約の加入と同時に申し込むため、比較的加入しやすい傾向にあります。将来、子ども自身が保険に入れないリスクを少しでも軽減したいという親心から、お守り代わりに加入しておく、という考え方もあるでしょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
医療保障を充実させたいなら医療保険の加入がおすすめ
もし、あなたが子どもの医療保障を手厚くしたいと本気で考えているのであれば、学資保険の特約ではなく、医療特約なしの学資保険と単体の「子ども向け医療保険」を別々に契約することをおすすめします。
この方法には、以下のような大きなメリットがあります。
- 保障内容が充実している
入院・手術はもちろん、先進医療、通院、三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)など、特約よりもはるかに幅広い保障を、ニーズに合わせて手厚く準備できます。 - 保険料が比較的安い
子どもは病気やケガのリスクが大人より低いため、単体の医療保険でも月々1,000円~2,000円程度の比較的安い保険料で充実した保障内容の保険に加入できます。 - 保障期間を自由に選べる
学資保険の満期に関係なく、10年更新型や終身保障型など、必要な保障期間を自由に設定できます。若いうちに終身保障の医療保険に加入すれば、一生涯にわたって安い保険料で保障を確保できるという大きなメリットがあります。 - 保険の見直しがしやすい
将来、家計の状況や医療制度の変化に合わせて、学資保険はそのままに医療保険だけを解約したり、別の保険に乗り換えたりと、柔軟な見直しが可能です。
教育資金の準備は返戻率の高い学資保険で効率的に行い、医療への備えは保障内容が充実した単体の医療保険で行う。この「貯蓄」と「保障」の分離が、最も合理的で無駄のない選択と言えるでしょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の医療特約だけを解約できる?
「とりあえず医療特約を付けて加入したけれど、やっぱり不要だったかも…」
「家計が苦しくなってきたので、少しでも保険料を安くしたい」
このような場合、学資保険の主契約は続けながら、医療特約だけを解約することは基本的に可能です。保険会社のコールセンターや担当者に連絡し、所定の手続きを行うことで、特約部分の保険料負担をなくすことができます。
ただし、注意点が一つあります。それは、学資保険の主契約を解約して、医療特約だけを残すことはできないということです。特約はあくまで主契約に付随するものなので、主契約がなくなれば特約も自動的に消滅します。
もし途中で医療保障が不要になったと感じた場合は、特約のみを解約することで、返戻率を改善し、月々の保険料負担を軽くすることができます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
まとめ
今回は、「学資保険に医療特約は必要か」というテーマについて詳しく解説しました。
最後に、この記事の要点をまとめます。
結論としてほとんどのご家庭においては学資保険に医療特約を付けず、その分の費用を貯蓄に回すか、あるいは単体の医療保険で備える方がより合理的でメリットが大きいと言えるでしょう。
学資保険は、お子さまの大切な未来を支えるための重要な金融商品です。目先の安心感だけでなく、長期的な視点で家計全体のバランスを考え、ご自身の家庭の価値観やライフプランに合った最適な選択をしてください。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!