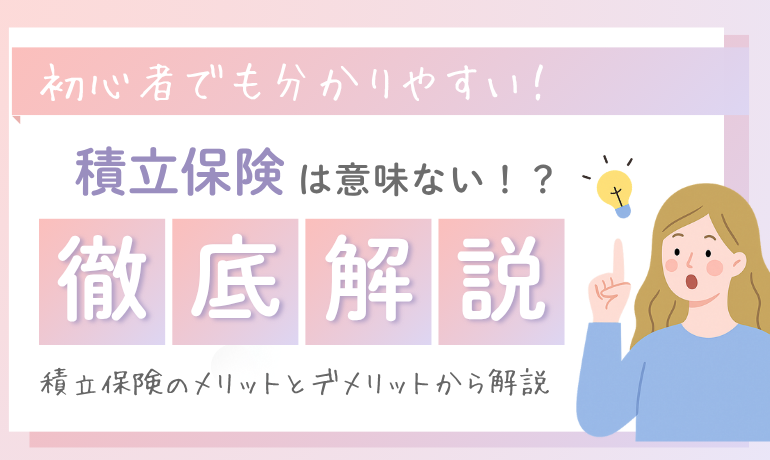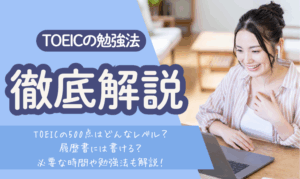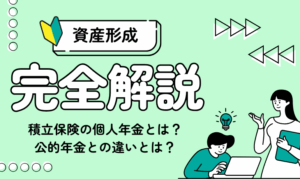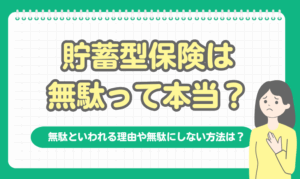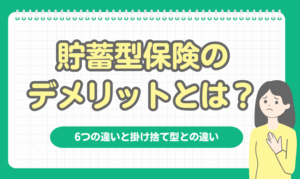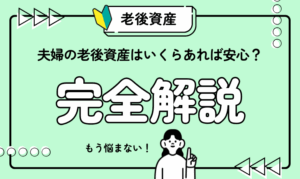「老後の資金準備や子どもの教育資金のために、積立保険を検討している」
「でも、インターネットやSNSで『積立保険は意味ない』『保険で貯蓄をしてはいけない』という声を見て、加入をためらっている」
「すでに加入しているけど、このまま続けていいのか不安…」
将来のために備えたいという堅実な考えを持つ方ほど、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。
結論から言うと、積立保険が「意味ない」かどうかは、加入する人の目的によって大きく異なります。 万人にとって意味がないわけでも、逆に誰にでもおすすめできる万能な商品というわけでもありません。
この記事では、「積立保険は意味ない」というキーワードを軸に、なぜそのように言われるのか、その理由となるデメリットを詳しく解説します。さらに、積立保険のメリットやどのような人に向いていないのか、そして積立保険が合わないと感じる方向けの代替となる資産形成方法まで、網羅的にご紹介します。
この記事を読み終える頃には、あなたが積立保険に加入すべきかどうかの明確な判断基準を持ち、ご自身のライフプランに最適な資産形成の一歩を踏み出せるようになっているはずです。
積立保険は意味ない?いらないかは加入の目的次第
冒頭でも述べた通り、積立保険に意味があるかないかは、あなたが保険に何を求めるか、つまり「加入の目的」によって決まります。まずは積立保険の基本的な仕組みを理解し、どのような目的を持つ人に合っているのか、あるいは合わないのかを見ていきましょう。
積立保険とは、その名の通り、保険料の一部が積み立てられていき、将来的にまとまったお金(満期保険金や解約返戻金)を受け取れる「貯蓄性」と、万が一の死亡や高度障害状態に備える「保障性」を兼ね備えた生命保険の一種です。
毎月支払う保険料が、将来のための貯蓄と、万が一の時のための保障の両方に充てられる仕組みだと考えると分かりやすいでしょう。
積立保険には、目的や保障内容によっていくつかの種類があります。代表的なものは以下の通りです。
・終身保険: 保障が一生涯続く保険です。解約しない限り死亡時に保険金が支払われますが、途中で解約すれば解約返戻金を受け取れるため、貯蓄目的で活用されることも多いです。特に、払込期間を短く設定する「短期払込積立終身保険」は、払込完了後の返戻率が高くなる傾向があります。
・養老保険: 保障期間(満期)が決まっている保険です。満期まで生存していれば満期保険金が、期間中に死亡した場合は死亡保険金が支払われます。生死混合保険とも呼ばれ、保障と貯蓄の両方の性質をバランス良く持っています。
・個人年金保険: 公的年金とは別に、個人で老後資金を準備するための保険です。契約時に定めた年齢(60歳、65歳など)から、一定期間または一生涯にわたって年金形式でお金を受け取れます。
・学資保険: 子どもの教育資金を準備するための保険です。進学のタイミングなど、決まった時期にお祝い金や満期保険金が支払われます。契約者(親)に万が一のことがあった場合、以降の保険料の支払いが免除される特約が付いているのが一般的です。
この解説でわかるように、積立保険は単なる「貯蓄」ではなく、あくまで「保険」としての機能がベースにあります。この点を理解することが、意味があるかないかを判断する上で非常に重要になります。
資産を増やす目的の人には意味がない
では、どのような人に積立保険は「意味ない」のでしょうか。それは、「保障よりも、効率的に資産を増やしたい」という目的を持っている人です。
もしあなたの目的が、銀行預金よりも高いリターンを目指して、手元の資金・お金を積極的に増やしていく「資産運用」であるならば、積立保険は最適な選択肢とは言えません。なぜなら、後述するデメリットでも詳しく触れますが、積立保険は投資信託のような金融商品と比較して、お金の増えるスピードが非常に緩やかだからです。
保障機能にかかるコストや保険会社の経費などが保険料に含まれているため、支払った保険料の全額が貯蓄に回るわけではありません。そのため、同じ金額を投資に回した場合と比較すると、将来受け取れるリターンはどうしても見劣りしてしまいます。
【積立保険が意味ない・おすすめしない人】
・投資や資産運用に関する知識があり、自身で積極的にお金を増やしたい人
・保障と貯蓄は分けて考え、それぞれ最適な商品を選びたい合理的な思考を持つ人
・元本割れのリスクを許容してでも、高いリターンを狙いたい人
・すぐに使える資金としての流動性を重視する人

貯蓄と保障を両立したい人には意味がある
一方で、「貯蓄が苦手で、強制的にでも将来のためのお金を貯めつつ、万が一の保障も確保したい」という目的を持っている人には、積立保険は非常に「意味がある」選択肢となります。
「毎月コツコツ貯金しようと思っても、ついつい使ってしまう」「銀行口座にお金があると安心できない」といった貯金が苦手な方にとって、給与天引きや口座振替で半ば強制的に保険料が引き落とされる積立保険の仕組みは、着実に資産を形成していくための強力なサポートになります。
また、一家の大黒柱で「自分に万が一のことがあったら、遺された家族の生活が心配だ」という方にとっては、死亡保障という安心を得ながら、同時に将来のライフイベント(子どもの教育、住宅購入の頭金、老後資金など)に備えられる点は大きなメリットと言えるでしょう。
【積立保険が意味がある・おすすめの人】
・貯金が苦手で、強制的に貯める仕組みが欲しい人
・万が一の保障を確保しながら、将来のための貯蓄も同時に進めたい人
・投資などのリスクは取りたくない、元本割れは避けたいという安定志向の人
・将来のライフプラン(子どもの進学、老後など)が明確で、その時期に合わせて確実にお金を受け取りたい人
このように、積立保険は「資産を増やす」という目的には不向きですが、「保障を得ながら強制的に貯蓄する」という目的には非常に適した商品なのです。
積立保険が意味ないといわれる理由とは?4つのデメリット
「資産を増やす目的なら意味がない」と言われる背景には、積立保険が持つ構造的なデメリットが存在します。ここでは、「積立保険は意味ない」という主張の根拠となる4つの大きなデメリットについて、詳しく掘り下げていきましょう。
1. 利率が低くて大きく増やせない
積立保険が「意味ない」と言われる最大の理由は、その利率の低さにあります。
積立保険で将来受け取れるお金がいくらになるかは、「予定利率」という指標が大きく影響します。これは、保険会社が契約者から預かった保険料を運用する際に約束する利回りのことです。しかし、この予定利率は、長引く低金利の影響で歴史的に低い水準にあります。
そのため、満期まで保険料を払い続けても、支払った保険料総額に対して受け取れる満期保険金や解約返戻金がわずかに上回る程度(返戻率が100%〜105%程度)というケースが少なくありません。場合によっては、払込期間が短いと元本割れすることさえあります。
例えば、毎月2万円を30年間(総額720万円)積み立てた場合を考えてみましょう。
これはあくまでシミュレーションであり、投資信託には元本保証がなくリスクが伴いますが、リターンの差は歴然です。お金を「増やす」という観点で見ると、積立保険の非効率さが際立ってしまいます。いつでも100%以上のお金が戻る積立保険を探すのは、現在の低金利下では非常に困難と言えるでしょう。
2. インフレで実質的な価値が下がってしまう
あまり語られませんが、積立保険にはインフレリスクという大きな弱点があります。インフレとは、物価が継続的に上昇し、相対的にお金の価値が下がることです。
積立保険は、契約した時点の予定利率で固定される長期契約がほとんどです。これは、将来どれだけ金利が上昇しても、契約時の低い利率が適用され続けることを意味します。
例えば、30年後に300万円の満期保険金を受け取る契約をしたとします。しかし、もしこの30年間で物価が2倍になっていたらどうでしょうか。契約時には300万円で買えたものが、満期時には150万円分しか買えなくなっている、つまりお金の実質的な価値が半分に目減りしてしまっているのです。
現在の日本は、長年のデフレから脱却し、インフレ傾向にあります。将来にわたって物価が上昇し続ける可能性を考えると、固定金利である積立保険は、インフレに対応できず、資産価値を守れないというデメリットを抱えています。
3. 途中解約すると元本割れする可能性が高い
積立保険は、途中解約に非常に弱いというデメリットがあります。特に契約してから年数が浅い段階で解約すると、受け取れる解約返戻金がそれまでに支払った保険料の総額を大幅に下回る、いわゆる「元本割れ」を起こす可能性が非常に高くなります。
なぜなら、支払った保険料から、死亡保障などの保障コストや、保険会社の運営にかかる事業経費などが優先的に差し引かれるからです。残った部分が貯蓄に回されるため、ある程度の期間継続しないと、貯蓄部分が払込保険料を上回らなくなってしまいます。
人生には、失業、病気、結婚など、予期せぬライフイベントの変化がつきものです。急にお金が必要になったとしても、積立保険を解約すると損をしてしまうため、資金の流動性が低い(必要な時にすぐに使えない)点は大きなデメリットです。この「一度始めたらやめにくい」という性質が、多くの人にとって足かせとなる場合があります。
4. 掛け捨て型より保険料が高い
「保障も貯蓄も」を一本で、というのは聞こえがいいですが、その分保険料は割高になります。
同じ死亡保障額で比較した場合、貯蓄性のない掛け捨て型の保険と比べると、積立保険の保険料は数倍高くなることも珍しくありません。
例えば、30歳男性が死亡保障1,000万円を確保する場合を考えてみましょう。
差額の約13,000円〜17,000円が貯蓄に回っていると考えることもできますが、先述の通り、その運用効率は高くありません。
もし「保障は保障、貯蓄は貯蓄」と割り切れるのであれば、安い掛け捨て型保険で必要な保障を確保し、浮いた差額分をNISAやiDeCoといった、より収益性の高い方法で運用する方が、合理的で効率的な資産形成につながる可能性が高いのです。この考え方が、「保険で貯蓄をしてはいけない」と言われる大きな理由の一つです。
積立保険に加入する意味とは?5つのメリット
ここまでデメリットを強調してきましたが、もちろん積立保険にはそれを上回る可能性のあるメリットも存在します。特に「貯蓄が苦手」「リスクを取りたくない」という方にとっては、大きな価値を感じられるでしょう。ここでは、積立保険に加入する5つの意味(メリット)を見ていきます。
1. 満期保険金や解約返戻金が受け取れる
積立保険の最も基本的なメリットは、将来、満期保険金や解約返戻金という形でまとまったお金が受け取れる点です。
契約時に将来受け取れる金額が(為替などの変動がなければ)ほぼ確定しているため、子どもの大学入学資金や自分のセカンドライフの資金など、ライフプランに合わせた計画的な資金準備が可能です。
銀行の普通預金に入れておくだけではなかなか貯まらないという人でも、保険という形で天引きされることで、着実に目標額を準備できる安心感があります。保険金という形で、将来の自分や家族への仕送りをしているような感覚で続けられるでしょう。
2. いざというときに保障が受けられる
貯蓄機能ばかりに目が行きがちですが、積立保険はあくまで「保険」です。契約者である被保険者に万が一のことがあった場合、死亡保険金や高度障害保険金が支払われ、遺された家族の生活を守るという重要な役割を果たします。
掛け捨ての保険とは異なり、貯蓄をしながら保障も得られるため、「もしもの時の備え」と「将来のための準備」を一本化できる手軽さが魅力です。特に、扶養家族がいる方にとっては、この保障があるという精神的な安心感は、何物にも代えがたいメリットと感じられるでしょう。
3. 確実に資産形成ができる
「貯金が苦手」な人にとって、これ以上ないメリットが「強制的に貯蓄できる」仕組みです。
給与振込口座から毎月自動で保険料が引き落とされるため、自分の意志の強さに関係なく、半ば強制的に資産形成を進めることができます。手元にお金があると使ってしまうという方でも、「初めからなかったもの」として生活費のやりくりをする習慣が身につくでしょう。
銀行預金のように簡単には引き出せない(解約すると損をする)というデメリットは、裏を返せば、安易に取り崩すことを防ぎ、目標達成まで貯蓄を継続させるための「ストッパー」として機能します。この強制力こそが、積立保険が多くの人に選ばれてきた大きな理由です。
4. 契約者貸付も利用できる
「途中解約すると元本割れするなら、急にお金が必要になった時に困るのでは?」という不安を和らげる制度が「契約者貸付」です。
これは、その時点での解約返戻金の一定の範囲内(通常は7〜9割程度)で、保険会社からお金を借りることができる制度です。保険を解約する必要がないため、保障はそのまま継続されます。
審査も比較的簡単で、銀行のカードローンなどよりも低い金利で借りられることが多いため、一時的に資金が必要になった際のつなぎとして活用可能です。この契約者貸付は、積立保険の流動性の低さをカバーする、セーフティネットのような役割を果たします。
5. 生命保険料控除で税金が安くなる
積立保険に加入して保険料を支払うと、「生命保険料控除」という制度を利用でき、所得税や住民税の負担を軽くすることができます。
年末調整や確定申告の際に、支払った保険料に応じた一定額が所得から差し引かれ(所得控除)、その結果として課税対象となる所得が減り、税金が安くなる仕組みです。
控除額には上限がありますが、税制上の優遇を受けながら貯蓄と保障の準備ができる点は、他の金融商品にはない保険ならではのメリットと言えるでしょう。
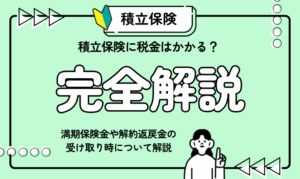
積立型と掛け捨て型の保険の違い
積立保険を検討する上で、必ず比較対象となるのが「掛け捨て型保険」です。両者の違いを正しく理解することで、自分にはどちらが合っているのかが見えてきます。
以下に、積立型と掛け捨て型の違いを簡単な表にまとめました。
| 比較項目 | 積立型保険 | 掛け捨て型保険 |
| 貯蓄性 | あり(満期保険金や解約返戻金がある) | なし(基本的に戻ってくるお金はない) |
| 保険料 | 高い | 安い |
| 解約返戻金 | あり(ただし早期解約は元本割れの可能性大) | ほとんどないか、あってもごくわずか |
| 目的 | 保障+貯蓄 | 保障のみ |
| 向いている人 | 貯金が苦手な人、保障と貯蓄を一本化したい人 | 保障と貯蓄を分けたい人、保険料を安く抑えたい人 |
見ての通り、両者は全く異なる性質を持っています。
どちらが良い・悪いという話ではありません。「保険料が高くても、強制的に貯蓄できる仕組みと保障をセットで得たい」と考えるなら積立型が向いています。一方で、「保障は最低限でいいから保険料を抑え、浮いたお金は自分で自由に運用したい」と考えるなら掛け捨て型とNISAなどを組み合わせる方が合理的です。このように、ご自身の価値観やライフプランに合わせて選択することが重要です。
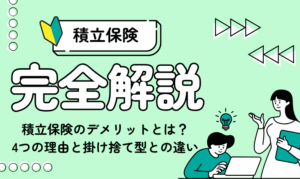
積立保険が意味ないと感じる人におすすめの資産形成方法
ここまで読んで、「自分には積立保険は合わないかもしれない」「もっと効率的に資産を増やしたい」と感じた方も多いでしょう。そのような方には、積立保険の代替となる、より収益性を追求できる資産形成方法があります。
ここでは、特におすすめの代表的な方法を3つご紹介します。ただし、これらの方法は積立保険と異なり元本保証がない点、つまり投資した金額より資産が減るリスクがあることを十分に理解しておく必要があります。
1. NISA(ニーサ/少額投資非課税制度)
NISAは、個人投資家のための税制優遇制度です。通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をして得た利益(配当金、分配金、譲渡益)には約20%の税金がかかりますが、NISA口座内で得た利益には税金がかからないという非常に大きなメリットがあります。
2024年から始まった新しいNISA制度では、非課税で投資できる上限額が大幅に拡大し、制度も恒久化されたため、長期的な資産形成の柱として活用しない手はありません。
・つみたて投資枠: 年間120万円まで。長期・積立・分散投資に適した、国が厳選した低コストの投資信託などが対象。コツコツ積み立てたい初心者におすすめ。
・成長投資枠: 年間240万円まで。投資信託のほか、個別株などにも投資可能。より積極的にリターンを狙いたい方向け。
まずは「つみたて投資枠」で、全世界株式や米国株式などに連動するインデックスファンドを毎月一定額、淡々と積み立てていくことから始めるのが王道です。ネット証券であれば、月々1,000円といった少額からでも始められます。
2. iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)
iDeCoは、老後資金の準備に特化した私的年金制度です。原則として60歳まで資金を引き出すことはできませんが、その分、税制上の優遇措置が非常に手厚いのが特徴です。
・掛金が全額所得控除: 支払った掛金の全額が所得から控除され、所得税・住民税が安くなります(生命保険料控除よりも節税効果が高い)。
・運用益が非課税: NISAと同様、運用期間中に得た利益には税金がかかりません。
・受け取るときも税制優遇: 年金または一時金で受け取る際にも、公的年金等控除や退職所得控除といった控除が適用されます。
「老後資金」という明確な目的があり、途中で引き出せないという制約を「強制的な貯蓄」としてメリットと捉えられる方には、NISAと並行して活用したい非常に強力な制度です。
3. 投資信託の特定口座での積立投資
NISAやiDeCoの非課税枠を使い切った後や、老後資金や教育資金といった目的以外の資金(住宅購入の頭金、車の購入費用など)を、ある程度リスクを取って運用したい場合には、証券会社の「特定口座」で投資信託を積み立てる方法があります。
特定口座は、利益が出た場合の税金の計算や納税を証券会社が代行してくれるため、確定申告の手間が省ける(源泉徴収ありの場合)というメリットがあります。
NISAやiDeCoと同様に、全世界株式やS&P500などのインデックスファンドをコツコツ積み立てるのが基本戦略です。ゆうちょ銀行などの身近な金融機関でも取り扱いはありますが、手数料(信託報酬)が安く、品揃えが豊富なネット証券で口座を開設するのがおすすめです。
まとめ:あなたの目的は「保障」か「資産形成」か
今回は、「積立保険は意味ない」というテーマについて、その理由やメリット・デメリット、そして代替となる資産形成方法まで詳しく解説しました。
改めて、この記事の結論をまとめます。
・積立保険が意味ない人: 資産を効率的に増やすこと(資産運用)を最優先に考える人。
・積立保険が意味ある人: 貯金が苦手で、万が一の保障を得ながら強制的に貯蓄をしたい人。
積立保険は、決してすべての人にとって「意味ない」商品ではありません。その特性を正しく理解し、ご自身の価値観やライフプラン、そして何より「加入の目的」と照らし合わせることが最も重要です。
もしあなたが、保障と貯蓄は分けて考え、より効率的な資産形成を目指したいのであれば、保険は割安な掛け捨て型で必要な分だけ確保し、NISAやiDeCoといった税制優遇制度を最大限に活用して投資に回すのが賢明な選択と言えるでしょう。

一方で、面倒なことは抜きにして、一本で保障と貯蓄を両立させたい、強制力のある仕組みでなければ貯められない、という方にとっては、積立保険は心強い味方になります。
「意味ない」という言葉に惑わされるのではなく、ご自身にとって本当に必要なものは何かをじっくりと考え、後悔のない選択をしてください。この記事が、そのための第一歩となれば幸いです。
おすすめの積立保険はこちらをチェック!
もし、本記事を読んで「自分には積立保険が合っているかもしれない」「他の積立保険と比較してみたい」と感じた方は、各保険会社の商品を比較検討してみることをおすすめします。専門家やファイナンシャルプランナーに相談できる保険相談店舗などを活用するのも良いでしょう。
より具体的な保険商品のおすすめや生命保険ランキングなどを知りたい方は、ぜひ関連記事も合わせてご覧ください。