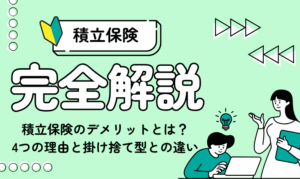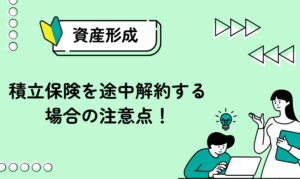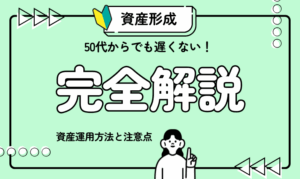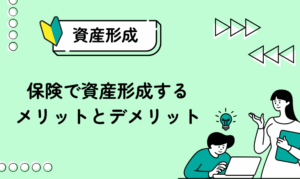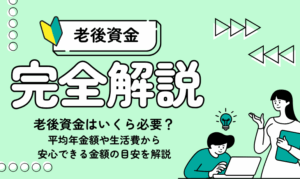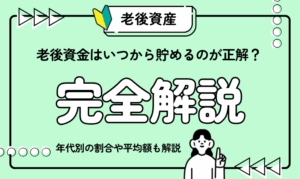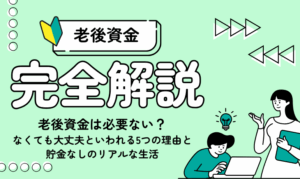「将来のために、そろそろ資産形成を始めないといけないな…」
「でも、何から手をつければいいのか分からない」
「投資は怖いイメージがあるし、損はしたくない」
人生100年時代と言われる現代、老後資金や教育資金、理想のライフプラン実現のために、資産形成の重要性はますます高まっています。しかし、いざ始めようと思っても、多くの情報が溢れていて、何が自分に合った方法なのかを見極めるのは難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな資産形成の第一歩を踏み出そうとしている初心者の方に向けて、おすすめの資産形成方法を徹底的に解説します。
特に、「大きなリスクは負いたくない」「まとまった資金はないけれど、今からコツコツ始めたい」という方にぴったりの、低リスクな資産運用の種類から、年代別・目的別の具体的な進め方まで網羅的にご紹介します。
この記事を読めば、あなたに最適な資産形成の方法が見つかり、漠然としたお金の不安を解消して、着実に未来へ備えるための一歩を踏み出せるはずです。
初心者におすすめ!低リスクな資産形成方法5選
資産形成と聞くと「ハイリスク・ハイリターン」な投資を想像する人もいますが、初心者の方は、まず値動きが比較的おだやかで安心して始めやすい「低リスク」な金融商品から始めるのがおすすめです。ここでは、初心者におすすめの低リスクな資産形成方法を5つ、その種類や特徴を詳しく解説します。
国債や債券
債券とは、国や地方公共団体、企業などが、投資家から資金を借り入れるために発行する「借用書」のようなものです。中でも、日本政府が発行する債券を「国債」と呼びます。
投資家は債券を購入することで、発行体に対してお金を貸していることになります。満期(償還日)になると、購入した金額(額面金額)が全額払い戻されるほか、保有している期間中は定期的に利子を受け取ることができます。
初心者におすすめの理由
債券が初心者におすすめの最大の理由は、その安全性の高さにあります。特に日本国が発行する個人向け国債は、国が元本の支払いを保証しているため、極めて安全性が高い金融商品です。
また、最低1万円から購入できる手軽さも魅力です。価格の変動も株式に比べて小さいため、日々の値動きに一喜一憂することなく、落ち着いて資産形成に取り組むことができます。
投資信託
投資信託(ファンド)とは、多くの投資家から集めた資金を一つにまとめ、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券、不動産など国内外の様々な資産に分散して投資・運用する金融商品です。その運用で得られた成果が、投資額に応じて投資家に分配されます。
例えるなら「資産運用の詰め合わせパッケージ」です。どの株式や債券を選べば良いか分からない初心者でも、専門家に運用を任せることができます。
初心者におすすめの理由
投資の基本は「分散投資」ですが、個人で複数の株式や債券を買い集めるのは大変です。投資信託は1本購入するだけで、自動的に数十から数百、時には数千の銘柄に分散投資できるため、リスクを効果的に抑えることができます。
また、多くの証券会社では月々1,000円や100円といった少額からの積立設定が可能です。「つみたてNISA」などの制度を利用すれば、コツコツと無理のない範囲で資産形成を始められます。
不動産小口化商品
不動産小口化商品とは、通常は数千万円~数億円といった高額な不動産を、1口数万円~100万円程度の小口に分割して販売する商品です。投資家は少額の資金で、都心のオフィスビルや商業施設、マンションなどの共同オーナーの一人になることができます。
不動産投資でありながら、現物の不動産を直接購入・管理する手間がなく、手軽に始められるのが特徴です。不動産クラウドファンディングもこの一種に含まれます。
初心者におすすめの理由
「不動産投資に興味はあるけれど、いきなりローンを組んで物件を買うのはハードルが高い」と感じる方に最適です。少額から不動産のオーナーになる体験ができ、不動産投資の第一歩として踏み出しやすいでしょう。
また、不動産から得られる賃料収入が利益の源泉となるため、比較的安定した分配金が期待できるのも魅力です。
高配当ETF
ETF(Exchange Traded Fund)は「上場投資信託」の略称で、その名の通り、証券取引所に上場している投資信託のことです。株式と同じように、証券会社を通じてリアルタイムで売買できます。
中でも「高配当ETF」は、配当利回りが高い複数の株式銘柄を組み合わせて作られたETFです。これを保有することで、定期的に分配金を受け取ることができます。
初心者におすすめの理由
高配当ETFを1つ購入するだけで、複数の高配当企業に分散投資できるのが大きなメリットです。自分でどの企業の配当が高いか、業績は安定しているかを一つひとつ分析する手間が省けます。
また、投資信託に比べて信託報酬が低い傾向にあるのも嬉しいポイントです。長期的に保有する際のコストを抑えられます。
REIT(リート)
REIT(リート)は「Real Estate Investment Trust」の略で、日本語では「不動産投資信託」と訳されます。多くの投資家から集めた資金で、オフィスビル、商業施設、マンション、ホテル、物流施設といった複数の不動産を購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する金融商品です。
仕組みは投資信託と似ていますが、投資対象が不動産に特化しているのが特徴です。証券取引所に上場しており、株式と同じように売買できます。
初心者におすすめの理由
不動産小口化商品と同様に、少額の資金で間接的に様々な不動産のオーナーになれる点が魅力です。現物の不動産を所有する際に発生する固定資産税や修繕費、管理の手間などは一切かかりません。
また、REITは利益の90%超を分配するなどの条件を満たせば、法人税が実質的にかからない仕組みになっています。そのため、収益を効率的に投資家に分配しやすく、比較的高い分配金利回りが期待できます。
リスクなしで資産形成したい人におすすめの方法2選
「投資はやっぱり怖い」「絶対に元本割れはしたくない」という方もいらっしゃるでしょう。リスクを一切取りたくないという方には、資産を「増やす」ことよりも「着実に貯める・守る」ことに重点を置いた方法がおすすめです。
預貯金
預貯金は、銀行や信用金庫などの金融機関にお金を預ける、最も身近で基本的な資産形成の方法です。普通預金や定期預金など、目的に応じて様々な種類があります。
初心者におすすめの理由
誰にとっても馴染み深く、手続きが簡単な点が最大の魅力です。資産形成の第一歩として、まずは給料からの天引きなどで自動的に貯まる仕組みを作る「先取り貯蓄」を始めるのがおすすめです。生活費やいざという時のための「生活防衛資金(生活費の3カ月~6カ月分が目安)」を確保する上でも、預貯金は不可欠です。
積立保険
積立保険とは、万が一の際の「保障」機能と、将来のためにお金を「貯蓄」する機能の両方を兼ね備えた保険商品です。毎月決まった保険料を支払うことで、死亡保障や医療保障などを確保しつつ、満期時や解約時には満期保険金や解約返戻金を受け取ることができます。代表的なものに「養老保険」「終身保険」「個人年金保険」「学資保険」などがあります。
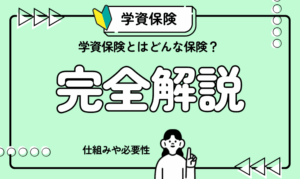
初心者におすすめの理由
保険料として半強制的に支払うため、貯金が苦手な人でも計画的にお金を貯めやすいという特徴があります。また、万が一のことがあった場合には、支払った保険料以上の保険金が受け取れるため、家族の生活を守るという保障の役割も果たしてくれます。

株式投資での資産運用はしないほうがいい?
「資産運用といえば株式投資」というイメージを持つ方も多いでしょう。しかし、初心者が十分な知識や準備なしに、いきなり個別企業の株式売買を始めることは、あまりおすすめできません。その理由と、特に株式投資をしないほうがいい人の特徴を理解しておきましょう。
初心者が自分で株式売買するリスク
株式投資は、企業の成長性や将来性を自分で分析し、株価が安い時に買って高い時に売ることで利益(キャピタルゲイン)を狙うのが基本です。これには、経済ニュースや企業の決算情報などを読み解く専門的な知識と、多くの勉強時間が必要になります。
また、株価は日々、様々な要因で大きく変動します。昨日まで上がっていた株が、今日いきなり暴落することも珍しくありません。このような価格変動リスクは、債券や投資信託に比べて非常に高くなります。
感情に流されて「もっと上がるかも」と高値で買ってしまったり、「これ以上損したくない」と慌てて底値で売ってしまったり(狼狽売り)と、冷静な判断が難しくなり、結果的に大きな損失を出してしまうケースが後を絶ちません。
株式投資をしないほうがいい人の特徴
以下のような特徴に当てはまる場合、個別株への投資は一旦立ち止まって考えるべきです。
・失うと困る「お金」で投資しようとしている人: 株式投資に使うお金は、最悪の場合ゼロになっても生活に支障が出ない「余裕資金」であることが大前提です。生活費や近い将来に使う予定のあるお金(教育資金や住宅購入の頭金など)を投資に回すのは絶対にやめましょう。まずは、生活防衛資金をしっかりと確保することが最優先です。
・なぜその株を買うのか「理由」を説明できない人: 「人気だから」「誰かにおすすめされたから」といった曖昧な理由で投資するのは非常に危険です。その企業の事業内容や業績、将来性を自分なりに理解し、なぜ今この株に投資する価値があるのかを説明できるだけの根拠を持つことが重要です。
・リスクを正しく「理解」していない人: 株式投資は元本が保証されておらず、投資した資金を失う可能性があることを十分に理解する必要があります。「絶対に儲かる」という考えで始めると、損失が出た時に冷静に対処できなくなります。
・短期的な利益ばかりを追い求める人: 株式投資で安定した成果を出すには、長期的な視点が不可欠です。短期的な値動きに一喜一憂し、頻繁に売買を繰り返すと、手数料がかさむばかりでなく大きな損失につながりやすくなります。
もちろん、十分な勉強とリスク理解、そして余裕資金の確保ができた上で挑戦するのは自由です。しかし、ほとんどの初心者にとっては、まずは投資信託などを通じて間接的に多くの株式に分散投資するほうが、はるかに堅実で始めやすい方法と言えるでしょう。
投資を始める初心者におすすめの制度
日本には、個人の資産形成を後押しするための、非常に有利な税制優遇制度があります。それが「NISA」と「iDeCo」です。投資を始めるなら、この2つの制度を活用しない手はありません。それぞれの特徴を理解し、自分に合った制度を最大限に活用しましょう。
NISA(少額投資非課税制度)
NISA(ニーサ)とは、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品(投資信託や株式など)から得られる利益(分配金、配当金、譲渡益)が非課税になる制度です。通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座内での取引であれば、その税金が一切かかりません。
2024年からは新しいNISA制度がスタートし、より使いやすく、恒久的な制度となりました。新NISAには、2つの投資枠があります。
つみたて投資枠: 年間120万円まで。長期・積立・分散投資に適した、国が定めた基準を満たす投資信託などが対象。コツコツ積立投資を行うのに最適です。
成長投資枠: 年間240万円まで。投資信託のほか、個別株やREITなど、比較的幅広い商品が対象。
この2つの枠は併用可能で、合計で年間最大360万円まで投資できます。そして、生涯にわたって非課税で保有できる上限額(生涯非課税保有限度額)は1,800万円です。さらに、NISA口座で保有している商品を売却すれば、その商品の簿価(取得価額)分の非課税枠が翌年以降に復活し、再利用できるという大きなメリットもあります。
どんな人におすすめか?
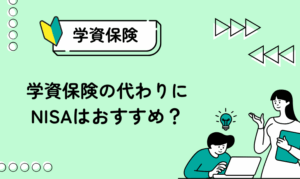
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)は、自分で掛金を拠出し、自分で選んだ金融商品(定期預金、保険、投資信託など)で運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取る「私的年金制度」です。公的年金に上乗せする形で、自分自身の老後資金を準備することができます。
メリット
iDeCoには、NISAにはない強力な3つの税制優遇があります。
掛金が全額所得控除: 毎月支払う掛金の全額が所得から控除されます。これにより、その年の所得税と翌年の住民税が軽減されます。例えば、毎月2万円(年間24万円)を拠出する課税所得300万円の会社員の場合、年間で約4.8万円もの節税効果が期待できます。
運用益が非課税: NISAと同様に、運用期間中に得た利益(利息、分配金など)には税金がかかりません。
受け取り時にも控除がある: 60歳以降に受け取る際も、「公的年金等控除(年金形式)」や「退職所得控除(一時金形式)」の対象となり、税負担が軽減されます。
デメリット・注意点
原則60歳まで引き出せない: 最大の注意点です。老後資金を確実に準備するための制度なので、途中で資金が必要になっても、原則として引き出すことはできません。そのため、iDeCoに拠出するお金は、当面使う予定のない余裕資金に限定する必要があります。
各種手数料がかかる: 加入時や毎月の掛金拠出時、資産の受け取り時に手数料がかかります。
どんな人におすすめか?
NISAとiDeCoはどちらか一方を選ぶものではなく、併用することでそれぞれのメリットを活かせます。「いつでも引き出せるNISA」と「老後まで引き出せないiDeCo」という特性を理解し、自分のライフプランや目的に合わせて活用していくのが賢い方法です。
年代別:おすすめの資産形成の方法
資産形成の最適なアプローチは、年齢やライフステージによって異なります。ここでは、20代から50代までの年代別に、おすすめの資産形成の方法や考え方のポイントを解説します。
20代におすすめの資産形成
20代最大の武器は「時間」です。若いうちから資産形成を始めることで、利息が利息を生む「複利の効果」を最大限に活かすことができます。運用期間が長くとれるため、多少のリスクを取ってでも、将来的に大きなリターンが期待できる資産(株式など)の割合を多めにすることも可能です。
具体的な方法
まずは少額からの「つみたて投資」: 社会人になったら、まずは月々5,000円や1万円からでも良いので、NISAの「つみたて投資枠」を活用して積立投資を始めましょう。全世界株式や米国株式(S&P500など)に連動する低コストのインデックスファンドがおすすめです。
iDeCoの開始も検討: 会社員や公務員であれば、iDeCoに加入して節税メリットを享受するのも非常に有効です。ただし、60歳まで引き出せないことを念頭に、無理のない範囲の掛金で始めましょう。
自己投資も忘れずに: 20代は、自身のスキルアップやキャリアアップにお金と時間を使う「自己投資」も非常に重要な資産形成です。将来の収入を増やすことが、何よりの資産形成につながります。
注意点
生活防衛資金(生活費の3カ月分程度)を預貯金で確保することが最優先です。収入がまだ不安定な時期でもあるため、いきなり大きな金額を投資に回すのではなく、収入の5~10%を目安に、コツコツと継続することを目標にしましょう。
30代におすすめの資産形成
30代は、キャリアアップによる収入増が期待できる一方で、結婚、出産、住宅購入といった大きなライフイベントが重なる時期でもあります。資産形成を本格化させると同時に、ライフプランに合わせた資金計画がより重要です。20代同様、まだ運用期間は長くとれるため、積極的な姿勢を継続しつつも、将来の支出に備えたバランス感覚が求められます。
具体的な方法
NISA・iDeCoの積立額を増やす: 収入の増加に合わせて、NISAやiDeCoへの積立額を増やしていきましょう。目標は収入の10~15%程度です。共働きの場合は、夫婦それぞれが制度を活用することで、非課税メリットを最大限に活かせます。
ライフイベント資金の準備: 数年以内に使う可能性のある住宅購入の頭金や子供の教育資金などは、NISAの枠内でも比較的リスクの低い債券ファンドで運用するか、あるいはリスクを避けて預貯金や個人向け国債で確実に準備するなど、目的別に資金を色分けして管理することが大切です。
保険の見直し: 家族構成の変化に合わせて、生命保険や医療保険を見直しましょう。必要な保障を確保しつつ、不要な保険料を削減できれば、その分を投資に回すことができます。
注意点
様々な支出が増える時期だからこそ、「先取り貯蓄・投資」の仕組みを確立し、着実に資産を積み上げることが重要です。ライフプランが具体的になるにつれて、いつまでに、いくら必要なのかをシミュレーションしてみましょう。
40代におすすめの資産形成
40代は、子供の教育費の負担がピークに達する一方、役職に就くなどして収入が安定し、老後が現実的な目標として見えてくる年代です。資産形成においては、「ラストスパート」と「守り」の両方を意識する時期と言えます。これまで築いてきた資産を減らさずに、老後資金を確実に上積みしていくことが目標となります。
具体的な方法
老後資金のシミュレーション: 公的年金の見込額(ねんきんネットで確認可能)や退職金の額を把握し、老後に必要な生活費との差額を計算してみましょう。ゴールが明確になることで、iDeCoやNISAで今からあといくら準備すべきかが見えてきます。
iDeCoの活用を最大化: 節税効果の大きいiDeCoは、40代こそ積極的に活用したい制度です。まだ加入していない場合は、すぐにでも始めることをおすすめします。掛金の上限額まで拠出することを検討しましょう。
資産配分(ポートフォリオ)の見直し: これまで株式中心で積極的に運用してきた人も、徐々に値動きの安定した債券の比率を高めるなど、リスクを抑えた運用へのシフトを考え始める時期です。
注意点
教育費や住宅ローン返済で家計が苦しい時期ですが、老後資金の準備を先延ばしにはできません。家計を見直し支出を削減することで、投資に回す資金を捻出する努力が求められます。

50代におすすめの資産形成
50代は、資産形成の「仕上げ」の時期です。これからは資産を大きく「増やす」ことよりも、これまで築いてきた資産を定年退職後にどのように「使う」か、どうやって「守る」かを考える「出口戦略」が最重要テーマとなります。新規で大きなリスクを取るような投資は避けるのが賢明です。
具体的な方法
リスク資産の段階的な縮小: 定年退職が近づくにつれて、株式などのリスク資産の割合を徐々に減らし、預貯金や個人向け国債といった安全資産の割合を増やしていきましょう。これは、退職直前に市場が暴落して資産が大きく目減りするリスクを避けるためです。
退職金の運用計画: 受け取る予定の退職金を、退職後の生活費としてすぐに使うのか、あるいは一部を運用に回して資産寿命を延ばすのか、あらかじめ計画を立てておくことが重要です。退職金を受け取った途端に、金融機関からハイリスクな商品を勧められるケースもあるため、注意が必要です。
iDeCoや年金の受け取り方を検討: iDeCoや企業年金を「一時金」で受け取るか、「年金」として分割で受け取るか、あるいは併用するかによって、税金や社会保険料の負担が変わってきます。自分のライフプランに最も有利な受け取り方を検討し始めましょう。
注意点
「退職金で投資デビュー」は非常に危険です。退職金は、長年の労働の対価である大切な資産です。これを元手にリスクの高い投資に手を出すのは避け、まずは安定的な運用を心がけましょう。50代からの資産形成は、守りを最優先に考えることが鉄則です。
ケース別:おすすめの資産形成の方法
資産形成の目的は人それぞれです。ここでは、「子供の教育資金」「老後資金」「公務員の資産形成」という3つの具体的なケースに分けて、おすすめの方法を解説します。
子供のための資産形成におすすめの方法
子供の将来のための資金、特に大学進学などにかかる教育資金は、使う時期と必要額がある程度決まっているのが特徴です。そのため、「必要な時期に」「確実に」準備できている状態を目指す必要があります。
学資保険: 昔からある定番の方法です。毎月保険料を支払うことで、子供の進学時期に合わせて祝金や満期保険金が受け取れます。最大のメリットは、契約者(親)に万が一のことがあった場合、以降の保険料の支払いが免除され、保障はそのまま継続される点です。確実性は高いですが、貯蓄性(リターン)は低い傾向にあります。
NISA口座の活用(親名義): 親自身のNISA口座を活用して、教育資金を準備する方法です。例えば、全世界株式インデックスファンドなどで運用すれば、学資保険よりも高いリターンが期待できます。ただし、元本保証はなく、運用がうまくいかないリスクもあります。子供が18歳になるまでの期間が10年以上あるなど、長期で運用できる場合に有効な選択肢です。
両者の組み合わせ: 「ベースとなる資金は学資保険で確実に準備し、上乗せ分をNISAで積極的に運用する」というように、両方を組み合わせるのが最もバランスの取れた方法と言えるでしょう。
注意点
子供のための資金は、使う時期が近づいてきたら(例えば大学入学の5年前など)、徐々にリスクの低い預貯金や債券に移していく「リバランス」が重要です。
老後のための資産形成におすすめの方法
豊かなセカンドライフを送るための老後資金準備は、資産形成における最大のテーマの一つです。これは長期戦になるため、税制優遇制度をフル活用し、コツコツと積み上げていくのが王道です。
iDeCo(個人型確定拠出年金): まさに老後資金準備のために作られた制度です。「掛金が全額所得控除」「運用益が非課税」「受け取り時も控除あり」という3つの強力な税制優遇は、他のどの金融商品にもない大きなメリットです。老後資金準備の中核として、最優先で活用すべき制度と言えます。
NISA(少額投資非課税制度): iDeCoと並行して、NISAも積極的に活用しましょう。iDeCoは60歳まで引き出せないため、60歳以前にリタイアした場合の生活費や、iDeCoの非課税枠を使い切った後の追加の資産形成として役立ちます。いつでも引き出せる流動性の高さも魅力です。
公的年金の繰下げ受給: 公的年金は原則65歳から受け取れますが、受け取り開始を66歳以降に遅らせる「繰下げ受給」が可能です。1カ月繰り下げるごとに受給額が0.7%増え、75歳まで繰り下げると最大で84%も増額された年金を生涯受け取ることができます。これも立派な老後の資産形成の一つです。
注意点
まずは、公的年金がいくらもらえるのかを把握することが第一歩です。「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認し、老後の生活にいくら不足するのかを計算した上で、iDeCoやNISAでの目標額を設定しましょう。
公務員におすすめの資産形成の方法
公務員は収入が安定しており、手厚い退職金制度があるため、民間企業の会社員に比べて資産形成の計画を立てやすいという強みがあります。この安定性を活かし、堅実に資産を増やしていくのがおすすめです。
iDeCoの活用: 公務員もiDeCoに加入できます(2024年11月までの掛金上限は月額1.2万円ですが、2024年12月からは制度が変更され、多くの公務員の上限額が月額2万円に引き上げられました)。毎年の節税メリットは非常に大きいため、必ず活用したい制度です。
NISAでの積立投資: 安定した収入を活かし、NISAのつみたて投資枠で、全世界株式やS&P500などのインデックスファンドをコツコツ積み立てていくのが王道です。ボーナスなど余裕がある月には、成長投資枠の活用も検討しましょう。
財形貯蓄制度: 勤務先に制度があれば、給与天引きで貯蓄ができる財形貯蓄も手軽な方法です。特に、使用目的が住宅取得や年金準備に限定される「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」は、合計550万円までの元本から生じる利子が非課税になるメリットがあります。
注意点
安定しているからこそ、積極的な資産運用に縁遠いと感じる方もいるでしょう。しかし、現在の低金利では預貯金だけでは資産はほとんど増えず、インフレで目減りしてしまいます。将来のゆとりのために、iDeCoやNISAといった制度を活用した「守りながら増やす」投資の視点を持つことが重要です。
資産形成の勉強におすすめの書籍やYouTube
資産形成を成功させるためには、正しい知識を身につけることが不可欠です。最後に、初心者の方が資産形成の全体像を学び、自分に合ったポートフォリオ(資産の組み合わせ)を考える上で役立つ、おすすめの書籍とYouTubeチャンネルをご紹介します。
おすすめの書籍
1.『本当の自由を手に入れる お金の大学』(両@リベ大学長)
「貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う」という、お金にまつわる5つの力を網羅的に、かつ非常に分かりやすく解説したベストセラーです。イラストや図解が豊富で、活字が苦手な人でもスラスラ読めます。資産形成の土台となる家計改善から、NISAやiDeCo、不動産、株式投資まで、この一冊で基本的な知識が身につきます。何から勉強すれば良いか分からない人が、最初に手に取るべき一冊です。
2.『改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん』(ロバート・キヨサキ)
世界中で読み継がれる、お金に関する考え方を根底から変えてくれる名著です。具体的な投資手法ではなく、「資産と負債の違い」や「お金のために働くのではなく、お金に働いてもらう」といった、資産形成に取り組む上でのマインドセット(心構え)を学ぶことができます。この本を読むことで、なぜ資産形成が必要なのかを深く理解し、モチベーションを高めることができるでしょう。
おすすめのYouTubeチャンネル
1.「両学長 リベラルアーツ大学」
上記で紹介した書籍『お金の大学』の著者である両学長が運営するチャンネルです。お金に関するあらゆるテーマを、関西弁の親しみやすい語り口でアニメーションを使って分かりやすく解説してくれます。動画の数が非常に多く網羅的なので、自分が知りたいテーマ(NISA、iDeCo、保険、節約術など)から見ていくだけで、どんどん知識が深まっていきます。
2.「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」
「銀行員YouTuber」として活動する小林亮平さんのチャンネルです。特にNISAやiDeCoといった制度の解説が非常に丁寧で、初心者の方がつまずきやすいポイントを先回りして解説してくれます。おすすめの金融機関や具体的な商品の選び方まで紹介してくれるため、知識をインプットするだけでなく、実際に行動に移す際に非常に参考になります。
まとめ
今回は、資産形成を始めたい初心者の方に向けて、おすすめの方法を網羅的に解説しました。
最後に、この記事のポイントを振り返ります。
初心者は低リスクな資産形成から: まずは「国債」「投資信託」「REIT」など、値動きが比較的おだやかで、分散投資が効いている商品から始めるのがおすすめです。
リスクを取りたくないなら: 元本保証の「預貯金」や、保障と貯蓄を兼ね備えた「積立保険」が選択肢になりますが、インフレに弱いというデメリットを理解しておきましょう。
お得な制度をフル活用: 投資を始めるなら、「NISA」と「iDeCo」は必須です。運用益非課税のメリットを最大限に活かしましょう。
年代や目的に合わせて方法を選ぶ: 20代・30代は時間を味方に、40代・50代は守りを意識するなど、自分のライフステージに合った戦略を立てることが大切です。
学び続けることが成功の鍵: 書籍やYouTubeなどを活用し、正しい知識を身につけることが、長期的な資産形成の成功につながります。
将来のお金の不安は、何もしなければ消えることはありません。しかし、今日ここで得た知識をもとに、ほんの小さな一歩でも行動を起こせば、その不安は着実に和らいでいきます。
まずは証券会社の口座を開設してみる、月々1,000円からでもNISAで積立投資を始めてみる、iDeCoの資料請求をしてみる。どんな小さなことでも構いません。
この記事が、あなたの輝く未来のための資産形成を始める、確かなきっかけとなることを心から願っています。