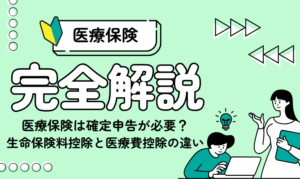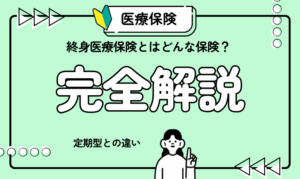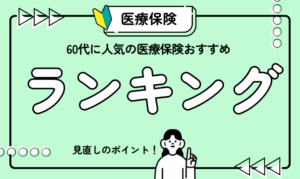「病気やケガで急な出費が…」そんな万が一の事態に備えるのが医療保険です。しかし、いざ医療保険を選ぼうと思っても、「種類が多すぎて何が違うのかわからない」「自分にはどんな保険が必要なの?」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
日本の医療保険制度は、私たちが普段使っている保険証が示す「公的医療保険」と、任意で加入する「民間の医療保険」の2階建て構造になっています。
この記事では、初めて医療保険の加入を検討している方に向けて、医療保険の全体像から、公的医療保険と民間医療保険のそれぞれの種類、保障内容、違いまでをわかりやすく解説します。この記事を読めば、医療保険の基本的な知識が身につき、自分に必要な保障を見つけるためのヒントが得られるでしょう。
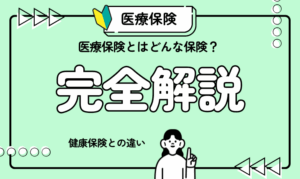
【一覧】医療保険制度の種類
日本の医療保険制度は、大きく分けて「公的医療保険」と「民間の医療保険」の2種類で成り立っています。それぞれの特徴と主な種類を一覧で確認し、全体像を掴みましょう。
公的医療保険と民間医療保険の概要
| 公的医療保険 | 民間の医療保険 | |
| 加入義務 | 義務あり(国民皆保険制度) | 任意 |
| 目的 | 国民の医療費負担を軽減するための相互扶助制度 | 公的医療保険でカバーしきれない部分を自己で補うための備え |
| 運営主体 | 国、地方自治体、健康保険組合など | 生命保険会社、損害保険会社など |
| 保険料 | 所得などに応じて決まる | 年齢、性別、保障内容、健康状態などに応じて決まる |
| 主な保障内容 | 診察、治療、薬剤、入院などの費用の一部負担 | 入院給付金、手術給付金、通院給付金、先進医療給付金など |
公的医療保険の種類一覧
| 分類 | 保険制度の名称 | 主な対象者 |
| 被用者保険 | 組合管掌健康保険(健康保険組合) | 大企業の会社員、その家族 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) | 中小企業の会社員、その家族 | |
| 共済組合 | 公務員、私立学校教職員、その家族 | |
| 船員保険 | 船員、その家族 | |
| 地域保険 | 国民健康保険 | 自営業者、フリーランス、パート・アルバイト、無職の人など |
| 高齢者医療 | 後期高齢者医療制度 | 75歳以上のすべての人、65歳以上75歳未満で一定の障害がある人 |
民間の医療保険の種類一覧
| 分類 | 保険の種類 | 特徴 |
| 保障期間による分類 | 定期医療保険 | 10年、15年など一定期間の保障。保険料は比較的安いが、更新時に保険料が上がることがある。 |
| 終身医療保険 | 一生涯の保障。保険料は加入時から変わらないが、定期型よりは割高になる傾向がある。 | |
| 保険料の性質による分類 | 掛け捨て型 | 保障機能に特化しており、貯蓄性がない。保険料が安く、手厚い保障を準備しやすい。 |
| 貯蓄型 | 保障機能に加え、解約返戻金や満期保険金などでお金が戻ってくる可能性がある。保険料は割高になる。 |
医療保険には様々な種類があり、それぞれに役割と特徴があります。

公的医療保険制度の種類
公的医療保険制度は、日本に住むすべての人がいずれかの制度に加入し、保険料を出し合うことで、病気やケガをした際の医療費の負担を軽減する「国民皆保険制度」に基づいています。私たちが病院の窓口で保険証を提示することで、医療費の自己負担が原則3割に抑えられるのは、この制度のおかげです。
公的医療保険は、職業や年齢によって主に以下の3つの種類に分けられます。
国民健康保険
国民健康保険は、他の公的医療保険に加入していない人を対象とした医療保険制度です。運営主体は市区町村および国民健康保険組合です。
主な対象者
・業者、フリーランス
・農業・漁業従事者
・パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
・退職して職場の健康保険を任意継続しなかった人
・無職の人
会社を退職した場合や、個人事業主として独立した場合などには、この国民健康保険への加入手続きが必要になります。保険料は、前年の所得や世帯の加入者数などに基づいて計算されます。
被用者保険
被用者保険とは、会社員や公務員など、事業所に雇用されている人(被用者)と家族が加入する医療保険の総称です。「社会保険」と呼ばれることも多く、保険料は勤務先と折半して負担するのが一般的です。被用者保険は、勤務先の規模や業種によって、さらに以下の4つの種類に分けられます。
組合管掌健康保険(健康保険組合)
主に大企業やそのグループ企業の従業員が加入する健康保険です。企業が単独または共同で「健康保険組合」を設立し、運営しています。健康保険組合によっては、法律で定められた給付(法定給付)に加えて、独自の付加給付が提供される場合があります。
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
主に中小企業の従業員が加入する健康保険で、「協会けんぽ」という愛称で知られています。全国健康保険協会が運営しており、加入者数が最も多いのが特徴です。都道府県ごとに保険料率が設定されています。
船員保険
船員として働く人を対象とした、独立した医療保険制度です。医療保険だけでなく、労働災害保険や雇用保険の役割も併せ持っているのが特徴です。
共済組合
公務員や私立学校の教職員とその家族が加入する医療保険です。国家公務員共済組合や地方公務員共済組合、私立学校教職員共済など、所属する組織によって組合が分かれています。健康保険組合と同様に、独自の付加給付が充実している場合があります。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が加入する医療保険制度です。また、65歳以上75歳未満の方でも、一定の障害があると認定された場合は加入できます。
それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退し、この制度に移行することになります。運営主体は、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」で、市区町村が窓口業務を担当します。
公的医療保険制度の医療費負担の割合の種類
公的医療保険に加入していると、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担額が軽減されます。この自己負担割合は、年齢や所得によって以下のように定められています。
| 年齢 | 所得区分 | 自己負担割合 |
| 義務教育就学前(6歳未満) | – | 2割 |
| 義務教育就学後~69歳 | – | 3割 |
| 70歳~74歳 | 現役並み所得者以外 | 2割 |
| 現役並み所得者 | 3割 | |
| 75歳以上(後期高齢者医療制度) | 一定以上の所得がある方 | 2割 |
| 現役並み所得者 | 3割 | |
| 上記以外の方 | 1割 |
「現役並み所得者」とは、課税所得が145万円以上ある被保険者およびその人と同一世帯の被保険者を指します。ただし、収入額によっては1〜2割負担となる場合があります。
子ども医療費助成制度など、自治体によっては独自の助成制度により、自己負担がさらに軽減されます。
公的医療保険制度があるおかげで、医療費を全額負担することなく、必要な医療を受けることができます。

公的医療保険制度の給付制度の種類
公的医療保険の役割は、窓口での自己負担を軽減するだけではありません。医療費が高額になったり、病気で働けなくなったりした場合など、様々な状況に応じて現金が支給される「給付制度」も充実しています。
療養の給付・家族療養費
医療機関で保険証を提示して受ける診察、治療、薬の処方、入院などの医療サービスそのものを「療養の給付」と呼びます。被保険者本人が受ける給付を「療養の給付」、被扶養者(家族)が受ける給付を「家族療養費」と呼び、どちらも自己負担割合は同じです。
入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院中の食事代や、療養病床に入院する65歳以上の人が負担する居住費についても、一部を公的医療保険が負担してくれます。標準的な食費・居住費から自己負担額を差し引いた分が「入院時食事療養費」や「入院時生活療養費」として給付されます。
保険外併用療養費
保険診療と保険適用外の治療を併用した場合に、保険診療部分については公的医療保険の給付が受けられる制度です。例えば、将来的に保険適用を目指す「評価療養」や、患者の快適性を高める「選定療養」が該当します。
訪問看護療養費・家族訪問看護療養費
主治医の指示に基づき、自宅で看護師などによる療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合に、費用の一部が給付されます。被保険者本人は「訪問看護療養費」、家族は「家族訪問看護療養費」として給付を受けられます。
高額療養費・高額介護合算療養費
医療費の自己負担額には、1カ月の上限が設けられており、上限額を超えた分が後から払い戻される制度を「高額療養費制度」といいます。上限額は年齢や所得によって異なります。大きな手術や長期の入院で医療費が高額になっても、家計への負担が過度になるのを防ぐことができます。
また、医療保険と介護保険の両方を利用している世帯では、1年間の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合にその超えた分が支給される「高額介護合算療養費制度」もあります。
移送費・家族移送費
病気やケガにより移動が困難な患者が、医師の指示で緊急的に転院などが必要になった場合の移送費用が支給される制度です。すべての移送が対象となるわけではなく、保険者が「緊急その他やむを得ない」と認めた場合に限られます。
傷病手当金
病気やケガの療養のために仕事を休み、事業主から十分な給与が受けられない場合に支給される手当です。以下の4つの条件をすべて満たした場合に、給与の約3分の2が最長で1年6カ月間支給されます。
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
自営業者などが加入する国民健康保険には、原則としてこの制度はありません。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者またはその被扶養者が出産した際に、子ども一人につき一定額が支給される制度です。2023年4月以降の出産については、原則として50万円が支給されます。医療機関へ直接支払われる制度を利用すれば、窓口での負担を軽減できます。
出産手当金
出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けられなかった場合に支給される手当です。産前42日から産後56日までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象に、給与の約3分の2が支給されます。
埋葬料・家族埋葬料
被保険者が業務外の事由で亡くなった場合、生計を維持していて、埋葬を行う人に「埋葬料」として5万円が支給されます。被扶養者が亡くなった場合は「家族埋葬料」が支給されます。
公的医療保険制度の範囲外となる医療の種類
手厚い保障が魅力の公的医療保険ですが、すべての医療費が対象となるわけではありません。以下のようなケースは、原則として保険適用の対象外となり、費用は全額自己負担となります。
・正常な妊娠・出産にかかる費用 (異常分娩など、治療が必要と判断された場合は保険適用となる)
・美容目的の整形手術 (例:二重まぶたの手術)
・健康診断、人間ドック (検査の結果、病気が見つかり治療が開始された場合は保険適用となる)
・予防接種 (インフルエンザワクチンなど)
・先進医療 (厚生労働大臣が定める高度な医療技術。技術料は全額自己負担だが、診察など基礎部分は保険適用)
・選定療養 (差額ベッド代、予約診療、時間外診療など)
・業務上や通勤中のケガ(労災保険の対象)
特に、先進医療を受ける場合は数百万円単位の費用がかかることもあります。また、入院時の差額ベッド代や食事代、交通費、そして療養中の生活費の減少など、見えない負担も発生します。
公的医療保険の「弱点」を補い、より安心して治療に専念できるように備えるのが「民間の医療保険」の役割です。
民間の医療保険の種類
民間の医療保険は、生命保険会社や損害保険会社が販売している商品で、加入は任意です。公的医療保険を土台として、上乗せの保障を自分で準備するためのものです。商品内容は多種多様ですが、主に以下の観点で分類できます。
保障内容の種類
民間の医療保険は、病気やケガによる入院や手術といった特定の事態に備えるのが基本です。主契約となる基本保障に、様々な「特約」を付加することで、保障内容を自分に合わせてカスタマイズできます。
・主契約(基本保障): 入院給付金、手術給付金が中心。
・特約(オプション):
先進医療特約: 全額自己負担となる先進医療の技術料を保障。
がん特約: がんと診断された場合の一時金や、入院・通院治療を手厚く保障。
三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)特約: 所定の状態で一時金が受け取れる。
女性疾病特約: 乳がんや子宮筋腫など、女性特有の病気による入院を手厚く保障。
通院特約: 入院後の通院や、入院を伴わない通院を保障。
定期医療保険と終身医療保険
保障が続く期間(保険期間)によって、「定期医療保険」と「終身医療保険」の2つに大別されます。
・定期医療保険
特徴: 10年、15年、あるいは60歳まで、80歳までといったように、保険期間が一定です。保険期間が満了すると、健康状態にかかわらず更新できる商品が多いですが、更新後の保険料はその時点の年齢で再計算されるため、一般的に高くなります。
メリット: 保険料が割安なため、子どもが独立するまでなど、一定期間だけ手厚い保障が欲しい場合に適しています。
デメリット: 更新のたびに保険料が上がり、最終的に保障がなくなる商品もあります。
・終身医療保険
特徴: 解約しない限り、保障が一生涯続きます。
メリット: 加入時の保険料のまま、一生涯の保障を確保できます。若いうちに加入すれば、比較的安い保険料で長く保障を得られます。
デメリット: 同じ保障内容の場合、定期医療保険に比べて加入当初の保険料は割高になります。
掛け捨て型と貯蓄型
支払った保険料が戻ってくるかどうかで、「掛け捨て型」と「貯蓄型」に分けられます。
・掛け捨て型医療保険
特徴: 貯蓄性がなく、解約返戻金や満期保険金がほとんどないか、まったくないタイプの保険です。その分、保険料が安く設定されています。現在販売されている医療保険の主流はこのタイプです。
メリット: 安い保険料で、入院や手術に対する手厚い保障を準備できます。「保障は保障、貯蓄は貯蓄」と割り切って考えたい方におすすめです。
デメリット: 保険を使わなかった場合、支払った保険料は戻ってきません。
・貯蓄型医療保険
特徴: 保障機能に加えて、貯蓄性も兼ね備えています。一定期間後に生存していれば「生存給付金」が受け取れたり、解約時に「解約返戻金」が支払われたりします。
メリット: 保障を得ながら、将来のためにお金を貯めることができます。
デメリット: 掛け捨て型に比べて保険料が割高になります。途中で解約すると、支払った保険料総額を下回る金額しか戻ってこない場合が多いです。
民間の医療保険の給付金の種類
民間の医療保険に加入していると、具体的にどのような場面で、どのような給付金が受け取れるのでしょうか。ここでは、代表的な給付金の種類について解説します。
入院給付金
病気やケガで入院した場合に受け取れる給付金で、医療保険の最も基本的な保障です。「入院給付金日額 × 入院日数」で計算されるのが一般的です。日額は5,000円や10,000円など、契約時に自分で設定します。
最近では、日帰り入院から保障される商品が主流ですが、「1入院あたりの支払限度日数」や「通算の支払限度日数」が定められています。
手術給付金
公的医療保険の対象となる手術や、保険会社が定める所定の手術を受けた場合に受け取れる給付金です。給付額のタイプは主に2種類あります。
・入院給付金日額連動型: 「入院給付金日額 × 20倍」など、入院給付金日額に応じた倍率で支払われるタイプ。手術の種類によって倍率が変わるのが一般的です。
・定額給付型: 手術の種類にかかわらず、一律で10万円、20万円といったまとまった金額が支払われるタイプ。
通院給付金
入院給付金が支払われる入院をし、その退院後に通院した場合に受け取れる給付金です。一般的には特約として付加します。「退院後180日以内の通院を30日まで保障」といった条件が定められていることが多く、入院を伴わない通院は対象外となるケースがほとんどです。
先進医療特約
公的医療保険の対象外である「先進医療」にかかる技術料を保障する特約です。多くの医療保険に付加でき、月々100円~数百円程度の保険料で、総額2,000万円程度までの高額な先進医療費に備えることができます。利用頻度は低いものの、経済的な理由で治療を諦めることがないように、検討する価値が高い特約です。
まとめ:公的保険を理解し、自分に必要な民間保険を選ぼう
今回は、医療保険の種類について、公的医療保険と民間医療保険の2つの側面から詳しく解説しました。
・公的医療保険: 日本の国民皆保険制度の根幹。職業などによって種類が分かれ、医療費の自己負担軽減や高額療養費制度など、手厚い保障が受けられる。
・民間の医療保険: 公的医療保険ではカバーしきれない費用(差額ベッド代、先進医療費、療養中の生活費など)を補うための任意加入の保険。保障期間や貯蓄性の有無、特約の組み合わせで自分に合った保障を設計できる。
初めて医療保険を検討する方は、まず私たち全員が加入している公的医療保険の仕組みと、その限界点を正しく理解することが大切です。その上で、「公的保険だけでは、もしもの時に何が足りなくなるだろうか?」と考えてみましょう。
・入院した場合、個室を希望するかもしれない(差額ベッド代)
・最新の治療法(先進医療)も選択肢に入れたい
・病気で働けなくなった時の収入減が心配
・がんと診断されたら、治療費以外にもお金がかかりそう
こうした不安やニーズに対して、民間の医療保険がどのような解決策を提示してくれるのかを比較検討していくことが、あなたにとって最適な保険選びにつながります。この記事が、あなたの医療保険に対する理解を深め、未来への備えを考えるきっかけとなれば幸いです。